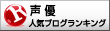エーザイとバイオジェンが共同開発した、認知症の新薬「レカネマブ」が日本でも承認されました。
私の母は中程度の認知症と診断されていて、父も認知障害が明らかに出てきているので…
この薬には関心がありました。
それで、自分で調べたことと、駆け出しの医薬品の研究開発者である息子に質問した回答をもとに…
この薬が認知症患者にとって、画期的な福音になり得るのかどうかを、少し書いてみたいと思います。
わかりやすく、間違いなく書けるかどうか心配ですが。
レカネマブは、主にアルツハイマー型の認知症に向けて開発された薬です。
この認知症は、脳内にアミロイドβというたんぱく質の一種が溜まることによって、脳細胞が破壊されて起きます。
最も症例が多くて、一般的な認知症とされています。
レカネマブは、アミロイドβの生成を抑えるための抗体を、直接体内に注入することで効果を発揮します。
息子の言によると…
まず認知症というのはとても複雑で多様な病気で、それだけに治療薬を開発するのも困難な病気だと。
そしてレカネマブは「これまでに開発されたどの薬よりも、効果がはっきり期待できる」薬だとのこと。
ただし、脳細胞が壊れて行くのを「抑制する」薬なので、既に現れている症状が「治る」ものではない。
認知機能をもとに戻すためには、一度壊れてしまった脳細胞を再生することが必要になるが、それはできない。
この薬で出来ることは、あくまでも認知症の「進行を抑える」ことで「治す」ことではない。
まずこの点を押さえておかないと、誤解が生じると思います。
また、この薬が効果を発揮するのは、軽度の認知症と、初期認知障害の患者さんのみで…
既に中程度に進行してしまった認知症には、効果があると証明されていないそうです。
それから、この薬には効く症例の人と、効かない症例の人がいるということ。
そして、効くか効かないかの判断をするために、体に負担のかかる(苦痛を伴う)検査が必要だそうです。
なので、あまり高齢過ぎる方には、体の負担が大きすぎると言える。
比較的若い人や、体力のある人向け、ということになるかもしれません。
また副作用についての注意も喚起されていて、脳内に小規模の出血がある人や…
血栓を防止したり、血液をサラサラにするための薬を飲んでいる人には、適用しない方が安全だと。
もうここまでの説明で、中程度の認知症である私の母にも…
既に90歳近い高齢で、しかも血液をサラサラにする薬を服用している父にも、使えないことがわかりました。
また、もう一つの問題は、この薬が「抗体薬」という種類の薬品だということ。
抗体薬は、物質を人工的に合成して作る、合成薬、低分子薬という種類のものとは違って…
もともとの作り方は、マウスなどに抗原(病気の原因となる物質)を入れて、それに対抗する抗体を生産させ…
その抗体細胞を集めて、これと、爆発的に増殖する特殊な細胞とを人工的に融合させて作った…
「ハイブリドーマ細胞」というものを生成し、それをさらに培養・増殖させて…
そこから化学的な方法で、特別な病気に対抗する抗体となるたんぱく質だけを取り出す、というやり方で作られます。
近年はその途中で、遺伝子組み換え操作などの過程を組み込んで「ヒト化抗体」「完全ヒト化抗体」を作る…
などという作業を加えて、副作用を減らしていますが…
いずれにしても、抗体医薬というのは、とても複雑な工程を経て製造されるため…
コストと手間が非常に多くかかるのは、不可避なのが現状となっています。
結果的に、薬価がとても高価になってしまうことが欠点とされます。
また、特殊なたんぱく質から出来ているため、飲み薬の形にすると、消化器官で壊れてしまうため…
静脈注射(点滴)で投与する以外に、用法はありません。
なので、高額な薬代が必要な上、点滴などの医療費がかさんでしまう、というのが不可避になります。
ちなみに、既に使用が開始されている米国では、年間の薬代が、一人当たり360~370万円かかるそうです。
(1ドル=140円で計算した場合)
あくまでも「進行を抑える」ための薬ですから、継続して投与しないといけない上に、高価であると。
日本では医療保険適用で3割負担としても、純粋な薬代だけで年間120万円以上の費用がかかる計算になります。
しかも保険治療となれば、7割は健保組合や国庫など、公的な機関が負担するわけですから…
社会的な医療コストの負担も大きい。
息子によれば「ポンポンと出せるような値段の薬じゃない」ということになります。
認知症患者の数は、日本国内で数百万人と言われますが、非常に高価な薬ということを考えると…
1.患者に経済力があること
2.社会的な医療コストを考えて「より有効な人」のために優先して使われる結果になるであろうこと
→勤労年齢である若年のうちに発症したとか、社会的重要度が高い人とか…
という使用条件が出来てしまうことは避けられないのではないか、と思います。
周囲が「この人は認知症に違いない」と気付く、中程度に進行してしまう前に、認知症と診断されるケースが少ない…
ということも鑑みると、新薬レカネマブの恩恵にあずかれる人は、ごく一部ではないでしょうか。

これだと「認知症患者への福音」となるのは、難しいのではないかと思われます。
息子いわく。
「こういう薬で現状つないでいる間に、僕ら『低分子』系(合成薬の創薬)の人間が…」
「もっと安くていい薬を開発するために頑張らないと、だね」
とのこと。
息子が、抗体医薬やバイオ医薬の分野に進まずに、低分子化合物の合成医薬を専門に選んだのは…
より安く大量に生産できる=大多数を占めるお金のない患者さんや、経済発展途上国の患者さんが使える…
そういう薬を作りたい、という思いからだとのこと。
息子が直接、低コストの認知症薬の開発に携わるかどうかは分かりませんが…
私たちの世代が生きている間に、人類が、認知症の悩みから解放されるかどうか。
寿命だけ延ばしたところで、認知機能が完全に壊れてしまっては、生きている意味に疑問が生じますから。
期待はしたいところです。