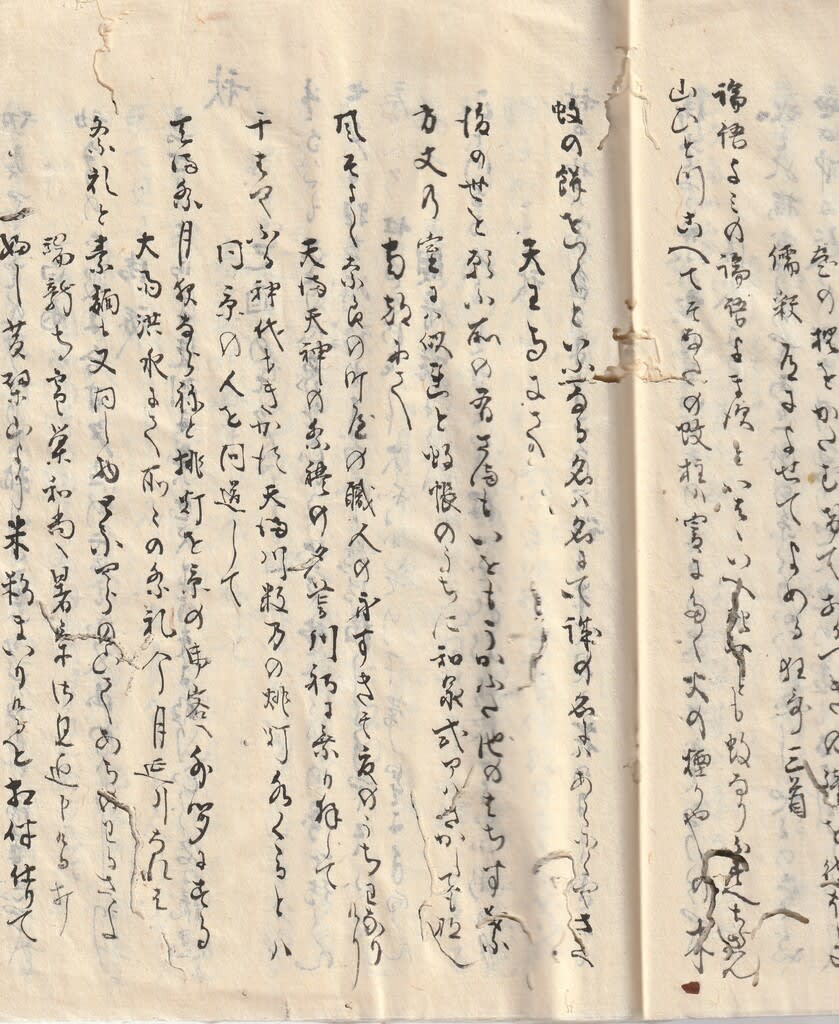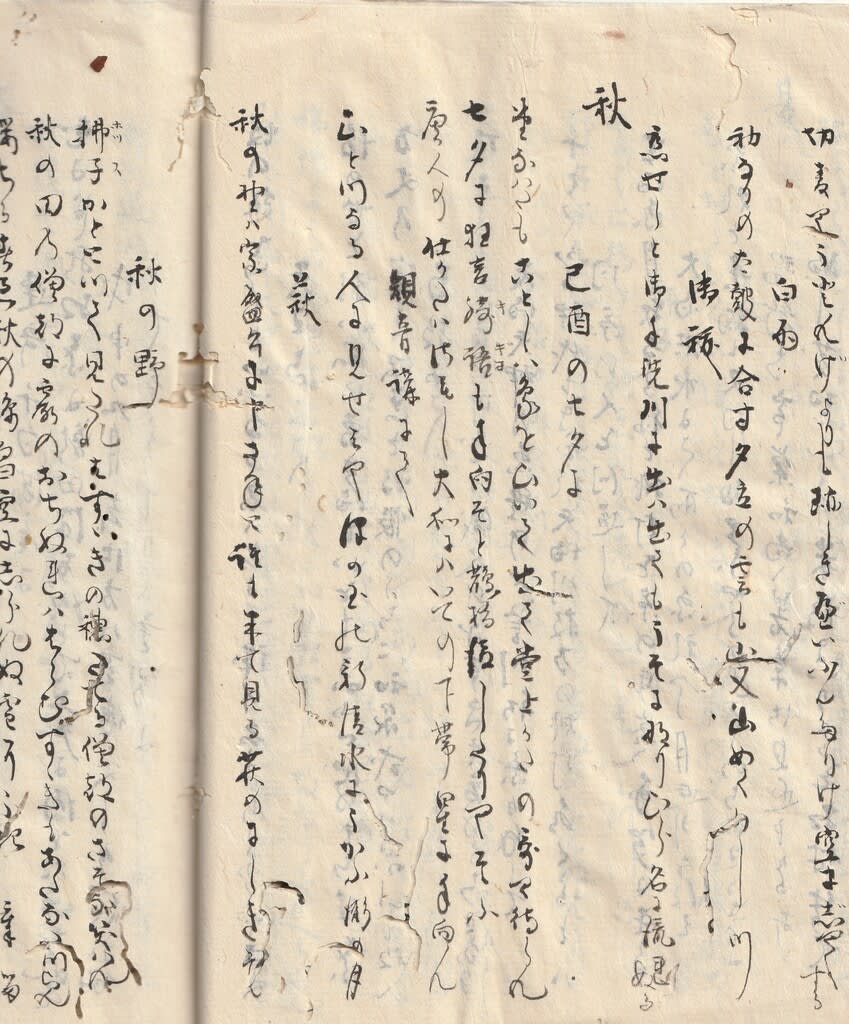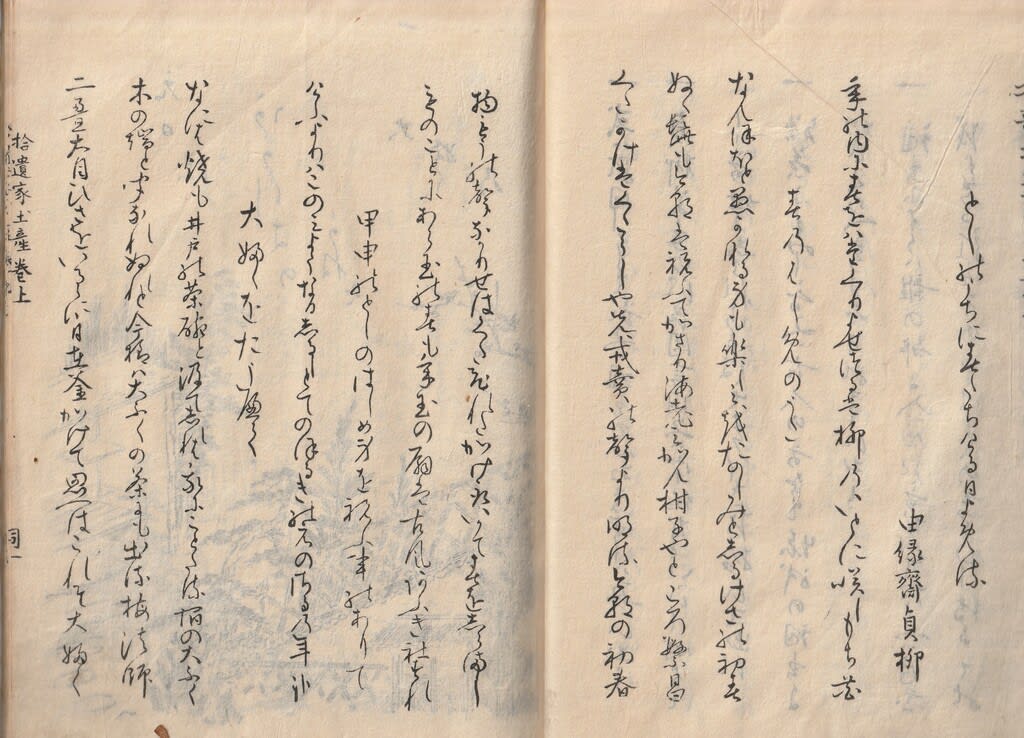母が見ていたテレビ番組で三津浜焼なるものを紹介していた。
三津浜といえば、広島から松山行フェリーに乗ると、昔はそのあたりに着いていた。
さて、三津浜焼はお好み焼の一種で、広島のような生地の上に先に炒めた麺をのせて、キャベツはその次、裏返した後二つ折りにして供されるところが、番組でも広島とは似て非なるものと紹介されていた。
ところが、私には、この三津浜の焼き方は昔の広島と全く同じに見えた。もちろん、具材は三津浜特有の紅白ちくわなどが入っていたが、出来上がりは昔の広島と同じだった。
先に麺をのせるのは、我々はオールドスタイルと呼んでいて、うどん派の私はわざわざこの焼き方のお店を探して食べている。今はそばを後から乗せて裏返し、そばをパリッとさせるのが主流だが、オールドスタイルだと卵と野菜が絡みやすい利点もあり、うどん入りはこちらの方がうまいと私は思っている。
また、出来上がってソースを塗った後、二つ折りにしてトトントンと大きなへらで切れ目を入れて、持って行った皿に入れてテイクアウト、というのが近所のお好み焼き屋さんでは当たり前の光景だった。いまでも、呉市や島しょ部では二つ折りが普通に行われている。広島市内では、他地方のお好み焼きの影響だろうか、昭和50年代ごろから鉄板でへらで食べる人が増えてきて、変容していったように思われる。
前にも書いたが、お好み、なのだから好きに焼いて食えばいい。ただ、番組に出ていた広島出身のタレントも広島とは違うと言っていて、昔の記憶が失われていくのは残念なことだと思って、書いてみた。子供のころ、祖父がバスで広島市内に出かけたらお土産は旧バスセンターの、にしき堂の生地にカレーが入った細長いまんじゅう(名前はしらない)、芸備線で出かけたら麗ちゃんのお好みと決まっていた。包んだ新聞紙にソースが染み出していたものだ。私にとってのソウルフードは、二つ折りで皿に入ったうどん入り、ということになる。