また毎日新聞が財務省の犬として的外れの社説を書いている。日本の失われた30年は景気後退局面に国債を発行して減税か財政出動をしなかったからだ。中学生の公民や高校生の政治・経済にも書いてある基本中の基本である。
それを財政が破綻するなどとあり得ないことを叫び不景気に増税を強行すれば経済は破綻する。戦争も内戦もないのにここまで経済が停滞したのはそれが原因だ。毎日新聞はそれさえわからないどうしようもない新聞だ。有害にすぎる。
>景気の長期低迷による「失われた30年」から抜け出せるかどうかの正念場だ。経済の活力を取り戻すには、国や企業が過去の失敗を真摯(しんし)に反省し、人を重視した社会に転換する必要がある。
その通りだが、財務省の犬の毎日新聞にはなぜ経済が低迷したのか正しい理由がわからない。毎日新聞をはじめとする新聞に従えば失われた40年になろう。
>円相場が約34年ぶりの安値水準に沈んでいる。日米の金利差が背景とされるが、日銀が17年ぶりに利上げしても、相場の流れは変わらなかった。春闘は2年連続で大幅な賃上げとなったが、物価高に追いつかない。家計は生活防衛を強いられ、「日本は貧しくなった」と感じる人が増えている。
円安はそれほど問題とは思わない。輸出企業は過去最高益を更新しているはずだからその法人税で食料やエネルギーの高騰に補助金を出せば良い。円安はしばらく続くかもしれないが、経常収支は大幅な黒字なのだ。そのうち必ず円高になる。数年単位だとは思うが。物価高への対処は食料自給率の向上と原発再稼働が必要だ。それまでは補助金を出すしかない。
>「世界第2位の経済大国」は遠い昔の話となった。来年には国内総生産(GDP)でインドにも抜かれ、5位に転落する見通しとなっている。
>なぜこうなったのか。
インドは高成長が続くのに岸田文雄は数十兆円の莫大な援助をしているのだ。その援助を国内の中間層・貧困層のために使えばどれだけの国民が助かったことか。
>著書「日本の経済政策」で失われた30年を検証した小林慶一郎・慶応大教授は「国も企業も目先の成果を追うことにこだわって道を誤った」と分析する。
新聞や財務省の御用学者の分析は的外れで増税と緊縮財政の理由付けに過ぎない。
>トリクルダウン起きず
>最大の誤りは、バブル崩壊後の1990年代以降、企業が長らく働き手をコストとしか見なさず、人員削減や正規から非正規雇用への切り替えなどを進めたことだ。
>当時は、中国の台頭などで経済のグローバル化が加速し、対応を迫られていた。国際競争力が低下する中、収益確保の「即効薬」としてリストラに走った。新卒採用も大幅に絞られ、いわゆる氷河期世代を生んだ。
>天然資源の乏しい日本が唯一の強みとしてきた人材基盤は大きく劣化した。2000年代以降の世界的なデジタル革命の波に乗り遅れ、革新的な商品やサービスを創出できなくなったのは、人材投資を怠ってきたツケだ。
指摘は正しい。企業が人材を大切にせず、リストラ、非正規雇用に走ったから人材がいなくなり、消費も減った。しかし国内がバブル崩壊で需要が激減しているのにそれ以外の方法はないだろう。国が積極財政で金を市場に流すしかなかったのだが、新聞は銀行救済に反対したのではなかったか。革新的な商品やサービスを創出できなくなったのは人材の劣化もあるが、それ以上に国内の需要不足だ。需要がないところに新しい商品やサービスは生まれない。
>政府・日銀の政策も的外れだった。大型の財政出動が繰り返されたが、景気刺激効果は一時的で国の借金を膨らませただけだった。
さらっと決めつけているがとんでもないことだ。大型の財政出動が行われた小渕恵三内閣では景気が回復しつつあったのだ。しかし森善朗もそれを踏襲したのだが、失言の連発で潰されてしまった。あと2年小渕恵三内閣が続いていれば不況から抜け出せたのではないか。
>小泉純一郎政権は「聖域なき構造改革」を旗印に不良債権処理を加速させたものの、経済を底上げできなかった。むしろ新自由主義的な発想で進めた雇用改革などが格差を拡大させ、消費者心理を悪化させた。
結局緊縮財政だからな。訳もわからず喝采した自分が恥ずかしくて仕方ない。日本の一等地や優良企業が外資に買われてしまった。小泉純一郎と竹中平蔵は間違いなく売国奴だ。
>約11年に及ぶ日銀の異次元の金融緩和策の副作用も大きい。脱デフレを掲げる第2次安倍晋三政権が推進したアベノミクスの看板政策だった。国債を大量購入し、市中に出回るお金の量を増やしたが、物価上昇率を2%に上げる目標をなかなか達成できなかった。
異次元の金融緩和は間違いではない。アベノミクスが失敗したのは緊縮財政だったからだ。消費税増税を決めたのは野田佳彦だが、安倍晋三もその路線に乗っかったのだ。消費税増税前の第二次安倍晋三政権は経済に薄日がさしていたが消費税増税と歳出抑制でおじゃんだ。第二次安倍晋三政権の7年8か月では1%しか経済が成長していないのだ。
>円高の是正や株価回復で潤ったのは輸出企業や富裕層ばかりで、恩恵が国民全体に広く行き渡るトリクルダウンは起きなかった。格差が広がり、経済や社会を支える中間層を細らせた。
法人税減税と株高で潤うのは輸出企業と富裕層だけだ。不況なのに消費税増税を強行すれば中間層・貧困層は生きていけなくなるに決まっているではないか。正気ではない。
> 「金利のない世界」が常態化したことで、政府は国債の金利負担を気にせず、バラマキ的な財政支出を続けた。
これが財務省の犬の大嘘なのだ。政府は積極財政などしていない。消費税増税に代表される緊縮財政を強行してきたのだ。財務省の犬の新聞に騙されてはいけない。消費税の廃止ないし減税が必要な局面なのだ。
>将来不安の払拭が必要
>多くの企業は資金調達が容易になったにもかかわらず、低収益の事業を継続した。リスクを覚悟で画期的な事業に挑むアニマルスピリットが失われた。
莫迦を言ってはいけない。需要がないところに新しい事業は生まれない。国が積極財政をしない限り企業は新しい事業に取り組むことはない。
>国の財政の悪化や、企業の人件費圧縮の姿勢は働き手の将来不安を高めた。年金や医療など社会保障制度の持続可能性が疑われ、所得も増えない中、個人消費が盛り上がらなかったのは当然だ。
財務省の犬はすぐこれだ。将来不安から消費が減ったわけではない。個人の財布の中身がないのだ。使おうにも使えるはずがないではないか。
>長期低迷から脱するためには何が必要か。
>小林教授は「働き手が安心して力を発揮できるよう、国や企業は不確実性の払拭(ふっしょく)に努めるべきだ」と指摘する。
>政府は財政規律を取り戻し、社会保障制度改革に真正面から取り組む。企業は社員教育など人材投資を強化する。こうした対応こそが求められている。
違う。長期低迷から脱するには政府の積極財政が必要なのだ。金がないことが日本の問題なのだから減税と財政出動で景気を良くするしかないのだ。財政規律と称して緊縮財政を続ければ失われた50年になる。財務省の犬毎日新聞に騙されてはいけない。
>経済的な事情などで希望する仕事に就けなかった人が、キャリアアップを目指せる仕組みも不可欠である。
>国は新たな知識や技能を身につけるリスキリングへの支援を打ち出す。企業や大学と連携を強め実効性を高めるべきだ。北欧のように全額を公費で賄い、無料で学べるようにするのも一案だろう。
>起業に失敗した若者らの再起を支える政策も充実させなければならない。
>人口が減り続ける日本が生き残るには、年齢や性別、国籍に関係なく、一人一人が活躍できる社会を構築するしかない。希望をもって働ける環境を取り戻すことこそが、失われた30年の教訓を生かす道である。
それに必要なものはなんだかわかるか。金だ。金がないから大学や研究機関が研究者を馘にせざるを得ないのだ。財務省が教育費、科学技術予算を増やす以外解決方法はない。財務省の犬の新聞はさらなる消費税増税を狙っている。それは絶対に阻止せねばならない。
財務省の犬の新聞のプロパガンダに騙されてはいけない。まずは新聞を不買・解約することだ。そうして財務省の犬に金を払って支えてはいけない。自分で自分の首を絞めるようなものだからだ。難しいが、家族友人親戚知人にも新聞の不買・解約を勧めて欲しい。プロパガンダの影響力を減らすにはそれが一番だからだ。
テレビも財務省の犬でしかない。ドラマやバラエティ、スポーツ、アニメは面白ければ見て構わない。つまらないなら消そう。そしてワイドショーは新聞に負けないほどのプロパガンダだ。消すしかない。
自民党は腐り果てたから政権交代しかないが、立憲民主党執行部も財務省の犬なのだ。単純に立憲民主党に政権交代しては民主党政権の二の舞だ。少数政党に投票して消費税減税機運を高めたい。選挙も家族親戚友人知人に投票を促して欲しい。政治に国民が関心を持つことが大事だからだ。
最後にランキングボタンを押してくれるようお願いする。ランキングが上がればより多くの人に読まれるし、私の気持ちも上向くからだ。
それを財政が破綻するなどとあり得ないことを叫び不景気に増税を強行すれば経済は破綻する。戦争も内戦もないのにここまで経済が停滞したのはそれが原因だ。毎日新聞はそれさえわからないどうしようもない新聞だ。有害にすぎる。
~~引用ここから~~
景気の長期低迷による「失われた30年」から抜け出せるかどうかの正念場だ。経済の活力を取り戻すには、国や企業が過去の失敗を真摯(しんし)に反省し、人を重視した社会に転換する必要がある。
円相場が約34年ぶりの安値水準に沈んでいる。日米の金利差が背景とされるが、日銀が17年ぶりに利上げしても、相場の流れは変わらなかった。春闘は2年連続で大幅な賃上げとなったが、物価高に追いつかない。家計は生活防衛を強いられ、「日本は貧しくなった」と感じる人が増えている。
「世界第2位の経済大国」は遠い昔の話となった。来年には国内総生産(GDP)でインドにも抜かれ、5位に転落する見通しとなっている。
なぜこうなったのか。
著書「日本の経済政策」で失われた30年を検証した小林慶一郎・慶応大教授は「国も企業も目先の成果を追うことにこだわって道を誤った」と分析する。
トリクルダウン起きず
最大の誤りは、バブル崩壊後の1990年代以降、企業が長らく働き手をコストとしか見なさず、人員削減や正規から非正規雇用への切り替えなどを進めたことだ。
当時は、中国の台頭などで経済のグローバル化が加速し、対応を迫られていた。国際競争力が低下する中、収益確保の「即効薬」としてリストラに走った。新卒採用も大幅に絞られ、いわゆる氷河期世代を生んだ。
天然資源の乏しい日本が唯一の強みとしてきた人材基盤は大きく劣化した。2000年代以降の世界的なデジタル革命の波に乗り遅れ、革新的な商品やサービスを創出できなくなったのは、人材投資を怠ってきたツケだ。
政府・日銀の政策も的外れだった。大型の財政出動が繰り返されたが、景気刺激効果は一時的で国の借金を膨らませただけだった。
小泉純一郎政権は「聖域なき構造改革」を旗印に不良債権処理を加速させたものの、経済を底上げできなかった。むしろ新自由主義的な発想で進めた雇用改革などが格差を拡大させ、消費者心理を悪化させた。
約11年に及ぶ日銀の異次元の金融緩和策の副作用も大きい。脱デフレを掲げる第2次安倍晋三政権が推進したアベノミクスの看板政策だった。国債を大量購入し、市中に出回るお金の量を増やしたが、物価上昇率を2%に上げる目標をなかなか達成できなかった。
円高の是正や株価回復で潤ったのは輸出企業や富裕層ばかりで、恩恵が国民全体に広く行き渡るトリクルダウンは起きなかった。格差が広がり、経済や社会を支える中間層を細らせた。
「金利のない世界」が常態化したことで、政府は国債の金利負担を気にせず、バラマキ的な財政支出を続けた。
将来不安の払拭が必要
多くの企業は資金調達が容易になったにもかかわらず、低収益の事業を継続した。リスクを覚悟で画期的な事業に挑むアニマルスピリットが失われた。
国の財政の悪化や、企業の人件費圧縮の姿勢は働き手の将来不安を高めた。年金や医療など社会保障制度の持続可能性が疑われ、所得も増えない中、個人消費が盛り上がらなかったのは当然だ。
長期低迷から脱するためには何が必要か。
小林教授は「働き手が安心して力を発揮できるよう、国や企業は不確実性の払拭(ふっしょく)に努めるべきだ」と指摘する。
政府は財政規律を取り戻し、社会保障制度改革に真正面から取り組む。企業は社員教育など人材投資を強化する。こうした対応こそが求められている。
経済的な事情などで希望する仕事に就けなかった人が、キャリアアップを目指せる仕組みも不可欠である。
国は新たな知識や技能を身につけるリスキリングへの支援を打ち出す。企業や大学と連携を強め実効性を高めるべきだ。北欧のように全額を公費で賄い、無料で学べるようにするのも一案だろう。
起業に失敗した若者らの再起を支える政策も充実させなければならない。
人口が減り続ける日本が生き残るには、年齢や性別、国籍に関係なく、一人一人が活躍できる社会を構築するしかない。希望をもって働ける環境を取り戻すことこそが、失われた30年の教訓を生かす道である。
令和6年4月30日毎日新聞社説
~~引用ここまで~~
>景気の長期低迷による「失われた30年」から抜け出せるかどうかの正念場だ。経済の活力を取り戻すには、国や企業が過去の失敗を真摯(しんし)に反省し、人を重視した社会に転換する必要がある。
その通りだが、財務省の犬の毎日新聞にはなぜ経済が低迷したのか正しい理由がわからない。毎日新聞をはじめとする新聞に従えば失われた40年になろう。
>円相場が約34年ぶりの安値水準に沈んでいる。日米の金利差が背景とされるが、日銀が17年ぶりに利上げしても、相場の流れは変わらなかった。春闘は2年連続で大幅な賃上げとなったが、物価高に追いつかない。家計は生活防衛を強いられ、「日本は貧しくなった」と感じる人が増えている。
円安はそれほど問題とは思わない。輸出企業は過去最高益を更新しているはずだからその法人税で食料やエネルギーの高騰に補助金を出せば良い。円安はしばらく続くかもしれないが、経常収支は大幅な黒字なのだ。そのうち必ず円高になる。数年単位だとは思うが。物価高への対処は食料自給率の向上と原発再稼働が必要だ。それまでは補助金を出すしかない。
>「世界第2位の経済大国」は遠い昔の話となった。来年には国内総生産(GDP)でインドにも抜かれ、5位に転落する見通しとなっている。
>なぜこうなったのか。
インドは高成長が続くのに岸田文雄は数十兆円の莫大な援助をしているのだ。その援助を国内の中間層・貧困層のために使えばどれだけの国民が助かったことか。
>著書「日本の経済政策」で失われた30年を検証した小林慶一郎・慶応大教授は「国も企業も目先の成果を追うことにこだわって道を誤った」と分析する。
新聞や財務省の御用学者の分析は的外れで増税と緊縮財政の理由付けに過ぎない。
>トリクルダウン起きず
>最大の誤りは、バブル崩壊後の1990年代以降、企業が長らく働き手をコストとしか見なさず、人員削減や正規から非正規雇用への切り替えなどを進めたことだ。
>当時は、中国の台頭などで経済のグローバル化が加速し、対応を迫られていた。国際競争力が低下する中、収益確保の「即効薬」としてリストラに走った。新卒採用も大幅に絞られ、いわゆる氷河期世代を生んだ。
>天然資源の乏しい日本が唯一の強みとしてきた人材基盤は大きく劣化した。2000年代以降の世界的なデジタル革命の波に乗り遅れ、革新的な商品やサービスを創出できなくなったのは、人材投資を怠ってきたツケだ。
指摘は正しい。企業が人材を大切にせず、リストラ、非正規雇用に走ったから人材がいなくなり、消費も減った。しかし国内がバブル崩壊で需要が激減しているのにそれ以外の方法はないだろう。国が積極財政で金を市場に流すしかなかったのだが、新聞は銀行救済に反対したのではなかったか。革新的な商品やサービスを創出できなくなったのは人材の劣化もあるが、それ以上に国内の需要不足だ。需要がないところに新しい商品やサービスは生まれない。
>政府・日銀の政策も的外れだった。大型の財政出動が繰り返されたが、景気刺激効果は一時的で国の借金を膨らませただけだった。
さらっと決めつけているがとんでもないことだ。大型の財政出動が行われた小渕恵三内閣では景気が回復しつつあったのだ。しかし森善朗もそれを踏襲したのだが、失言の連発で潰されてしまった。あと2年小渕恵三内閣が続いていれば不況から抜け出せたのではないか。
>小泉純一郎政権は「聖域なき構造改革」を旗印に不良債権処理を加速させたものの、経済を底上げできなかった。むしろ新自由主義的な発想で進めた雇用改革などが格差を拡大させ、消費者心理を悪化させた。
結局緊縮財政だからな。訳もわからず喝采した自分が恥ずかしくて仕方ない。日本の一等地や優良企業が外資に買われてしまった。小泉純一郎と竹中平蔵は間違いなく売国奴だ。
>約11年に及ぶ日銀の異次元の金融緩和策の副作用も大きい。脱デフレを掲げる第2次安倍晋三政権が推進したアベノミクスの看板政策だった。国債を大量購入し、市中に出回るお金の量を増やしたが、物価上昇率を2%に上げる目標をなかなか達成できなかった。
異次元の金融緩和は間違いではない。アベノミクスが失敗したのは緊縮財政だったからだ。消費税増税を決めたのは野田佳彦だが、安倍晋三もその路線に乗っかったのだ。消費税増税前の第二次安倍晋三政権は経済に薄日がさしていたが消費税増税と歳出抑制でおじゃんだ。第二次安倍晋三政権の7年8か月では1%しか経済が成長していないのだ。
>円高の是正や株価回復で潤ったのは輸出企業や富裕層ばかりで、恩恵が国民全体に広く行き渡るトリクルダウンは起きなかった。格差が広がり、経済や社会を支える中間層を細らせた。
法人税減税と株高で潤うのは輸出企業と富裕層だけだ。不況なのに消費税増税を強行すれば中間層・貧困層は生きていけなくなるに決まっているではないか。正気ではない。
> 「金利のない世界」が常態化したことで、政府は国債の金利負担を気にせず、バラマキ的な財政支出を続けた。
これが財務省の犬の大嘘なのだ。政府は積極財政などしていない。消費税増税に代表される緊縮財政を強行してきたのだ。財務省の犬の新聞に騙されてはいけない。消費税の廃止ないし減税が必要な局面なのだ。
>将来不安の払拭が必要
>多くの企業は資金調達が容易になったにもかかわらず、低収益の事業を継続した。リスクを覚悟で画期的な事業に挑むアニマルスピリットが失われた。
莫迦を言ってはいけない。需要がないところに新しい事業は生まれない。国が積極財政をしない限り企業は新しい事業に取り組むことはない。
>国の財政の悪化や、企業の人件費圧縮の姿勢は働き手の将来不安を高めた。年金や医療など社会保障制度の持続可能性が疑われ、所得も増えない中、個人消費が盛り上がらなかったのは当然だ。
財務省の犬はすぐこれだ。将来不安から消費が減ったわけではない。個人の財布の中身がないのだ。使おうにも使えるはずがないではないか。
>長期低迷から脱するためには何が必要か。
>小林教授は「働き手が安心して力を発揮できるよう、国や企業は不確実性の払拭(ふっしょく)に努めるべきだ」と指摘する。
>政府は財政規律を取り戻し、社会保障制度改革に真正面から取り組む。企業は社員教育など人材投資を強化する。こうした対応こそが求められている。
違う。長期低迷から脱するには政府の積極財政が必要なのだ。金がないことが日本の問題なのだから減税と財政出動で景気を良くするしかないのだ。財政規律と称して緊縮財政を続ければ失われた50年になる。財務省の犬毎日新聞に騙されてはいけない。
>経済的な事情などで希望する仕事に就けなかった人が、キャリアアップを目指せる仕組みも不可欠である。
>国は新たな知識や技能を身につけるリスキリングへの支援を打ち出す。企業や大学と連携を強め実効性を高めるべきだ。北欧のように全額を公費で賄い、無料で学べるようにするのも一案だろう。
>起業に失敗した若者らの再起を支える政策も充実させなければならない。
>人口が減り続ける日本が生き残るには、年齢や性別、国籍に関係なく、一人一人が活躍できる社会を構築するしかない。希望をもって働ける環境を取り戻すことこそが、失われた30年の教訓を生かす道である。
それに必要なものはなんだかわかるか。金だ。金がないから大学や研究機関が研究者を馘にせざるを得ないのだ。財務省が教育費、科学技術予算を増やす以外解決方法はない。財務省の犬の新聞はさらなる消費税増税を狙っている。それは絶対に阻止せねばならない。
財務省の犬の新聞のプロパガンダに騙されてはいけない。まずは新聞を不買・解約することだ。そうして財務省の犬に金を払って支えてはいけない。自分で自分の首を絞めるようなものだからだ。難しいが、家族友人親戚知人にも新聞の不買・解約を勧めて欲しい。プロパガンダの影響力を減らすにはそれが一番だからだ。
テレビも財務省の犬でしかない。ドラマやバラエティ、スポーツ、アニメは面白ければ見て構わない。つまらないなら消そう。そしてワイドショーは新聞に負けないほどのプロパガンダだ。消すしかない。
自民党は腐り果てたから政権交代しかないが、立憲民主党執行部も財務省の犬なのだ。単純に立憲民主党に政権交代しては民主党政権の二の舞だ。少数政党に投票して消費税減税機運を高めたい。選挙も家族親戚友人知人に投票を促して欲しい。政治に国民が関心を持つことが大事だからだ。
最後にランキングボタンを押してくれるようお願いする。ランキングが上がればより多くの人に読まれるし、私の気持ちも上向くからだ。













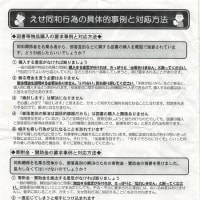
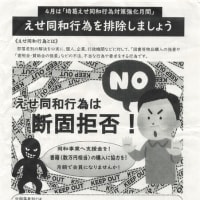
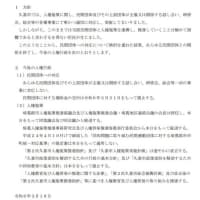
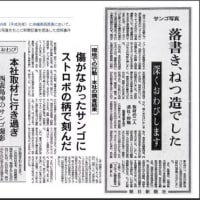

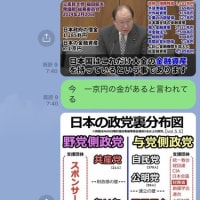
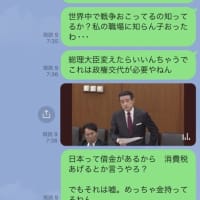
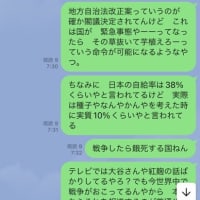
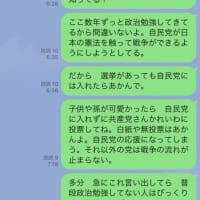
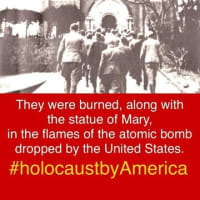







https://news.yahoo.co.jp/articles/7fb1cec6af03bdb21f49f0b0bc70eda29da1734f/