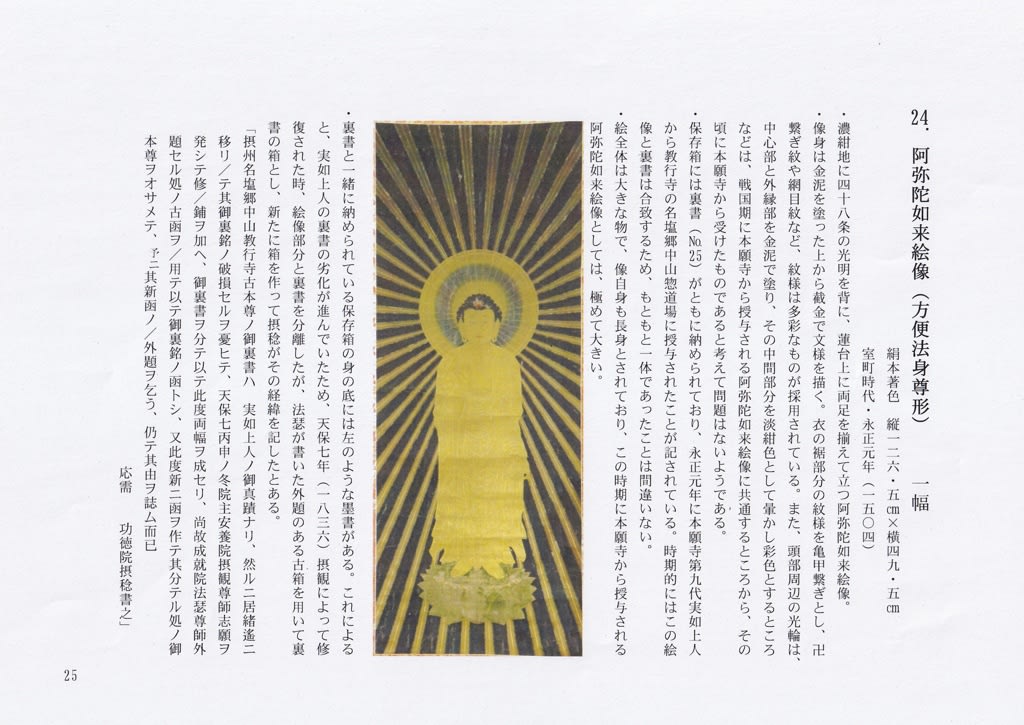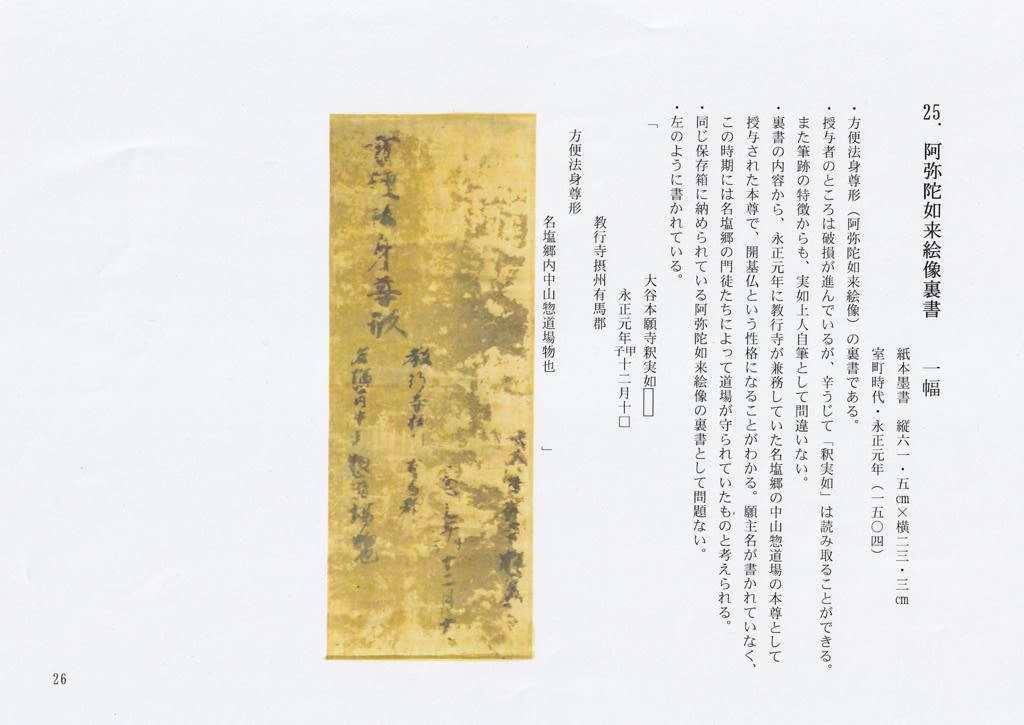住職の娘です。


5月18日(土)は浄土真宗本願寺派兵庫教区・神戸別院(モダン寺)の慶讃(きょうさん)法要のご縁にあわせていただきました。
浄土真宗・立教開宗800年、宗祖親鸞聖人ご生誕850年記念法要。
厳かな空気のもと勤修されました。
残念ながら、昨年、わたしはご本山での慶讃法要に参拝できませんでした。
ライブ配信を拝見していましたが、やはり空気が感じられません。
その点、この度の神戸別院における慶讃法要では道俗とも一体感のあるご唱和…有難い気持ちでお参りすることができました。
儀式の様式美があります。
また、多少難しくとも、有難い言葉を音にのせるというのは本当に素晴らしいです。

正直、ゴールデンウィークに肋骨を痛めて以来、外出も億劫だったのですが、お参りに行くことがてきて有り難かったです。
ちなみに、まだ大きく息を吸うと痛みがあるので、お勤めは厳しい状況です。
永代経法要の準備も…💦

ともあれ、どんな状況であろうと、こうして尊いご縁にあわせていただきましたこと、感謝申し上げます。
南無阿弥陀仏