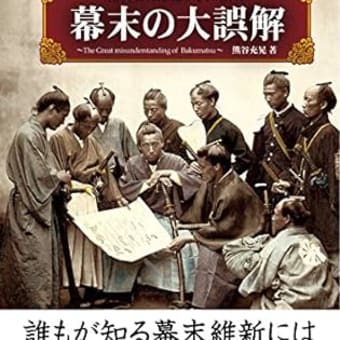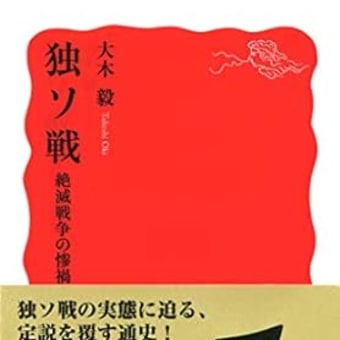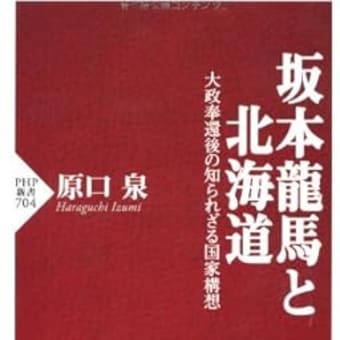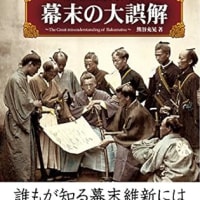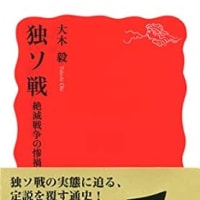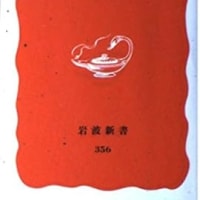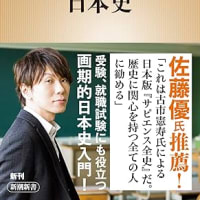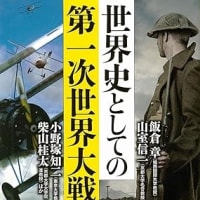小説家の望月が数々の古代の謎を解き明かし、その内容を小説として発刊するという小説。小説という形をとっているが、古代史の謎に対する自説提示である。その「自説」はあまりに面白いので、忘れてしまうには惜しい。可能な限り備忘録として書き留めておきたい。
1.稲作伝来の経路は、稲作適地ではない大陸北部経由ではなく、大陸から海伝いに直接日本列島へ、その後朝鮮半島へ。
2.倭人という呼び名は稲作を列島にもたらした呉の人々が自分たちを「ウォ」と名乗ったから。
3.大陸にあった勢力が「倭」と認識していた地域は、対馬海峡を挟んだ九州と朝鮮半島南部のことだった。
4.紀元前後の日本列島では、北九州、出雲、ヤマトが大きな3つの勢力だったが、ヤマトの勢力増大に対抗するため北九州は出雲と手を組んだ。出雲勢力はその後、ヤマト勢力に滅ぼされ、「山陰」と呼ばれ日陰者扱いされることになった。
5.古事記は国内向け、日本書紀は大陸の唐政権に提示するためのヤマト勢力、天武朝の正当性を訴えるための書物。古事記はヤマト勢力に多くの豪族たちを味方とするための各勢力の正当性を示す由来書のような性格。
6.スサノオは新羅から来たアマテラスの弟。アマテラスは天皇家の先祖、つまり天皇家は新羅由来となるが、真偽は不明。
7.皇祖神には天津神系(天皇家の祖先)と国津神系(豪族の祖先)がある。イザナギ、アマテラス、ニニギ、イワレヒコのラインが天津神系、スサノオは天津神系だったのが櫛名田姫と結婚して国津神系となった。しかしその後もニニギは国津神系のコノハナサクヤヒメと結婚、イワレヒコもウガヤフキアエズという天津神系が国津神系の玉依姫と結婚して神武天皇となるイワレヒコを産む。
8.全国にスサノオを祀る神社が数多いのは、出雲を代表する新羅勢力をヤマトの勢力が葬り去ったため、ヤマト勢力は祟りを恐れて多くの神社を建立した。
9.大化の改新は、味方につけてきた各豪族を天皇の配下に位置づける税制、法律、祭祀、外交、戸籍などの新ルール書作りだった。
10.北九州、出雲から始まった四隅突出型墳丘墓は日本海沿いに広がった新羅・出雲勢力の象徴。東北弁は出雲弁と同じ出自。
11.箸墓古墳の作られた年代は280年以降。書紀は「倭迹迹日百襲姫命」の墓としているが、それは卑弥呼ではなく壹與の墓。魏の使い張政は、卑弥呼の救援要請で呼ばれたが、到着したのは247年、翌年卑弥呼は死去した。箸墓は巨大墳墓であり、倭人伝の記述直径100歩とあまりに違いすぎる。卑弥呼の墓は北九州の平原遺跡。
12.纒向遺跡は秦氏が主導して200年ころに作られた大規模な都の跡。
13.「君が代」は北九州に君臨した王を讃えた歌。糸島郡には細石神社、桜谷神社の祭神は苔牟須売(コケムスメ)ノ神、博多湾には千代の松原がある。志賀島の志賀海神社の祝詞は「君が代」の歌詞と全く同じ。
14.邪馬臺国ではなく邪馬壹(ヤマイ)国。邪馬臺国はヤマトに存在したという主張を正当化するため江戸中期の学者松下見林が改ざん、新井白石も追認したため。
15.伊都国は糸島半島、奴国は博多近辺、邪馬壹国の場所は大分近辺。南には強力な敵対勢力の狗奴国があり、それが大和平野の南、和歌山あたりでは説明できない。「女王国の北に一大率を置き・・それは伊都国」との記述、東の海の向こうにある別の国、という説明も難しくなる。投馬国以降の里程は日数で表され、距離ではない。
16.対馬の神は日神で奈良に繋がり、壱岐の神は月神で京都につながる。いずれも秦氏がスポンサーとなっている。秦氏は技術者集団でもあり、製鉄、養蚕、機織り、酒造、塩田、灌漑、石積みなどを日本列島にもたらした。
17.秦氏と関わりが深いのは、松尾大社、稲荷社、八幡神社。奉納とは秦氏が納めたに由来する。
18.中臣氏は壱岐氏に由来、人と神の中を取り次ぐとして中津臣の姓を賜り、その後の藤原氏、そしての五摂家へとつながる。
19.「倭人伝」が伊都国をそっけなく形容しているのは、魏の直轄官を駐留させていたから。一大率とは魏にとっての大率を設置した場所だったから。
20.紀元前後から3世紀頃の大陸政権と倭国の力の差は圧倒的。倭国のメンバーは常に大陸勢力を意識していた。そのため、倭国は乱れていて、女王を立てないとまとまりが取れないほど情けない土地である、と本国に報告させていた。前漢、後漢、公孫氏、そして魏呉蜀の三国時代へと、政権交代ごとに大陸の様子を伺うように朝貢を重ねた。
21.日本書紀の記述と大陸の書物の間に矛盾が生じないよう、大変な苦労があった。中でも、神功皇后の存在は明確に魏志倭人伝における邪馬壹国の存在を意識している。応神が即位したのは70歳のときだが、仲哀が没した後、それまでの70年間は大王が不在。その期間こそが倭人伝が邪馬壹国について記述している時代と重なる。その矛盾を埋める存在が神功皇后。
22.神武東征の実態は、伊都国王がヒミコ死去のあと、壹與を伴い、数年をかけて瀬戸内海を東進して大和平野に至った事実に基づく。
小説内容は以上。
著者は小説家であるが、本書を書き上げるためにどれだけの書籍を読み漁ったのだろうか。そもそも小説だし、筆者も学者ではないから、正当な学説ではないことはもとより、何を書いても自由。だからこそ、思いつくまま、気がついたことはすべて注ぎ込んだのではないだろうか。だから読者は楽しめるし、古代史の謎解きとしてこれほどのエンターテインメント小説はないのではないかと思う。古代史ファンならば本書は必読と言いたい。