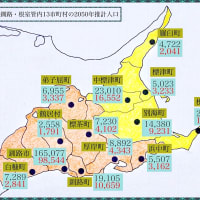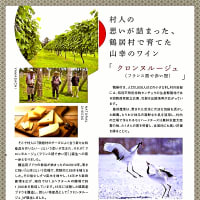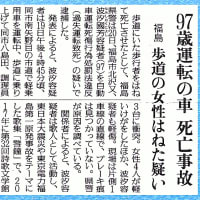第二期北太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)の一環で、日本沿岸の小型捕鯨業者で組織する「地域捕鯨推進協議会」が実施主体となって行われた釧路沖秋季調査捕鯨について、十一月二日、調査団は「期間中60頭のミンククジラを捕獲した」(11月3日付『釧路新聞』第1面)と、記者会見で発表した。調査は九月九日から十月三十日までで、市内の鮮魚店で「刺身用鯨肉は店頭にもう出ない」と言われ、急遽、女房に購入してもらった。
第二期北太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)の一環で、日本沿岸の小型捕鯨業者で組織する「地域捕鯨推進協議会」が実施主体となって行われた釧路沖秋季調査捕鯨について、十一月二日、調査団は「期間中60頭のミンククジラを捕獲した」(11月3日付『釧路新聞』第1面)と、記者会見で発表した。調査は九月九日から十月三十日までで、市内の鮮魚店で「刺身用鯨肉は店頭にもう出ない」と言われ、急遽、女房に購入してもらった。 春の鯨類捕獲調査が東日本大震災の影響で釧路沖に変更されたため、今年度は季節による変化も調査の目的の一つで、科学的成果が得られたという。例年に比べ気象状況が不安定で、調査日数が短かったが、「昨年と同程度となる144群150頭のミンククジラを発見」(同新聞)し、上限の六十頭を捕獲した。終日調査日数が昨年の二割に満たなかったにもかかわらず、上限枠の捕獲ができたことは、沿岸海域におけるミンククジラの資源量に問題がないことを示している。
春の鯨類捕獲調査が東日本大震災の影響で釧路沖に変更されたため、今年度は季節による変化も調査の目的の一つで、科学的成果が得られたという。例年に比べ気象状況が不安定で、調査日数が短かったが、「昨年と同程度となる144群150頭のミンククジラを発見」(同新聞)し、上限の六十頭を捕獲した。終日調査日数が昨年の二割に満たなかったにもかかわらず、上限枠の捕獲ができたことは、沿岸海域におけるミンククジラの資源量に問題がないことを示している。
沿岸海域での調査捕鯨の主たる目的は、鯨類の捕食が漁業資源に与える影響を調べることであり、その意味で、今年度の春季・秋季二回の釧路沖調査は有効だったと思われる。つまり、春季はスケソウやオキアミを捕食する未成熟の個体群がわずかに釧路沖に分布し、秋季には、カタクチイワシの魚群を追って多くの成熟個体が釧路近海に広範囲に現れることが分かった。サンマの補食がなかったことは、サンマ漁場が調査海域外に形成されたためだろう。今後、ミンククジラの生息数が増えれば、スケソウ・カタクチイワシ・サンマの資源量に影響が出ることは間違いない。カタクチイワシは日本で最も漁獲量の多い魚だが、食物連鎖の上でも他の動物にとって重要な魚種である。
最近の「社 会」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事