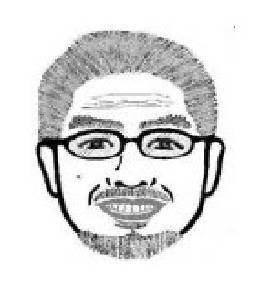この前、ある職場を訪問して待合室で待っていたら、
職場で何かしら騒ぎが起こっていた。聞くともなしに聞いていると、どうやらそこの上司がまだ作成途中の原稿をメールとして宛先に間違って送信してしまったらしく、その送信したメールを取り返したいと躍起になっているようである。「先方に失礼にあたるので何としてでも取り戻したい何とかしろ」と部下を叱咤激励している。どうやら大事なお得意さんらしい。部下が「送ってしまったメールは取り戻せません」と言うと、「そんな使い勝手の悪いものならシステムを直せ、使っているのは人間だ」とご立腹である。しかし、今すぐ直せるわけもなく、結局は丁重なお詫びと訂正のメールを改めて送ることで一件落着したようだ。
ここで上司が主張していることはごもっともである。
人間の使うシステムであれば、人間の使い勝手がいいように改善すべきである。しかし、ここでもう一つ突っ込んで考えてみると、一人の人間が使い勝手がいいと思っていることは、単にその人間がそう思っているだけであり、全ての人間のために使い勝手がいいという訳ではないし、そこまで考えを巡らしている訳でもない。そこに落とし穴がある。いい加減なのである。一番いい加減なのは「人間」なのである。そのいい加減な主張をみんな聞いて従っていたらせっかくのシステムが使い物にならないものになってしまう。
別にこの上司を責めているわけではないし、
この上司がすべていい加減だと言っているわけではない。人間とはいい加減な動物であり、それがまた人間の人間たる良さなのである。機械やコンピュータみたいに馬鹿でクソ真面目な人間は創造的な分野では使い物にならない。いちいち指図し命令してやらないと動けないような人間に高度で複雑な仕事は任せられない。そんなことができるのは人間がいい加減だからである。昔、人工知能(AI)の研究が盛んだった頃(今でも盛んかも知れないが)、この人間のいい加減さを追求した「ファジー」という言葉が流行った。わた菓子みたいに境界がぼんやりしてつかみ所がなく、かといって中心(本質)はしっかりと押さえられているような概念であろうか。
「ファジー」は結局あまり普及しなかったし、人工知能も下火になった。
コンピュータをファジーにしてしまうと、どんな結果が出るのか人間にも推測できなくなる。その結果を「こんな結果もあるんだな」と参考にし反省することはあっても、結局は何故このようになったかを分析しないと具体的な対策ができない。すなわち処理はファジーでやったが、その後でこのファジー部分を詳細に分析し直すことになる。そうであれば最初からファジー部分をなくしてきっちりと処理した方がいいことになる。結局はファジーは研究開発段階で有効な手法であるが、一旦知識体系ができてしまえばファジー部分もしっかりと定義してやらないと現実のシステムには使えないのである。ただし、結果がファジーでも許される分野は別だが・・・。
現実に使う道具はファジーであってはならない。
モノサシが計るたびに違ったり、同じ手順を踏んでも結果がやるたびに異なったりでは道具としては失格である。また、人間が要求した通りの結果が得られ、その結果も人間が推測できるものでなければならない。そして、試行錯誤を経てその要求が高度になればなるだけ結果もより精度と品質の高いものになるような道具が最高である。使い込めば使い込むほどいい仕事ができることになる。要求と180度違った結果ばかりが出て、何故そうなったかわからないのでは道具としては失格であり、こんな道具でいくら試行錯誤しても目標にはいつまでたっても到達しない。道具の役目を果たさないばかりか存在そのものが害を及ぼす。
コンピュータが馬鹿でクソ真面目なのは取り柄である。
馬鹿だと言うことは人間が結果を予測できることである。人間の能力を超え、人間に予測のできないような結果を出すようなコンピュータは研究開発段階で存在しても実用の段階では存在し得ない。存在しても人間が困ってしまう。コンピュータを扱う主人は人間である。クソ真面目であると言うことは、いい加減さが全くないことである。万が一起こり得るような間違いも一切犯してはならない。完璧にクソ真面目でなければならない。いい加減な分野は人間が担任する。人間もコンピュータもいい加減になってしまったら滅茶苦茶になってしまう。
話は例の上司の電子メールに戻って、
一旦送られた電子メールを送り主が相手のサーバーから削除できるようにする機能を追加することは可能である。しかし、不特定多数の利用者がサーバーの個人のファイルを直接削除するという危険な行為が日常茶飯事になされることになる。それだけでも危険であるが、こういう機能が追加されるとこの機能を積極的に悪用する輩が当然のごとく現れる。故意にサーバーの他人のファイルを削除してシステムを混乱させることが可能になる。システムを「人間の使い勝手がいい」ように改善するのは結構だが、もう一歩踏み込んで冷静に考えるととんでもない改善である場合もある。
それよりも、間違って送信したことは「人間」として素直に謝るべきである。
それは、コンピュータが悪いわけでもないし間違ったのは「人間」である。間違ったことの失礼は先方に謝罪のメールを送ればいいのである。間違ったことに対する対策は十分可能であり、何もシステムそのものを変更する必要はない。体裁やメンツや恥を考えているのは「人間」だけであり合理的なコンピュータは何とも思わないし、かえって間違いがあったことを明確にすることの意義のほうが重要である。間違いをごまかすのは許されないし間違ったメールを受け取った人間も寛容でなければならない。ただし、取り返しのつかない間違いもある。部外秘の情報を電子メールの同報機能で不特定多数に配信してしまったとか、口座振り込みの金額のゼロをひとつ多くつけてしまったとかである。「人間はいい加減な動物である」と言うことを肝に銘じて反省し教訓としなければならない。
すき焼きのたれの宣伝で「甘さも辛さもちょうどいい」というのがあるが、
誰にとって「ちょうどいい」のだろうと疑ってしまう。開発した人にとってなのか、国民全部の統計をとった結果なのか、単にいい加減に「ちょうどいい」と言っているのか、いずれにしてもファジーである。「ちょうどいい」のは個人毎に違うはずである。そうであれば不特定多数の消費者に売り出すすき焼きのたれは、少し味を直せば「甘さも辛さもちょうどいい」になるものであり、少し味を直す作業は個人毎に個別にやらなければならない。この個人毎に個別にやるべき機能を満足していない「道具」は失格である。
反対に、あれも便利これも便利と機能を継ぎ足した道具はかえって不便である。
便利と思っているのは一部の人であり、すべての人が便利だとは思っていない。また、ひとつの道具ですべての仕事をする必要はないのである。そういう道具をいっぱいつけられてもほとんどの道具は使わないままになってしまうし、逆に使いたい道具は中途半端で使いづらい。中途半端とは変なところで機能が限定されて肝心なところで応用が利かないのである。目的や用途を絞り込んで本当に必要な機能を実現した道具は使いやすいし、そういう道具は利用者のレベルに合わせて使い勝手を選択できるようになっている。使い込めば使い込むほど使い勝手が良くなる。
職場で何かしら騒ぎが起こっていた。聞くともなしに聞いていると、どうやらそこの上司がまだ作成途中の原稿をメールとして宛先に間違って送信してしまったらしく、その送信したメールを取り返したいと躍起になっているようである。「先方に失礼にあたるので何としてでも取り戻したい何とかしろ」と部下を叱咤激励している。どうやら大事なお得意さんらしい。部下が「送ってしまったメールは取り戻せません」と言うと、「そんな使い勝手の悪いものならシステムを直せ、使っているのは人間だ」とご立腹である。しかし、今すぐ直せるわけもなく、結局は丁重なお詫びと訂正のメールを改めて送ることで一件落着したようだ。
ここで上司が主張していることはごもっともである。
人間の使うシステムであれば、人間の使い勝手がいいように改善すべきである。しかし、ここでもう一つ突っ込んで考えてみると、一人の人間が使い勝手がいいと思っていることは、単にその人間がそう思っているだけであり、全ての人間のために使い勝手がいいという訳ではないし、そこまで考えを巡らしている訳でもない。そこに落とし穴がある。いい加減なのである。一番いい加減なのは「人間」なのである。そのいい加減な主張をみんな聞いて従っていたらせっかくのシステムが使い物にならないものになってしまう。
別にこの上司を責めているわけではないし、
この上司がすべていい加減だと言っているわけではない。人間とはいい加減な動物であり、それがまた人間の人間たる良さなのである。機械やコンピュータみたいに馬鹿でクソ真面目な人間は創造的な分野では使い物にならない。いちいち指図し命令してやらないと動けないような人間に高度で複雑な仕事は任せられない。そんなことができるのは人間がいい加減だからである。昔、人工知能(AI)の研究が盛んだった頃(今でも盛んかも知れないが)、この人間のいい加減さを追求した「ファジー」という言葉が流行った。わた菓子みたいに境界がぼんやりしてつかみ所がなく、かといって中心(本質)はしっかりと押さえられているような概念であろうか。
「ファジー」は結局あまり普及しなかったし、人工知能も下火になった。
コンピュータをファジーにしてしまうと、どんな結果が出るのか人間にも推測できなくなる。その結果を「こんな結果もあるんだな」と参考にし反省することはあっても、結局は何故このようになったかを分析しないと具体的な対策ができない。すなわち処理はファジーでやったが、その後でこのファジー部分を詳細に分析し直すことになる。そうであれば最初からファジー部分をなくしてきっちりと処理した方がいいことになる。結局はファジーは研究開発段階で有効な手法であるが、一旦知識体系ができてしまえばファジー部分もしっかりと定義してやらないと現実のシステムには使えないのである。ただし、結果がファジーでも許される分野は別だが・・・。
現実に使う道具はファジーであってはならない。
モノサシが計るたびに違ったり、同じ手順を踏んでも結果がやるたびに異なったりでは道具としては失格である。また、人間が要求した通りの結果が得られ、その結果も人間が推測できるものでなければならない。そして、試行錯誤を経てその要求が高度になればなるだけ結果もより精度と品質の高いものになるような道具が最高である。使い込めば使い込むほどいい仕事ができることになる。要求と180度違った結果ばかりが出て、何故そうなったかわからないのでは道具としては失格であり、こんな道具でいくら試行錯誤しても目標にはいつまでたっても到達しない。道具の役目を果たさないばかりか存在そのものが害を及ぼす。
コンピュータが馬鹿でクソ真面目なのは取り柄である。
馬鹿だと言うことは人間が結果を予測できることである。人間の能力を超え、人間に予測のできないような結果を出すようなコンピュータは研究開発段階で存在しても実用の段階では存在し得ない。存在しても人間が困ってしまう。コンピュータを扱う主人は人間である。クソ真面目であると言うことは、いい加減さが全くないことである。万が一起こり得るような間違いも一切犯してはならない。完璧にクソ真面目でなければならない。いい加減な分野は人間が担任する。人間もコンピュータもいい加減になってしまったら滅茶苦茶になってしまう。
話は例の上司の電子メールに戻って、
一旦送られた電子メールを送り主が相手のサーバーから削除できるようにする機能を追加することは可能である。しかし、不特定多数の利用者がサーバーの個人のファイルを直接削除するという危険な行為が日常茶飯事になされることになる。それだけでも危険であるが、こういう機能が追加されるとこの機能を積極的に悪用する輩が当然のごとく現れる。故意にサーバーの他人のファイルを削除してシステムを混乱させることが可能になる。システムを「人間の使い勝手がいい」ように改善するのは結構だが、もう一歩踏み込んで冷静に考えるととんでもない改善である場合もある。
それよりも、間違って送信したことは「人間」として素直に謝るべきである。
それは、コンピュータが悪いわけでもないし間違ったのは「人間」である。間違ったことの失礼は先方に謝罪のメールを送ればいいのである。間違ったことに対する対策は十分可能であり、何もシステムそのものを変更する必要はない。体裁やメンツや恥を考えているのは「人間」だけであり合理的なコンピュータは何とも思わないし、かえって間違いがあったことを明確にすることの意義のほうが重要である。間違いをごまかすのは許されないし間違ったメールを受け取った人間も寛容でなければならない。ただし、取り返しのつかない間違いもある。部外秘の情報を電子メールの同報機能で不特定多数に配信してしまったとか、口座振り込みの金額のゼロをひとつ多くつけてしまったとかである。「人間はいい加減な動物である」と言うことを肝に銘じて反省し教訓としなければならない。
すき焼きのたれの宣伝で「甘さも辛さもちょうどいい」というのがあるが、
誰にとって「ちょうどいい」のだろうと疑ってしまう。開発した人にとってなのか、国民全部の統計をとった結果なのか、単にいい加減に「ちょうどいい」と言っているのか、いずれにしてもファジーである。「ちょうどいい」のは個人毎に違うはずである。そうであれば不特定多数の消費者に売り出すすき焼きのたれは、少し味を直せば「甘さも辛さもちょうどいい」になるものであり、少し味を直す作業は個人毎に個別にやらなければならない。この個人毎に個別にやるべき機能を満足していない「道具」は失格である。
反対に、あれも便利これも便利と機能を継ぎ足した道具はかえって不便である。
便利と思っているのは一部の人であり、すべての人が便利だとは思っていない。また、ひとつの道具ですべての仕事をする必要はないのである。そういう道具をいっぱいつけられてもほとんどの道具は使わないままになってしまうし、逆に使いたい道具は中途半端で使いづらい。中途半端とは変なところで機能が限定されて肝心なところで応用が利かないのである。目的や用途を絞り込んで本当に必要な機能を実現した道具は使いやすいし、そういう道具は利用者のレベルに合わせて使い勝手を選択できるようになっている。使い込めば使い込むほど使い勝手が良くなる。