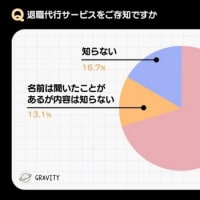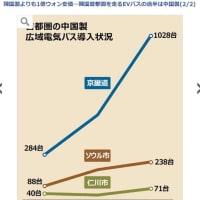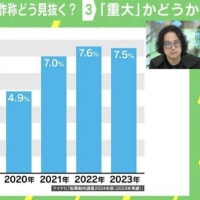【書評】ジェットエンジンに取り憑かれた男 前間孝則著
この本の主題となる人物は永野治氏(1911年10月9日-1998年2月22日(87没)だ。旧東京帝大卒であるがその当時から海軍委託学生であり、卒業後は航空廠(国家が行った兵器開発部門)へ配属し、終生ジェットエンジン開発を進めた技術者だ。
戦中から、海外でジェットエンジンの開発が進められているとの情報を知り、日本でも開発気運が高まって来ていた。当時最先端で開発を進めていたのが同盟国ドイツであり、日独潜水艦交易で僅かな断片情報が得られる中で、永野らも独自開発を続け敗戦間際に僅か数十分の試験飛行に成功(橘花)したところで敗戦となる。

敗戦後7年を経てサンフランシスコ講和条約が成立し、やっと再び日本は独立国になった。ただし、同時に交わされた日米安保条約の成立と共に、真の独立国になったかは、いささか懐疑的ではあるが・・・。そして、航空技術の開発も再開されることなり、永野も航空技術者として米軍のライセンス生産とか機体保守の経験から、独自の国産ジェットエンジンの開発を再スタートさせた。しかし、この独自開発は難航しつつ1959年に初号機が完成、1960年に初飛行が成功した。
この時点くらいまで永野の所属企業は石川島重工であったが、1960年12月に石川島重工は播磨造船と合併し、石川島播磨重工(現在のIHI)となった。その後、石川島播磨重工では、自衛隊納入の米軍戦闘機などの国産化を進めた。
この本で知ることとして、戦前永野が所属していた組織は空技廠という航空関連の開発組織だった様だ。この様な国家としての戦略技術の研究機関や製造、人員養成のための機関といえば、戦中は海軍工廠は全国各地に設営されたり、海軍工作学校、陸軍登戸研究所、陸軍中野学校、鉄道技術研究所などなど、あったことを予て多種の本や地方の近代史などから知るところだったが、その一種なのだろう。
戦後の永野は、石川島重工に所属しつつ、ジェットエンジンの開発を進めるのだが、石川島から永野を招いたのが、あの土光敏夫だと知った。土光と云えば、石川島社長から東芝社長を経て、経団連会長となり高名な第2臨時行政調査会の会長として知るところだ。その土光も、元来は永野と同じくタービン技術開発者であったことを今更ながら知るところだ。
また、永野に戻るが、IHIを退いた後も、若手技術者を集め勉強会を開催したりと終生に渡り技術者の思考を忘れなかったと云うことが記されている。一方、さまざまな書籍にも触れつつ、教養高い人物であったこととして、下記のウェルズの書籍から引いた言葉を座右の銘として発していたという。
HGウェルズ 世界史大系(Outline of History)の中で引いてるロジャーベーコン(13世紀のイギリスの哲学者)の説いたところ。それは、「人間世界の諸悪は無知によるものであり、無知の根源は➀権威崇拝、②習慣、③群集心理、④虚栄心の4つだと指摘している。そして自分の目で世界を見なさい」と説いている。
日本のジェットエンジン技術も高度化しつつあり、現在のジェットエンジン世界市場の占める3大メーカーは、GE、プラット&ホイットニー、ロールスロイスの3社は変わらぬが、日本はその部品サプライヤーとして欠かせぬ位置にいる。しかし、日本独自の量産旅客機が三菱スペースジェットが生まれようとしたが、やや悲観的な状況に陥っている。
ジェットエンジンについては、量産という意味では未だ花開かない状態だ。ただ、IHI開発のXF9というエンジンが、10年を超える開発期間を経て、ほぼ完成の域に達し様としている様だ。XF9は戦闘機用低バイパス比ジェットエンジンで、水力11トン(アフターバーナー使用時15トン)、推力偏向ノズル付きと最先端のテクノロジーが盛り込まれているものだ。
戦後の産業史を顧みて、日本はまず造船でトップに成り上がるが、今や造船は斜陽産業だ。そして、80年代にトップとなった電子産業と自動車だが、電子産業は空洞化しつつ、残された自動車は今や大きな岐路を迎えている。このまま日本の全車両メーカーが生き残るのは難しい様に思えるし、生き残ったとしても製造を日本で続けられるか不透明さが拡大しつつある様に感じる。
この本の主題となる人物は永野治氏(1911年10月9日-1998年2月22日(87没)だ。旧東京帝大卒であるがその当時から海軍委託学生であり、卒業後は航空廠(国家が行った兵器開発部門)へ配属し、終生ジェットエンジン開発を進めた技術者だ。
戦中から、海外でジェットエンジンの開発が進められているとの情報を知り、日本でも開発気運が高まって来ていた。当時最先端で開発を進めていたのが同盟国ドイツであり、日独潜水艦交易で僅かな断片情報が得られる中で、永野らも独自開発を続け敗戦間際に僅か数十分の試験飛行に成功(橘花)したところで敗戦となる。

敗戦後7年を経てサンフランシスコ講和条約が成立し、やっと再び日本は独立国になった。ただし、同時に交わされた日米安保条約の成立と共に、真の独立国になったかは、いささか懐疑的ではあるが・・・。そして、航空技術の開発も再開されることなり、永野も航空技術者として米軍のライセンス生産とか機体保守の経験から、独自の国産ジェットエンジンの開発を再スタートさせた。しかし、この独自開発は難航しつつ1959年に初号機が完成、1960年に初飛行が成功した。
この時点くらいまで永野の所属企業は石川島重工であったが、1960年12月に石川島重工は播磨造船と合併し、石川島播磨重工(現在のIHI)となった。その後、石川島播磨重工では、自衛隊納入の米軍戦闘機などの国産化を進めた。
この本で知ることとして、戦前永野が所属していた組織は空技廠という航空関連の開発組織だった様だ。この様な国家としての戦略技術の研究機関や製造、人員養成のための機関といえば、戦中は海軍工廠は全国各地に設営されたり、海軍工作学校、陸軍登戸研究所、陸軍中野学校、鉄道技術研究所などなど、あったことを予て多種の本や地方の近代史などから知るところだったが、その一種なのだろう。
戦後の永野は、石川島重工に所属しつつ、ジェットエンジンの開発を進めるのだが、石川島から永野を招いたのが、あの土光敏夫だと知った。土光と云えば、石川島社長から東芝社長を経て、経団連会長となり高名な第2臨時行政調査会の会長として知るところだ。その土光も、元来は永野と同じくタービン技術開発者であったことを今更ながら知るところだ。
また、永野に戻るが、IHIを退いた後も、若手技術者を集め勉強会を開催したりと終生に渡り技術者の思考を忘れなかったと云うことが記されている。一方、さまざまな書籍にも触れつつ、教養高い人物であったこととして、下記のウェルズの書籍から引いた言葉を座右の銘として発していたという。
HGウェルズ 世界史大系(Outline of History)の中で引いてるロジャーベーコン(13世紀のイギリスの哲学者)の説いたところ。それは、「人間世界の諸悪は無知によるものであり、無知の根源は➀権威崇拝、②習慣、③群集心理、④虚栄心の4つだと指摘している。そして自分の目で世界を見なさい」と説いている。
日本のジェットエンジン技術も高度化しつつあり、現在のジェットエンジン世界市場の占める3大メーカーは、GE、プラット&ホイットニー、ロールスロイスの3社は変わらぬが、日本はその部品サプライヤーとして欠かせぬ位置にいる。しかし、日本独自の量産旅客機が三菱スペースジェットが生まれようとしたが、やや悲観的な状況に陥っている。
ジェットエンジンについては、量産という意味では未だ花開かない状態だ。ただ、IHI開発のXF9というエンジンが、10年を超える開発期間を経て、ほぼ完成の域に達し様としている様だ。XF9は戦闘機用低バイパス比ジェットエンジンで、水力11トン(アフターバーナー使用時15トン)、推力偏向ノズル付きと最先端のテクノロジーが盛り込まれているものだ。
戦後の産業史を顧みて、日本はまず造船でトップに成り上がるが、今や造船は斜陽産業だ。そして、80年代にトップとなった電子産業と自動車だが、電子産業は空洞化しつつ、残された自動車は今や大きな岐路を迎えている。このまま日本の全車両メーカーが生き残るのは難しい様に思えるし、生き残ったとしても製造を日本で続けられるか不透明さが拡大しつつある様に感じる。