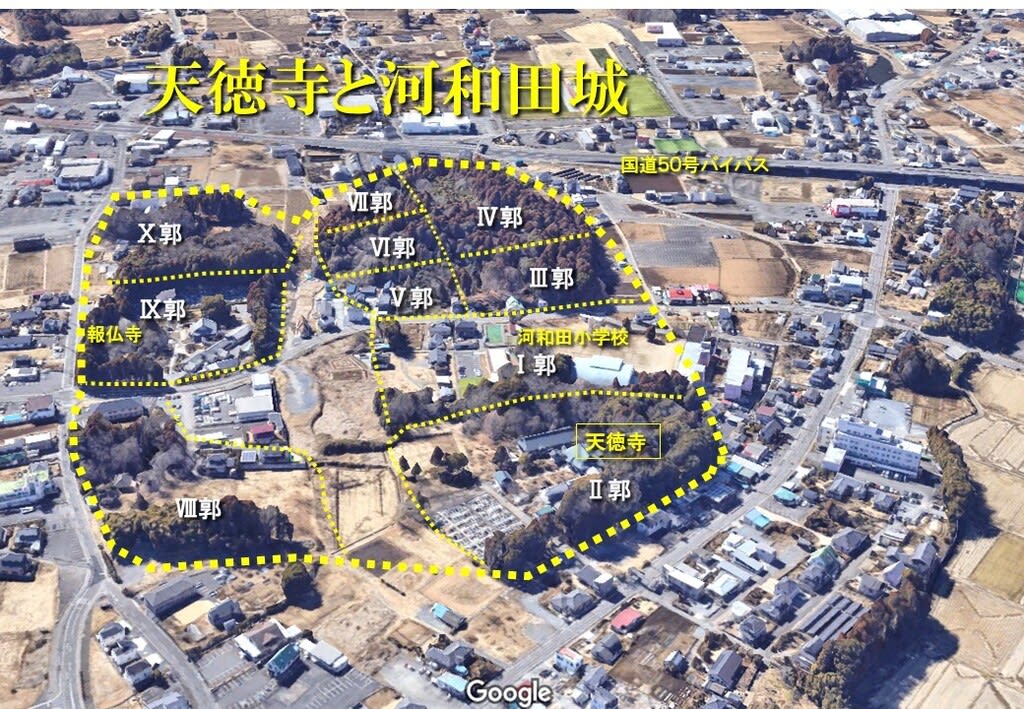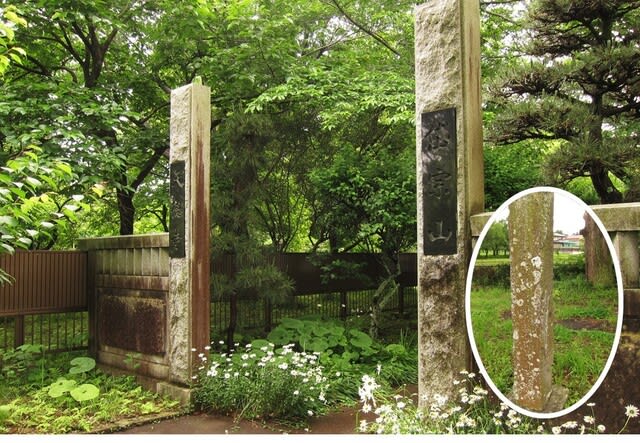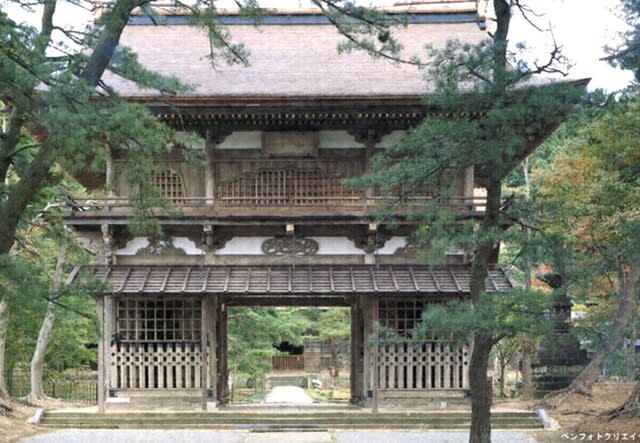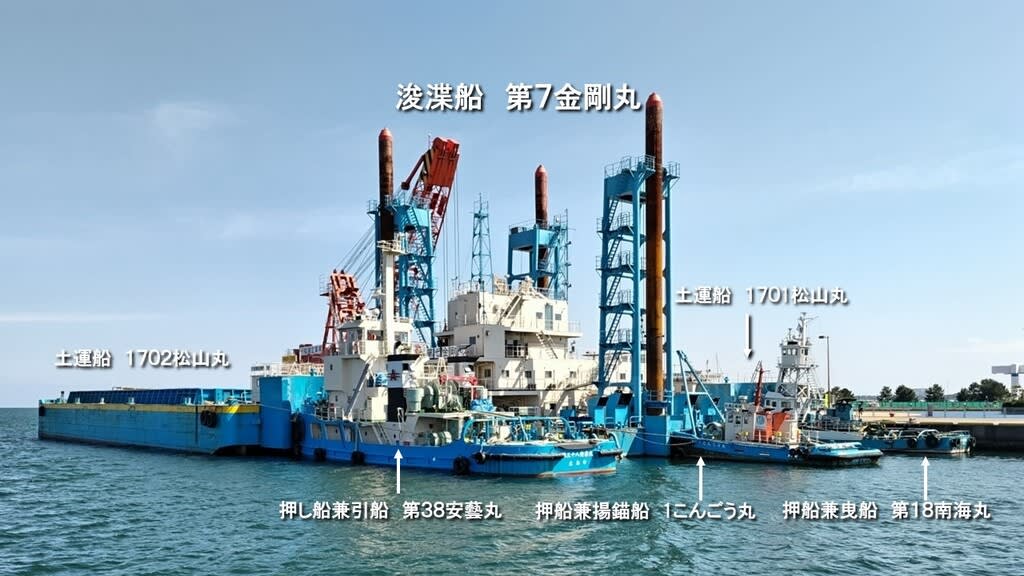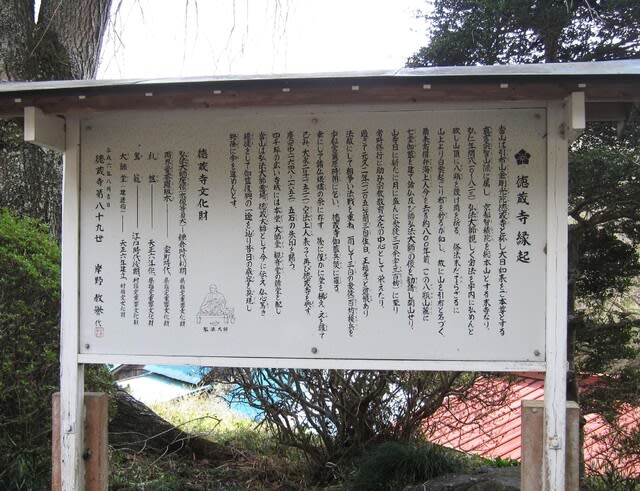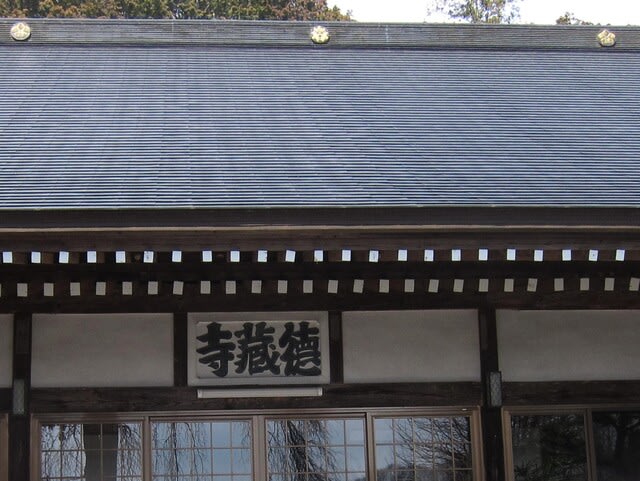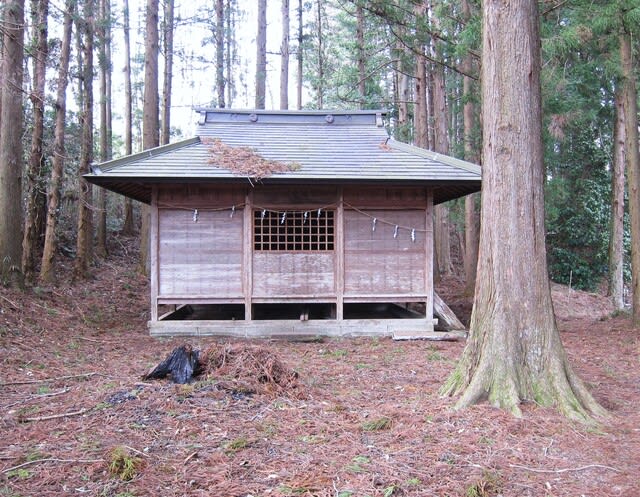5月末の偕楽園は、むせかえるような緑に囲まれていました。

周りの緑地帯を含めての偕楽園公園は300へクタールの広さで、都市公園では世界第二位とされます。その中心にある千波湖は、偕楽園の借景としての池、そして水戸城の大きな水堀の役目を果たしました。

春に梅の花を愛でた梅林はこの時期、青梅が鈴なり……ところがびっくり!!梅林を歩いてみると梅の実がほとんど見当たりません。鈴なりどころか探してみても、やっと数個が目に付く有様です。

たまたま作業中の方にお聞きしたところ、今までにないほどの絶不作と言っておられました。これは全国的な状況のようで、和歌山の南高梅も平年の3割以下の収穫で価格が高騰、埼玉県の越生では梅直売のイベントを中止などがニュースでも報じられていました。

この不作の原因は、暖冬で梅の開花が早かったため、花がまだ不完全の状態で雌しべなどが機能しなかったり、また受粉を媒介する昆虫類がまだ活動してなかったからといわれています。それと去年が豊作だったために、いわゆる「隔年結実」の影響もあるかもしれません。

何とか数個の実を付けている梅の樹は、ほとんどが「実生野梅」という原種の梅で、しかも老木が多いような気がしました。

意気軒高な老木に敬意を表して、梅の実と生っている老体の写真を並べてみました。頑張れ御同輩!です。
毎年、収穫した偕楽園の梅は6月上旬に市民の方に販売されます。今年も6月8日(土)に販売され、1キロ袋入りが200円、お一人1袋限り先着1000名様という告知が出ましたが、その数が揃うのかなと心配してしまいます。

そもそも偕楽園には約3000本、弘道館は約800本という梅の樹がありますが、そのうち約4割は花ウメという観賞用の梅で、ほとんど実が生りません。それでも両園合わせて20トン収穫の年もありましたが、近年はだんだん減少し豊作の昨年も約10トンでした。※梅の実落としの写真は以前撮影のものです。
また水戸市では梅の花ばかりでなく実の生産地としても名を高めようと、いまジョイント仕立てという梅の栽培法を奨励しており、この成果が「ふくゆい」というブランド名で市場に登場しています。

これは主枝を隣の木と接いで何本もの木を直線状の集合木として栽培する方法で、5年で成木並みの収穫と施肥、管理、作業の効率化が図れるとされます。※ジョイント支柱の写真は以前撮影のものです。
さて園内を歩いてみると、梅林や散策道には季節の花が顔を見せていました。

足元にはムラサキカタバミ(紫片喰)、南米原産の帰化植物が野性化し環境省の要注意外来生物に指定されていますが、攘夷を主張した偕楽園創設者の斉昭公もこの可愛さでは許してくれるでしょうか。

南崖の斜面には咲き始めたホタルブクロの釣鐘状の薄い赤紫色が鮮やかです。

向学立志の像は、辞書を手にした旧制水戸高校生の高下駄とマント姿です。20年くらい前までは高齢の卒業生がマント姿で梅まつり期間中に参集していましたが、さすがに見かけなくなりました。

足元の花はシモツケ(下野)です。隣県のシモツケ(栃木県)で発見されたのが命名由来の落葉低木です。

緑が濃くなるこれからの時期、しばらくの間は静かな園内になりますが、182年前に斉昭公が開園した当時を偲んだり、梅の老木を鑑賞したり…、また違った偕楽園の顔を見つけることができることでしょう。