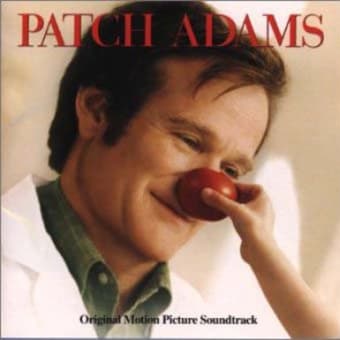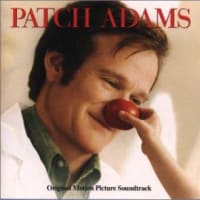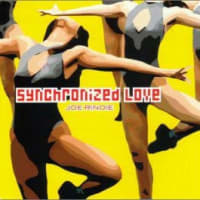「人の子よ、汝一片の木を取りその上にユダおよびそのともなるイスラエルの子孫と書き、また一片の木を取りその上にヨセフおよびそのともなるイスラエルの全家と書くべし。・・しかして汝これを供に合わせて一本の木となせ。・・我イスラエルの子孫をその往けるところの国々より出し、四方よりかれを集めてその地に導き、その地において汝らを一つの民となしてイスラエルの山々に居らしめん。・・再び二つの国に分かれざるべし。彼等また・・身を汚すことあらじ。・・」
(エゼキエル書第37章16~23節)
そうですか,そうですか......では始めましょう。
サンカのことは謎に包まれております。出エジプト記のはるか前にゴシェンの地にセム族が住んでいました。そんなことからリンク先の皆様のご協力を戴きながら神代文字の分析を含めて連載していきましょう。読者の皆様の研究成果も期待しております。たった一人のエチオピア女性から人類は始まりサハラ砂漠との死闘をへてシュメール,ゴシェンなどへ移動したと考えられますので日本からゴシェンの地に移動したとは今のところ考えられませんがそうとも言えない資料も多く発見されています。

漢字が流入する前の【古代日本文字】山窩(サンカ)文字
http://bit.ly/rqcqPb
ルーツは縄文時代から日本に存在した原日本人であるようで、渡来人によるとされる弥生文明、大和朝廷による中央集権の軍事的敗者なのかも知れません。
山窩とは、明治以降の官憲用語であり、差別的な意を含むと言われていて、身殻別八万物運(ミカラワケヤヨロヅノモノハコビ)が正しい呼び方とされています。
古代日本と山窩
封印された古代文字
これはヘブライ語
米国の作家で,南イリノイ大學教授のLionel Bender氏はWadai-Darfur=Language in Ethiopiaの論文でSemitic Language(セム語=アラム語)のエチオピア起源説を発表したように言語学者は歴史学者であり考古学者でなければならない典型だと思います。
以下の原文は管理人様の許可を得て引用・解説・要約をいたしますが原文を尊重してあります。
(一)プロローグ
明治時代になり鎖国を解いた日本へと渡って来た欧米の人々は、原始的なアジア人の国との先入観を打ち砕かれることになった。それと同時に、マルコポーロによりもたらされた黄金の国という幻想も破壊されたに違いない。
しかし中でも所謂ユダヤ人と呼ばれる系統の人々は、東洋の果ての小さな異国で自分たちとの不思議な共通点や何とも言えない懐かしさを感じ、驚き喜んだ。
何故ならば彼らユダヤ人には、古代に失われたとされる部族の同胞があり、世界中を放浪し離散しながらも消失した同胞を探し求め続けていたからだ。
安住の地に国家を築いていた時代は歴史の彼方に消え、南北に分裂したユダヤ人国家は強大な帝国により滅亡させられた。
帝国の捕囚から解放されても、彼らに安住の地は与えられず(モーゼを指導者として)四十年以上も砂漠を彷徨い続けたユダヤ人にとって、神との契約が唯一の希望の光であった。
モーゼは羊の群れを先導し「神の山」に来た。注:このシナイ山は間違っているので改めて記事にします。
聖書ものがたり・出エジプト記参照
その彼らが歴史の闇に埋もれた同胞を探し求めるのも、何時かは総てのユダヤ民族が一同に集められるとする神との約束の故であったのだろう。
先の大戦で悪名高いホロコーストをはじめ数々の迫害や差別を乗り越えて、遂にユダヤ人の国『イスラエル』が建国されたのは20世紀に入ってからだった。現在もその立地や建国の経緯によって、周辺のアラブ諸国との摩擦が耐えない。
それはさて置き私達日本人と日本、ユダヤ人との何か不思議な関係については興味が尽きないのも事実である。
今回のシリーズでは『ユダヤ人と日本人の秘密』水上 涼(著)や『古代日本・ユダヤ人渡来伝説』坂東 誠(著)の主張を中心に私なりにこの謎にチャレンジしてみたい。
そもそものユダヤ人(ヘブライ人)とは黒髪に黒い瞳の民族であるとされ、現在みられる白人系のユダヤ人は古代にコーカソイド系の国家が丸ごとユダヤ教に改宗して誕生したものらしい。
何故に日本人を見て彼らが『失われた十部族』を連想するのか、これでお分かりになるだろう。本来のユダヤ人とは私達、日本人と同様の外見を有しているからだ。
勿論それだけなら他にも同様の外見をした人々は存在する、が重要なのはその文化であり、日本人の慣習などに古代ユダヤと共通点が多く存在するからである。
来日したユダヤ系の人々は、まず日本人の外見に驚き、その風俗を知って更に驚いた。
彼らにとってみれば日本と日本人を知れば知るほど、失われた同胞の子孫を連想させる多くの痕跡に出会い、感激と親愛の情が湧きあがったのである。
詳しくは知らないが、彼のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)もユダヤ人であり、ハーンに日本への帰化と永住を決意させたのも、この感情だったのかも知れない。
『失われた十部族』とは、ユダヤ十二部族の内の一部なのだが、ルペン族、ダン族、イッサカル族、マナセ族、エフライム族、ゼブルン族、アシュエル族、ナフタリ族、ベニヤミン族、レビ族などである。
これらの部族は統一国家イスラエルを形成していたが、やがて分裂してイスラエルは北のイスラエル王国と南のユダ王国とに袂を分かつ。
アッシリアからの侵略により、北のイスラエル王国が滅亡し、その時に先に挙げた10部族が行方不明となった。やがて有名なバビロンの虜囚により南のユダ王国も滅亡し、残った人々がユダヤ人と呼称されるようになった。
それ以来ユダヤ人は離散し、世界に散っていたが1948年のイスラエル建国によって二千年振りに国家を形成するに到った。
北イスラエルを構成していたのは先に挙げた失われた十部族が主だが、無論のこと部族ごとに完全に分かれていたとは考え難い。イスラエルの12部族は各々に得意技があり、どの技も生活に欠かせないものであれば、両方の王国に総ての部族が居住していていたと考える方が自然だ。
恐らくは主だった部族の根拠地が、北のイスラエルと南のユダにそれぞれ存在しており、北には10部族の、南には2部族の根拠地が在ったと考えるのが妥当であろう。
北のイスラエル王国が滅亡した時に、姿を消した10部族を残された2部族が探し求めている。その気持ちは伝統的にユダヤ人に継承されており、東洋の島国日本を訪れた時に、彼らをして日本と日本人に注目させたのであろう。
ユダヤ教のラビの研究報告や、イスラエル大使の伊勢神宮参拝の事実、噂の域を出ないが正式なイスラエルの調査団が来日したこともあったようだ。
歴代イスラエル大使が参拝するという伊勢神宮には、イスラエル国旗にデザインされているダビデ王の紋章が数多く存在している。(管理人注:六芒星などは戦後つけられたもの)
伊勢神宮の六芒星参照
無論のこと世界には、自分達こそ失われた十部族の末裔だと名乗る人々が存在する。
アフガニスタンやグルジアの一部にも、同様の習慣や伝説を持つ人々が居るらしい。
古代世界では私達が想像する以上に、人々の移動は広範囲に及んでいる。
北イスラエル王国がアッシリア帝国により滅亡した時、ユダヤの人々はユーフラテス川の東側に集められたという。それ以後には歴史から消えてしまったこの人々だが、やはり各地を放浪したらしく、研究者によればカスピ海にもその痕跡が確認できるという。
各地に居住しその文化的慣習の名残を留めつつ、その地に定住せずに更に新天地を求めて旅立った人々も存在したのだろう。勿論、その地に定住した人々もいたに違いないが、
更に東進した人々が最終的にたどり着いた地が日本だったのではあるまいか。
シルクロードの最終地点とされる地も日本である事実を考えれば、古代世界に於いて旅の終着点が日本列島であったと考えることは自然であろう。
旧約聖書によればイスラエルの始祖はアブラハムであり、イサク、ヤコブと続き、ヤコブの十二人の子供が十二部族の祖となったとされている。
イスラエルの意味は「神に勝つもの」だそうで、ヤコブが天使と試合をしてこれを打ち負かしたので天使は「お前は今後、イスラエルと名乗れ」と言って去ったというエピソードに由来しているとされる。
アダムからイエスまでの血統図
現代のユダヤ人はスペイン系のセファラディと東欧系のアシケナジに大別されるが、この現在のユダヤ人の大半を占めるアシケナジはずっと後に(8世紀)に改宗したカザール人の子孫であるらしい。
アラブ人の祖イシュマエルの子孫
話しはまた聖書に戻るが出エジプト記で神はモーゼに対して、一々ご丁寧にも私はアブラハムの神でありイサクの神でもあり、ヤコブの神だと名乗っている下りがあるらしい。
何故にそんな風に名乗るのか、と考えれば、アブラハム、イサク、ヤコブはひとつの系統ではなく別々の系統の民族ではなかったかとの考えに行き当たる。
またヤコブが子である十二部族に示した祝福が、また奇妙にも別け隔てが激しく明らかに悪意に満ちている様な内容のものがある。
中でもダンは道のかたわらのヘビとか、イッサカルは奴隷となって追い使われる、ベニヤミンは引き裂く狼などと、とても祝福とは思えぬ内容である。
これらは、やはりイスラエル人も多民族で構成されていたであろうと、予想させるに十分な証拠ではないだろうか。
聖書を編纂したのはユダ族であるが、ヤコブが異民族の召使に産ませた子供もおり、十二部族の間にも身分の差が在ったのだろう。
この様にユダヤ人の系譜も実は複雑であり、単一でなかったことが伺える。中にはエジプト系の人々のように肌の浅黒い種族も居たに違いない。
あたかもユダヤ人が単一の民族であるかの様に見せかけた聖書の記述は、この限りでは何らかの意図があって記されたものであろう。
(管理人注:とりあえずそういうことはアーサー・ケストラーの『ユダヤ人とは誰か』第13支族・カザール王国の謎をお読みください。
アーサー・ケストラーはこの本の出版で謎の死をとげている。だから読むべきであろう。
カ(ハ)ザール王国の謎
13支族の分布図
「ハザール王国」は7世紀にハザール人によってカスピ海から黒海沿岸にかけて築かれた巨大国家です。9世紀初めにユダヤ教に改宗して、世界史上、類を見ないユダヤ人以外のユダヤ教国家となりました。
各地に残るユダヤの足跡
ここでは古代から現代にまで続いて残っている、ユダヤと日本の不思議な共通点を坂東氏の著書を参考に拾い挙げてみる。
『平安都と琵琶湖と太秦』
古代社会でも最も有名な帰化人といえば『秦氏』であろう。聖徳太子の側近に秦河勝(はたのかわかつ)が居り、この人が宮廷での雅楽を世襲してきた東儀家の遠祖といわれている。河勝は渡来人であり、秦の苗字が示すように秦氏の出身であろう。
秦氏は雅楽、絹織物、土木、農耕などの技術を持っており、その技術を背景に巨大な富を蓄え政治的にも影響力を及ぼすようになった。
その秦氏が主導して作り上げたのが平安京であるという。これはヘブライ語のイールシャローム(エルサレム)を日本語にすると平安京となるのだそうだ。そればかりでなく、何とエルサレムの付近にはキネレット湖があり、これは琵琶の意味だそうでエルサレムという街の名とキネレットという湖の名をそのまま写したのが平安京と琵琶湖だといえよう。
そして東映映画村で有名な太秦(うずまさ)という不思議な地名もまた、秦氏を暗示する。彼の地は秦氏の居住した地区であるとされ、ヘブライ語のウズ・マシアッハが訛ったものと考えられている。その意味は『救い主の栄光』または『救い主の力』となるそうだ。
また太秦に残る木嶋坐天照御魂人神社(このしまにますあまてるみたまじんじゃ)は別名を蚕の社(かいこのやしろ)と呼ばれ、秦氏が絹織物の技術を所持していた名残を示すものであろう。更には三本柱の鳥居が現存する神社としても有名である。
この意味は恐らく、キリスト教の教義である『三位一体』を象徴するものであろうとする研究結果を発表している学者もいる。
つまり秦氏はキリスト教徒であり、恐らくはユダヤ系の流れをくむ氏族であったと予想されるに十分な証拠といえるかも知れない。
更に坂東氏の著書では、蚕の社の側にある『大酒神社』について、本来の文字から古代ユダヤ王国のヒーロー、ダビデ王を祭った神社であると結論付けている。
また広隆寺には、モーセの十戒に酷似した十膳戒という十戒が存在する。
この広隆寺は、秦河勝が建立した寺だとされている。
秦河勝が仕えたとされる聖徳太子は、その能力の高さもさることながら、出生のエピソードが某有名な人物にそっくりである。その人物とは言わずと知れたキリストその人であるが、両名とも馬小屋で生まれたとされている。古代には馬小屋で子供を産む世界的な習慣でも存在したのか、そんな馬鹿なはずはない。
秦河勝の関連記事11件
上の関連記事のなかに『日本語とヘブライ語」の比較がある。「大和民族はユダヤ人だった 」の著者であるユダヤ人言語学者ヨセフ・アイデルバーグは、 カタカナとヘブライ語の驚くほどの類似性を指摘していた。また、日本語の中にヘブライ語の単語が混在していることも指摘していた。 彼は以下のような発言をしていた。
「私は14年の歳月をかけて世界各地の言語を調べあげた。世界には中南米のマヤ人をはじめ、いくつも“失われたイスラエル10支族”の候補となる民族がいるのだが、日本語のようにヘブライ語起源の言葉を多数持つところはなかった。一般に日本語はどの言語にも関連がないため“孤語言語”とされているが、ヘブライ語と類似した単語が優に3000語を超えて存在している。」
秦河勝?=日本にやってきたサンカ(山窩)? まだ結論は早いだろう。
聖徳太子の逸話は恐らくキリスト誕生のエピソードを、模倣して造り上げられたのであろう。
聖徳太子が制定したとされる『十七条の憲法』や『官位十二階』も、大陸や朝鮮半島の影響、無論キリスト教的な影響を受けて、発想されたものかも知れない。
何しろ、側近には大陸を1万キロにも渡って踏破したユダヤ人の末裔、秦河勝が居たのだから。
『トラの巻とトラーの巻物』
私達にとってトラの巻といえば、困った時に開く参考書の様な感覚があるが、イスラエルにもトラーと呼ばれる巻物が存在する。
このトラーとはモーセ五書の事で巻物にしてあり、ユダヤ人はどんな時にもこれから知恵と霊感を得るのだという。このことはまさに日本人のいうトラの巻と極めて近く、本来はトラーの巻物であったものが、トラの巻と変化したものだろうと考えられる。ユダヤ人の中にはトラーではなく、トラと呼ぶ人もいるという。
『偶像崇拝の禁止と三種の神器』
ユダヤ教では偶像崇拝を禁じており、砂漠を流浪していた時代に、戒めを破り偶像を崇拝したとしてユダヤ人は罰を与えられている。
一方で日本の神道も偶像崇拝を行っていない、ご神体は一般に鏡であり、鏡に映る自らの姿に己の内なる神性を見出すためである。
また岩などがご神体の場合それ自体が神ではなく、神の宿る寄り代としての役目であると認識されている。
信仰の形は違っても、偶像崇拝をしないその精神は日本もユダヤも同じなのである。
更にはユダヤ人が大切にしていた『アーク』(契約の箱)には、十戒を刻んだ石板・マナの坪・アロンの杖と呼ばれる三種の神器が納められていた。
このアークは神そのものではなく、やはり神の寄り代と考えられている。
そして日本でも三種の神器が存在する。鏡と剣とマガ玉である。
『神殿と神社の造りの共通点』
日本の神社の造りは鳥居と参道、手水場を経て拝殿が在り、奥に本殿が建てられているというのが一般的な造りである。対してユダヤの神殿にも門と清めの場と拝殿と奥殿というほぼ同様の造りに成っている。イスラエルの会見の幕屋は、古代イスラエルの人々が礼拝する為に用いたテントのような礼拝所のことである。
しかも本殿、奥殿には一般の参拝者の立ち入りは許されず、年に数度だけ宮司やラビだけが立ち入ることを許されている。この様に、両者の神殿や儀礼は非常に似通っていて、参拝者が拝殿の前に用意された清めの水で、穢れを落としてから参拝する作法も同じなのである。
『失われたアークと神輿』
アークとはユダヤ人が神との契約に際し、契約を刻んだ石板を入れた大切な箱であり現在は失われて行方不明だといわれる。記録によると、このアークは蓋の両端にケルビムと呼ばれる翼を持った天子の像が付いている。
アークが顕在であった時代に、人々は箱の前後に棒を通し、担いで進んだという。
その様はまるで日本の神輿であり、神輿にも鳳凰などに見立てた鳥の飾りが付いている。
こうして例を挙げれば切りが無いくらいの日本とユダヤの共通点は多いが、他にも塩で清める習慣や、相撲はスモーというヘブライ語が語源であるとか、イスラエルのヘロデ門に刻まれている菊花紋、伊勢神宮の灯篭に刻まれているダビデの星、諏訪大社の御柱祭りと伝説のレバノン杉などなどである。
また私達が子供の頃に踊ったフォークダンスの定番『マイム・マイム』とは、ヘブライ語で『水だ、水だ』という意味であるらしい。これについては、失われた十部族とは無関係ではあろうが、何故にイスラエルの曲が教育現場へ普及とされたのかと考えると、少し不思議な気がする。
古代日本に息づくユダヤ
水上氏の著述によると、三社祭りで有名な浅草は浅草寺の浅草神社の紋はユダヤのガド族の紋章だという。浅草寺は千数百年の歴史を誇り、ここの紋章は三網紋であるが、その由来は三人の漁師が網を揚げたところ、金の観音像が引っ掛かってきた伝説に由来するらしいが、この説は真っ赤な偽物であるとする。
それはイスラエルのガド族の紋章を更に簡略化し図案化したものであり、ガド族は浅草神社の氏子となった。
日本に於ける紋章の起源はシュメール・パビロンにあり、との学説は戦前に唱えられている。その中で日本の原民族について、モン・クメール、マラヨ・ポリネシア、ツングースが主要な構成民族であるが、中心となる天孫族はシュメール族とバビロニアンだとの説を昭和2年に三島敦雄氏が発表されている。
天皇のことをミカド或いはスメラミコトと呼んだりもするが、この語源はバビロニアンのミクド(天から降臨した、開拓者の意味)だとし、スメラミコトはサマリアの皇帝という意味であり、聖書に登場するサマリア人は失われた部族に含まれる。
インドとチベットの国境近くに須弥山がある。この山の断面図が曼荼羅である。チベット語でカンリンボチェといいまたの名をSUMERUという。五体投地の荒行はこの山を108周する。ボン族は左周りであるが修行途中で死体が転がっていてもそれは本望なのである。空海は唐から根本曼荼羅を持ち帰ったがさらに別の根本曼荼羅が発見されている。
空海はいろは歌の暗号を残した。日本史には封印された長い年月があるからだろう。
(=「と か な く て し す」 つまり 「咎なくて死す」)「いろは歌」の暗号より)
いろはにほへと
ちりぬるをわか
よたれそつねな
らむうゐのおく
やまけふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす
一般に庵紋と呼ばれる建物を図案化した日本に於ける幾つかの家紋は、旅路の途中で即席に造った神殿で、その前途の安全と幸福を祈ったことの名残だ。
庵とは仮の建物の意味であり、私達日本人の遠い流浪の記憶を示すものなのである。
また武士の家紋にもユダヤの象徴が見られ、鹿児島の島津家はルベン族、仙台の伊達家はシメオン、高知の山内家をレビ族の子孫とした人物がいた。その理由はこれ等の武家の家紋と似た文様がかつてのシメオンやレビ族の根拠地とされる場所から見つかっているからなのだという。
島津氏と四国の長曽我部氏の祖先は秦氏であるとされており、現在では意味を失ってしまったものの、家紋には彼らの祖先の象徴が残されているのである。
先に挙げた幾つもの証拠とこれ等を合わせると、どうやら私達の祖先はシュメール、南洋方面、北方アジアなどの各方面から列島へ移住して来たらしいが、その中でもシュメール方面からの人々が力を持ったようだ。
秦氏といい、平安京といい、祭りといい日本の伝統的な行事や習慣は彼らのそれに塗り替えられているのである。
日本の神話の元であり、古文書では唯一の正史として認定されている『古事記・日本書記』は彼ら渡来人の子孫が作り上げたものであるようだ。
例えばイザナギとイザナミの結婚のシーンだが、天の御柱を男女の二神が逆方向に巡って出会い、その時にイザナミは「あなにやし、えおとこを」イザナギは「あなにやし、えおとめを」と言ったと古事記にはある。
この『あなにやし』とは、普通には「ああ、なんとよい男なのでしょう」という様に感嘆符として解釈されている。
しかしこの意味は、日本語では本当のところは意味不明なのである。それよりも、ヘブライ語と解釈すると「アニーアシー」という言葉が近く、この意味は「私は結婚します」であるらしく、そうだとすれば古事記のイザナミとイザナギの結婚シーンと完全に附合する。この神話の冒頭のシーンは、実際にユダヤの結婚の儀式に近いものであるらしい。
『管理人注:「魏志倭人伝」によれば、3世紀半ばの日本列島のどこかに、女王卑弥呼の邪馬台国があったことは間違いない。しかし、当時のことを記すわが国の歴史書=『古事記』と『日本書紀』(以下では「記紀」と略記)には、その所在地が記されていない。(記紀(きき)とは、『古事記』と『日本書紀』との総称である。『古事記』の「記」と『日本書紀』の「紀」を併せて「記紀」という。)「記紀」は、天皇家によるわが国支配を正当化するねらいを持つ史書である。その中に、天皇家の体面を汚す過去は記録できない。中国に朝貢していた倭王に関する記録がほとんど無視されているのは、そのためであろう。したがって、邪馬台国という国名をもじった題の暗号形式の落書は、その題によって、国家の体面を汚すなと権力者に向かって訴えているのではなかろうか。(=「と か な く て し す」 つまり 「咎なくて死す」)「いろは歌」の暗号より)』
ユリ・コーヘン氏は、ユダヤの神話と日本の神話が極めて似ていると主張している。
殊にその冒頭部分はアダムとイヴの二人の男女から始まるユダヤ神話に対し、日本ではイザナギとイザナミの二人から始まるのである。
また唯一神と八百万の神は正反対の概念であるように見えるが、ユダヤ教の唯一神は全地に臨在する。それは総ての存在に神が宿るとする八百万神の考えと矛盾するものではないと考えているようである。神とは遍在するものであり、その意味では全てに神が宿るのは当然だとする考え方である。
伊勢神宮 その1
伊勢神宮 その2
伊勢神宮 その3
そして伊勢神宮には秦氏を祖先とすると思われる家系の人が、代々の宮司を務めている。
現在は外宮のみだが以前は内宮の神官も兼務していた、渡会氏の名前がその証拠として挙げられるという。渡会氏の名前は渡来とも表記する場合もあり、渡来民そのものを指す名だとされる。また、渡会氏の祖先は大幡主命(オオハタヌシのみこと)であるとされ、この命の名は大秦ではなかったかと推測される、つまりユダヤ系の渡来氏族である秦氏との繋がりが見えるのである。
檜原神社
更に神宮の灯篭にはダビデの星が刻まれているが、実はこれはそう古いものではなく近年になって神社側からの要望により入れられたものであるらしい。
何故にその要望が成されたのか、不明であるという。
表が伊勢神宮なら裏は下鴨神社であろう。
伊勢の地名そのものもまた謎であるが、ユダヤ人研究家によればヘブライ語の「イェシェ」から派生した言葉で『神の救い』という意味であるそうだ。
そして伊勢神宮の御神体である鏡にはヘブライ語が刻まれてあるとは、三笠宮殿下が研究の為にご覧になったのを新聞に投稿なさったとか、その写しを見た人が居るとかの噂がある。一般人は見られないので真偽の程は不明である。