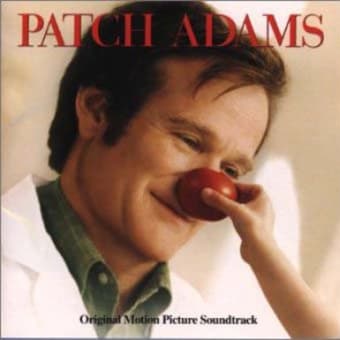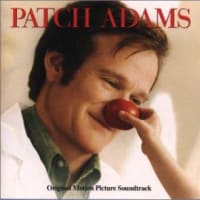http://web.archive.org/web/20170502154930/http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/861.html
「自分探しなんて無駄なこと?」
http://www.gruri.jp/article/2014/08131130/
“ありのままの”“自分たちのサッカー”をどう考える? 養老孟司さんが説く「自分探しなんてムダなこと」
「自分」の壁..... 養老孟司 著 注:バカの壁は第三者が書いたことが分かっています。
管理人注:解剖が専門の氏は私の嫌いな人間の一人です。この人のやり方は.....相手が見ているに違いないものを言葉にし,相手が感じているに違いないものを言葉にし,相手が聞いているに違いないものを言葉にするという臨場感を創り出し本を買って読まなくてはいけないというストックホルム症候群を作り上げるのです。そうしないと本なんて売れないのです。自費出版してご覧なさい.....3冊売れれば大成功なのです。
関連記事:カルトの教義 その3
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2957
『目の前にいるアバターは、あなた自身です。ということは、アバターにもあなた自身の人格があります。つまり、2人のあなたがいるわけです。ただ、アバターはあくまでもダミー。本当に守るべきあなた(本物)は、アバターの1歩後ろにいます。ここで注意してほしいことがあります。アバターはもう1人のあなたですが、ダミーでもあるので敵の警戒心を解く位の人格、本物のあなたよりも隙が多い人格にしなければなりません。極端に言うと、本物よりも少し低いIQの持ち主にします。(中略)』
今年の流行語は何になるだろうか。「レジェンド」「号泣」「ダメよ~ダメダメ」「STAP細胞」等々。すでにいろいろな候補が登場しているが、「隠れキーワード」とも言える言葉がある。
「自分」だ。
■「ありのまま」?「自分たちのサッカー」?
え? そんなフツーの言葉のどこが? と思われるだろうか。
でも、「アナと雪の女王」の「ありのままで」のサビの歌詞はご存知の通り「ありのままの“自分”になるの」だ。ありのままの自分になって自由になる、という歌詞はどこかかつての大ヒット曲「世界に一つだけの花」にも通じるところがある。とにかく、簡単に “自分”を肯定的に捉えることが前提だ。こうした「ナンバーワンではなくてオンリーワンでいい」というメッセージは多くの共感を得ているようだ。
一方で、「自分」絡みのコメントで不興を買ったのがサッカー日本代表かもしれない。選手たちは大会を終えて口々に「“自分”たちのサッカーができなかった」とコメントしていた。結果が悪かったこともあり、このコメント自体かなりバッシングの対象にもなったのである。「自分たちのサッカーって何だよ」「相手がいるんだから当たり前だろ!」等々。そういえばかつての大会後、中田英寿選手が「自分探しの旅」に出るとコメントしたときにも、賛否さまざまな反応があったことが思い出される。
■自分探しなんてムダなこと
そして、もう一つ「自分」といえば、東大名誉教授の養老孟司さんが『バカの壁』に始まる「壁」シリーズの最新刊として刊行したのが『「自分」の壁』。
この本は、「自分とは何か」という根源的な問いに答えるところから始まっている。著者の養老さんは、幼稚園の頃からその問題を考えてきたというだけあって、答は実に深く、また意表をつく指摘も多い。中でも、「自分探しなんてムダなこと」というオビのコピーは、自分探しに汲々としている人の胸に刺さるのではないか。
戦後の日本では、戦争への反省もあって「個人」の「個性」をひたすら重視する教育をするようになった。しかし、それ自体が本当に日本人に適していたのか。同書の中で養老さんは疑問を呈している。
「『個性を伸ばせ』『自己を確立せよ』といった教育は、若い人に無理を要求してきただけなのではないでしょうか。身の丈に合わないことを強いているのですから、結果が良くなるはずもありません。それよりは世間と折り合うことの大切さを教えたほうが、はるかにましではないでしょうか」
たしかに「アナ雪」のエルサは当初、世間と折り合う方法を知らなかったが、最終的に自分をコントロールする方法を見つけて、幸福をつかんでいる。ある意味で、「折り合う」ことをおぼえたのかもしれない。
こんな意見に対して、「それでは世間や他人の顔色をうかがってばかりの人間になるんじゃないか」と心配する人もいることだろう。しかし、「そんな心配はいらない」と養老さんはこう述べる。
「個性だとか自分らしさなんてものは、そもそもすでにその人の中にあるのです。そんなものを探す必要はありません。『自分探し』なんて言うけど、じゃあ探しているのは誰なんだよ、ということになる。
伝統芸能の世界では、弟子は徹底的に師匠を真似ます。『とにかく同じようにやれ』と言われ、長い間、真似をし続ける。それでもどこか師匠と違うところがどうしても出てくるものです。それが個性であり、『自分らしさ』でしょう。
『本当の自分』というものは、最初から発見できるものでも、発揮できるものでもありません」
こうしたメッセージへの共感もあってか、同書はすでに20万部突破のベストセラーに。『バカの壁』に始まる「壁」シリーズは4冊の累計で600万部を突破している。きっかけは「アナ雪」でもサッカーでもいいが、たまには「自分」という大きな問題を考えてみるのもいいかもしれない。
関連記事:スタニスラフスキーの演技論
http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/440.html
『現在の新宿2丁目はかつての赤線地帯である。パンパンくずれの梅毒もちの女の掃き溜めであったこの2丁目も作家にかかると見違える女になる。
「青春の門」自立篇で早稲田大学へ入ったばかりの信介は,ある日校門の前にいた2年生の緒方に出会い,物語は始まる。緒方は演劇を専攻し信介は,はじめて新宿2丁目の「かおる」を知る。学生は金がない時,かおるのもとへ本を持参して金を借り,バイトが終わると借りた金と引き換えに本を返してもらう。
いつもかおるの部屋は,貧乏学生の本でうまっていた。悲しい真理を知りつくしている哲学者的「かおる」と楽しい真理しか知らない学生との交流を描いている。
緒方は信介に言う。夜になると面白いぞ あっちでもこっちでも女達の例の声がきこえてな。あれは客に早く行かせるための演技にすぎんがね。
「スタ二スラフスキーの演技論]では,まず自分が感情移入して その役と状況に没入してしまわなきゃならん。
だがここは演技で没入しちまったら意味がないだろ。自分はあくまでも醒めていて,客だけを興奮させなきゃならんのだからな。
夢中にならず真に迫る,という困難な命題が彼女達には課せられているわけだ................』
その命題がクリア出来る日陰の女のみが生き残るのである。そういう女性は年収数億円稼ぎホストクラブ通いなど眼中になく数年で引退して悠々自適の生活をしたり銀座の雇われマダムでなくオーナーママとなるのです。あるいはたまに末期ガンになって80過ぎの大富豪と結婚しあっという間に巨額の財産を築いた女性もいるのです。管理人はパリでそういう日本人女性を見ました。歌舞伎町あたりの売れっ子風俗嬢も結局は仕事の鬱憤を晴らすためホストに入れ込んで,しまいには歌舞伎町金融から金を借り......AVやソープに売られ南へ南へと流れて行くのです。しかし現在はそんな暗い話ではなく自らAVに飛び込んでくる「明るいキチガイ」が大多数を占めるようになってしまった。それをキチガイが見るのです。若者を性の巣窟におびき寄せることはイルミナティの戦略の一つなのです。
“ありのままの”“自分たちのサッカー”をどう考える? 養老孟司さんが説く「自分探しなんてムダなこと」
「自分」の壁..... 養老孟司 著 注:バカの壁は第三者が書いたことが分かっています。
管理人注:解剖が専門の氏は私の嫌いな人間の一人です。この人のやり方は.....相手が見ているに違いないものを言葉にし,相手が感じているに違いないものを言葉にし,相手が聞いているに違いないものを言葉にするという臨場感を創り出し本を買って読まなくてはいけないというストックホルム症候群を作り上げるのです。そうしないと本なんて売れないのです。自費出版してご覧なさい.....3冊売れれば大成功なのです。
関連記事:カルトの教義 その3
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2957
『目の前にいるアバターは、あなた自身です。ということは、アバターにもあなた自身の人格があります。つまり、2人のあなたがいるわけです。ただ、アバターはあくまでもダミー。本当に守るべきあなた(本物)は、アバターの1歩後ろにいます。ここで注意してほしいことがあります。アバターはもう1人のあなたですが、ダミーでもあるので敵の警戒心を解く位の人格、本物のあなたよりも隙が多い人格にしなければなりません。極端に言うと、本物よりも少し低いIQの持ち主にします。(中略)』
今年の流行語は何になるだろうか。「レジェンド」「号泣」「ダメよ~ダメダメ」「STAP細胞」等々。すでにいろいろな候補が登場しているが、「隠れキーワード」とも言える言葉がある。
「自分」だ。
■「ありのまま」?「自分たちのサッカー」?
え? そんなフツーの言葉のどこが? と思われるだろうか。
でも、「アナと雪の女王」の「ありのままで」のサビの歌詞はご存知の通り「ありのままの“自分”になるの」だ。ありのままの自分になって自由になる、という歌詞はどこかかつての大ヒット曲「世界に一つだけの花」にも通じるところがある。とにかく、簡単に “自分”を肯定的に捉えることが前提だ。こうした「ナンバーワンではなくてオンリーワンでいい」というメッセージは多くの共感を得ているようだ。
一方で、「自分」絡みのコメントで不興を買ったのがサッカー日本代表かもしれない。選手たちは大会を終えて口々に「“自分”たちのサッカーができなかった」とコメントしていた。結果が悪かったこともあり、このコメント自体かなりバッシングの対象にもなったのである。「自分たちのサッカーって何だよ」「相手がいるんだから当たり前だろ!」等々。そういえばかつての大会後、中田英寿選手が「自分探しの旅」に出るとコメントしたときにも、賛否さまざまな反応があったことが思い出される。
■自分探しなんてムダなこと
そして、もう一つ「自分」といえば、東大名誉教授の養老孟司さんが『バカの壁』に始まる「壁」シリーズの最新刊として刊行したのが『「自分」の壁』。
この本は、「自分とは何か」という根源的な問いに答えるところから始まっている。著者の養老さんは、幼稚園の頃からその問題を考えてきたというだけあって、答は実に深く、また意表をつく指摘も多い。中でも、「自分探しなんてムダなこと」というオビのコピーは、自分探しに汲々としている人の胸に刺さるのではないか。
戦後の日本では、戦争への反省もあって「個人」の「個性」をひたすら重視する教育をするようになった。しかし、それ自体が本当に日本人に適していたのか。同書の中で養老さんは疑問を呈している。
「『個性を伸ばせ』『自己を確立せよ』といった教育は、若い人に無理を要求してきただけなのではないでしょうか。身の丈に合わないことを強いているのですから、結果が良くなるはずもありません。それよりは世間と折り合うことの大切さを教えたほうが、はるかにましではないでしょうか」
たしかに「アナ雪」のエルサは当初、世間と折り合う方法を知らなかったが、最終的に自分をコントロールする方法を見つけて、幸福をつかんでいる。ある意味で、「折り合う」ことをおぼえたのかもしれない。
こんな意見に対して、「それでは世間や他人の顔色をうかがってばかりの人間になるんじゃないか」と心配する人もいることだろう。しかし、「そんな心配はいらない」と養老さんはこう述べる。
「個性だとか自分らしさなんてものは、そもそもすでにその人の中にあるのです。そんなものを探す必要はありません。『自分探し』なんて言うけど、じゃあ探しているのは誰なんだよ、ということになる。
伝統芸能の世界では、弟子は徹底的に師匠を真似ます。『とにかく同じようにやれ』と言われ、長い間、真似をし続ける。それでもどこか師匠と違うところがどうしても出てくるものです。それが個性であり、『自分らしさ』でしょう。
『本当の自分』というものは、最初から発見できるものでも、発揮できるものでもありません」
こうしたメッセージへの共感もあってか、同書はすでに20万部突破のベストセラーに。『バカの壁』に始まる「壁」シリーズは4冊の累計で600万部を突破している。きっかけは「アナ雪」でもサッカーでもいいが、たまには「自分」という大きな問題を考えてみるのもいいかもしれない。
関連記事:スタニスラフスキーの演技論
http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/440.html
『現在の新宿2丁目はかつての赤線地帯である。パンパンくずれの梅毒もちの女の掃き溜めであったこの2丁目も作家にかかると見違える女になる。
「青春の門」自立篇で早稲田大学へ入ったばかりの信介は,ある日校門の前にいた2年生の緒方に出会い,物語は始まる。緒方は演劇を専攻し信介は,はじめて新宿2丁目の「かおる」を知る。学生は金がない時,かおるのもとへ本を持参して金を借り,バイトが終わると借りた金と引き換えに本を返してもらう。
いつもかおるの部屋は,貧乏学生の本でうまっていた。悲しい真理を知りつくしている哲学者的「かおる」と楽しい真理しか知らない学生との交流を描いている。
緒方は信介に言う。夜になると面白いぞ あっちでもこっちでも女達の例の声がきこえてな。あれは客に早く行かせるための演技にすぎんがね。
「スタ二スラフスキーの演技論]では,まず自分が感情移入して その役と状況に没入してしまわなきゃならん。
だがここは演技で没入しちまったら意味がないだろ。自分はあくまでも醒めていて,客だけを興奮させなきゃならんのだからな。
夢中にならず真に迫る,という困難な命題が彼女達には課せられているわけだ................』
その命題がクリア出来る日陰の女のみが生き残るのである。そういう女性は年収数億円稼ぎホストクラブ通いなど眼中になく数年で引退して悠々自適の生活をしたり銀座の雇われマダムでなくオーナーママとなるのです。あるいはたまに末期ガンになって80過ぎの大富豪と結婚しあっという間に巨額の財産を築いた女性もいるのです。管理人はパリでそういう日本人女性を見ました。歌舞伎町あたりの売れっ子風俗嬢も結局は仕事の鬱憤を晴らすためホストに入れ込んで,しまいには歌舞伎町金融から金を借り......AVやソープに売られ南へ南へと流れて行くのです。しかし現在はそんな暗い話ではなく自らAVに飛び込んでくる「明るいキチガイ」が大多数を占めるようになってしまった。それをキチガイが見るのです。若者を性の巣窟におびき寄せることはイルミナティの戦略の一つなのです。

- 民暴事案での暴力団の行動パターンは、大きく分けて次の3段階があると言われています。
- ■第1段階 接近
まず標的を定め、機関紙購読要求、下請要求、不祥事案その他様々な「ネタ」をもとに接近を図ってきます。
- ■第2段階 攻撃
コンタクトに成功すると、いろいろな脅しのテクニックを用いて、困惑させ、恐れさせ、心理的に追い込んできます。
- ■第3段階 目的達成、再攻撃
心理的に追いつめられて金を出すと、彼らにとっては目的達成と言うことになります。 しかし、金を出したことによって、組みし易い相手として認識され、何回も脅してきます。また、ほかの暴力団の標的にもなります。
- こうした過程で、彼らが用いる典型的な脅しのテクニックは、概ね次の4つに要約されるようです。
- 1 恐怖心培養戦術
一般市民が持っている、「暴力団は怖い」というイメージを利用して、巧妙に恐怖心を植え付ける手口です。
暴力団の代紋や肩書き入りの名刺を示したり、入墨をちらつかせる。突然机をたたき大声をあげる。「若い者が黙っていない。」などと脅し文句を言う。組事務所に呼び出しをかけるなど様々なテクニックを使います。
- 2 頭脳混乱戦術
不当な要求を執拗に繰り返して長時間居座ったり、早朝や夜中に自宅に電話を掛けたり、応対者を精神的、肉体的に疲れさせ、「何とかこの状況から逃れたい。」という心理状態に追い込む手口です。
- 3 嫌がらせによる日常業務妨害戦術
忙しい時間帯を狙って、何回でも面会を強要したり、大勢で会社に押しかけて社内をうろつく、会社の出入口にたむろして通行者を威圧する、時には街宣車を繰り出すなどの嫌がらせを行い業務を妨害する手口です。
- 4 脅し役となだめ役の分担戦術
あらかじめ脅し役となだめ役を決めておき、脅し役が大声で怒鳴ったり、厳しい言葉で責めたてると、なだめ役が時折りなだめ、あたかも会社の味方のようなことを言って錯覚させ、最終的には、なだめ役が会社と脅し役の双方の言い分をとりなすようにして金品での解決を促し、脅し役もなだめ役の顔を立てて仕方なく引き下がったように芝居をして、結局目的を達する手口です。
黒木昭雄たった一人の捜査本部
http://blogs.yahoo.co.jp/kuroki_aki
警察はなぜ堕落したのか
http://blogs.yahoo.co.jp/kuroki_aki/6593808.html
いつものように黒木氏の遺体は解剖せず
http://blog.livedoor.jp/bettycat530-shinjitsu/archives/7616536.html
参考:グーグルはこの方法で成功した
https://eb.store.nikkei.com/asp/ShowItemDetailStart.do?itemId=D3-00031955C0&n_cid=STORE441
グーグルは、この方法で成功した!
グーグル会長がビジネスの真髄を初公開!
■グーグル現会長で前CEOのエリック・シュミットと、前プロダクト担当シニア・バイスプレジデントのジョナサン・ローゼンバーグは、グーグルに入社する以前から経験豊富なIT業界のトップ・マネジャーだった。だが、2人が入社したグーグルは、「他とは違ったやり方をする」ことで有名だ。これは、ビジョナリーであり、人とは反対の行動をとりがちな共同創業者2人、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンの方針に沿ったものだった。
■入社してすぐにエリックとジョナサンは悟った。グーグルで成功するには、ビジネスとマネジメントの方法をすべて学び直さなければならない、と。本書では、著者2人がグーグルの成長に貢献しながら学んだ「教訓」を豊富な事例とともに語る。
■テクノロジーの進歩は消費者と企業のパワーバランスを激変させた。この環境下では、多面的な能力を持つ新種の従業員??スマート・クリエイティブ??を惹きつけ、魅力的で優れたプロダクトを送り出す企業だけが生き残れる。戦略、企業文化、人材、意思決定、イノベーション、コミュニケーション、破壊的な変化への対応といったマネジメントの重要トピックを網羅。
■グーグルで語られる新しい経営の「格言」(「コンセンサスには意見対立が必要」「悪党を退治し、ディーバを守れ」「10倍のスケールで考えよ」……など)やグーグル社内の秘話を、驚異的なスピードで発展した社史とともに初めて明かす。
■すべてが加速化している時代にあって、ビジネスで成功する最良の方法は、スマート・クリエイティブを惹きつけ、彼らが大きな目標を達成できるような環境を与えることだ。本書は、ただその方法をお教えするものである。
■序文はグーグルCEO兼共同創業者のラリー・ペイジが執筆した。
■【著者】
エリック・シュミット(Eric Schmidt)
2001年グーグル入社。同社がシリコンバレーのベンチャー企業からハイテク業界の世界的リーダーへ成長するのに貢献。現在は取締役会長として対外的問題に責任を持つ。他社とのパートナーシップやさまざまなビジネス関係の構築、政府との関係、ハイテク分野のオピニオンリーダーとして活躍するほか、グーグルCEOをはじめ経営上層部に事業や政策問題について助言を行っている。2001年から2011年までグーグルCEOを務めた。
グーグル入社以前はノベルとサン・マイクロシステムズで経営幹部を歴任。プリンストン大学で電気工学を専攻、カリフォルニア大学バークレー校で修士、博士(いずれもコンピュータ科学)を取得。アメリカの大統領科学技術諮問委員会、イギリスの首相諮問委員会の委員を務めるほか、エコノミスト・グループ、メイヨー・クリニック、カーン・アカデミーの取締役を務める。シュミット・ファミリー財団を通じた慈善事業では、海洋生物の研究や教育を含めた気候変動問題に集中的に取り組み、とくに自然科学とエンジニアリング分野の最先端の研究に力を入れている。
アリババ創業者は数学1点
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/2934
これから少ない資本で起業の機会は無限にあります。諦めたらもうすべて終わりです。挑戦することです。座して死ぬか挑戦して死ぬかのどちらかです。女は強い男には何も言いません。これは覚えておいてください。大事なことを言います.....ロスチャイルド家創業者のアンセルム・ロスチャイルドは13歳で父親を亡くしオッペンハイム銀行に生活の糧を得ました。そこでアンセルムは卑屈なほど低姿勢で仕事をしたのです。そして認められ正社員となって行くのです。給料を払う人間からして偉そうにしている人間が一番嫌いなのですよ。管理人の社長経験からして給料を貰う立場の人間が一番楽だということ。