
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(77)
日独仏蘭が一緒に働くと…
アムステルダム(オランダ)
昔から知識人や文化人と称される人たちの「欧米では…」と「欧」と「米」を一括りに
する物言いに違和感と嫌悪感を抱いてきた。欧米という言葉は、概ね日本を卑下或いは揶
揄する文脈の中で使われる(使われてきた)ことが多い様に思われる。
「欧」と「米」は全く違うし、欧の中でも北と南、東と西では言語も文化も感性も著しく異なる。にも拘らず、文明開化以降「欧米」という言葉は有無を言わさぬ正義であるかのような気色の悪いニュアンスを纏ってきた。少なくとも私にはそう感じられる。
欧米というのは地理的概念より、むしろ白人の国家という意味合いを強く含んでいる。だから、「欧米」を「西洋」と言い換えるなら、少しはスッキリするかも知れない。「全米」という言葉も好きではない。
ミネソタやアイダホのような田舎と西海岸や東海岸を一緒くたに論じることなどできるはずがないではないか。「大谷の快挙に全米が震撼、感動!」などと聞くと「そんな訳ないやろ」と突っ込みたくなってしまう。
中国についても同じだ。俗に、「北京愛国、上海出国、広東売国」と言われるように地域によって人々の性格、物の考え方は千差万別である。異文化間コミュニケーションというジャンルの学問があるくらいだから、歴史、文化、価値観を異にする人間が一緒に仕事をすると意図せぬ誤解、行き違いが発生してしまうのは当然だろう。
アムステルダムで、オランダ人、フランス人、ドイツ人、そして「カスタマー=お客様」としての日本人と仕事をしたときのことを思い起こしてみた。本連載の第4回「飾り窓強盗事件(2022/8/20)」にも書いたが、私は1987年に設計、管理、据付部門の担当者らと3週間の予定でアムステルダムに出張した。
自動車メーカーN社から自動車部品用自動倉庫を建設するプロジェクトを受注したので、独仏蘭との現地工事事務所設立準備のため、お客様や下請け企業との折衝、経理、工程管理、原価管理といったエンジニアリングと工事遂行以外の雑事一般を引き受ける「アドミ要員」として派遣されたのだ。わかりやすく言うと、「何でも屋」である。
一緒にやってきた同僚たちは、予定どおり3週間で帰国したが、私は秋風の立ち始めたアムステルダムに一人取り残され、再編成された部隊が戻るまでの3カ月間、アムステルダムに張り付いただけでなく、更に3カ月も追加で滞在することになったのだ。

▲ドイツのサブコン(下請け企業)とブレーメンで
私が働いていた会社では、国内では多くの自動倉庫の実績を有するものの、海外では台湾の小規模案件の工事経験しかなかった。全く知見・経験のない欧州で、しかも主契約者としてオランダ、フランス、ドイツのサブコン(下請け企業)を束ねて工事を遂行しなければならない。
早い話が、各国で異なる工業規格、安全規格、消防法、建築基準法、労働法、税法などの整合性を確保し、すべてのプロジェクト関係企業を取り纏める必要があったのだ。
アムステルダムの街は、街中に張り巡らされた運河沿いに、意匠を凝らしたファサードが印象的な古い建物が肩を寄せ合うように連なっている。私は、この美しい街に住むことができると思うと、ワクワクしていた。
しかし、言語、価値観、思考法、歴史的背景の異なる多くの集団が一緒に仕事をするのだから、衝突しない訳がない。あちらで頭をぶつけ、こちらで躓いたので、たった1年で髪の毛の半分が白くなった。もっとも、一緒に駐在していたОさんは、髪の毛が半分抜けてしまったから、私は少しだけ幸せだったのかもしれない。と、こんな状況で仕事をしていた。

▲ドイツのサブコン(下請け企業)とブレーメンで

▲オランダ人のN社職員E(右)とは気が合った
秋が深まったある日の午後、現場事務所で工程会議をしているとN社の職員Eが駆け込んできた。インドネシア系オランダ人の彼とは、妙に気が合い、仕事以外の話も沢山する間柄だった。Eは息を弾ませながら、西日を背にして言った。
「自動倉庫建屋の建築業者の作業員が高さ6mの足場から落下した。重傷らしい」
「彼は大丈夫? 命に別状は?」
「詳しいことはまだ分からない」
落下した作業員の状態を心配しながらも、私の脳裏には様々な思いが同時に駆け巡った。この現場で初めての人身事故である。日本でなら、状況によっては、工事の元請けである当社の安全管理責任が問われる筈だ。工事中断ともなれば、工程管理上大問題である。賠償、メディア対策、安全管理責任者の処罰、そうなると代替要員を確保しなければならない。
即座に、N社、建築業者、他のサブコン(Subcontractor=下請け業者)、そして当社とプロジェクト関係者がN社の会議室に招集された。事故原因の究明チームの組成と究明プロセスの策定、再発防止策、工事工程変更要否確認などを話し合った。

▲事故が起きた建設中の自動倉庫
日本だと、一体誰が責任を取るのかで紛糾する可能性が高い。しかし、その時最優先されたのは、「何故事故が起きたのか」を特定し、再発防止策を関係者全員に徹底することだった。幸い、その後の第三者調査機関による査定の結果、当社及びサブコンの現場責任者も安全管理責任を問われることはなかった。
落下の原因は、当該作業員が当日朝、現場監督から安全装備(ヘルメット・安全靴・耳栓・安全保護ゴーグル・高所作業用安全ベルトなど)の着用義務についてきちんと注意喚起されていたにも拘らずそれを遵守しなかったことだと客観的に証明されたからだ。
つまり、自己責任である。これは、論理的に正しい結論だが、もしこの事故が日本の現場で起こったとしていたら、そう簡単に片付けられることはなかったに違いない。落下した男性は、腰椎と肋骨を何本か折る重傷で、機能障害が残るという。幸い、安全義務違反ではあったが、保険による救済措置で彼と家族の生活は保障されると聞き、安堵した。

▲プロジェクト運営委員会会議の議長を務めた筆者
N社のオランダ人社員と日本から派遣された日本人プロジェクトチーム、独仏蘭のサブコン3社の代表者、そして主契約者の当社でWeekly Steering Committee Meeting(毎週の
プロジェクト運営委員会会議)を開催していた。
私はこの会議の議長(chairman)だったのだが、毎週のこの会議は地獄のような時間だった。ご承知のようにドイツとフランスは犬猿の仲で、いつもいがみ合う。オランダはドイツと日本に対して第二次大戦の遺恨を燻らせている。お客様の内部でもオランダ人と日本人スタッフの間で意見が対立することも珍しくはなかった。
これらの複雑な関係の中で、プロジェクトを運営してゆくのは至難の業である。だが、秋の出来事は、まだましな方だった。最悪の季節が待っていたのである。
フランス人は納期が遅れようと機器の品質問題が起きようとしっかり3週間くらいはバカンスを楽しむ。フランス人たちが仕事に復帰すると、今度はドイツ人やお客様のオランダ人が1週週間の休暇を取る。
みんながバラバラに休むので、大方ひと月ほどプロジェクト関係者全員が揃うことはない。当然、プロジェクト管理上の空白部分が生まれる。しかし、日本人だけは夏休みなしで働き続けたのだった。
オランダ人、フランス人、ドイツ人のみんなから「日本人はエライ。夏休みなしで働き続けるなんて! ホントに尊敬するよ!」と褒めそやされるのだが、言葉とは裏腹に「おまえら、バカだな。何のための人生だ!?」だと憐れんでいるのがはっきりと見て取れる。
悔しいったらありゃしない。同時に、彼らが羨ましいったらありゃしない。でも、悲しいことに日本人って奴は、目的達成のためなら自己犠牲も何のその、頑張ってしまう。
尤も、米世論調査会社ギャラップの世界の従業員エンゲージメント(仕事への意欲、組織への貢献意欲など)に関する調査によると、2023年時点で「仕事に意欲的、積極的に取り組む人」の割合が日本は6%にとどまり、世界最低水準であることが判明した。世界全体(23%)、東アジア(18%)と比べ、低さが際立っているのだ。
この工事を遂行していた1987年当時と今の日本人を比較すると、同じ日本人だろうかという疑念が湧き、「異文化」の世界を生きているようで空恐ろしい気がする。当時の生真面目で余裕のない日本社会が良かったとは決して思わないが、やはり、一抹の寂しさを覚えてしまう。
国によって、仕事のやり方、段取りは大きく違う。フランスのサブコンは、納入機器を工場でざっくり仕上げた状態で現場に持ち込んでくる。他の機器類との取り合い(インターフェース)や据え付け精度などは現場の状況に応じて、臨機応変に対応するスタイルだ。
工場での立ち会い検査の際、完成度を高めて現場に搬入するよう要求しても、彼らは聞く耳を持たない。納期的に余裕を持って現場に搬入しても、製作精度が低いものだから、アンカーボルトの位置が数ミリもずれていて固定できないことや、既存機器との高さが揃わず調整に長時間を要することも珍しくはなかった。意見が対立した時の彼らの常套句は、「フランスでは…」だ。自分たちのやり方が絶対に正しいと信じて疑うことを知らない。
ドイツ人はフランス人とは対照的に、工場内でできる限り精度の高い加工と組み立てを行うので現場内搬入された機器はジグソーパズルのようにピタッと所定の位置に納まるのである。意見が対立したとき、ドイツ人はフランス人の様にドイツのやり方が絶対正しい等とは言わないが、なかなか自説を曲げようとはしない。そんな時には奥の手がある。理詰めというヤツだ。
「OK、あなたの意見は理解した。あなた方の機器とフランス製機器の物理的整合性と制御プログラムの整合性について私たちに責任を負うのはあなたたちだ。しかし、N社に対して最終責任を負うのは主契約者である私たちではないか。私たちが責任を負うからには、私たちの考えを呑んで貰う必要がある。それともあなたたちがN社に直接責任を負うことにしますか。なんなら、そういう覚書(Memorandum of Agreement)を作成しても良いが…」
ま、ドイツ人との交渉にはそんな感じだ。「誰が責任者(ボス)」なのかをはっきりさせて臨むというのが。失敗と経験から辿り着いた彼らの結論である。
さて、オランダ人はどうか。
私の知る限り最も国際的で開放的、合理的且つ現実的、寛容、自己主張は強いが相手を尊重する、概ね悪いところは思い浮かばない。敢えて言えば、自由奔放な発想に優れているにも拘わらず議論に於いては、中途半端が嫌いで「ちょっとそれは脇に置いといて」という発想が皆無で、何かに躓いてしまうとそこから先に全く進めなくなってしまうことぐらいか。
そんなオランダを象徴する話題を3つ紹介しよう。
オランダではマリファナは合法だ。但し、18歳以上の成人に限る。2002年に世界で初めて安楽死を合法化したオランダでは、アムステルダム始め、街の運河に面した道路にフェンスがない。その理由は、フェンスを設置して美観を損なうのが嫌だから。
フェンスの代わりにオランダの小学校では、運河に落ちたときを想定して、服を着たまま泳ぐ訓練を義務化している。
もう一つ、印象に残っている話がある。オランダのメシがまずいという話を以前書いたことがあるが、オランダでは「衣食住」の「衣」と「食」がなくて、「住遊」だという。彼らはホントに衣装には無頓着だ。スーツ姿の男性を見かけることは殆ど無いし、女性はジーンズにTシャツやシンプルなジャケットなどのカジュアルな出で立ちが多く、スカートをはいている人は珍しい。
「住」には金と時間をかける。居心地の良い空間を造ることに執念を燃やすと言っても良いかも知れない。オランダの家の特徴は大きな窓。暗くジメジメとした冬に少しで多く陽の光を採り入れる為だ。窓ガラスが少しでも汚れていればたちまち近所のお節介なマダムたちから苦情が寄せられる。オランダ人はケチで有名だが、何故か、家具や照明器具には出費を厭わない。身分不相応とも思えるほどだ。
そして、「遊」だが、オランダ名物の自転車で美しい街を巡る、郊外の湿地帯に出かけていって風車を眺めながらのピクニック、犬を運河に飛び込ませて犬を喜ばせ、そして自分も喜ぶ。要は、金のかからない自分だけの小さな楽しみを見つけるのが本当に得意なのである。

▲フェンスのないオランダの運河
さて、そんな様々な個性の人間が一緒に仕事をしていて、数え切れないほどの衝突や軋轢を経験した。しかし、プロジェクトの完成納期に間に合わない可能性が出てきたとき、信じられないことが起こった。自然に、日独仏欄連合チームとして力を合わせる空気が醸成されていったのである。
普段残業をしないフランス人たちが何日も徹夜で作業をした。気難しい制御エンジニアが夜中に、カマンベールチーズを輪切りにしたリンゴで挟んだ夜食を日独蘭のメンバーに差し入れてくれたりした。ドイツ人たちはいつものとおり黙々と作業を続けた。
日本人は、みんな寝不足でふらふらになりながら仕事を続けた。N社のオランダ人と日本人プロジェクトチームは「何か困ったことはないか?」「手伝えることはないか?」と心を配ってくれた。
プロジェクトの完工式には、N社と当社の社長、アムステルダム市長や政府の役人、政治家など多数の来賓が出席したのだが、自動倉庫機能のデモンストレーションを恙なく終えることができたとき、プロジェクトに携わってきた多くの人の目にはうっすら涙が滲んでいた。もちろん繊細な私の目にも。
多くの異文化に遭遇し、「違い」を乗り越える経験をイヤと言うほど重ねてきたのだが、亡き妻との「異文化間摩擦」にはうまく対応できなかった。経験を生かして、もう少し寛容に、優しくできたのではないかと未だに悔やんでいる。
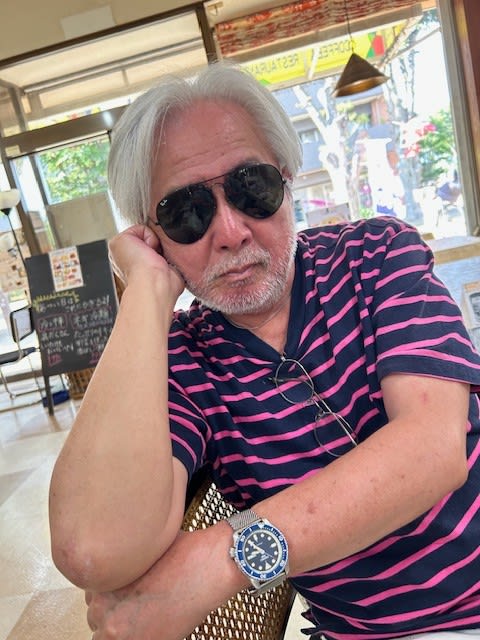
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。

























