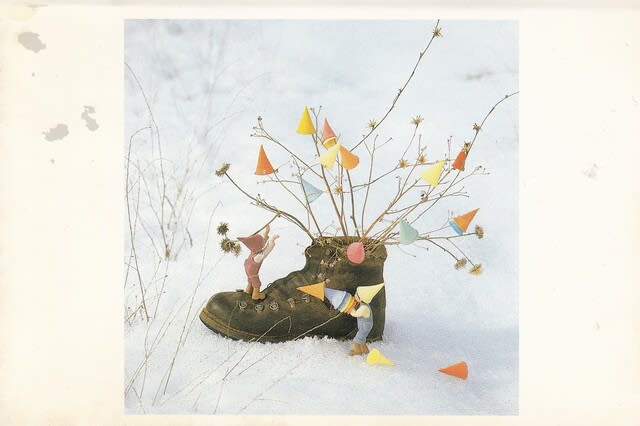個性的に生きている人間、女。男支配の社会が続いてきた世界の中でも、とくに日本で、自己主張をきちんと持ち、そして自分の生きていること、仕事、すべてに対して己一人の責任を持って対応して生きている女性に対しては、とかく風当たりが強いのです。決して、優しい、柔らかい、暖かい風だけがふいているわけではないと、私は思います。[i]
以上は、87年に澤地久枝が、癌を患いながら単身ニューヨークへ渡り闘病生活を送りながら仕事を続けた千葉敦子を偲んで行ったスピーチの中の一説である。それから、16年が経っているが、今も男性中心社会であることはこれまで見てきたとおりである。その中で女性が自立していくことは、決して容易なことではない。だが、わたしたちは「女だから」という理由であきらめてはいけない。遙洋子は著書の中でこんな高慢男に行き逢ったことを述べている。込み合った新幹線の車内での出来事である。一人の男性が座席の背もたれを思いっきり倒し、両足を思いっきり前に伸ばして坐っていた。そこに障害のあるお年寄りを抱きかかえた女性が入ってきた。その男性の後ろに坐ろうとしたが倒れた背もたれで通れない。「すみません」と声をかけても睨まれるだけだ。通りかかった女性車掌が「すみません。少し起こしていただけますか・・・」と頼んでも、男性はうっとうしそうにジロッと睨んだだけだった。見かねたほかの男性客が「手伝いましょうか」と声をかけた。その女性は「大丈夫です。何度も乗ってますが、声をかけられたのは初めて。ありがとう」と言った。結局、男性車掌がきて、無理やり前の男性の背もたれを起こして二人を通すことで一見落着した。こんな高慢男が育つ裏には、数多くの女性のあきらめがある、と遙は述べる。冷遇への、不平等への、幸せへの、そして、自分の人生へのあきらめ・・・。女性のあきらめが多いほど、立派な高慢男が完成する。障害の高齢者を抱え、現実を担っている女性に、他人はあてにしないという「あきらめ」の極地を見た。男性車掌を呼んできた女性車掌にも、「女の言うことは聞いてもらえない」というあきらめをみた。確かに女ごときの言うことなんぞ聞く男ではないだろう。それでも女性車掌はあきらめずにもっと訴えるべきだった。「あきらめ」は何も主婦だけのものではない。働く女性にも深く根ざしている。至る所で高慢男を見る度に、私はその妻を思う。一人の女性のあきらめが、社会で常に問題を起こす高慢男を育てる。どうか幸せになることをあきらめないでほしい。それが世のため人のためだ、と遥は述べる。[ii] 日本の男性にこのような傲慢男がいるのは、裏返せば女性も努力が足りないということになる。私たちは全力をふるってたたかってからでなければ負けたと思ってはならぬ。とりわけ明瞭だと思われるのは、幸福たらんと欲しなければ絶対に幸福にはなれぬ。それ故、自分の幸福を欲し、それをつくらなければならない。[iii]
キャリア、家族、人間関係、そして余暇は、互いに交錯し合い、影響し合い、補い合い、個人が選ぶ道は、個性、目標、人生の状況によって変わっていく。[iv] どんな場合でも、自分の人生は、自分で引き受けなければならない。他人が代われるものではないのだ。生きること、選ぶこと、それはあくまでも個人の問題だ。生きることは各人に委ねられた責任なのだから、生活の中で、独自の生活哲学を自ら作り上げていくことが大きな課題となる。日常生活の原理や哲学はそれぞれの人々が、己自身に戻って独自に構想しなければならないものなのである。[v]「ある」ためには生活における個人の創意の可能性を回復しなければならないだろう。人生はマラソンに例えることができる。それもただのマラソンではなく、いくつかのハードルを飛び越えながら走っていくのだ。独立、結婚、転職、出産など、いくつものハードルがあって、今はどこを飛び越えたから次はこの問題を飛び越えようと絶えず現時点を見つめながら前方に向かうことを意識していかなければならない。自分はどんな人間で、最終的には何を目標にしてどうやって実現させていくのか、自分なりのゴールを持つことだ。「私」とは誰なのか、今どこに向かおうとしているのか。こうした問いかけをしない人はいないだろう。地球上に何億といる人間の中で、これは自分にしかできないことという自信や自分の生き方に深い信念を持った自分を見出していく努力を怠ってはならない。私たちは、先ず「個」としてあるのだ。結婚していても、単身のままであっても、子供がいてもいなくても、性役割を担う前に、女性も一人の人間として、自らの人生に責任を持って生きなければならない。池田理代子は、1970年代『ベルサイユの薔薇』のなかで、オスカルという男装の女性を創造した動機を次のように述べている。
真実描きかたったことはといえば、一点につきている。女性の人間としての自我の確立とそれによってもたらされる能動的な人生である。そのことは、作品中においてオスカルが父・ジャルジェ将軍に語りかける「感謝いたします、このような人生を与えてくださったことを、女でありながらこれほどにも広い世界を・・・人間として生きる道を・・・」という言葉に集約されている。この作品が描かれた1972年という時代の日本は、まだそういったことが意識ある女性たちによって意図的に語られ啓蒙されていかねばならない、そういった社会であった。今の若い女性たちにとっては想像もつかないかもしれないが、女性が社会に出て仕事をすることが是か非かというようなことが、当事者ではない男性たちによって議論され、「男性と肩を並べて社会進出をしようというような女性を、僕らは抱きたいとは思わない」などといった、極めて論点のずれた滑稽な発言が堂々とテレビなどで、知識人といわれる男性たちによって披露されたりした社会であった。四年制の一流大学を立派な成績で出た女性達が、出版社といった一見時代の潮流を最も鋭敏に汲み取りそうな職場で、正社員にもなれず男性社員の補助に甘んじさせられていたような、そんな社会であった。女性には、自分で選び取れる自由な人生などまだない時代だったのである。[vi] すでに繰り返し記述しているとおり、均等法施行を境に女性の生き方は多様化してきた。
しかし、企業で働く女性にとって、男性優位の企業風土の中では女性を受け入れる体制が未熟なために、自分の持ち味を発揮させることができていないケースは今も少なくない。日本型企業社会の中でOLであり続けるのは容易なことではないのだ。林真理子は次のようなメッセージを働く女性に送る。あなたは、「自分だけが損をしているのではないか」という思いにとらわれていませんか。働く女性はみなその感情に苦しめられています。一生懸命やっている人ほど、いつも小さな憤りを胸に抱いているのかもしれません。要領のいい人が得をして、楽しく時を過ごしている。それなのにどうして自分は正当に評価されないのだろうか。どうして自分だけはつまらない仕事ばかり押し付けられるのだろうか。そういう時、私は自分をこう励まし続けてきました。「あなたぐらい心がまっすぐで、きちんと生きている人はいない。あなたはいつか認められる」と。自分を愛し励まし続けるというのは、プライドを持つということです。プライドさえあればたいていのことは切り抜けられる。みっともないことをしないでも済みます。[vii]
1994年時点で、ルイ・ヴィトン・ジャパンの人事・総務部長を務める竹内洋子は、キャリアは自分で築いていくものだと述べる。
私はこれまでの生き方を通じ、知らず知らずにキャリアは自分のもの、そして自分で築くものと思ってきました。しかし、日本的経営のなかでは一企業内完結型のキャリア形成が主流であり、一生の間に結婚、出産、子育てといくつかのライフステージが変わる女性は、その都度仕事との二者択一を求められ、キャリアも断念せざるをえませんでした。必然的に、ほとんどの女性にとって、終身雇用にもとづいた年功序列制度のもとでは、キャリア開発などはのぞむべきではなかったのです。ところが、バブル経済の崩壊にともなう経済状況の急変は雇用の形態や日本的経営そのものまで変えようとしています。現に今起こっている大量の中高年を中心としたレイオフや、若い層も含めた配置転換、ホワイトカラーのリストラや管理者層の年俸制の導入をみても、終身雇用制の崩壊が始まったことは否定のしようがありません。終身雇用の崩壊によって、働く者の人生を企業のなかにストックしておくことができなくなり、したがって年功序列での評価はもはや不可能となるでしょう。このような状況下では、キャリアを企業任せにしていては、永久に時の流れに取り残されてしまうのではないでしょうか。これまでは、厳しい選抜はあっても、年功序列というエスカレータに乗っていれば頂上にたどり着くことができました。しかし、今起こりつつあることは、そのエスカレータ自体がはずされようとしているのです。したがって、キャリアは自分のもので、自分で築くものと認識を改めるべきではないでしょうか。このような経済状況の変化とマネージメントの変化は、むしろ女性にとってはチャンスが広がる好機だと思います。私は、二つの言葉を贈りたいと思います。それは、「あなたも可能性の塊」「チャンスは前髪しかない」ということです。私が「あなたも可能性の塊」と聞いたのは、高校二年のとき、評論家の丸岡秀子さんの講演会でした。50歳を超えた方が、「今でも私は自分の可能性を信じている」と言われたことに新鮮でしかも強烈な驚きを覚えました。どちらかというと、人生において不器用な私ですが、「可能性の塊」ということを心から信じて今まで実践してきました。そして、チャンスの女神は前髪しかないそうです。通り過ぎてからでは、アッとおもっても、後ろ髪がないのでつかめないのです。チャンスと思ったら恐れずにつかみ、当ってみる。失敗してもよいではありませんか。やり直しは何度でもできます。自分の目的意識を明確にもち、不足の点は補い、描いた自分のキャリア・ヴィジョンにしたがって、何度でもチャレンジしてみてはどうでしょうか。そうすれば、時間がかかっても女性が時代をつくりだすときがきっと来ると思います。[viii] キャロル・カンチャーが述べるように、目的を持って人生を生き、その目的がキャリアの目的と一致するときにはじめて、「私は何者なのか。私は何になりたいのか」という誰もが抱く疑問の答えが見えてくる。それは人生に意味を与える仕事とライフワークの選択を可能にしてくれる。[ix] 自分に忠実であれば、挫折も自分が成長し次の段階へと進むきっかけにすることができる。要は自分で物事を決めることができるかどうかということだ。自分で物事を決めることができるのは、フロムが述べるところの「あること」であろう。私たちは、自分で確信をもって「こうありたい」という人生を生きたい。
**************
引用文献、
[i] 澤地久枝「千葉敦子さんを偲ぶ」千葉敦子『昨日と違う今日を生きる』180頁、角川文庫、1988年。
[ii] 遙洋子『働く女は敵ばかり』237-239頁、朝日新聞社、2001年。
[iii] アラン著、串田孫一・中村雄二郎訳『幸福論』277-278頁、白水社、1990年。
[iv] キャロル・カンチャー著、内藤龍訳『転職力―キャリア・クエストで成功をつかもう』23頁、光文社、2001年。
[v] 山岸健『日常生活の社会学』76頁、日本放送出版協会、1978年。
[vi] 池田理代子『ベルサイユのばら大事典』146頁、集英社、2002年。
[vii] 林真理子『日経ウーマン2002年8月号』200号記念特集、これからの私たちの仕事と暮らし、日経ホーム出版社。
[viii] 竹内洋子「キャリアは自分でつくる-今こそ女性がキャリアを伸ばすとき」内橋克人・奥村宏・佐高信編『就職・就社の構造』148-149頁、岩波書店、1994年。
[ix] キャロル・カンチャー、前掲書、25頁。