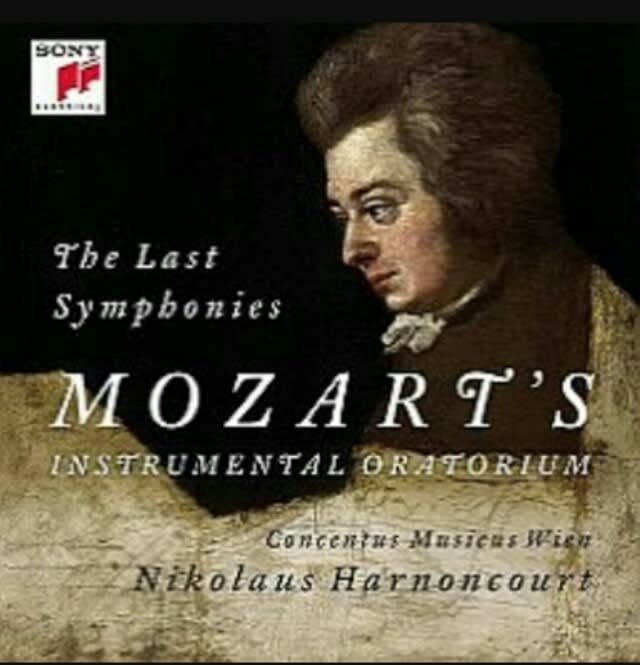クリスティ&レザール・フロリサンの実演をはじめて聴いたのは、彼らの初来日、1995年11月、三鷹芸術劇場においてである。
パーセル:歌劇「妖精の女王」とM.シャルパンティエ:歌劇「病は気から」の2演目で、いずれもコンサート形式であった。もう細部は記憶していないけれども、その清新で生き生きとした音楽による心沸き立つ感動だけは未だに心に残っている。ついでにもうひとつ覚えているのは、ホールのレストランで食べたピラフにまったく味がなかったこと。塩を入れ忘れたのではないか? と同行した友人と語り合ったものである。
まあ、塩加減の話はどうでもよい。
その後、クリスティ&レザール・フロリサンは、2003年と2006年にも来日したようだが、それは聴いていないから、今宵は21年ぶりの再会ということになる。
客の入りはザッと見渡して、4割程度だったろうか?
いかにも空席が目立ったのは、下記のようなプログラムが予告されていたため、ただ単に歌手たちがアリアを披露する音楽会と認識されたためではなかろうか? そうだとすれば、知名度の高いスター歌手がいるわけではないし、かといって、オラトリオや受難曲をじっくり聴けるわけでもない、ということで、チケットが売れなかったのもやむを得まい。かくいうわたしも、コンサートのコンセプトなどは何も知らないまま客席に着いたのだが、いざ始まってみると、実に知的で、愉快な音楽ショーだったのだ。
つまり、ストラデッラ、ヘンデル、ヴィヴァルディ、チマローザ、モーツァルト、ハイドンなどのアリアや重唱を繋ぎながら、二部構成のドラマとして再創造されていたのである。この辺り、宣伝の段階でもっと内容の面白さをアピールできれば、もう少し違っていたのではなかろうか?

レザール・フロリサンのアンサンブルは美しい。
弦五部は4-4-3-3-2、管はオーボエとトラヴェルソが各2、それにチェンバロというシンプルな編成なのだが、ピリオド楽器としては、しなやかでありながらも、重厚感のあるサウンドで、その低音がズシンと腸に響いてくる。
6人の歌手たちも、1人1人の技量が優れているだけでなく、アンサンブルのバランスが絶妙で、そのハーモニーの美しさは「まさにこれ、これです。こういうハーモニーが欲しいのです」と我がすべての合唱団員に伝えたい衝動に駆られるほど。
さらに、クリスティの指揮にも魅せられた。まったく、虚飾のない運動なのだが、その指、腕、全身から音楽の波が生み出され、それがオーケストラや歌手たちに伝播してゆく様は壮観。「まさにこれ、こういう指揮者にならなくては」と自分に言い聞かせたものである。
ひとつだけ難を言えば、サントリーホールという器は、彼らには些か大きすぎた。
「せめて、オペラシティだったら良かったのに・・・」とは、休憩時間に聞こえてきた女性たちの会話だが、思わず頷いてしまった。さらに紀尾井ホールくらいの規模であれば、彼らはもっと楽に歌い演じられたはずで、客席からもより細やかなニュアンスを受け取ることが出来たに違いない。
しかし、この演奏会が感動的であったことに間違いない。
彼らのアジア・ツアーはこのあと、ソウル~上海~マカオとつづくが、日本での公演は一夜のみ。この稀少な機会に立ち会えたことを幸運に思う。

<イタリアの庭で~愛のアカデミア>
- 日時
- 2016年10月13日(木) 19:00 開演
- 指揮
- ウィリアム・クリスティ
- 出演
- ソプラノ:ルシア・マルティン=カルトン
メゾソプラノ:レア・デザンドレ
カウンターテナー:カルロ・ヴィストリ
テノール:ニコラス・スコット
バリトン:レナート・ドルチーニ
バス:ジョン・テイラー・ウォード
オーケストラ:レザール・フロリサン
- ストラデッラ: カンタータ『アマンティ・オーラ』から
- ヘンデル: オペラ『オルランド』/オラトリオ『時と真理の勝利』から
- ヴィヴァルディ: オペラ『オルランド・フリオーソ』/『離宮のオットー大帝』から
- チマローザ: オペラ『みじめな劇場支配人』から
- サッロ: オペラ『カナリー劇場支配人』から
- モーツァルト: バスとオーケストラのためのアリエッタ『御手に口づけすれば』
- ハイドン: オペラ『歌姫』/『騎士オルランド』から、他