
Information – 四方館 DANCE CAFE –「出遊-天河織女篇-」
―山頭火の一句― 昭和5年の行乞記、9月23日の項
9月23日、雨、曇、同前-都城市・江夏屋-
8時から2時まで都城の中心地を行乞、ここは市街地としてはなかなかよく報謝して下さるところである。
今日の行乞相はよかつた、近来にない朗らかさである、この調子で向上してゆきたい。
一杯二杯三杯飲んだ-断つておくが藷焼酎だ-いい気持ちになつて一切合切無念無想。
-略- 同宿の坊さんはなかなかの物知りである、世間坊主としては珍しい、ただものを知つてゐて物を味はつてゐない、酒好きで女好きで、よく稼ぎもするがよく費ひもする、もうひとりの同宿老人は気の毒な身の上らしい、小学校長で敏腕家の弟にすがりつくべくあせつてゐる、煙草銭もないらしい一服二服おせつたいしてあげた。
酔ふた気分は、といふよりも酔うて醒めるときの気分はたまらなく嫌だけれど、酔ふたために睡れるのはうれしい。アルコールをカルチモンやアダリンの代用とするのはバツカスに対して申訳ないが。
―表象の森―「群島-世界論」-13-
語り、歌うこと‥。ことばが純粋な口誦性のなかで完結していた長い時の堆積をもつ文化においては、人間同士をむすびあわせる身体と感情と思考の環は、ほとんど例外なく物語と歌謡のなかで創造されてきた。そのとき物語とは双方向的な即興性に満ちた対話のことであり、歌謡とは旋律にのせた自由なことばの掛け合いのことであった。
アイルランド古来から、ゲール語で「オダース・ベール」-oideas beil-と呼ばれる知恵は、「口誦の教え」と直訳できるその意味からも解るように、もっぱら口と耳を回路とした声の伝達を媒介とするコミュニケーションの形式だった。歌、神話語り、物語り、地名の喚起、叙事詩の朗誦といったかたちをもって行われたこの「教え」は、大陸近代が創造した制度的「教育」がもっぱら文字言語に依拠した思考回路を想定していたのに対し、思考=イデアの口誦的な伝達に信をおいた、群島的な学びの方法論だった。そこで言葉は、大気の震動として運ばれてゆく声であり、息として外に向かって発せられる律動であり、抑揚をともなって聞き手の耳に歌いかけられる音楽であった。この音としての物質性こそが言葉の唯一無二の本姓であり、それは恣意的な表記の記号性のなかに取り込まれることを永遠に拒むvernacular-土着的-な原理だった。
言語の肉体性、それを誰よりも微細に感じとるのがDialectの群島に家を持つ詩人たちである。大陸的原理に冒された国家語の浸透がいまだ不完全な、ゆらめくDialectの島では、言葉は肉体的な存在そのものであり、それが「舌」と呼ばれてきた身体語彙の由来を証明してもいた。その意味で、大陸と群島のせめぎ合いの界面で起こる言語をめぐる葛藤と紛争は、いわば舌の疾患であり、その治療のためには時に思い切った手術が要請されることもあった。
-今福龍太「群島-世界論」/13.音楽の小さな環/より















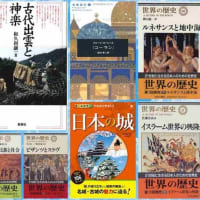




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます