概念と自我
ヘーゲルは彼の主張するところの「概念」がどのようなものであるかを少しでも理解させようと、大論理学第二巻の冒頭の「概念についての概論」のなかで、自我と概念との関係を説明している。それは次のようなものである。概念を理解する上で自我の本質を把握することの重要性を次のように述べている。
>>
「概念とは、それ自身が自由であるような現実存在へと概念が到達しているその限りでは、自我あるいは純粋な自己意識にほかならない。自我はなるほど諸概念すなわち規定された諸概念をもっているが、しかし、自我とは概念として定在するにいたっている純粋概念そのものである。それだから自我の本性をなしている根本規定のことを考える場合には、なにか周知のもの、すなわち表象にとって熟知されているもののことが考えられているのだと前提されていよう。
だがしかし、自我はまず第一にこの純粋な自己へと関係する統一であり、しかもそうであるのは、直接にではなく、自我があらゆる規定態と内容とを捨象して、自己自身との制限されていない相等性という自由へと還帰することによってである。こうして自我は普遍性である。捨象する運動として現れるあの否定的なふるまいによってのみ自己との統一であり、そして、その統一はすべての規定された存在を自己のうちに解消して含んでいる。
第二に自我はまたまさに自己自身へと関係する否定性として直接的に個別的に絶対的に規定された存在である。そしてそれは自己を他者に対立させ、他者を排除しているところの、個体的な人格性である。その絶対的な普遍性は同時にまさに直接的に絶対的な個別性でもある。そして、それ自体で自立的な存在は端的に定立された存在であり、そして、定立された存在との統一によってもっぱらそれ自体で自立的な存在であるのだが、このような絶対的な普遍性が、それ自体で自立的な存在がまたまさに概念としての自我の本性をなしている。もしも上述の二つの契機、個別性と普遍性、それ自体で自立的な存在と定立された存在が、それらのそれぞれの観念的な姿と同時に、それらの完全な統一において把握されないならば、自我についても概念について何ものも概念的に把握することはできないのである。」
<<
<<
「自我は思考することによって対象を貫き通す。だが、対象は思考のうちにあってはじめて、それ自体で自立的である。対象が直観または表象のうちにあるときは、それはまだ現象に過ぎない。思考は対象がはじめにもって現れる直接性を揚棄して、そうして対象から一つの規定された存在をつくる。しかし、この対象の規定された存在は、対象のそれ自体の自立的な存在であり、言い換えれば、対象それ自体のもつ客観性である。それゆえに、対象はその客観性を概念のうちにもっており、そして概念はその中に対象を受け入れている自己意識の統一である。だから、対象の客観性あるいは概念は、それ自身が自己意識の本性であり、自我そのもの以外のいかなる諸契機または諸規定ももってはいないのである。」
<<
ここでヘーゲルが言わんとしているのは、要するに、彼のいう概念を理解するためには、自我の本性についての、すなわち思考の本質についての理解が前提とされるということなのだろう。なぜなら、概念と自我と思考は同一物でもあるからだ。これらの論述によっても、事物を概念的に把握するということがどのようなことであるかが、おおよそ推測できるだろう。
しかし、概念は本質とは異なる。どのように異なるのか。それは、本質が単なる反省のレベルの概念であり、概念においてこそ理念(真理)に関わるレベルの概念であることだろう。単なる本質は真理とは関わりを持たない。概念においてはじめてその真理性が問題になる。だから、本質についての判断は、反省の段階における判断であり、悟性的なレベルの判断であるといえる。
付録
日本語の本質と伝統のために、私たちは日常の生活語で、哲学的な思考と認識を展開することがなかなか難しい。(あるいは、それはドイツ語などでも同じであり、哲学することそのものの難しさであると言えるのかもしれない。実際のところはまだ私にもよくわからない。)が、しかし、いずれにせよ、心がけとしては、我が国における哲学の伝統の確立と品位ある国民の形成のためにも、日常の生活語で哲学して行く努力が必要だろう。現代日本国民に見るように、形而上学なき国民は、アニマルに等しいから。
ふだん哲学などとは無縁の世界に暮らしている人たちのために、老婆心ながら一言するなら、ここで「自我」とは「Ich」のことであり、「あなた」のことであり「わたし」のことである。すべての人間は、「わたし」であり、「自意識」 でもある。「自我と概念」という世人にはおどろしい標題になってしまったが、要するに考えようとしていることは、「わたし」あるいは「自意識」と「概念」との関係である。ただ、ここで言う概念は単なる思考規定に、悟性的なものには留まらない。「美」や「真理」「善」、「法則」、「論理」などといった理性的な概念と、普遍的な「わたし」=「自意識」との関係が問題にされている。
付記2 (哲学の大衆化と少数者) 2010・07・20
当初、この小文の標題を「概念と自我」として公表したにもかかわらず、どうにもそれが気に掛かっていた。それは付録1にも書いたように、少しでも哲学的思考の能力を日本国民も培う必要があると考えていて、そのためにも、一般日本人が日常生活で使っている生活語で哲学できるような哲学用語とはどのようなものであるべきか、という思いが潜在的にあったからである。抽象的な哲学的概念はもちろん、わたしたちの生活の中に根拠を持っているのだが、日本語の発生と成立の過程からいっても、日常生活における思考の道具としての常識的な用語と哲学的概念が明確に区別されて使われるのはやむをえないとしても、その距離が大きすぎるのである。それも程度の問題である。
日常的な常識的思考と精密な哲学的思考とはもちろん区別はされなければならないが、しかし、それでも哲学的思考が日常の一般的な社会生活のなかで行われている常識的な、自然発生的な思考に深く根拠を持つことも言うまでもない。というよりも、前者は後者を母胎として生まれてくるのであり、その精髄に他ならない。
封建時代から今日にいたるまで比較的に時間的にも日が浅く――まだ、二百年も経っていない――厳格な階級社会であった武家社会の伝統が長く、また儒教的な権威主義と事大主義の慣習の色彩の濃い我が国のような文化の環境のなかで、そのなかで「哲学」に従事した者には、とくに、西田幾多郎のような旧帝国大学の権威主義的な教授の多かったことにも、哲学が国民一般大衆とは縁の遠い、何か小難しい取っつきがたいもののような印象や先入観をもたれることになっている、その原因の一端をになっているのかもしれない。
とはいえ、たしかにそうした面もあるにはあるとしても、やはり「哲学」は遠く古代ギリシャの昔から、一般大衆とは縁の薄い、少数者の特権的な分野であったということはできる。人類の大多数は生存のために、日々のパンのために過酷な日常生活を強いられている。そうしたところに「哲学」に従事するという恵まれた余暇を持ちうるのは、その事柄からいって、少数者に限られている。まして、ヘーゲルやカントのように、生涯をその学問科学のために捧げるのは例外中の例外にすぎない。また、そこに哲学の意義も限界もあるのだから、哲学はそれを享受するしかないし、それに満足すべきなのである。哲学の大衆化といった愚かなことを考えるのは、哲学というものの概念をよく知らない者が犯す自己矛盾なのだ。
ヘーゲルは小論理学第二版の序文のなかで「真理の科学的な認識は、すなわち哲学は真理を意識する特殊な仕方であって、そうした仕事にしたがうのは、すべての人ではなく、ただ少数の人に過ぎない」とも語っている。










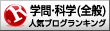


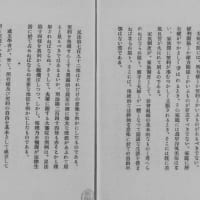

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

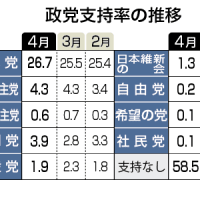











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます