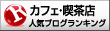古来、中国、朝鮮、日本では、赤は太陽や火、血を象徴する
生命の色で、魔よけの力があると信じられていました。
その赤に近い色をしている小豆は、食べることによって
邪気を払い、身を守ってくれると考えられていたのです。
そのため宮廷行事や儀式に使われたのをはじめ、
さまざまな形で今も残っています。
と言う事なので!是非小豆をいっぱい食べて
今年もスタートしましょうヾ(*´∀`*)ノ
本日も皆様のご来店心よりお待ちしております。

「あずきの栄養」
たんぱく質→小豆の主成分は炭水化物ですが、分量的には少ないながらも良質なたんぱく質も含んでいます。 そのたんぱく質を構成するのがアミノ酸で、なかでも人間の体内でつくれない種類の必須アミノ酸を含んでいるのが小豆の特徴です。
ビタミン→ビタミンB群が豊富で、糖質をエネルギーに変えるB1、皮膚の健康維持に必要なB2、B6に富んでいます。さらに、少量のビタミンEや葉酸も。
ミネラル→とくに食塩に含まれるナトリウムの排出を促すカリウムを多く含むので、高血圧やむくみの予防効果などが期待できます。また、鉄分も豊富で貧血や冷え性の改善に役立つとされています。
食物繊維→小豆にはゴボウやワカメの数倍もの食物繊維が含まれています。大腸の働きを助け、便秘や大腸ガン予防に役立つといわれる不溶性食物繊維と、血中コレステロールや血糖値の上昇を抑える効果が期待できる水溶性食物繊維、双方とも豊富です。
ポリフェノール→大豆のイソフラボン、お茶のカテキン、赤ワインのアントシアニンなど、おもに植物に含まれる苦みや色素の成分のこと。これらは活性酸素を抑制し、抗酸化作用をもたらす働きが検証されてきたことから、生活習慣病や老化を予防する効果で知られるようになりました。とりわけ、小豆や金時豆に含まれるのはカテキングルコシドというポリフェノールで、高い抗酸化作用が報告されているほか、小豆の赤い皮に含まれるアントシアニンは赤ワインの1.5倍も多いとか。また、あんこをつくるために小豆に砂糖を加えると、メラノイジンという物質が生成され、これも抗酸化作用をもたらすといわれています。
サポニン→小豆の特有成分で、とくに煮汁に多く含まれるサポニンは、利尿作用があるほか、コレステロールや中性脂肪を抑える働きがあり、生活習慣病の予防に役立つといわれる栄養素です。
と本日はこんな感じでまとめてみましたヾ(*´∀`*)ノ