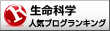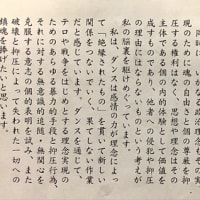夜中に雪が降った。氷の粒のような感触があった。
きのう昼すぎに、ひとりで初稽古をしたのだが、そのときに感じたものが、ふとダブった。
冷たいのに熱いもの。暗いのに明るいもの。消えてゆくのに確かなもの、、、。
正月明けの稽古で踊ってみようと楽しみに選んでおいた音楽の中にシューベルトのソナタが幾つかあって、それを聴き、稽古をした。
いづれも比較的おだやかで静かな音楽だが、踊っていると、熱というのか、激しい感情のうねりが肚の底からこみあげてくる。そして、時折、なんだか怖いものに追いかけられているような感覚が襲ってきて不安になる。しかしまたすぐに、もとの感情のうねりがもどってきて、身体が熱く激しい感覚になってゆく。
雲の隙間から日が射すように感情が見え隠れする。今までに無い感覚だった。後期のソナタは特に気持ちがぐらぐらして、深い森に迷い込んだような感覚におそわれた。
むかし、舞台でこの音楽を踊ろうとしたときに友人から停められたことがあった。あんなおそろしいものをやるのは、まだしばらく先にしないとだめだよ、まだオマエはあの曲をわかってないよ。と。
その意味がうまく呑み込めないままだったが、いま急にその友人の気持ちが腑に落ちた。耳が変わってきたのだろうか。それとも、年齢や経験とともに少しづつ敏感になってゆくような部分が、心臓や神経のどこかにあるのだろうか。
踊りながら音楽を聴くのは、測り合うようでもあるし、問答しているようでもある。耳を凝らしている。何一つ聴き逃さないようにと思う。音楽と対峙することに、どうしてもなる。音楽には、聴く者の心に眠っている感情を呼び覚ます力を宿しているものがあるが、それは作曲家が音楽に注入した魂の力が働くからなのかもしれない。
踊りながら、聴きながら、もしかすると、シューベルトはこの最後のソナタで、心の暗部や底なしの穴を音のなかに響き入れてしまったのだろうか、と思えて仕方がなかった。
暗さゆえに感じるかすかな光の美しさに似ている。底のない果てしなさを想う。そのなかに消えてゆく響きの切なさを感じる。
音が自分の身体に入ってくる一瞬、そのシューベルトの音といっしょに、見知らぬところに落下してゆくような感覚がうまれてきた。
新作への試行錯誤の途中だが、音楽なるものとの出会い直しが、自分のなかで始まっているようにも感じた。
____________________________________________________