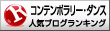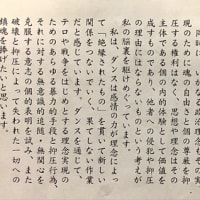先週末、作品を2つ鑑賞しました。ヤン・ファーブル氏演出/振付のダンス『死の天使』(埼玉芸術劇場大ホール)と、細江英公氏の写真絵巻『死の灰』(杉並公会堂グランサロン)です。
ヤン・ファーブル氏。いまでは最も敬愛する舞踊作者のひとりですが・・・。
今回の作品は、半畳ほどのとても小さな踊り台を150名に限定された観客が密集して囲む。さらにその周囲を4つの大スクリーンが囲んで半裸の男性ダンサー(ウィリアム・フォーサイス)が、語り踊る映像。彼の居場所は解剖学博物館、死者の身体が陳列されている。スクリーンから、すなわち彼方から、無をめぐり沈黙をめぐり、あふれこぼれる言葉、そのあとに残る行為あるいは踊りは、存在の輪郭をそっと消し去ろうとするかのごとく・・・。向き合う小さな踊り台では、半裸の女性ダンサーが立ち、埋めても埋まらぬ距離を埋め尽くそうとするかのごとく、激しくしゃべり、野獣のごとく動く。見つめる観客の密集さえもが、何かを埋め尽くそうとしている。それでも、そこはかとなく発生し続ける距離あるいは無。金縛りの中で体験するような空恐ろしいような1時間を、ダンサーはもがき、僕らはただただ見つめていた。複雑な思考の迷宮、死の影が充満する構造、その直中に立つ出演者をファーブル氏は「美の戦士」と呼ぶ。存在を立ち尽くして戦う、その姿の何と毅然としたことか。死は外側から襲いかかってくるけれど、生は内部からこそ湧き上がってくる。そんなことを、ふと思うのでした。ところで、この人の最初の来日公演は「劇的狂気の力」。その過激さと難解さに反発を示した方が多かったのだそうです。反発・抵抗・異議???。こんなに観客の想像力を信頼する人が外国には居るのだ、と当時、僕は勇気がわいたのでしたが・・・。今想えば、あの時いや、おそらくもっと最初の時点から、ファーブル氏は死や虚無や沈黙と真摯に向き合っているアーティストです。だから作品ひとつ創るたびに問いかけざるを得ない、挑発せざるを得ないのではないか。「あなたは生きているのですね」と。
同様の問いかけが、細江英公氏の写真展からも感じられました。こちらは形而上学というよりは、死者の存在そのものを魂の側から扱ったのではないかと僕は受けとりました。ポンペイの廃墟、アウシュヴィッツ、トリニティーサイト(人類最初の核爆発点)、そしてヒロシマ。これらの風景を灰色の濃淡で写し取った絵巻「死の灰」。僕は、アウシュヴィッツの収容所跡を、大学を出てすぐに訪ねたのですが、骨の芯まで冷え凍えたようになりました。どうして良いのか分からない、人間である事自体とても罪深いことであるような戦慄のなかで、なぜかゴメンナサイとひれ伏すような気持ちになった。あの、トラウマに近い体験を思い出しながら、細江氏の写真の中を歩きました。一枚一枚、透き通るような美しさです。地獄や痛みの痕跡を、美で弔うことなのでしょうか。生きている人間が死者とつながってゆこうとする静かな行為が、そこにありました。印象深かったのは、トリニティーサイトの写真。広大な砂漠に小さな記念碑、そのそばに古い原子爆弾がひとつ・・・。
メメント・モリ(死を想え)という言葉があります。生ある限り、死もかならず訪れる。
ダンスの練習や上演を行為するなかで、カラダの火を燃やせば燃やすほどに、いつかこのカラダが直面せざるを得ない「その時」を想わずにはいられぬことがあります。
そんなときダンスは、より白熱して限度を超えた燃焼を求めてゆくか、沈静化して微かな呼吸にさえ耳を澄ますギリギリの佇まいを求めてゆくか、といった、極端な二元化へと走り出してゆきそうになり、何をしたいかなどどうでもよくなります。ただコノ瞬間を確かにアリたいだけ。実は、踊りはそのようなものなのかもしれません。死、あるいは、その想念と寄り添いながらのイノチの体験。かぎりある身こそ、せいいっぱい燃やす、ということ。問いかけ、努力、現実、現象、こころとからだの・・・。死。芸術はしばしば、このイマジネーションを内部に宿して制作されます、いえ、芸術家でなくとも、僕らは小さな子どもの頃から、生きている限り、人は内部に死と向かい合って、あるのかもしれない。そういえば、"la mort(死) "は "amor(愛)" に、重なる。ことばあそびですが・・・。
ヤン・ファーブル氏。いまでは最も敬愛する舞踊作者のひとりですが・・・。
今回の作品は、半畳ほどのとても小さな踊り台を150名に限定された観客が密集して囲む。さらにその周囲を4つの大スクリーンが囲んで半裸の男性ダンサー(ウィリアム・フォーサイス)が、語り踊る映像。彼の居場所は解剖学博物館、死者の身体が陳列されている。スクリーンから、すなわち彼方から、無をめぐり沈黙をめぐり、あふれこぼれる言葉、そのあとに残る行為あるいは踊りは、存在の輪郭をそっと消し去ろうとするかのごとく・・・。向き合う小さな踊り台では、半裸の女性ダンサーが立ち、埋めても埋まらぬ距離を埋め尽くそうとするかのごとく、激しくしゃべり、野獣のごとく動く。見つめる観客の密集さえもが、何かを埋め尽くそうとしている。それでも、そこはかとなく発生し続ける距離あるいは無。金縛りの中で体験するような空恐ろしいような1時間を、ダンサーはもがき、僕らはただただ見つめていた。複雑な思考の迷宮、死の影が充満する構造、その直中に立つ出演者をファーブル氏は「美の戦士」と呼ぶ。存在を立ち尽くして戦う、その姿の何と毅然としたことか。死は外側から襲いかかってくるけれど、生は内部からこそ湧き上がってくる。そんなことを、ふと思うのでした。ところで、この人の最初の来日公演は「劇的狂気の力」。その過激さと難解さに反発を示した方が多かったのだそうです。反発・抵抗・異議???。こんなに観客の想像力を信頼する人が外国には居るのだ、と当時、僕は勇気がわいたのでしたが・・・。今想えば、あの時いや、おそらくもっと最初の時点から、ファーブル氏は死や虚無や沈黙と真摯に向き合っているアーティストです。だから作品ひとつ創るたびに問いかけざるを得ない、挑発せざるを得ないのではないか。「あなたは生きているのですね」と。
同様の問いかけが、細江英公氏の写真展からも感じられました。こちらは形而上学というよりは、死者の存在そのものを魂の側から扱ったのではないかと僕は受けとりました。ポンペイの廃墟、アウシュヴィッツ、トリニティーサイト(人類最初の核爆発点)、そしてヒロシマ。これらの風景を灰色の濃淡で写し取った絵巻「死の灰」。僕は、アウシュヴィッツの収容所跡を、大学を出てすぐに訪ねたのですが、骨の芯まで冷え凍えたようになりました。どうして良いのか分からない、人間である事自体とても罪深いことであるような戦慄のなかで、なぜかゴメンナサイとひれ伏すような気持ちになった。あの、トラウマに近い体験を思い出しながら、細江氏の写真の中を歩きました。一枚一枚、透き通るような美しさです。地獄や痛みの痕跡を、美で弔うことなのでしょうか。生きている人間が死者とつながってゆこうとする静かな行為が、そこにありました。印象深かったのは、トリニティーサイトの写真。広大な砂漠に小さな記念碑、そのそばに古い原子爆弾がひとつ・・・。
メメント・モリ(死を想え)という言葉があります。生ある限り、死もかならず訪れる。
ダンスの練習や上演を行為するなかで、カラダの火を燃やせば燃やすほどに、いつかこのカラダが直面せざるを得ない「その時」を想わずにはいられぬことがあります。
そんなときダンスは、より白熱して限度を超えた燃焼を求めてゆくか、沈静化して微かな呼吸にさえ耳を澄ますギリギリの佇まいを求めてゆくか、といった、極端な二元化へと走り出してゆきそうになり、何をしたいかなどどうでもよくなります。ただコノ瞬間を確かにアリたいだけ。実は、踊りはそのようなものなのかもしれません。死、あるいは、その想念と寄り添いながらのイノチの体験。かぎりある身こそ、せいいっぱい燃やす、ということ。問いかけ、努力、現実、現象、こころとからだの・・・。死。芸術はしばしば、このイマジネーションを内部に宿して制作されます、いえ、芸術家でなくとも、僕らは小さな子どもの頃から、生きている限り、人は内部に死と向かい合って、あるのかもしれない。そういえば、"la mort(死) "は "amor(愛)" に、重なる。ことばあそびですが・・・。