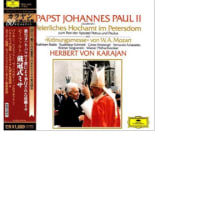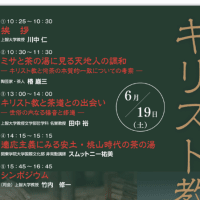歴程神学の課題
田中 裕
1984年に南山大学で開催された国際学会で、私はホワイトヘッド哲学とハヤトロギアの関係について論じた。[1]これは、有賀鐵太郎のオリゲネス研究や、キリスト教に於ける存在論の問題に触発され、ホワイトヘッド哲学をハヤトロギアの文脈で捉えた論文である。ハヤトロギアとは、ヘブル思想とギリシャ哲学との緊張と対立の只中に於いて成立した世界宗教であるキリスト教的な思惟を出エジプト記におけるモーゼの受けた神名の啓示という出来事、すなわち אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (ehyeh asher ehyeh) の動詞ハヤーに含意される神論を意味する。この出来事はユダヤ民族がエジプトという囚われの大地を離脱し、歴史的世界へと脱出したことを記念するものであるので、今後、この出来事に立脚する神論であるハヤトロギアを「歴程神学」と呼ぶことにする。
ハヤトロギアは単に時間と歴史的世界に対するキリスト者の独自の了解にとどまらず、物質的なもの(サルクス)と精神的なもの(プネウマ)にかんするキリスト教的な独自の了解、受肉、受難、死/復活というキリスト教神学の根本的な事柄に関わっている。それらはギリシャ的な理性にとっては愚かなことであり、ユダヤ人にとっては躓きであった。ハヤトロギアは、このような神学的な事柄を、我々の人格的な超越論的な経験に即して、いかに語るかという課題を提示する。そして、この問題を、後期のハイデッガーに由来する存在―神論の脱構築という文脈で考えたい。すなわち、存在者を存在せしめているものを高次の存在者として意識の前に現前するものとして立てる形而上学の脱構築という文脈で考えることが本論の課題である。
最初にホワイトヘッドの哲学とそれに影響を受けたヨーナスの生命の哲学を取りあげる。此処での課題は、「生あるもの」と「生きること」の間にある生命論的差異とでも云うべきものを問題とする。生きることを根拠づけるために大文字の「生」をもちだすことによって生の理解は成立するであろうか。寧ろ、「生の哲学」は「死生の哲学」にならざるを得ないのではないか。田辺元が嘗て云った様に、「生の存在学」は、「死の弁証法」に転換されるべきではないか、という観点からヨーナスとホワイトヘッドの生命哲学を論じたい。
次に、キリスト教との関わりという視点から、西田哲学を考察し、この哲学が汎神論から万有在神論へ、そしてその万有在神論をさえ越えるエレメントを有することを、「無の自覺的限定」のキリスト教論、「場所的論理と宗教的世界観」の宗教哲学を手引きとして考察する。そこでは、同一性が絶対否定を通してのみ成立するという「即非的弁証法」が、たんなる無媒介的直接性を表現する「即」の論理を越えてキリスト教的な超越論的経験の事実をどのように表現しえたかという問題を取りあげたい。
環境倫理の分野で先駆的な仕事をした哲学者であるハンス・ヨーナスは、「責任という原理」と対を為す主著である「生命の原理」や、その思想的な遺書とも云うべき講演記録「哲学・世紀末に於ける回顧と展望」のなかで、最も影響を受けた哲学者としてハイデッガーをあげると共に、後半生に於ける彼の生命哲学の構築にさいしてはホワイトヘッドの有機体の哲学に深く影響されたことを認めている。[2]
ヨーナスもホワイトヘッドも共に、存在よりも生成を基本的な範疇とし、生成を価値実現の過程として記述することによって、自然的存在と精神的価値、物質的なるものと観念的なるものの二元的分離を超克することを課題としている。そして、時間性に立脚する実存のカテゴリーを、人間を含む有機体生命にも適用できるように普遍化し、そのような有機的生命の進化の宇宙的なプロセスの中に人間存在を位置づける。次に、このような存在論=価値論を背景として、人間の当為と責任の問題が論ぜられる。その際に、同世代の互恵性にもとづく共時的倫理だけではなく、通時的な世代間倫理を主題化し、人間が他の人間に対してだけでなく、意識を持たぬ自然に対して有する責任をも含む「責任倫理」を構築する。上記の論点について、ヨーナスとホワイトヘッドの見方を比較しつつ、私自身の見解を述べておきたい。
人間中心主義から生命中心主義への転換を訴えるエコロジストは、「環境」という言葉そのものにも人間中心主義の残滓を認めて、その代わりに「生命圏」という言葉で人間を含む生命システム全体を表現することを提案している。[3] しかしながら、そのような「生命圏」を主張する論者であっても、生命圏にある物質的な世界の全体、すなわち無機物をも含めて一切の現実的な存在が、それぞれ固有の價値をもつという主張をすることは西欧の思想史に於いては希である。 ホワイトヘッドの形而上学は、この点に於いては、極めてラジカルである。そこでは、我々が無機物質と考えているものも、物質性と観念性の両極を兼ね備える活動的存在(actual entities) の結合体であり、宇宙をそれぞれの観点から抱握し、自らを実現する意味に於いては、一切の現実的存在が、他者に対してのみならず、自己自身に於ける価値を有するのである。
このように現実に存在しているものをすべて活動的存在として捉えるホワイトヘッドの有機体の哲学に対して、ヨーナスは「その知的な力強さと哲学的意義に於いて私達の時代に匹敵するものをもたない」ことを高く評価している。しかしながら、ヨーナスは、ホワイトヘッドとは違って、死せる無機物質と新陳代謝を特徴とする生命的有機体の間には決定的な断絶があるという観点から、「生命の登場と共に生じた存在論的革命」を強調し、ホワイトヘッドの有機体の哲学は、ライプニッツのような一元論的・モナド論的な考え方が強調されるために、「通常の物理的カテゴリーに従えば謎である生命の同一性が謎でなくなる」ことに不満を呈している。[4]
ホワイトヘッドに比べるとヨーナスは西欧のコスモロジーの伝統に忠実であって、無機の物質的世界を本質的に生命なき物体の集合体と考え、植物と動物、そして理性的な魂をもつ人間のみを生命の哲学の対象としている。生命とは無機物質への解体という意味での死と隣り合わせであり、そのような生命をもつ有機体の出現を、宇宙の歴史における『存在論的革命』と捉える発想がある。
しかしながら、生物と非生物との非連続性を強調するこのような考え方には、近代の科学的唯物論を前提としたうえで、宇宙に於ける生命の出現を説明しようとする近代的な自然観―ヨーナス自身はその克服を目指しているのであるが-の残滓があるのではないだろうか。
ヨーナスの批判は、一般にホワイトヘッドの自然哲学を汎生命主義として理解する誤解に基づいている。ある有機体が「生きている」かそうでないかは、一つ一つのミクロ的な活動的生起について云われることではなく、諸々の活動的諸生起の連鎖からなるマクロ的な構造化された社会存在について云われる事柄である。したがって、ホワイトヘッドの哲学は、より適切に云えば、汎主体主義(pan-subjectivism)なのであって、意識や生命を伴うとは限らない諸々の感受作用が目指す主体の生成を万有の基底にみとめる自然哲学なのである。
このように有機体という概念の適用範囲において、それをあくまでも無機物質との対比に於いて理解するヨーナスと、すべての現実存在を有機体として捉えるホワイトヘッドとの間に相違点があることは認められるが、ヨーナスの「生命の原理」とホワイトヘッドの「過程と実在」には、有機体の哲学という存在論を基盤として人間の自由と責任を基礎づけようとする課題が共通している。ヨーナスの場合、ハイデッガー的な実存の哲学を有機体の哲学によって乗り越えてゆくという文脈で「有機体と自由」を語り、「一方では観念論および実存主義の哲学の人間中心主義的な制約を、他方では自然科学の唯物論的な制約を共に打破すること」を試みたわけであるが、彼はその際に、ホワイトヘッドが「過程と実在」で試みた存在論と同じ試みを、彼の言葉で、次のように要約している。(op.cit. S.9)
人間が自己の内に見出す大いなる矛盾―自由と必然、自律と依存、自我と世界、関係と個別化、創造性と可死性―はもっとも原始的な生命形態の内にすでに萌芽的な原型を有しているのであって、それぞれの生命形態は存在と非存在の危うい均衡を保ちつつ、つねにすでに「超越」の内的な地平を自らの内に含む。
実存論的な時間分析と実存カテゴリーによって解明された人間存在の自己矛盾を、有機的生命分析に適用した「哲学的生物学」がヨーナスの構想であったが、ホワイトヘッドの試みたことは、ヨナスよりもさらにラジカルであった。そこでは、単に「原始的生命形態」と云うにとどまらず、あるとあらゆる現実存在の根柢にある創造性に着眼し、創造性によって産出され、自己決定する主体的な活動的存在がいかにして世界から生成するか、またそのような主体がいかにして自己超越体として、自己を世界に客観として与えるかを分析したものと云えるであろう。今此処に実存して、自己と世界と神の存在に関わる人間に於いて重要な意味をもつ範疇的図式を、記述的に一般化して、万有の根柢にある活動的存在そのものの生成論的分析に適用したところに『過程と実在』の思弁哲学の基本的な構想があったからである。
ハンス・ヨーナスは「生命の原理」の後で、環境倫理学に多大な影響を与えた「責任原理」を出版した。ホワイトヘッドには、形而上学の書としての「過程と実在」と「観念の冒険」における文明論はあるが、独立の倫理学的著作はない。しかしながら、「過程と実在」の範疇的図式論には、存在と当為を媒介する議論が含まれている。すなわち、範疇的図式は、八つの存在の範疇、二七の説明の範疇、九つの範疇的責務(Categorial Obligation)によって構成されるが、このなかの範疇的責務こそが、生成論によって存在論と倫理学を媒介する役割をはたしているのである。 ホワイトヘッドの議論に即して云えば、
(一)創造活動によって主体的統一性を獲得した活動的存在が、(二)客観的統一性と(三)客観的多様性を首尾一貫したかたちで保持しつつ、(四)物的抱握を基盤として精神的な価値を実現し、(五)観念的逆転の範疇によって過去の現実的世界を超越する新しい価値を実現し、 (六)変換の範疇によって個々の活動的存在が形づくる社会存在において公共世界に於ける価値の存続を実現し、(七)主体的調和の範疇において、諸々の感受作用、否定的な抱握作用の「共生(concrescence)」の創造過程によって生み出された「主体」が、同時にそれらの諸々の感受作用の主体として予定調和的に成立することを述べ、(八)そのような主体こそが、目的を志向的に感受の内的充実を目指すものであることを指摘し、最後に(九)自由と決定の範疇に於いて、活動的存在の内的な自己決定と外的な自由の存在論的な根拠を保証する。
この範疇的責務にかんする存在論的議論は、人間の行為に関わる倫理学そのものではないが、いかにして人間の倫理的な責務が、身体的な触発と観念的評価を統合から生じるか、また、個々の活動的生起が、いかにして自らの主体性と客観世界の多様性を統合し、自由と責任を負う主体として生成するかを、一般的に記述したものである。
ハンス・ヨーナスの生命哲学は、生と死が矛盾的に結合したものとして有機体を捉えていた。彼は、ホワイトヘッドの形而上学が、ライプニッツのモナドロジーとおなじく、死の問題を忘却しているのではないかという危惧を表明している。この危惧もまた、ホワイトヘッドの哲学を汎生命主義とみる誤解に根ざすものであるが、生命倫理でいう生とは死と切り離すことが出来ぬということ、したがって生命倫理は死生学という視点から捉えなければならないことを指摘したものとしては正当なものである。
私は2011年に上智大学で「共生」を主題とする国際会議を主催したが、「共生」もまた、死を免れることのない存在である我々自身のことを忘れては論じることの出来ない問題である。そもそも生物が生きるということ自体の中に、死が不可分のものとして前提されている。死者は、主観的存在としては消滅したとしても、客観としては、生者の内に依然として生きている存在である。ホワイトヘッドは、人間の生死の問題を、普遍的な存在論を背景として論じ、活動的な生起の生成と消滅の文脈に位置づける。すなわち、一個の活動的生起としての自己は、主体として消滅することによって、はじめて客観として他者の内に存在することができるものである。「死しても尚生きている」というのではなく、「死することによって生きる」という、この「客観的不滅性」の思想が、科学技術の時代に於ける死生学にたいして如何なる意味を持つかを考察しなければならない。
一つの含意は、死は独我論的あるいはモナド的な個体の経験する事柄ではないという事である。誰もが自己自身の死を経験できないにもかかわらず、個々の人間の実存にとって本質的な意味をもつ特異な可能性として死を捉えたことは実存哲学の洞察であったが、それだけでは一面的なのであって、死は、単なる実存的可能性にとどまるものではなく、その中に客観的・公共的側面を不可欠的にもたざるをえないという現実を直視しなければならないであろう。すなわち、他者の死は自己の生にとって、自己の死は他者の生にとって本質的な関わりをもつという意味で、死は現実の生と不可分である。
尊厳死や臓器移植や妊娠中絶のような生命倫理の諸問題を論じる場合、我々は、往々にして個人の死の選擇に関する自己決定権として論じがちであるが、生死を交差する自己と他者の関わりという、ホワイトヘッド哲学に固有の「共生」の視点を持つことが必要であろう。
現代の応用倫理学に於いては、正義の倫理と責任の倫理と並んで「ケアの倫理」の必要性が次第に認識されている。そこに於いては、自己と他者との具体的な関係性に立脚した倫理学が説かれ、「自律」と「普遍性」を重んじる「正義の倫理」と對立ないし、それを補完する倫理学の立場として登場した。生命倫理や医療倫理に於いては、患者の自己決定権の問題などを普遍的な原理に基づいて考察するだけでは医療の現場において生まれる複雑な状況に対応できないという反省が生まれ、医療状況の個別的な配慮を重視するようになった。とくにターミナル・ケアとグリーフ・ケアは、死に直面してもはや回復の望みのない患者に対する配慮であり、自己にとってかけがえのない伴侶や肉親の死によって受けた悲嘆に苦しむ人への配慮である。そのようなケアーは、倫理的な自己決定をおこなう主体そのものの存在が問題となる以上、普遍的な理性と意識的な生の立場に基づく個人主義の倫理では捉えきれず、理性よりも根源的な意識以前のレベルで成立する具体的関係と、そのような関係によって触発された情感をふくむトータルな人間把握をすることが肝要となるが、それこそがケアーの倫理に固有の領域である。
ホワイトヘッドは、「観念の冒険」において、そのような情感に立脚する具体的な関係こそが人間経験の根柢でありことを指摘している。彼は、「配慮(Concern)」というクエーカー教徒の用語を使って、主-客の情感的構造を、「主観としての経験の生起は、客観に対して配慮を持つ。そして配慮は同時に、客観を主観の経験に於ける構成要素として位置づけ、情感的色調(affective tone)は、この客観から引き出され、それへと差し向けられている」と述べる。この主-客構造は、知るものと知られるものとの関係ではなく、それよりも根源的な情感的関係である。言い換えれば、我々は理性的存在である以前のレベルで他者と情感的関係を通して交流しており、その段階においてすでに主体的に活動しているのである。そして、眞に活動的なる現実的存在は、常に客観で有ると同時に主観でもあるのであるから、ホワイトヘッドの云う「配慮」の構造は、意識や理性の働く以前の段階で、すでに相互主観的構造をもっている。言い換えるならば、「配慮」こそは、情念と理性との統合体である人格相互の交わりを根柢に於いて支える具体的関係に他ならない。他者によって配慮された人格的経験を持つものこそ他者を深く配慮しうると云うケアの倫理学の主張は、このように配慮を意識以前、理性以前の経験のレベルで捉えるときに、単なる主知主義的な形式的倫理学を越えて、「人格への配慮」を中心とする実質的な倫理的学への道を開くであろう。
次に単なる理性的な形而上学にとどまらず、ヨーナスの提起した神学的問題を、歴程神学の課題として取りあげよう。ヨーナスの「アウシュビッツ以後の神学」は、あえて批判哲学の禁を犯して、神話的な物語として語られたが、そこにおける中心的な論点は「神の全能」の否定である。アウシュビッツという根源悪の事実を前にして、「歴史の主」としての神の全能、神の善性、そして神の可知性をすべて認めることは論理的に不可能であるというトリレンマが議論の出発点である。ヨーナスは、ユダヤ教の「神の収縮」という神話を手掛かりに、アウシュビッツにおける神の無能力を弁明する。神はすでに人間を創造するときにその全能性を全面的に放棄したのであるから、人間は全能なる神の救済をあてにするのではなく、自らを創造した神に対して被造物としての責任を自覚し、本質的に偶然に支配されたこの世界に於て、被造物としての人類の存続に対して、自ら責任を負うべきことを論じている。
ホワイトヘッドの形而上学でも「神の全能」は否定される。しかし、それはヨーナスのように創造主の全能の放棄、ないし人間に対する全面的な譲渡という神話によって物語られるのではなく、形而上学の究極の範疇を神ではなく創造性(Creativity)とするところに示される。
創造性は如何なる意味でも対象化されざる根源的な活動であり、神よりも存在論的に先行する。時空を越えた無限なる現実的存在者としての神をすら超越する創造性は、一性と多性とならび、神と世界とに共通の超越論的述語であり、普遍の普遍(the universal of universals)である。
創造性は存在と価値に関しては無記であり、それが現実化するために神と世界を共に必要とする。現実的存在者としての神は、伝統的神学で前提されていたような有的な全能の創造主ではなく、神の存在は本性的に神ならざる有限なる時間的世界を必要とし、有限なる時間的世界もまた本性的に世界ならざる神を必要とするという意味で、創造性―神―世界は不可分の三一構造を形づくる。
創造性は、さらに一性と多性という超越論的述語と組み合わさって究極の範疇(the categories of the ultimate)を形成する。「多性」を「一性」とならんで超越論的述語とするところに、ホワイトヘッドが新プラトン主義の伝統を脱構築して、世界の多様性を肯定的に受容する形而上学を構想したことを示している。すなわち、自己同一性(self-identity)だけではなく、自己差異性(self-diversity)が創造性には必要であり、自己同一は、「多性」と「一性」が歴史の中で相互に創造的に転換するプロセスによって歴史的世界が成立する。「多は一となることによって、一によって多様化される(The many become one, and are increased by one)。
歴程神学における創造性(creativity)と神との関係は、シェリングの自由論に於ける「神の内なる自然」と神の関係、ないしベーメの「無底」と神の関係に先駆を認めることが出来るが、伝統的なキリスト教神学には見られぬものである。それはむしろ大乗仏教に於ける空性(sunyata)ないし真如と、真如より来るものとしての如来の関係(空性の顕了)に近いが、救済を歴史の中に於ける創造性の活動のただなかにおいて求める点が大乗仏教とは違っている。すなわち輪廻転生する生死の円環的連鎖、永劫回帰する世界(そこには来世においても新しきものは無い)からの解脱ではなく、一回きりのかけがえのない歴史的世界における創造活動の中で救済を求める点が、空性ではなく創造性を超越論的述語とした意味がある。すなわち、歴程において、既在性が物質的世界からの限定を表現するとすれば、将来性が理念的世界からの限定を表現するのである。両者の限定のもとに現在に於いて自己形成を行う主体は、自己創造的被造物(self-creating creature)であり、世界をその都度抱握することによって、世界を内在させ、そのことによってその現実世界を超越する存在として、他者としての諸々の現実的存在に自己を与える。この自己能与の結果が活動的生起の自己超越性(superjective nature)である。
この意味で、有限なる活動的生起は、物質性と理念性を両極として統合するモナドであるが、世界を内在させることによって、未来の本質的に新しい世界に向けて自己超越するのである。この点に於いて、個々の活動的生起は、創造的世界の創造的要素として、無限の現実的存在である神と世界との関係を、逆対応的に表現する。すなわち、神に於いては、無尽蔵の永遠的形相の理念的評価が先行し、物質的世界によるこれらの理念の世界による制約された実現が後行するのに対し、個々の有限なる活動的生起は、世界に於て既に実現された諸理念を物質的に抱握することから自己形成を開始し、自己の主体性を導く原初の目的因を神より理念的に与えられること(理念的転換)によっての自己をあたらしき存在として既存の世界に与える。神において先なるものは個的実存である活動的生起にとっては後なるものであり、神に於いて後なるものはその活動的生起にとっては先なるものである。このような神と個々の実存者との逆対応的関係によって世界の歴程が成立する。
最後に、キリスト教に於ける神と自然との共生というテーマをホワイトヘッドの宗教哲学を手引きとして考察しよう。新約聖書の正典ではないが、二世紀に成立したと推定されるトマス福音書のイエス語録77には次の言葉がある。(John S. Kloppenborg et al. Q-Thomas Reader,(Polebridge Press 1990)
イエス言ひ給ふ。我在りて万物の上なる光なり。我在りて万物なり。万物は我より出で、我に達せり。木を割りてみよ。我自らそこに在り。石を上げよ。そこに汝等我を見出すなり。
これは、トマス福音書の中で最も良く知られた一節である。新約聖書学者の佐藤研氏は一つの可能性として、トマス福音書は、禅宗における公案のような読まれ方をしたのではないかと述べている。公案が、究極的には「汝は何ものか?」と問い、本来の自己の所在を問うものであるならば、トマス福音書が志向するものもまた、イエスをイエスたらしめていた本来的自己にキリスト者が目覚めることを要求しているからである。
「木を割りてみよ・・」は、オクシュリンコス・パピルスにギリシャ語断片として見出されていたテキストであり、これについて、ホワイトヘッドは1926年に公刊した『宗教とその形成』の中で次のように言っている。(A.N. Whitehead, Religion in the Making, pp.61-62, Cambridge University Press, 1926 )
数年前あるエジプト人の墓で一枚のパピルスが発見されたが、この文献は、たまたま「キリストの語録」と呼ばれる初期キリスト教徒の編集書であった。その正確な信頼性とその正確な権威とがわれわれにとって問題なのではない。私がそれを引用するのは、キリスト生誕後の最初の数世紀間にエジプトにいた多くのキリスト教徒の心理状態を示すものとしてである。その当時、エジプトはキリスト教思想の神学的指導者たちを提供していた。我々は、この『キリストの語録』のなかに「木を割って見よ、そうすれば私はそこにいる」という言葉を見出すのである。これは内在性の強力な主張の一例に過ぎないが、セム族的概念からのはなはだしい離脱を示している。内在性は周知の現代的教説である。注意しなければならない点は、この教えが新約聖書の様々な部分に内包されていることであり、またキリスト教の最初の神学時代において顕在的であったということである。
この引用文は、極端な超越性と極端な内在性のドグマの双方を否定するホワイトヘッド自身の神学思想を投影したものでもあったが、彼が、引用したオクシュリンコス・パピルスの文は、20年後、やはりエジプトのナグハマディで発見されたコプト語訳のトマス福音書の一節であったことが判明した。トマス福音書について、その聖書学に於ける意義を洞察した最初の学者の一人であり、校訂者でもあったユトレヒト大学の古代キリスト教史家G・クイスペルは、上述の「木を割りて見よ・・」を含むイエス語録の言葉のいくつかをトマス福音書の中に認めたときに、直観的に、「この福音書には共観福音書に編集されているイエスの言葉伝承そのものが収録されている、すなわち現行の福音書よりも旧い段階の福音書ではないか」と思ったということである。(荒井献 「隠されたイエス-トマスによる福音書」(講談社 9頁)
私自身は、トマス福音書はイエス語録なる文藝様式のキリスト教文書が実在したことを示す重要な発見であると思うが、ここでは、トマス福音書にあって共観福音書にない言葉(アグラファ)が、歴史的イエスにさかのぼる伝承であるかどうかという聖書学者の専門的論争には立ち入らない。そういうことよりも、私は、ホワイトヘッドと同じように、イエスのこの言葉を伝えた最初期のキリスト教徒がもっていたキリスト理解から深く学び、それを適切に解釈することによって、彼らと共に生き、その精神を現代において継承することに関心があるのである。ここでは神と自然との「共生」という主題に関連づけて、このトマス福音書の言葉を解釈してみよう。
イエスは大工の息子であり、「木を割って・・」「石をあげて・・」ということばの示すように、彼は、樹木や岩石を加工し、家を造る手仕事労働に子供時代より親しかったであろう。そして、「木を割る・・」ことは、当然の事ながら、樹木の生命を犠牲にして、それを人間のために役立てることを意味している。我々が建築をするということは、樹木の生命を奪うことを意味するのであり、いうなれば樹木の死のお陰で我々は生活しているのである。
まことに汝等に告ぐ。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらむ。死なば多くの実を結ぶべし。(ヨハネ12.24)
というヨハネ伝のイエスは、御自身の受難を一粒の麦に喩えている。「野の花」「空の鳥」のなかに父なる神の心を感じ取る感性は、建築士が見捨てた石ころや、割れた樹木の中にさえ、いやそのような小さきものの中にこそ御自身を見出していたのではないか。端的に言って、イエスは、樹の痛みを知る人ではなかったろうか?仏教においても「草木国土悉皆成仏」という思想は、樹木を伐採して寺院を建築することを生業とする仏教者が、樹木に感謝する意をこめて言い始めたものであって、素朴なアニミズムなどではなかったという。私は、福音書の中に描かれたイエスのなかに、そのような、他者の犠牲を代償として生きなければならぬ人間の生のただ中に受肉したキリストのこころ、「悲しみの人にして悩みを知る」キリストの、すべての被造物におよぶ無限の愛と救済の意志を感じるのである。イエスによる救済は、只人間にのみむけられているのではない。それは「いと小さき物」を含むすべての被造物に対して向けられているのである。パウロもまた、ロマ書の中で次のように言う。
それ造られたるものは切に慕ひて神の子たちの現れんことを待つ。造られたるものの虚無に服せしは、己が願によるにあらず。服せしめ給ひしものによるなり。されどなほ造られたるものにも滅亡の僕たるさまより解かれて、神の子たちの光栄の自由に入る望みはのこれり。我等は知る、すべて造られたるものの今に至るまで共に嘆き、ともに苦しむことを。(ロマ書8.19-22)
キリスト教が人間のみを特別視して、他の被造物を顧みないと言うものがいるが、すくなくも初代教会の使徒の言葉は、そういうものではないようである。「すべての被造物が今に至るまで共に嘆き、ともに苦しむ」ことを知る彼らにとって、キリストの無化(ケノーシス)とその救済の行為は、ひとり人間のみにとどまらず、草木や石のごとき被造物にまで及ぶものであった。
キリスト教の典礼の中心は聖体拝領であり、最後の晩餐というかけがえのない歴史的出来事の反復であると同時に、神の食卓にまねかれて食事を共にする(conviviumの)儀式であった。それは、神自身にほかならぬキリストが自らの死によって、他者に内在し、他者と共に生きるという意味での「共生(convivium)」を表すものでもあった。ニーチェが神の死を語る遙か以前に、キリスト者のほうは、自己の死によって他者を生かす神自身の働きを記念していたのである。
[1] “Hayathology and Whitehead's Process Thought” presented at an international conference, Process and Reality:East and West, sponsored by Nanzan University and the Japan Society for Process Studies. pp.7-21.(1984)
[2] Hans Jonas, “Heidegger and Theology”, presented at the Second Consultation on Hermeneutics , convened by the Graduate School of Drew University, April 9-11, 1964, contained in the tenth essay of The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology, Northwestern University, 2001.pp.2,25n,28,29,81,95,96,252, ハンス・ヨーナス、「生命の哲学―有機体と自由」(細見和之・吉本稜訳)、法政大学出版局、2008, 2頁、「哲学・世紀末における回顧と展望」(尾形慶次訳)、東信堂、1996,24頁
[3] Thomas Berry, The Dream of the Earth, Sierra Club Nature and Natural Philosophy Library, San Francisco, 1988, p.22
[4] Hans Jonas, Das Prinzip Leben, Suhrkampf, 1977, S.177