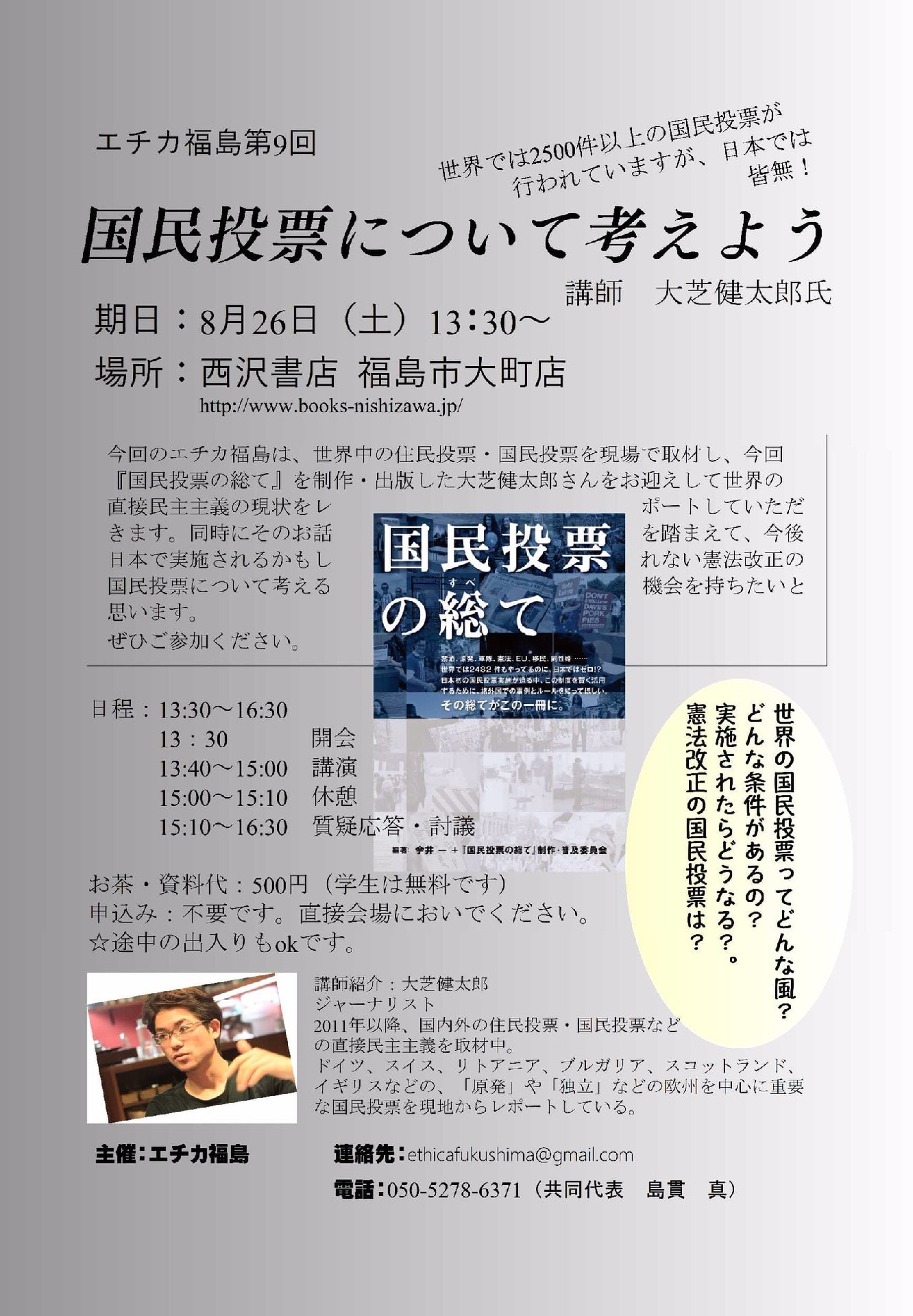まず①語りにおける身体性の重要さ。
Café de Logosはカフェや飲み屋で飲み食べする緩やかな場所だ。誰でもワイワイしゃべればいい。
郡山対話の会は、ある意味でその対極だ。もちろん対極とは言っても、語りの場として互いを尊重し、かつ安心してしゃべれる場を目指すということでは共通してもいる。だからコラボ企画も実現したのだろう。
だが、いつも参加しているCafé de Logosの世話人の方は 「知的に柔軟」であるのに対し、郡山対話の会のファシリテーターの方は 「身体的に柔軟」で、Café de Logosの参加者からみると今回はとても 「身体を伴った柔らかさ」を味わった感じがした。
そのときはとても 「身体」的な場だなあ、と思って参加していただけだったが、帰ってきてブログの記述を見るとファシリテーターの方の師匠が竹内敏晴とアーノルド・ミンデル、とある。なるほど、と思った。
方法として特別なことがあるわけではないが、一つ挙げておくと、彼(ファシリテーター)は普通未知の人が出会うときに行う簡単な場になじむための行為(ストレッチや自己紹介、簡単なゲームなど)を ホテルに入るように「チェックイン」と呼んでいた、それが印象的だった。つまり、 レトリックとしてそこは「場所」なのだろう。
対話には人の考えと人の考えが出会うという側面もあれば、まず何よりも身体が表現するという側面もあり、また目の前にいる他者の視線を意識したときに自分の中の思いを理解してもらいたいとかうまくしゃべりたいとか、どう思われるのだろうとか、様々な 「思い」が渦巻く側面もある。
そういう様々な側面を持ちつつ人が集う場所に 「チェックイン」するということは、バックグラウンドの異なる人がひと時そこに偶々集う、というイメージを与えるだろう。
まずそれが興味深かった。
そして次に興味深かったのは、ファシリテーターが机と椅子をあまり歓迎していなかった点だ。
想像でしかないが、机と椅子は身体を支えつつ縛る。机はテキストを見たりメモを取ることを支援しつつ、方向性(こちらと向こう)を固定する。椅子は体重を支えるが、(ファシリテーターによれば)下半身を固めてしまう。
その点が 「対話の身体」にとっては相応しくないのだろうと思った。
こう書いてくると対話の方法(メソッド、やりかた)の話にこだわっているかのようだが、そうではない。そこに驚いて興味を引かれている 「私」の身体が、「身体」と 「観念」とともに一瞬で動かされた、ということが言いたかった。
対話はまことに身体的な側面があるのだ。
あとは 「声」かな。発声、つまりそれは口蓋の使い方、という人類の 「歴史性」(進化、というか使い方)の問題でもあり、それは「姿勢」の問題でもあり、それらは、一人一人がどうやって他者と向き合っているか、という問題でもある。
一対一と違って複数人数の対話の場合、他者の身体を限定して全面的に意識することはできない。というか1対1であっても時折相手の瞳をのぞき込むことはあるにせよ、相手をそんなには注視してなどいない。ただし、他者としてはかなり意識してはいる。
たくさんの人を前にしたときに必要なのは 「声」だ。表情や身振りももちろん大切なのだろうが、ここは営業の自己啓発講座じゃないから、相手に伝える内容が大事だ……ということになると、メディアとしての 「声」の重要性は高いということになる。
ああ。
この身体性についてのぐるぐるは、 「まず竹内敏晴の本でも読め」ってことになりそうだからなめておく。
ただCafé de Logosでは無自覚だった意識(語りに対する甘え、といっても良い)が払拭された、それの身体観の変更が、ある種の 「場」をつくる「姿勢」によってなされたことに感動した、ということである。
この 「身体」と 「身体についての観念」についてはまた別に。
(この話、続く)