新「スカルボ」に対して原「スカルボ」は詩人の苦悩を歌って、あまりにもロマンティックであり、レンブラント風でもなければカロー風でもない。一方新「スカルボ」はといえば、“私”というものが背後に退き、スカルボが前面に出てゴシック的であり、カロー風でもある。特に最後の連は「ゴチック部屋」と同様に、極めてゴシック的であると言える。
「そして聖ベニーニュの薄暗い地下の納骨堂に、お前を壁によりかからせたまま葬ってやろう。そこでお前は気の向くままに、地獄で泣く子供たちの声を聞くことだろう。」
ところでなぜ「オンディーヌ」が本編に残され、原「スカルボ」がはずされたのかについて考えてみよう。オンディーヌはヨーロッパの民間伝承に伝わる“水の精”であり、後期ドイツロマン派のモット・フケーが『ウンディーネ』(オンディーヌのドイツ語読み)という大変ロマンティックな物語に仕立てたことで知られている。フケーのウンディーネの物語は水の精と人間との恋の物語であり、ウンディーネは人間への愛を貫くが、ベルトランのオンディーヌはそうではない。
オンディーヌは“私”に「夫となって湖の王として、ともにその宮殿を訪れよう」と誘うが、“私”が「自分はやがて死ぬ運命にある人間の女の方が好きだ」と答えると、
「機嫌を損ね恨みを胸に、幾雫かの涙を流したかと思うと、突如喊高い声をあげ、青い窓ガラスに白々と流れる水滴となって消え去った」
のである。
“オンディーヌ”というロマンティックなイメージとは逆に、フケーとは違ってあまりにも散文的であり、ある意味でカロー風でもある。『夜のガスパール』でベルトランが目指したのがそのような世界であるということは、それが旧来からの韻文定型詩で書かれず、散文詩として書かれたことからして当然のことでもあった。
「絞首台」Le Gibetもまた原「スカルボ」と同様ロマンティックに過ぎて、本編に残されなかったことを考えると、ベルトランが目指したものが見えてくる。
ロマン主義全盛の時代にはロマンティックとゴシックということが分かちがたく結びついていたのだが、ベルトランはゴシック的であることを保持しながら、ロマンティックなものから遠ざかろうとしていたのだということが。
『夜のガスパール』はベルトランの死後、ボードレールによって発見、再評価され、ボードレール自身の散文詩の試みにつながっていく。散文詩集『パリの憂鬱』Le Spleen de Parisがそれである。
ボードレールにおいてさえ『悪の華』はロマン主義の残り香を漂わせているが、『パリの憂鬱』によって初めて、ロマン主義が目指したものとはまったく違う“現代性”Modernitéを獲得することができた。
ベルトランはボードレールのように“現代性”を追求したのではなく、中世やゴシック建築にこだわり、ゴシック的なもののうちに止まったのではあるが、その散文詩という形式は極めて新しいものであった。それこそベルトランが生前まったく理解されなかった大きな理由であったろう。
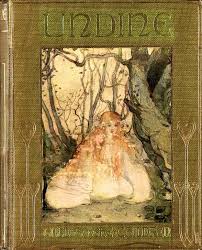
フケーの『ウンディーネ』
「そして聖ベニーニュの薄暗い地下の納骨堂に、お前を壁によりかからせたまま葬ってやろう。そこでお前は気の向くままに、地獄で泣く子供たちの声を聞くことだろう。」
ところでなぜ「オンディーヌ」が本編に残され、原「スカルボ」がはずされたのかについて考えてみよう。オンディーヌはヨーロッパの民間伝承に伝わる“水の精”であり、後期ドイツロマン派のモット・フケーが『ウンディーネ』(オンディーヌのドイツ語読み)という大変ロマンティックな物語に仕立てたことで知られている。フケーのウンディーネの物語は水の精と人間との恋の物語であり、ウンディーネは人間への愛を貫くが、ベルトランのオンディーヌはそうではない。
オンディーヌは“私”に「夫となって湖の王として、ともにその宮殿を訪れよう」と誘うが、“私”が「自分はやがて死ぬ運命にある人間の女の方が好きだ」と答えると、
「機嫌を損ね恨みを胸に、幾雫かの涙を流したかと思うと、突如喊高い声をあげ、青い窓ガラスに白々と流れる水滴となって消え去った」
のである。
“オンディーヌ”というロマンティックなイメージとは逆に、フケーとは違ってあまりにも散文的であり、ある意味でカロー風でもある。『夜のガスパール』でベルトランが目指したのがそのような世界であるということは、それが旧来からの韻文定型詩で書かれず、散文詩として書かれたことからして当然のことでもあった。
「絞首台」Le Gibetもまた原「スカルボ」と同様ロマンティックに過ぎて、本編に残されなかったことを考えると、ベルトランが目指したものが見えてくる。
ロマン主義全盛の時代にはロマンティックとゴシックということが分かちがたく結びついていたのだが、ベルトランはゴシック的であることを保持しながら、ロマンティックなものから遠ざかろうとしていたのだということが。
『夜のガスパール』はベルトランの死後、ボードレールによって発見、再評価され、ボードレール自身の散文詩の試みにつながっていく。散文詩集『パリの憂鬱』Le Spleen de Parisがそれである。
ボードレールにおいてさえ『悪の華』はロマン主義の残り香を漂わせているが、『パリの憂鬱』によって初めて、ロマン主義が目指したものとはまったく違う“現代性”Modernitéを獲得することができた。
ベルトランはボードレールのように“現代性”を追求したのではなく、中世やゴシック建築にこだわり、ゴシック的なもののうちに止まったのではあるが、その散文詩という形式は極めて新しいものであった。それこそベルトランが生前まったく理解されなかった大きな理由であったろう。
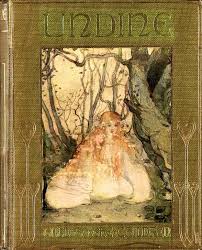
フケーの『ウンディーネ』





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます