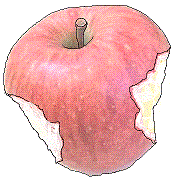
きょう、ようやく、森本あんりの『不寛容論 アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)の書評が朝日新聞にのった。すでに、與那覇潤が1月31日の産経新聞に本書の書評を寄せているし、宇野重規が新潮社の『波 1月号』に書評を寄せている。
私も本屋で立ち読みし、面白く思ったので、2週間前の2月6日に図書館に予約した。この本は横浜市で1冊しか購入していない。私は予約の31番目で、本は2週間借りれることになっているから、このままの調子でいくと、62週目、434日後に借りれることになる。1年半後に私が読めることになる。
横浜市は373万人の人口を抱え、19の図書館をもつのだから、予約が殺到すれば、購入の冊数を増やしても良いのではと思う。もし、横浜市が3冊購入してくれたら、私は半年後に読むことができるのにと思う。貧しい老人にとって、読書は一番の楽しみである。
宇野重規も書評を書いているように、この『不寛容論』は「不」がついているが、リベラルにおける「寛容」のありかたを、アメリカの文化史、宗教史のなかでとらえるものらしい。そして、「寛容」こそ「共存の哲学」である。リベラルはもともと「寛容な」という形容詞である。森本あんりは、その「寛容」を中世のカトリックの教義にさかのぼる、という。
それで終わらない。森本あんりは、「寛容」の意味について注意を喚起したいのだ。與那覇潤は書評でつぎのように指摘をする。
〈単なる「信念の欠如」の裏面に過ぎない寛容さは、かくして瞬時に「信念を持つ者への不寛容」へと転化する。だがそうだとすれば逆に、不寛容なまでの「自分の信念」の貫徹を通じて、異なる信念を同じように貫く隣人への寛容を育てることは、できないのだろうか。〉
そうなんだ。多くの日本人は「寛容」とか「許し」を安易に考えている。私が思うに、「寛容」や「許し」は、自分の信念や怒りを放棄したのではなく、いずれ相手も自分の信念に歩み寄ってくる、いずれ相手も自分の非を認め改める、と信じ、相手に暴力をふるうことなく、辛抱強く待つことである。相手を良しとしたのではない。自分の正しさを信じるからできるのだ。
戦前の日本企業や政府の暴力を許さない韓国人を、日本の識者の一部は1965年の日韓基本条約を盾に非難するが、それは安易すぎないか。「寛容」や「許し」を、暴力の受けた側に要求できるものではない。
どうも、それが、『寛容論』でなく『不寛容論』と、森本あんりがタイトルをつけた理由ではないか、とも私は思う。
1年半後に本書をよく読んで書評を書きたいが、そのまえに、ちょこちょこと本屋で立ち読みすることになるだろう









