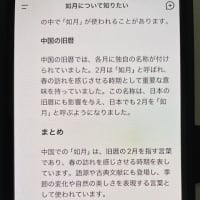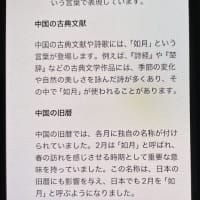日本語を哲学する 1
哲学は希哲の学また希賢の学であったと、すると愛知の学また愛智の学であったわけである。それは翻訳のゆえであるから、その説明から、検索をしてみると、そのトップに、
>人生・世界、事物の根源のあり方・原理を、理性によって求めようとする学問。また、経験からつくりあげた人生観。
▷ ギリシア philosophia (=知への愛)の訳語。「哲」は叡智(えいち)の意。
という。
そこで、さきに続いて、さきの哲学の定義は近代のものであったから、語源にさかのぼってみる。(ウイキペディア 哲学→#語源とその意味)
>古希: φιλοσοφία(philosophia、ピロソピアー、フィロソフィア)という語は、愛智という意味である。ギリシア語において φίλος(愛しい) の派生語 φιλεῖν(愛する) と σοφία(知恵、知、智) が結び合わさったものであるので、元来「philosophia」は「知を愛する」「智を愛する」という意味が込められている。20世紀の神学者ジャン・ルクレールによれば、古代ギリシアにおいてフィロソフィアとは認識のための理論や方法ではなくむしろ知恵・理性に従う生き方を指して使われ、中世の修道院でもこの用法が存続したとされる。一方、中世初期のセビリャのイシドールスはその百科事典的な著作『語源誌』(羅: Etymologiae)において、哲学とは「よく生きようとする努力と結合した人間的、神的事柄に関する認識である」と述べている。この語はヘラクレイトスやヘロドトスによって、形容詞や動詞の形でいくらか使われていたが、名称として確立したのはソクラテスやプラトンが用いるようになってから、とされている。
ここで分かるのは、哲に叡智、より良き知恵を求めての生き方を指していた、とする解釈である。翻訳には中国語の影響を示す記述がある。
>「哲学」の初出は西周の『百一新論[注 7]』1874年(明治7年)とされる。北宋の儒学者であった周敦頤の『通書』志學第十[19]に「士希賢」(士は賢をこいねがう)との文言があり、ここから「希哲学」の語が生まれ、中国西学が<Philosophy>の訳語として転用したものを西は採用し、さらにこれを変形させて(「希」の省略)、「哲学」とした[18][注 8]。
[注 8]この「哲学」という表現は中国語にも移入され、同言語でも「哲学」と表現するようになった。
^ 西周は主觀・客觀・概念・觀念・歸納・演繹・命題・肯定・否定・理性・悟性・現象・藝術(リベラルアーツの訳語)・技術など、西欧語のそれぞれの単語に対応する日本語を創生した。
[18]高野繁男「『哲学字彙』の和製漢語―その語基の生成法・造語法」『人文学研究所報』37:97p, 2004
なお、字通によると、哲は、
>字形 形声
声符は折(せつ)。〔説文〕二上に「知るなり」とし、折声とするが、金文の字形は、神梯の象である(ふ)と斤とに従う。その下に心を加えている形で、その字形は〔説文〕に重文として録するものにもみえる。
訓義
[1] さとる、さとい、明らか。[2] 知る、神明のことを知る。[3] さとく賢い、賢哲。
古辞書の訓
〔名義抄〕哲 サカシ・カシコシ・サトル・アキラカナリ・モノガタリ/ サトル・アキラカナリ・スミヤカニ 〔字鏡集〕哲 サトシ・トシ・サトル・タカシ・シル・アキラカナリ・シム・モノガタリ・カシコシ・スグルル・ヒカリ
>【哲王】てつおう(わう) 賢明な君。
とある。また、賢については、次の訓義がある。
>訓義
[1] かしこい、神につかえるもの。
[2] まさる、よい、すぐれる、たっとぶ。