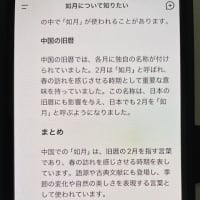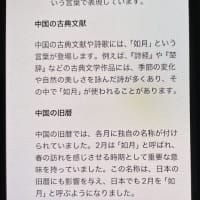【2】、あるべき憲法解釈
【1】で述べた認識を踏まえ、本懇談会は、あるべき憲法解釈として、以下を提言する。
1、憲法第9条第1項および第2項
(1)憲法第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定しており、自衛権や集団安全保障については何ら言及していない。しかしながら、わが国が主権を回復した52年4月に発効した日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)においても、わが国が個別的または集団的自衛の固有の権利を有することや集団安全保障措置への参加は認められており、また、わが国が56年9月に国連に加盟した際も、国連憲章に規定される国連の集団安全保障措置や、加盟国に個別的または集団的自衛の固有の権利を認める規定(第51条)について何ら留保は付さなかった。
憲法第9条第1項がわが国による武力による威嚇または武力の行使を例外なく禁止していると解釈するのは、不戦条約や国連憲章(45年)等の国際法の歴史的発展および憲法制定の経緯から見ても、適切ではない。46年に公布された日本国憲法は、20世紀前半の平和主義、戦争違法化に関する国際法思潮から大きな影響を受けている。わが国憲法第9条の規定は、20世紀に確固たる潮流となった国際平和主義の影響を深く受けているのであり、国際社会の思潮と孤絶しているわけではない。不戦条約は、「国際紛争解決ノ為」に戦争に訴えることを非とし、「国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争」を放棄することを規定することで、締約国間の侵略戦争の放棄を約束した。この戦争違法化の流れをくんで作成された国連憲章は、日本国憲法公布の1年前に採択されたものである。国連憲章は、加盟国の国際関係における「武力の行使」を原則として禁止したが、国連の集団安全保障措置としての軍事的措置および個別的または集団的自衛の固有の権利(第51条)の行使としての「武力の行使」を実施することは例外的に許可している。また、日本国憲法の起草経緯を見れば、憲法第9条の起点となったマッカーサー三原則(46年2月3日)の第二原則は、日本は自らの紛争を解決するための手段としての戦争を放棄する(Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes)となっている。政府も46年の時点で既に吉田総理が新憲法草案に関し、先述のとおり「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌ(略)」と述べていた(衆院本会議(46年6月26日))のであり、また、自衛隊創設時の国会答弁においては「戦争と武力の威嚇・武力の行使が放棄されるのは『国際紛争を解決する手段としては』ということである」「他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない」と述べていたのである(前掲の大村清一防衛庁長官答弁)。
これらの経緯を踏まえれば、憲法第9条第1項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」)は、わが国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇または武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、またPKO等や集団安全保障措置への参加といった国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。
なお、PKO等における武器使用を、第9条第1項を理由に制限することは、国連の活動への参加に制約を課している点と、下記5で述べるとおり「武器の使用」を「武力の行使」と混同している点で、二重に適切でない解釈であることを指摘しておきたい。
(2)憲法第9条第2項は、第1項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、わが国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的または集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。これら(1)および(2)と同様の考え方は前回08年6月の報告書でもとられていた。
(3)上述の前回報告書の立場、特に(2)で述べた個別的または集団的を問わず自衛のための実力の保持や、いわゆる国際貢献のための実力の保持は合憲であるという考え方は、憲法第9条の起草過程において、第2項冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が後から挿入された(いわゆる「芦田修正」)との経緯に着目した解釈であるが、政府はこれまでこのような解釈をとってこなかった。再度政府の解釈を振り返れば、前述のとおり、政府は、46年の制憲議会の際に吉田総理答弁において自衛戦争も放棄したと明言していたにもかかわらず、54年以来、国家・国民を守るために必要最小限度の自衛力の保持は主権国家の固有の権利であるという解釈を打ち出した。この解釈は最高裁判所でも否定されていない。しかし、その後の国会答弁において、政府は憲法上認められる必要最小限度の自衛権の中に個別的自衛権は入るが、集団的自衛権は入らないという解釈を打ち出し、今もってこれに縛られている。集団的自衛権の概念が固まっていなかった当初の国会論議の中で、その概念の中核とされた海外派兵の自制という文脈で打ち出された集団的自衛権不行使の議論は、やがて集団的自衛権一般の不行使の議論として固まっていくが、その際どうしてわが国の国家および国民の安全を守るために必要最小限の自衛権の行使は個別的自衛権の行使に限られるのか、逆に言えばなぜ個別的自衛権だけでわが国の国家および国民の安全を確保できるのかという死活的に重要な論点についての論証は、【1】・1・(1)の憲法解釈の変遷で述べたとおり、ほとんどなされてこなかった。すなわち、政府は「外国の武力攻撃によって国民の生命・自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」(72年10月に参院決算委員会に提出した政府の見解)として、集団的自衛権の不行使には何の不都合もないと断じ、集団的自衛権を行使できなくても独力でわが国の国家および国民の安全を本当に確保できるのか、ということについて詳細な論証を怠ってきた。
国家は他の信頼できる国家と連携し、助け合うことによって、よりよく安全を守り得るのである。集団的自衛権の行使を可能とすることは、他の信頼できる国家との関係を強固にし、抑止力を高めることによって紛争の可能性を未然に減らすものである。また、仮に一国が個別的自衛権だけで安全を守ろうとすれば、巨大な軍事力を持たざるを得ず、大規模な軍拡競争を招来する可能性がある。したがって、集団的自衛権は全体として軍備のレベルを低く抑えることを可能とするものである。一国のみで自国を守ろうとすることは、国際社会の現実に鑑みればむしろ危険な孤立主義にほかならない。
そもそも国連憲章中の集団的自衛権の規定は、45年の国連憲章起草の際に国連安全保障理事会の議決手続きに拒否権が導入されることになった結果、国連安全保障理事会の機能に危惧が抱かれるようになり、そのため個別的自衛権のみでは生存を全うできないと考えた中南米のチャプルテペック協定参加国が提唱して認められたものであるという起草経緯をあらためて想起する必要がある。
国連憲章では、第2条4により国際関係における武力の行使が禁じられているが、第51条に従って個別的または集団的自衛のために武力を行使する権利は妨げられない。これは、同条に明記されているとおり、自衛権が国家が当然に有している固有の権利(「自然権」(droit naturel))であるからである。また、今日、集団的自衛権は慣習国際法上の権利であるとされており、この点については国際司法裁判所もその判決中で明確に示している(86年6月「ニカラグア軍事・準軍事活動事件(本案)」国際司法裁判所判決)。国際社会における諸国間の国力差および国連安全保障理事会における拒否権の存在やその機能・手法を考えれば、国連の集団安全保障体制が十分に機能するまでの間、中小国は自己に対する攻撃を独力で排除することだけを念頭に置いていたら自衛は全うできないのであって、自国が攻撃された場合のみならず、他国が攻撃された場合にも同様にあたかも自国が攻撃されているとみなして、集団で自衛権が行使できることになっているのである。今日の安全保障環境を考えるとき、集団的自衛権の方が当然に個別的自衛権より危険だという見方は、抑止という安全保障上の基本観念を無視し、また、国連憲章の起草過程を無視したものと言わざるを得ないのである。以上を踏まえれば、上述した政府のこれまでの見解である、「(自衛のための)措置は、必要最小限度の範囲にとどまるべき」という解釈に立ったとしても、その「必要最小限度」の中に個別的自衛権は含まれるが集団的自衛権は含まれないとしてきた政府の憲法解釈は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適当ではない。事実として、今日の日本の安全が個別的自衛権の行使だけで確保されるとは考え難い。したがって、「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解釈して、集団的自衛権の行使を認めるべきである。
(4)なお、上記(3)のような解釈を採る場合には、憲法第9条第2項にいう「戦力」および「交戦権」については、次のように考えるべきである。
「戦力」については、自衛権行使を合憲と踏み切った主権回復直後の自衛隊創設後に至る憲法解釈変遷の際に「近代戦争遂行能力」と定義されたこともあったが、その後は、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものとされ、72年11月、吉国一郎内閣法制局長官は、「昭和29年12月以来は、憲法第9条第2項の戦力といたしまして、(略)近代戦争遂行能力という言い方をやめております」と明言した。現在では「自衛のための必要最小限度の実力」の具体的な限度は防衛力整備をめぐる国会論議の中で国民の支持を得つつ考査されるべきものとされている。客観的な国際情勢に照らして、憲法が許容する武力の行使に必要な実力の保持が許容されるという考え方は、今後も踏襲されるべきものと考える。
「交戦権」については、自衛のための武力の行使は憲法の禁ずる交戦権とは「別の観念のもの」であるとの答弁がなされてきた。国策遂行手段としての戦争が国連憲章によりjus ad bellum(戦争に訴えること自体を規律する規範)の問題として一般的に禁止されている状況の中で、個別的および集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置等のように国連憲章を含む国際法に合致し、かつ、憲法の許容する武力の行使は、憲法第9条の禁止する交戦権の行使とは「別の観念のもの」と引き続き観念すべきものである。ただし、合法な武力行使であってもjus in bello(戦時における戦闘の手段・方法を規律する規範)の問題として国際人道法規上の規制を受けることは当然である。
2、憲法上認められる自衛権
(1)個別的自衛権の行使に関する見解として、政府は、従来、憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、(1)わが国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という3要件に該当する場合に限られるとしている。このように、この3要件を満たす限り行使に制限はないが、その実際の行使に当たっては、その必要性と均衡性を慎重かつ迅速に判断して、決定しなければならない(武力攻撃に至らない侵害への対応については後述する)。
(2)集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていない場合にも、実力をもって阻止する権利と解されている。また、集団的自衛権の行使は、武力攻撃の発生(注・着手も含まれる)、被攻撃国の要請または同意という要件が満たされている場合に、必要性、均衡性という要件を満たしつつ行うことが求められる。
わが国においては、この集団的自衛権について、わが国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態がわが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、わが国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請または同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和および安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。そのような場合に該当するかについては、わが国への直接攻撃に結びつく蓋然性が高いか、日米同盟の信頼が著しく傷つきその抑止力が大きく損なわれ得るか、国際秩序そのものが大きく揺らぎ得るか、国民の生命や権利が著しく害されるか、その他わが国へ深刻な影響がおよび得るかといった諸点を政府が総合的に勘案しつつ責任を持って判断すべきである。また、わが国が集団的自衛権を行使するに当たり第三国の領域を通過する場合には、わが国の方針として、その国の同意を得るものとすべきである。さらに、集団的自衛権を行使するに当たっては、個別的自衛権を行使する場合と同様に、事前または事後に国会の承認を得る必要があるものとすべきである。
集団的自衛権は権利であって、義務ではないので、行使し得る場合であっても、わが国が行使することにどれだけ意味があるのか等を総合的に判断して、政策的判断の結果、行使しないことがあるのは当然である。わが国による集団的自衛権の行使については、内閣総理大臣の主導の下、国家安全保障会議の議を経るべきであり、内閣として閣議決定により意思決定する必要がある。なお、集団的自衛権の行使を認めれば、果てしなく米国の戦争に巻き込まれるという議論が一部にあるが、そもそも集団的自衛権の行使は義務ではなく権利であるので、その行使はあくまでもわが国が主体的に判断すべき問題である。この関連で、個別的または集団的自衛権を行使する自衛隊部隊の活動の場所について、憲法解釈上、地理的な限定を設けることは適切でない。「地球の裏側」まで行くのかうんぬんという議論があるが、不毛な抽象論にすぎず、ある事態がわが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるか、かつわが国の行動にどれだけの効果があるかといった点を総合的に勘案し、個別具体的な事例に則して主体的に判断すべきである。なお、繰り返しになるが、集団的自衛権は権利であって義務ではなく、先に述べたような政策的判断の結果として、行使しないことももちろんある点に留意が必要である。
(3)本来は集団的自衛権の行使の対象となるべき事例について、個別的自衛権や警察権をわが国独自の考え方で「拡張」して説明することは、国際法違反のおそれがある。例えば、公海上で日米の艦船が共同行動をしている際に、自衛艦が攻撃されていないにもかかわらず個別的自衛権の行使として米艦を防護した場合には、国連憲章第51条に基づきわが国がとった措置につき国連安全保障理事会に報告する義務が生じるが、「わが国に対して武力攻撃が発生した」という事実がないにもかかわらず個別的自衛権の行使として報告すれば、国連憲章違反との批判を受けるおそれがある。また、各国が独自に個別的自衛権の「拡張」を主張すれば、国際法に基づかない各国独自の「正義」が横行することとなり、これは実質的にも危険な考えである。
(4)情報通信技術の発展に伴い、今やサイバー空間は人々の生活に必要不可欠なものとなっている。サイバー空間は、インターネットの発達により形成された仮想空間であり、安全保障上も陸・海・空・宇宙に続く新しい領域であると言えるが、その法的側面については議論が続いているところである。ひとたびサイバー攻撃が行われれば、政府機関から企業に至る社会の隅々にまで深刻な影響を及ぼすこととなり、この問題の重要性が認識されるに至っている。現実にも、近年、諸国の政府機関や軍隊などに対するサイバー攻撃が多発しており、各国政府による取り組みや国際的な議論が行われているところである。
日進月歩の技術進歩を背景とするサイバー攻撃は、攻撃の予測や攻撃者の特定が困難であったり、攻撃の手法が多様であるといった特徴を有しており、従来の典型的な武力攻撃と異なる点も少なくない。そのため、サイバー攻撃の法的位置付けについて一概に述べるのは困難である。これまでのところ、サイバー攻撃が「武力攻撃」に該当しないと位置付けられている事例が多いように見受けられる。他方、一定の場合には、サイバー攻撃が、「わが国に対する急迫不正の侵害があること」という要件を含め、自衛権発動の3要件を満たす場合もあると考えられる。いずれにしても、どのような場合がそれに該当するかという点や、外部からのサイバー攻撃に対処するための制度的な枠組みの必要性等について、国際社会における議論にも留意しつつ、引き続き、検討が必要である。
3、軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加
軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加については、上記Iで述べたとおり、これまでの政府の憲法解釈では、正規の国連軍については研究中としながらも、いわゆる国連多国籍軍の場合は、武力の行使につながる可能性のある行為として、憲法第9条違反のおそれがあるとされてきた。しかしながら、上記【2】・1・(1)で述べたとおり、憲法第9条が国連の集団安全保障措置へのわが国の参加までも禁じていると解釈することは適当ではなく、国連の集団安全保障措置は、わが国が当事国である国際紛争を解決する手段としての武力の行使に当たらず、憲法上の制約はないと解釈すべきである。国連安全保障理事会決議等による集団安全保障措置への参加は、国際社会における責務でもあり、憲法が国際協調主義を根本原則とし、憲法第98条が国際法規の誠実な遵守を定めていることからも、わが国として主体的な判断を行うことを前提に、積極的に貢献すべきである。近年わが国は、武力の行使以外の後方支援等の領域においては、国際社会の秩序を維持するための活動への貢献の幅を着実に広げてきている。先に述べたとおり、01年9月に米国で同時多発テロ事件が発生したことを受け、同年11月には「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国連憲章の目的達成のための諸外国の活動に対してわが国が実施する措置および関連する国連決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(テロ対策特別措置法)を制定して、インド洋に自衛艦を派遣し補給支援活動を行った。また、03年には、「イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」(イラク人道復興支援特別措置法)により、戦後初めて多国籍軍が占領行政を行っている他国領域の陸上において自衛隊が人道復興支援活動に従事した。
国連憲章第7章が定める国連の集団安全保障措置には、軍事的措置と非軍事的措置があるが、非軍事的措置を規定した国連憲章第41条に基づく経済制裁への参加については、わが国はこれまでも、関連の国連安全保障理事会決議に基づく北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連および弾道ミサイル関連計画に関与する者に対して資産凍結等の措置を講ずるなど、積極的に協力を行ってきている。憲法前文で国際協調主義を掲げ、国連への協力を安全保障政策の柱の一つとしてきたわが国が、同じ国際社会の秩序を守るための国連安全保障理事会決議等に基づく国連の集団安全保障措置であるにもかかわらず、軍事力を用いた強制措置を伴う場合については一切の協力を行うことができないという現状は改める必要がある。
このように国連等が行う国際的な平和活動については憲法上制約がないとするとしても、国連憲章が本来予定した、国連軍の創設を含む形での集団安全保障体制が実現しておらず、また、国連安全保障理事会決議に基づく平和活動にも種々の段階があり、その原因、国連の参加の態様も個々の事例に応じて多様であるので、平和活動への参加に関しては、個々の場合について、政策上わが国が参加することにどれだけ意味があるのかなどを総合的に検討して、慎重に判断すべきことは当然である。
なお、言うまでもなく、軍事力を用いた強制措置を伴う国連の集団安全保障措置に参加するに当たっては、事前または事後に国会の承認を得るものとすべきである。
4、いわゆる「武力の行使との一体化」論
08年の報告書でも言及したとおり、「武力の行使との一体化」というのはわが国特有の概念である。特に90年代、湾岸戦争のころから、にわかに声高に議論され、精緻化が進んだ。それ以前に「武力の行使との一体化」の問題が国会で答弁されたことはあまりない。しかし、この議論は、国際法上も国内法上も実定法上に明文の根拠を持たず、最高裁判所による司法判断が行われたこともなく、国会の議論に応じて範囲が拡張され、安全保障上の実務に大きな支障を来たしてきた。
それ自体は武力の行使に当たらないわが国の補給、輸送、医療等の後方支援でも「他国の武力の行使と一体化」する場合には憲法第9条の禁ずる武力の行使とみなされるという考え方は、元来日米安全保障条約の脈絡で議論されたものである。このような考え方を論理的に突き詰める場合には、例えば政府は現在行われている日米同盟下の米軍に対する施設・区域の提供は米国の武力行使と一体化しないとしているが、現実に極東有事の際日米安全保障条約第6条の下で米軍が戦闘作戦行動のためにわが国国内の基地を使用し始めれば、わが国の基地使用許可は、米軍の「武力の行使と一体化」するので、日米安全保障条約そのものが違憲であるというような不合理な結論になりかねない。
このほか、国連平和協力法案(廃案)、PKO協力法案、周辺事態法案、テロ対策特別措置法案およびイラク復興支援特別措置法案の国会審議の際にもしばしば問題になったように、「武力の行使との一体化」論は、後方支援がいかなる場合に他国による武力の行使と一体化するとみなすのか、その判断を誰が行うのか、「戦闘地域」と「非戦闘地域」の区分は何か等、そもそも事態が刻々と変わる活動の現場において、観念的には一見精緻に見える議論をもって「武力の行使との一体化」論を適用すること自体、非現実的であり極めて困難である。例えば、ミサイル等軍事技術が急速に発達した現下の状況では、どこが「非戦闘地域」かを定性的に定義することは現実的でなくなっている。
「武力の行使との一体化」の論理のゆえに、例えば、日米間で想定した事態の検討にも支障があり得るとすれば、わが国の安全を確保していくための備えが十分とは言えない。この問題は、日米安全保障条約の運用のみならず国際的な平和活動への参加の双方にまたがる問題である。「武力の行使との一体化」論は、憲法上の制約を意識して、新たな活動について慎重を期すために厳しく考えたことから出てきた議論である。したがって、国際平和協力活動の経験を積んだ今日においては、いわゆる「武力の行使との一体化」論はその役割を終えたものであり、このような考えはもはやとらず、政策的妥当性の問題として位置付けるべきである。実際にどのような状況下でどのような後方支援を行うかは、内閣として慎重に検討して意思決定すべきものであることは言うまでもない。
5、PKO等への協力と武器使用
(1)わが国は、92年6月のPKO協力法制定以来、PKO協力法に基づき、延べ約1万人(14年3月末時点)の要員をPKO等に派遣し、着実に実績と経験を積み上げ、国民の支持と国際社会からの高い評価を得てきている。PKO等への協力は、わが国が国際社会の平和と安定に責任を果たすための最も有効な手段の一つであり、今後もPKO等への要員派遣を積極的に実施していくべきである。
他方、これまで、わが国のPKO等に対する協力は、当事者間の停戦合意を支える平和維持活動を中心とするPKO協力法制定当時のPKO等の実態を踏まえつつ、当時の国内世論にも配慮して抑制的に構築された制度に従って、いわゆるPKO参加5原則の下、運用上も慎重に行われてきた。国連は「主たる紛争当事者」の同意を基本原則としてPKOミッションを設立しているのに対し、現行PKO協力法の下では、「全ての」紛争当事者の受入れ同意が必要だとして運用してきた。また、停戦合意についても、国連では、停戦合意がない場合でも事実上の停戦状態を前提としてPKOミッションを設立しているが、わが国では、紛争当事者間の停戦合意を要件としている。このような状況は、全ての「紛争当事者」の特定が容易であり、紛争当事者間の明確な停戦合意の確認が容易であった国家間紛争から、「紛争当事者」を特定することが困難な場合もある内戦型または複合型へと紛争が質的に変化し、PKO等の役割・態様も多様化し、国連憲章第7章下の一定の強制力を付与された「強化されたPKO」も増えてきている今日の実態にそぐわない。
このようなPKOの実態との相違ならびにPKOの任務および活動主体の多様化を踏まえた上で、わが国のより積極的な国際平和協力を可能とするためには何が必要かとの観点から、いわゆるPKO参加5原則についても見直しを視野に入れ、検討する必要がある。
(2)PKOの活動の性格は、「武力の行使」のような強制措置ではないが、紛争当事者間の停戦の合意を維持し、また、領域国の新しい国づくりを助けるため、国連の権威の下で各国が協力する活動である。このような活動における駆け付け警護や妨害排除に際しての武器使用は、そもそも「武力の行使」に当たらず、憲法上の制約はないと解釈すべきである。
一方、政府は、これまで、PKO等におけるいわゆる駆け付け警護や妨害排除のための武器の使用に関しては、いわば自己保存のための自然権的権利に当たるものとは言えず、現行の憲法解釈の下では、相手方が「国家または国家に準ずる組織」である場合には、憲法で禁じられた「武力の行使」に当たるおそれがあるので認められないとしてきた。たとえば03年5月15日の参院外交防衛委員会において宮崎礼壹内閣法制局第一部長が「自衛隊の部隊の所在地からかなり離れた場所に所在します他国の部隊なり隊員さんの下に駆け付けて武器使用するという場合は、わが国の自衛官自身の生命または身体の危険が存在しない場合の武器使用だという前提だというお尋ねだと思います。(略)このような場合に駆け付けて武器を使用するということは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものだという説明はできないわけでございます。(略)その駆け付けて応援しようとした対象の事態、あるいはお尋ねの攻撃をしているその主体というものが国または国に準ずる者である場合もあり得るわけでございまして、そうでありますと、(略)それは国際紛争を解決する手段としての武力の行使ということに及ぶことが、及びかねないということになるわけでございまして、そうでありますと、憲法九条の禁じます武力の行使に当たるおそれがあるというふうに考えてきたわけでございます」と答弁している。
しかしながら、08年の報告書でも指摘したとおり、そもそもPKOは武力紛争の終了を前提に行う活動(あるいは武力紛争の開始・再発前にこれを予防するための活動)であり、PKOの国際基準で認められた武器使用が国連憲章で禁止された国際関係における「武力の行使」に当たると解釈している国はどこにもなく、自衛隊がPKO等の一員として、駆け付け警護や妨害排除のために国際基準に従って行う武器使用は、相手方が単なる犯罪集団であるか「国家または国家に準ずる組織」であるかどうかにかかわらず、憲法第9条の禁ずる武力の行使には当たらないと解すべきである。さらに、近年の複合型PKO等においては、国内紛争や脆弱国家への対応として、治安維持や文民の保護等の業務が重要となっており、具体的検討に当たっては、駆け付け警護や妨害排除のための武器使用を可能にするとともに、法制度上、こうした業務も実施できるようにすべきである。
重要なことは、このような武器使用は、国連においては明確に国連憲章第2条4により禁止されている国際関係における「武力の行使」とは異なる概念であると観念されていることである。PKOは、不偏性を持ち、主たる紛争当事者の同意を得て行われる活動であり、その任務は武力の行使が発生するのを防ぐための予防的活動か、武力行使が収まった後の平和維持や人道・復興支援である。その意味で、PKOは国連憲章が加盟国に対して禁じている国際関係における「武力の行使」を行う活動ではない。PKOは国連決議の下に組織されるいわゆる多国籍軍のような大規模な軍事活動を伴い得る平和執行とは峻別されるものである。また、国連憲章第7章下の一定の強制力を付与された「強化されたPKO」も、その実態はPKOの範疇を出ず、平和執行とは峻別されているものである。
6、在外自国民の保護・救出等
13年1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受けて、政府は、同年11月、外国におけるさまざまな緊急事態に際してより適切に対応できるよう、自衛隊による在外邦人等輸送(自衛隊法第84条の3)について、輸送対象者を拡大し、車両による輸送を可能とすること等を内容とする自衛隊法の改正を行った。しかし、この職務に従事する自衛官の武器使用の権限については、いわゆる自己保存型のままとし、救出活動や妨害排除のための武器使用を認めるには至らなかった。現状の解釈のままでは、必要な武器使用権限が確保されないため、現場に自国民救出のために自衛隊が駆け付けることはできない。
国際法上、在外自国民の保護・救出は、領域国の同意がある場合には、領域国の同意に基づく活動として許容される。在外自国民の保護・救出の一環としての救出活動や妨害排除に際しての武器使用についても、領域国の同意がある場合には、そもそも「武力の行使」に当たらず、当該領域国の治安活動を補完・代替するものにすぎないものであって、憲法上の制約はないと解釈すべきである。
なお、領域国の同意がない場合にも、在外自国民の保護・救出は、国際法上、所在地国が外国人に対する侵害を排除する意思または能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかに救済の手段がない場合には、自衛権の行使として許容される場合がある。憲法上認められる自衛権の発動としての「武力の行使」をめぐる国会の議論においては、在外自国民の保護・救出のための自衛権の行使が否定されているように見受けられるが、多くの日本人が海外で活躍し、13年1月のアルジェリアでのテロ事件のような事態が生じる可能性がある中で、憲法が在外自国民の生命、身体、財産等の保護を制限していると解することは適切でなく、国際法上許容される範囲の在外自国民の保護・救出を可能とすべきである。国民の生命・身体を保護することは国家の責務でもある。
7、国際治安協力
在外自国民の保護・救出以外の活動であっても、領域国の同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復および維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念される活動や、普遍的な管轄権に基づいて海賊等に対処する活動、すなわち国際的な治安協力については、国際法上は、国連の集団安全保障措置ではなく、国連憲章第2条4で禁止されている国際関係における「武力の行使」にも当たらない。このような活動についても、そもそも「武力の行使」に当たらず、憲法上の制約はないと解釈すべきである。そのような事例は、国連決議によって求められることもあれば、領域国の同意や要請の下で行われることもあれば、公海上のような国際公域における自発的な秩序維持の場合もある。端的な例として、アデン湾の海賊対処をこの観点から位置付けることも可能である。これには「アタランタ」作戦を開始した欧州連合(EU)諸国、北大西洋条約機構(NATO)諸国のほか、日本、中国、イラン、韓国等が参加している。国連は安全保障理事会決議第1816号等によって加盟国の協力を要請している。日本は09年から自衛隊と海上保安庁が協力して参加している。
このような治安協力は、国連憲章第2条4の禁ずる国際関係における「武力の行使」ではなく、武器の使用を伴う治安活動であるので、基本的に憲法問題は生じず、活動根拠の付与は法律レベルにより行うことができる。政府も国会において、海賊対処法案の審議の中で、自衛隊を派遣するに際し、「国や国に準ずる者と申しますか、国等が国等の行為として行われるものは、その定義上海賊行為からは除外されております。したがいまして、御懸念のような、憲法第九条によって禁じられた『武力の行使』に及ぶということはないものと考えております」と答弁している(09年6月4日参院外交防衛委員会における横畠裕介内閣法制局第2部長答弁)。
8、武力攻撃に至らない侵害への対応
一般国際法上、自衛権を行使するための要件は、国家または国民に対する「急迫不正の侵害」があることなどとされているが、わが国の国会答弁においては、「わが国に対する急迫不正の侵害」があった場合は、「武力攻撃」、すなわち、「一般に、わが国に対する組織的計画的な武力の行使」があった場合として極めて限定的に説明されている。また、自衛隊法等の現行国内法上、自衛権の発動としての武力を行使できる「防衛出動」は、「武力攻撃」、すなわちわが国に対する組織的計画的な武力の行使を前提としている。このことから、「武力攻撃」に至らない侵害への対応は、自衛権の行使ではなく、警察比例の原則に従う「警察権」の行使にとどまることとなる。しかし、事態発生に際し「組織的計画的な武力の行使」かどうか判別がつかない場合において、突発的な状況が生起したり、急激に事態が推移することも否定できない。「組織的計画的な武力の行使」かどうか判別がつかない侵害であっても、そのような侵害を排除する自衛隊の必要最小限度の行動は憲法上容認されるべきである。かかる自衛隊の行動は、その事態、態様により、国際法上は、自衛権に包含される活動として区分される場合もあれば、国際法の許容する法執行活動等として区分されることもあり得るが、いずれにせよ、国際法上合法な行為である限り許容されるべきである。
警察権の行使である自衛隊の行動類型としては、治安出動、警護出動、海上警備行動などがあり、また武器等防護という武器使用権限もあるが、治安出動のほか、警察権の行使としての自衛隊の行動による対処に当たり、事態認定や命令を出すための手続きを経る間に、状況によっては対処に事実上の間隙が生じ得る可能性があり、結果として事態の収拾が困難となったり、相手を抑止できなくなったりするおそれがある。また、対処に先立って自衛隊部隊を行動させるためには、治安出動下令前の情報収集(自衛隊法第79条の2)や防御施設構築措置(同法第77条の2)等の規定によるが、それぞれ「治安出動命令が発せられることおよび不法行為が行われることの予測」と「防衛出動命令が発せられることの予測」を下令要件とし、実際の下令までの手続き面で高い敷居が存在する。したがって、現行の自衛隊法の規定では、平素の段階からそれぞれの行動や防衛出動に至る間において権限上の、あるいは時間的な隙間が生じ得る可能性があり、結果として事態収拾が困難となるおそれがある。自衛隊法に切れ目のない対応を講ずるための包括的な措置を講ずる必要がある。
問題となる事例としては次のようなものがある。例えば、わが国領海で潜没航行する外国潜水艦が退去の要求に応じず徘徊を継続する場合への対応に際しては、一義的には海上警備行動による対応となるが、現行の国内法上は「武力攻撃事態」と認定されない段階では、「武力の行使」はもとより、それに至らない武器の使用による当該潜水艦の強制退去は困難である。したがって、軍艦または政府公船である外国船舶を停止させるための武器使用がどの程度認められるかについて、国際法の基準に照らし、警察官職務執行法の範囲にとらわれず、国内法における検討を進めていく必要がある。
また、国境の離島等に対して特殊部隊等の不意急襲的な上陸があった場合、仮に警察権の行使により対応する場合においても、自衛隊には平素からの同権限が認められているわけではなく、ましてや「武力攻撃事態」と認定されない段階では、防衛出動下での対応はできない。いったん離島が攻撃を受ければ、その攻撃の排除には相当の規模の部隊と期間が必要となる。同様に、原子力発電所等の重要施設の防護を例にとってみても、テロリスト・武装工作員等による警察力を超える襲撃・破壊行動が生起した場合は、治安出動の下令を待って初めて自衛隊が対応することにならざるを得ない。警察力を超える襲撃・破壊行動によるわが方の犠牲を最小限に抑えるためには、早い段階から速やかに自衛隊に十分な活動をさせることが有効だが、治安出動の発令手続きを経る間に、仮にも対応の時機を失するようなこととなれば、テロ、サボタージュ行為が拡大するなどして、その影響は甚大なものとなる可能性がある。
上記の例にもみられるように、武力攻撃に至らない侵害への対応について、現代の国際社会では、その必要性が高まってきており、各種の事態に応じた均衡のとれた実力の行使も含む切れ目のない対応を可能とする法制度について、国際法上許容される範囲で、その中で充実させていく必要がある。また、法整備にとどまらず、それに基づく自衛隊の運用や訓練も整備していかなければならない。
なお、武力攻撃に至らない侵害に対して措置を取る権利を「マイナー自衛権」と呼ぶ向きもあるが、この言葉は国際法上必ずしも確立したものではなく、また、国連憲章第51条の自衛権の観念を拡張させているとの批判を内外から招きかねないので、使用しないことが望ましい。