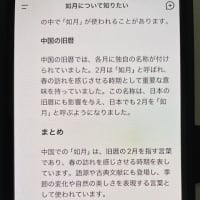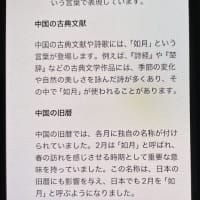2年前のその日、ひとつの命をおくる。病室は相部屋であったので、カーテンで仕切られた窓側のコーナーに、ベッドにしばりつくように寝ていた。食事はさだめられたとおりに摂って日に日に体力の回復を見る。動けないのだけは苦労した。とにかく首をつっぱって背中を浮かすしかない。全身突っ張って痛いのだから、そうでない、そうならない姿勢を探すことになる。電動の背もたれを上げ下げするのが一大事のことであった。その生活にカーテンの向こうの、もう一つの窓側のコーナーに元気な方がいたのだが・・・
テレビをご覧になる、そのためにはコインがいる、そのコインを請求してやり取りをし、ベッドから落としてナースコール、トイレに自力で行こうとしてベッドから落ちる、介護をしようとするとことわる、それで便器を持ち込んでするのだがうまくできたのかどうか、見回りが来てたしかめて清掃となる、それで世間話をする、なんともにぎやかい、だが、どうもようすがおかしい、だんだん声に張りがなくなる、ように思えたら、寝る息のままにお休みだったりして、それをくりかえして、生とのたたかいだった、そう聞こえてくる。
容態が急変したか、深夜の騒ぎにベッドをナースセンターに移したらしい、明けて戻ってきて事なきを思ったが、続々と、3人4人と家族が出入りする、それでまた付き添いで夜を過ごす、小康を得ていたかのような動きであった、どうもだいぶ具合が悪いらしい、ここの病室に来る人は大体が同じ疾患である、退院する前には同じ説明を2度聞いたような気がする、それは入院初日に聞いた同意書である、そうするとどうか、またの深夜にうめき声があり、人を呼ぶようであった、付き添い者はベッドを離れていた、ナースコールはしなかたのか。
あわただしく人の出入りがあって、急診に機械を持ち込んでもいたようであるが、次に静まり返った、家族がいただろうにどこへいっていたのか、しばらくして、天井を見上げながら息をひそめる気配を感じながら、忍び泣きを聞いた、あけてまた、つぎつぎと出入りがあって、ベッドの周りに椅子を据えて声をひそめていた、どうもなくなられたらしい、時を経て、出入りが激しくなり、ベッドは運び出された、あれほどにぎやかな、元気なようすであったのに、私はといえば、動けない身体を何とか持ち上げようと腐心する毎日だった。
あのとき呼んでいた、たしかに、家族がいたはずだから、近くならきこえていただろう、ナースコールを押せば、押すか押さないかで大声でやり取りをしていたから、異変だとして自分が押していればどうなったか、と、ふと気づいたときに、すべてのようすがなにもわからぬままの、結果でいえばそうであるという、隣り合うベッドの思いがよぎってしまった、カーテン閉じきったままの空間がすっと広がってそして、わたしにおしつけてきた、ひとごとではない、ひとごとどころではない、わが命だという思いとともに、だんだんとわかってきたのは、それもいつだったか。
こういうときにはどうするのだろうと、何かわかるか、告げられるか、だれもがなにごともすぎゆくままに、なにもわからないままに語ることはなかった、いつものように早起きで朝焼けをじっと見続けていた、それから誰にもこのできごとを話すことはなかった
テレビをご覧になる、そのためにはコインがいる、そのコインを請求してやり取りをし、ベッドから落としてナースコール、トイレに自力で行こうとしてベッドから落ちる、介護をしようとするとことわる、それで便器を持ち込んでするのだがうまくできたのかどうか、見回りが来てたしかめて清掃となる、それで世間話をする、なんともにぎやかい、だが、どうもようすがおかしい、だんだん声に張りがなくなる、ように思えたら、寝る息のままにお休みだったりして、それをくりかえして、生とのたたかいだった、そう聞こえてくる。
容態が急変したか、深夜の騒ぎにベッドをナースセンターに移したらしい、明けて戻ってきて事なきを思ったが、続々と、3人4人と家族が出入りする、それでまた付き添いで夜を過ごす、小康を得ていたかのような動きであった、どうもだいぶ具合が悪いらしい、ここの病室に来る人は大体が同じ疾患である、退院する前には同じ説明を2度聞いたような気がする、それは入院初日に聞いた同意書である、そうするとどうか、またの深夜にうめき声があり、人を呼ぶようであった、付き添い者はベッドを離れていた、ナースコールはしなかたのか。
あわただしく人の出入りがあって、急診に機械を持ち込んでもいたようであるが、次に静まり返った、家族がいただろうにどこへいっていたのか、しばらくして、天井を見上げながら息をひそめる気配を感じながら、忍び泣きを聞いた、あけてまた、つぎつぎと出入りがあって、ベッドの周りに椅子を据えて声をひそめていた、どうもなくなられたらしい、時を経て、出入りが激しくなり、ベッドは運び出された、あれほどにぎやかな、元気なようすであったのに、私はといえば、動けない身体を何とか持ち上げようと腐心する毎日だった。
あのとき呼んでいた、たしかに、家族がいたはずだから、近くならきこえていただろう、ナースコールを押せば、押すか押さないかで大声でやり取りをしていたから、異変だとして自分が押していればどうなったか、と、ふと気づいたときに、すべてのようすがなにもわからぬままの、結果でいえばそうであるという、隣り合うベッドの思いがよぎってしまった、カーテン閉じきったままの空間がすっと広がってそして、わたしにおしつけてきた、ひとごとではない、ひとごとどころではない、わが命だという思いとともに、だんだんとわかってきたのは、それもいつだったか。
こういうときにはどうするのだろうと、何かわかるか、告げられるか、だれもがなにごともすぎゆくままに、なにもわからないままに語ることはなかった、いつものように早起きで朝焼けをじっと見続けていた、それから誰にもこのできごとを話すことはなかった