メタエンジニアの眼シリーズ(130)「日本語の世界」(2)
TITLE: 「日本語の世界」(つづき)
書籍名;『日本語の世界』 [1980-1986]
編者代表;大野晋と丸谷才一 発行所;中央公論社
発行日;1980.9.15
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
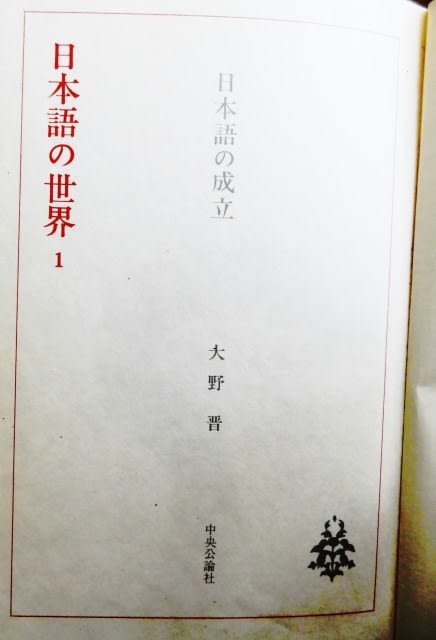
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分
21世紀は、西欧文明期から東洋文明期への転換の世紀と云われている。
東洋文明とは、中国文明やインド文明を指す。辺境の日本文明はどうだろうか。従来、日本文明は親類の無い孤独な文明と云われてきた。しかし、縄文時代から1万年以上も続く文明が孤独なわけがない。中国や朝鮮を親類と呼ぶのには、お互いに問題がある。日本語の起源を探せば、そこに親類が存在することになる。
前回は、本の概要を説明した。今回は、その内容。この第1巻は、日本語の成立に関してのみなのだが、その精緻さは呆れるほどだった。特に母音と子音の種類や数、組み合わせについては、エンジニアや数学者を凌ぐほどと云えるくらいに思えた。
第1、2章は「神話の時代」で、主に大洋州とアジア地域の神話と比べて、その共通性を述べている。多くの国の神話が、女神の死体を切り刻んで埋めたところから、新たな穀物が育ったことを示していることから、女性型の土偶を破壊して、バラバラに埋める祭祀を行ったとの説を主張している。また、日本には「神代文字」があるとの説は、はっきりと否定している。それぞれに、根拠となる理由を示しているのが良い。
第3章の「日本語の重層的成立」では、まず日本語の特質を7つ挙げている。母音で終わる音節構造、形容語が形容される語の前にくる、動詞の目的語は動詞の前に来るなどである。これら七つの条件に最も適合するのが、タミール語だとしている。同じ照葉樹林文化の地に居住するドラヴィタ族(インド北西部に居住)が、BC1600年頃アーリア人の侵略で南方へ移動したことを挙げているが、これはインダス文明との類似を思わせる。私は、従来、古代神道にこのあたりの名残があるように感じている。
古代朝鮮語やモンゴル語との比較も、詳細に述べられているが、ある時期から導入されたもので、古代の日本語とは区別されている。
第5章の「音韻の変遷」が詳しくかつ面白い。古代日本語は4母音で、それが8母音になり、9世紀後半に現在の5母音になった。この変遷は、唇の開閉と舌の位置の状態から、不均衡、不安定などの理由で変化したことが説明されている。それらはすべて、その時代につくられた文献から推測されている。論理思考がまさにエンジニアのそれと同じだ。
第6章「日本の東と西」は、雑煮の餅の形から始まる。東は角で西は丸がはっきりとしている。これは、女性の定住率と深い関係があることを、統計値で説明している。B型肝炎の抗原基についても同じだ。東日本では沢といい、西日本では谷という。
東西の力関係は、縄文時代は圧倒的に東で、稲作が広がって西が有利になり、鎌倉時代以降は東が有利。つまり、1千年くらいで交代が起こっている。世界文明の東西交代は600~800年なので、日本での変化はそれよりも遅いが、そろそろ日本の中心も西へ移るのかもしれない。
第1の東国;碓氷峠と箱根峠より東
第2の東国;信濃、甲斐、駿河、伊豆、遠江
第3の東国;飛騨、美濃、尾張、三河
この分類は、鎌倉時代から江戸時代の地域の変遷も表してているが、著者は方言や表現方法で違いを説明している。
「助詞のガ」の使いかたは、あまり気にしていなかったが、深い意味がある。江戸時代以降に定着したのだが、「我が国」、「我が家」など、自分を卑下したり、身内の親しみを表すという。奈良時代の東国の歌にも「ガ」が使われているが、例えば、「赤駒が」の用法は東国で、「赤駒の」は畿内人のうたであり、東国では駒が身内扱いされていたためとしている。
第7章は「帰化人が漢字を教えた」で、第1の帰化人を漢人としている。後漢の王族の末裔で、倭漢直(やまとのあやのあたひ)と西文首(かはちのふみのおびと)と呼ばれ、それぞれ大和と河内に定住した。
彼等は、魏と晋の発音を伝えた。
第2の帰化人は、200年後に新羅によって滅ぼされた百済、高句麗からの亡命者で、船史(うねのふびと)、津史(つのふびと)と呼ばれ、大化の改新に関与した。「呉音」は、呉から直接に伝わったのではなく、百済経由で伝わったとしている。
漢字の訓読みは、日本独特ではなく、百済でも使われていたが、朝鮮ではその後使用されなくなり、日本独特のものになった。すでに万葉集の中に実例がある。31音の歌が、21字で表されており、そこでは「春」の字は、春の意味ではなく、「はる」の字として使われている。
第8章は、「文章を制作しはじめる」で、古事記と日本書紀の成立の詳細を述べている。特に古事記では、『全部日本語で訓み通せるような日本の神々の物語と、その後をつぐ歴史をかきたい。』との願いから、日本式の文体が考え出された。その際には、法華経などが参考にされた。
『編者が中国語訳の仏典を、文章の参考にするところが大きかった結果生じた言葉遣いと思われる。
このように、古事記は中国語訳の仏典を参考にしているが、今日でも古事記は、稗田阿礼の暗誦を太安麿が書き付けたのだと素朴に信じている人がある。しかし古事記・日本書紀はそれ以前の文献を集成し、文章化したものである。そこで、古事記・日本書紀以前に、神話についても文字化された記録があったのだということをいくつか立証してみよう。』(pp.209)として、神々の名前の例を挙げている。また、その際に口伝では起こりえない誤伝があり、書き写しの間違えだったことも、証拠の一つに挙げている。日本書紀との比較も精緻に行われているが、結果的には通説を踏襲している。
第9書「ウタを記録する」は、奥が深い(すべての章がそうなのだが、ここは特に感じた)。
『ひるがえって漢宇を見ると、「詠」は「言」を「永」く引く意をあらわすし、「謡」は「言」を細長く伸ばす意であるという。また、「歌」は「可」を二つ重ねて「欠」と合わせた字で、「可」とは本来、「 型(かぎがた)に曲折する意であり、「欠」はロを大きく開く意であるという説がある。してみると、「歌」とは、ロを大きく開いて、声に曲折をつけるという意味を表わしていたと推定される。中国語には、いまーつ「詩」という字がある。「詩」は「志」と相通じる言葉である。』(pp.235)
その後、「ウタ」がどのような経緯で成立したかを、掛け合い、神前の祝詞などの例で示しているが、最終的には、『心に湧いてきて、止めようもないこと、それを表すウタがそのまま名詞として固定された』(pp.238)としている。「ウタガフ」も、『すでに生じた事態に対して自分の以前からの用意、相手の知らない事情などを明らかにしようと述べ立てること』(pp.237)としている。
最後に、いろは歌について述べ、弘法大師作の説をはっきりと否定している。大師の時代の音節は48または49で47文字であるのは、11世紀の京都の発音に準じているとのことが示されている。
ここで、少しタミル語についてWikipediaの記述をあたってみる。
『タミル語は、ドラヴィダ語族に属する言語で、南インドのタミル人の言語である。同じドラヴィダ語族に属するマラヤーラム語ときわめて近い類縁関係の言語だが、後者がサンスクリットからの膨大な借用語を持つのに対し、タミル語にはそれが(比較的)少ないため、主に語彙の面で異なる。インドではタミル・ナードゥ州の公用語であり、また連邦レベルでも憲法の第8付則に定められた22の指定言語のひとつであるほか、スリランカとシンガポールでは国の公用語の一つにもなっている。世界で18番目に多い7400万人の話者人口を持つ。(中略)
南インドのタミル・ナードゥ州で主に話されるほか、ここから移住したスリランカ北部および東部、マレーシア、シンガポール、マダガスカル等にも少なくない話者人口が存在する。これらはいずれも、かつてインド半島南部に住んでいたタミル人が自ら海を渡ったり、あるいはインドを植民地化した英国人がプランテーションの働き手として、彼らを移住させた土地である。』
しかし、現代のタミール語の発音は複雑であり、古代語の段階でどれほどの共通項があったかについては、何も記されていない。
TITLE: 「日本語の世界」(つづき)
書籍名;『日本語の世界』 [1980-1986]
編者代表;大野晋と丸谷才一 発行所;中央公論社
発行日;1980.9.15
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
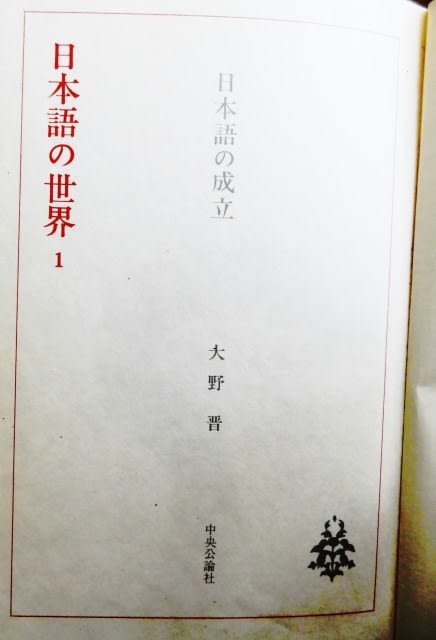
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分
21世紀は、西欧文明期から東洋文明期への転換の世紀と云われている。
東洋文明とは、中国文明やインド文明を指す。辺境の日本文明はどうだろうか。従来、日本文明は親類の無い孤独な文明と云われてきた。しかし、縄文時代から1万年以上も続く文明が孤独なわけがない。中国や朝鮮を親類と呼ぶのには、お互いに問題がある。日本語の起源を探せば、そこに親類が存在することになる。
前回は、本の概要を説明した。今回は、その内容。この第1巻は、日本語の成立に関してのみなのだが、その精緻さは呆れるほどだった。特に母音と子音の種類や数、組み合わせについては、エンジニアや数学者を凌ぐほどと云えるくらいに思えた。
第1、2章は「神話の時代」で、主に大洋州とアジア地域の神話と比べて、その共通性を述べている。多くの国の神話が、女神の死体を切り刻んで埋めたところから、新たな穀物が育ったことを示していることから、女性型の土偶を破壊して、バラバラに埋める祭祀を行ったとの説を主張している。また、日本には「神代文字」があるとの説は、はっきりと否定している。それぞれに、根拠となる理由を示しているのが良い。
第3章の「日本語の重層的成立」では、まず日本語の特質を7つ挙げている。母音で終わる音節構造、形容語が形容される語の前にくる、動詞の目的語は動詞の前に来るなどである。これら七つの条件に最も適合するのが、タミール語だとしている。同じ照葉樹林文化の地に居住するドラヴィタ族(インド北西部に居住)が、BC1600年頃アーリア人の侵略で南方へ移動したことを挙げているが、これはインダス文明との類似を思わせる。私は、従来、古代神道にこのあたりの名残があるように感じている。
古代朝鮮語やモンゴル語との比較も、詳細に述べられているが、ある時期から導入されたもので、古代の日本語とは区別されている。
第5章の「音韻の変遷」が詳しくかつ面白い。古代日本語は4母音で、それが8母音になり、9世紀後半に現在の5母音になった。この変遷は、唇の開閉と舌の位置の状態から、不均衡、不安定などの理由で変化したことが説明されている。それらはすべて、その時代につくられた文献から推測されている。論理思考がまさにエンジニアのそれと同じだ。
第6章「日本の東と西」は、雑煮の餅の形から始まる。東は角で西は丸がはっきりとしている。これは、女性の定住率と深い関係があることを、統計値で説明している。B型肝炎の抗原基についても同じだ。東日本では沢といい、西日本では谷という。
東西の力関係は、縄文時代は圧倒的に東で、稲作が広がって西が有利になり、鎌倉時代以降は東が有利。つまり、1千年くらいで交代が起こっている。世界文明の東西交代は600~800年なので、日本での変化はそれよりも遅いが、そろそろ日本の中心も西へ移るのかもしれない。
第1の東国;碓氷峠と箱根峠より東
第2の東国;信濃、甲斐、駿河、伊豆、遠江
第3の東国;飛騨、美濃、尾張、三河
この分類は、鎌倉時代から江戸時代の地域の変遷も表してているが、著者は方言や表現方法で違いを説明している。
「助詞のガ」の使いかたは、あまり気にしていなかったが、深い意味がある。江戸時代以降に定着したのだが、「我が国」、「我が家」など、自分を卑下したり、身内の親しみを表すという。奈良時代の東国の歌にも「ガ」が使われているが、例えば、「赤駒が」の用法は東国で、「赤駒の」は畿内人のうたであり、東国では駒が身内扱いされていたためとしている。
第7章は「帰化人が漢字を教えた」で、第1の帰化人を漢人としている。後漢の王族の末裔で、倭漢直(やまとのあやのあたひ)と西文首(かはちのふみのおびと)と呼ばれ、それぞれ大和と河内に定住した。
彼等は、魏と晋の発音を伝えた。
第2の帰化人は、200年後に新羅によって滅ぼされた百済、高句麗からの亡命者で、船史(うねのふびと)、津史(つのふびと)と呼ばれ、大化の改新に関与した。「呉音」は、呉から直接に伝わったのではなく、百済経由で伝わったとしている。
漢字の訓読みは、日本独特ではなく、百済でも使われていたが、朝鮮ではその後使用されなくなり、日本独特のものになった。すでに万葉集の中に実例がある。31音の歌が、21字で表されており、そこでは「春」の字は、春の意味ではなく、「はる」の字として使われている。
第8章は、「文章を制作しはじめる」で、古事記と日本書紀の成立の詳細を述べている。特に古事記では、『全部日本語で訓み通せるような日本の神々の物語と、その後をつぐ歴史をかきたい。』との願いから、日本式の文体が考え出された。その際には、法華経などが参考にされた。
『編者が中国語訳の仏典を、文章の参考にするところが大きかった結果生じた言葉遣いと思われる。
このように、古事記は中国語訳の仏典を参考にしているが、今日でも古事記は、稗田阿礼の暗誦を太安麿が書き付けたのだと素朴に信じている人がある。しかし古事記・日本書紀はそれ以前の文献を集成し、文章化したものである。そこで、古事記・日本書紀以前に、神話についても文字化された記録があったのだということをいくつか立証してみよう。』(pp.209)として、神々の名前の例を挙げている。また、その際に口伝では起こりえない誤伝があり、書き写しの間違えだったことも、証拠の一つに挙げている。日本書紀との比較も精緻に行われているが、結果的には通説を踏襲している。
第9書「ウタを記録する」は、奥が深い(すべての章がそうなのだが、ここは特に感じた)。
『ひるがえって漢宇を見ると、「詠」は「言」を「永」く引く意をあらわすし、「謡」は「言」を細長く伸ばす意であるという。また、「歌」は「可」を二つ重ねて「欠」と合わせた字で、「可」とは本来、「 型(かぎがた)に曲折する意であり、「欠」はロを大きく開く意であるという説がある。してみると、「歌」とは、ロを大きく開いて、声に曲折をつけるという意味を表わしていたと推定される。中国語には、いまーつ「詩」という字がある。「詩」は「志」と相通じる言葉である。』(pp.235)
その後、「ウタ」がどのような経緯で成立したかを、掛け合い、神前の祝詞などの例で示しているが、最終的には、『心に湧いてきて、止めようもないこと、それを表すウタがそのまま名詞として固定された』(pp.238)としている。「ウタガフ」も、『すでに生じた事態に対して自分の以前からの用意、相手の知らない事情などを明らかにしようと述べ立てること』(pp.237)としている。
最後に、いろは歌について述べ、弘法大師作の説をはっきりと否定している。大師の時代の音節は48または49で47文字であるのは、11世紀の京都の発音に準じているとのことが示されている。
ここで、少しタミル語についてWikipediaの記述をあたってみる。
『タミル語は、ドラヴィダ語族に属する言語で、南インドのタミル人の言語である。同じドラヴィダ語族に属するマラヤーラム語ときわめて近い類縁関係の言語だが、後者がサンスクリットからの膨大な借用語を持つのに対し、タミル語にはそれが(比較的)少ないため、主に語彙の面で異なる。インドではタミル・ナードゥ州の公用語であり、また連邦レベルでも憲法の第8付則に定められた22の指定言語のひとつであるほか、スリランカとシンガポールでは国の公用語の一つにもなっている。世界で18番目に多い7400万人の話者人口を持つ。(中略)
南インドのタミル・ナードゥ州で主に話されるほか、ここから移住したスリランカ北部および東部、マレーシア、シンガポール、マダガスカル等にも少なくない話者人口が存在する。これらはいずれも、かつてインド半島南部に住んでいたタミル人が自ら海を渡ったり、あるいはインドを植民地化した英国人がプランテーションの働き手として、彼らを移住させた土地である。』
しかし、現代のタミール語の発音は複雑であり、古代語の段階でどれほどの共通項があったかについては、何も記されていない。









