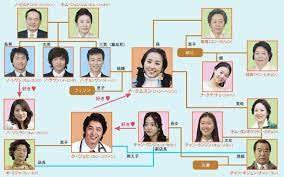
韓国ドラマ「がんばれ!クムスン」(150)
「美容室は?」
「探しています。秀(スー)の面接を受け、連絡を待ってます」
「秀? うん、そこもいいわね。復職できるなら、また戻る?」
「院長・・・」
「もうすぐデザイナーの昇格テストよ」
「はい、知ってます」
「その試験のためにも復職したい?」
「はい。許可をいただければ」
「・・・ジェヒとも結婚したいし・・・?」
「・・・」
「あなた・・・ジェヒのどこがいいの?」
「・・・」
「ジェヒは――あなたのどこがいいの?」
「・・・」
黙っているクムスンを見てミジャは頷く。
「いいわ――だったら結婚しなさい」
「院長・・・」
「許可はするけど、子供はダメよ」
「・・・」
「子供は置いてきて。それなら許可するわ」
「・・・」
「他は何でも譲れる。あなたがジェヒより条件が悪くてもいい。結婚歴? そうね、最近は離婚する人も多いし、目をつむることもできる。他の条件はすべて目をつむることができても――子供はダメよ」
クムスンの目はみるみる潤んでくる。
「いくら考えてもダメなの。私には過酷なことなの。独り身で育てたジェヒに人の子を育てさせるなんて、到底できないわ」
「・・・」
「子供を置いてきなさいそしたら結婚を許してあげる。身を切るようなことだけど、それでもあなたはジェヒを得るのよ」
「・・・」
「クムスン――世の中に無料(タダ)はないわ。何でも対価を支払うのよ」
クムスンの頬を涙が伝いだす。
「分かったわね? 子供は諦めて」
ミジャと別れた後、クムスンはヨンオクの家に向かった。たどり着くとすぐインターホンを押した。
応対に出たのはヨンオクだった。
「お話があります。出てきてください」
ヨンオクは喜び、胸はずませてクムスンを迎えに出た。
「来てくれたのね」
しかし、クムスンはいきなり怒りをぶつけてくる。
「なぜ捨てたんです?」
「・・・」
「なぜ私を捨てたの? おばあちゃんが怖かったなら私を連れて出るべきだわ。なぜ捨てたの?」
「・・・」
「いいえ――その時は気が動転して置いていったとして・・・幼くして夫をなくしよりどころもない婚家で、おばあちゃんは鬼みたいに辛くあたるし」
「・・・」
「だから――正気じゃなくて逃げたのは理解できます。でも迎えに来てほしかった。正気に戻って生活が安定したなら・・・何年が過ぎたあとでも迎えに来てくれるべきでしょ。立派な夫と再婚し、大きな家に住んで、ウンジンも産んで裕福に暮らしてるのに着てくれるべきでしょ」
クムスンの話を聞きながらヨンオクは涙を浮かべた。見る見るうちに頬を伝いだす。
「私を引き取って大学にも通わせて。他の女性のように立派な女性にさえ育ててくれれば――少なくとも院長に母親みたいに子を捨てろと言われなかったわ。養母にまで――母親は私を捨てて裕福に暮らしてると言われなかったわ」
「クムスン・・・」
「答えてください。どうしてですか? 答えてください。どうして捨てたの?」
「・・・」
クムスンは泣き出す。
「私は・・・こんなに優しいママに――捨てられたのが信じられないのに・・・生まれたばかりの私を・・・」
ヨンオクはクムスンの手を取った。
クムスンはその手をふりほどく。
「クムスン」
クムスンは我に返った。母にぐちをこぼしにきた自分にいたたまれなくなった。
「・・・もう行きます。失礼します」
冷たい態度で背を返す。母に会った時間を打ち消すようにそそくさ歩き出す。
クムスンの心の痛みをひしひしと感じながらヨンオクは叫んだ。
「クムスン!」
歌をうたっていたスンジャが訊ねる。
「お出かけですか?」
「そうだ」
ジョムスンは答えて水を飲む。
「クムスンの婚家に」
「何しに?」
「フィソンのことでよ。考えれは考えるほど、良心のない人たちだわ。いままでまともにフィソンの面倒も見なかったでしょ。クムスンが冬に――フィソンをおぶって青汁配達をしてた時、面倒みなかったでしょ」
「いろんな言い訳で面倒を見ませんでした。最近までお義母さんが子守をしてたわ」
「そうなの。そんな扱いをしておいて――クムスンに苦労をさせ、良心のかけらもないったら・・・」
「でも、婚家の立場ではジョンワンの唯一の血筋だわ。それも男の子で・・・」
「・・・」
「だから、婚家に行っても興奮したらダメですよ」
「まだ老いぼれてないわ。孫娘が人質に捕らわれてるのよ」
「・・・」
「とにかく今日は、行って結論を出してこないと――舅たちがフィソンを諦めると言うまでは帰らないわよ。じゃあ、行ってくる」
ジョムスンは腰をあげた。
ジョムスンはノ家を訪れ、ピルトとジョンシムの二人を目の前にした。
ピルトが訊ねた。
「今日はどんなご用で?」
「ええ、それが――遠まわしに言っても仕方ないので、単刀直入に言わせてもらいます」
「・・・」
「フィソンを譲ってください」
二人は目を見合わせる。
「確かに――フィソンはジョンワンの息子です。唯一の血筋だし胸の痛むことだと思います。ですが――フィソンはクムスンの息子です。自分の腹の中で10ヶ月も大切に育てて、胸を痛めて産んだ子です。そんな子を置いて、自分の幸せのために結婚するなんて人間にはできないことです」
「お話は分かりました」とピルト。「ですが、フィソンを手放すことはできません。フィソンを他人の家に出すなんて、フィソンはジョンワンの唯一の肉親なんです。私たちにはジョンワンのような存在です。なのに手放せますか?」
「それでもフィソンのために手放すべきです。フィソンのことを考えないと。母親と離れて暮らすことはできません。人間なら子から母親を奪おうとしますか?」
「それはちょっと・・・人間ならと仰るのは、私たちは人でなしですか?」
「そういう意味じゃなくて、不快でしたらすみません――よくご存知のはずです。3年も暮らしてたならクムスンがどんな子か」
「・・・」
「フィソンを置いていけと言うなら、その言葉はつまり・・・一生クムスンに結婚するなというのと同じです」
「違います。私たちはクムスンを喜んで結婚させます。結婚準備も手伝います」
「まあ、本当に――そんな話が通るとでも?」
「いいえ、私は継父のもとになぜフィソンを連れて行くのか分かりません」
「じゃあクムスンに、一生、結婚するなと?」
「そうじゃないんです。子供を手放せばいいんです。人の子はしょせん人の子なんです。自分の子ができたら変わります」
「他人の子を養子にして実子以上に育てる人だっています。どうして悪くばかり考えますか? それに、うちのジェヒは本当にいい青年です」
「”うちのジェヒ”?」
「それはですね・・・つまり・・・もう一度、この通りにお願いします」
「お話は分かりましたが、考えは変わりません。これでお帰りを――私たちの意志は伝えましたし、こうやって話す理由もありませんので」
ジョムスンはノ家を出た。
「簡単には渡してくれないようだわ。本当にどうしたら・・・クムスンはどうなるの」
「今日はどんなご用件で?」
シワンはジェヒに訊ねた。
「その前に――年上ですから私から先輩とお呼びしても?」
「・・・」
「聞いた話では大学の先輩のようですし、先輩と呼びます」
「ええ、どうぞ」
「お察しの通り――クムスンさんの件です。助けてください」
「・・・」
「フィソンを大切に育てます」
「お気持ちはありがたいです。いくら愛する女でもその息子を育てるのは難しい決心なのに」
「はい。難しい決心でした。クムスンさんの結婚歴も、子供のいる事実も、本当に驚いて逃げ出したこともあります」
シワンは苦笑を覗かせる。自分の話をされてるような気がするからだった。
「結局は諦められず、先輩に助けを求めています」
「・・・」
「お願いします。本当に努力します」
「私も同じく妻の子を育てる立場です」
「・・・」
「だけど私は、簡単に決心できませんでした。ひどく慌てて――ためらいました。とても苦しみました」
「・・・私もフィソンに会う前はそうでした。でも会ってみると、逆に気が楽になりました。フィソンがかわいくて昔の自分を見るようでした。私も父親がなく、フィソンを見たら――あの子がとても愛しくて、好きになりました」
「・・・」
「母の問題が残っているのは確かです。何としても許可をもらいます」
「・・・」
「ですが――本当にフィソンが好きで、愛する気持ちは本当です。私は子は愛で育つと思っています」
「・・・」
「本当に私が愛すれば――それがフィソンに伝わって本当の親子になれます」
二人は店を出た。
シワンはジェヒに握手を求めようとした。彼が気に入ったからだ。しかし、それができず一礼しあって別れた。
シワンを見送り、携帯の電源を入れるとクムスンのメールが入っていた。
――電話に出ないので帰ります。あとで電話します。
クムスンに電話を入れるとクムスンの携帯は電源オフだった。
母親に会うと言っていたのが気になり、母親に電話する。
「母さん――今、どこ? 美容室? クムスンと会ったの? どうして会ったの? 何と言ったんです?」
「家で話して。出かけるから切るわ」
携帯は切れた。
衣服売り場を一緒に歩きながら、クマはテワンに文句を並べ立てている。
「テワンさんの家がそんなに古臭いなんて信じられない」
「もうやめろよ」
「19世紀じゃあるまいし、子を手放せだなんて」
「うるさいな。ずっと吠え立てるつもりか? 俺はうるさい女は嫌いだ」
「吠え立てる? 私を犬だというの?」
「汚いな。唾が飛んでるぞ」
「今度、人格冒涜と女性を卑下したら許さない」
「言いすぎだ。人格冒涜に女性卑下だなんて」
「うるさい女という発想がそうよ」
「ああ、もう・・・お前からクムスンの香りはしないな。そうじゃなく義姉の臭いがするよ」
「何のこと? 私、香水は使ってないわ」
テワンは黙って先を歩き出す。
荷造りしてるのにいちいち口を挟んでくるキジョンにウンジュは訊ねた。
「私が行くのが嫌なの?」
「当然だろ・・・」
荷造りを続けながらウンジュは言う。
「だったら、普段からよくしてよ。もう決めたの」
「本当に行くのか?」
「・・・」
「どうしても? ここに残ったらダメかな」
「パパ」ウンジュは立ち上がる。「もしかして、何かあった?」
「・・・」
「パパ・・・」
クムスンがフィソンを連れて帰ってくる。
洗濯物を取り込んでいたジョンシムはフィソンに「お帰り」と歩み寄り、言葉を交わそうとする。
するとクムスンはフィソンを自分の方に引き寄せ、やんわりジョンシムから引き離すしぐさを取る。
「どういうつもり?」
「フィソンの面倒は私がやります」
「・・・」
「フィソン、行くわよ」
「待ちなさい」
「フィソンを寝かせたらうかがいます。お話することもあります。その時にお願いします」
「・・・」
クムスンが茶の間に腰をおろす。テワンを除く4人がそこに座っている。
クムスンが切り出した。
「話してみなさい」とピルト。
「フィソンは――私が連れていきます」
「お前――」
「フィソンは私の子で私が母親です。そして私には――母親の資格もあります」
「そりゃ資格はあるよ」
「なら連れて行きます。彼が死んで一人になった時、お二人は子供を産むなと仰いました。ですが、その時も私は産むと決心して最後まで守りました」
「そうだったな。でも、反対したのはお前のためだった」
「そして今まで一生懸命育てました。今年、就職する前は一日中フィソンに尽くしたし、就職後も――お義母さんに迷惑をかけないよう本当に頑張りました」
「それは分かるわ」
「だからフィソンを諦めてください」
「ダメだ」
「お義父さま。お二人のお許しがなくても連れていきます。フィソンは私の息子で――私に権利があります。親権も私にあります」
「何だと?」
「はい――お義父さまが本気だと知り、私もインターネットで色々調べました。それで親権は私にあるのを知りました。ですから、許可なしにフィソンを連れていけるし、お二人に反対する権利はありません」
「何だと? どうしたって! だからどうするんだ? 勝手に連れていくのか?」
「はい」
「・・・」
「最後までお許しをいただけなくても、フィソンを連れて行きます」
「何だと、黙れ!」
「すみません。お二人が反対しても今回は従えません。死んでもフィソンは私が連れて行きます」
ピルトは席を立った。部屋に戻った。
ジョンシムが追いかけてくる。
「あなた、怒ってどうするのよ。どうにかしてなだめるべきなのに・・・」
「なだめるだと? あいつが何だと・・・」
「クムスンが怒って出ていったらどうするのよ。本当に困ったわ」
ピルトはジョンシムを睨む。
「そのうち突然、フィソンを連れて出て行ったら・・・本当にどうしたら・・・」
ピルトは大きくため息をついた。
ジョンシムはクムスンの部屋に行った。
「ねえ、クムスン」
「・・・」
「クムスン――違うわよね。怒って言っただけでしょ?」
「お義母さん・・・」
「違うでしょ? 私たちにあんなことを言うなんて思わなかった。親権だなんて・・・今朝、父さんがひどいことを言ったから・・・怒って言ってみたんでしょ?」
「お義母さん・・・お義母さんもですよね? フィソンを手放せだなんて」
「私もフィソンなしに生きられない」
「お義母さん、それは私も同じですよ」
「クムスン」ジョンシムはクムスンの手を取る。「お願い、お願いだから――フィソンを私たちに任せ、結婚して幸せになって」
「・・・」
「フィソンは私たちがいる。私たちからフィソンまで取らないで。シワンたちももうすぐいなくなるわ。あなたもフィソンもいなくなったら。私たちはどうすればいいの?」
「・・・」
「きっと知らないわ。今まであなたを――ジョンワンの代わりと思って暮らしていたの」
「・・・」
「なのに急に結婚するというし・・・私の気持ちが分かる?」
「お義母さん・・・」
「結婚をやめろというわけじゃないのよ。当然、あなたはまだ若いし行くべきよ。結婚するべきよ。クムスン――フィソンは諦めて。お願い。フィソンを諦めてもこれから夫もできるし、子供だって産むでしょ。かわいそうな老人だと思ってフィソンを私たちに任せて。お願い。私たちを哀れに思って――置いていって。私たちがしっかり育てるから」
「お義母さん・・・ならフィソンは? 母親と別れるフィソンは? 一度、フィソンの立場で考えてみてください」
「・・・」
「私にはよく分かります。いくら祖父母といっても母親とは違います」
「・・・」
「すみません。ほんとうにすみません」
ジョンシムは肩の力を落とした。
「どうすれば・・・ほんとうにどうしたら・・・フィソンなしではダメなの。ジョンワンには会えないし・・・フィソンまでいなかったら・・・」
「・・・」
「あの・・・それじゃあ、クムスン・・・それなら―」
ジョンシムはクムスンの手を再び取った。
「結婚を諦めて」
「・・・」
「ダメなの?」
「行くにしてももう少し後で・・・フィソンが小学生になって・・・いえ、違うわ・・・」
「どうしよう・・・」
ジョンシムは目を潤ませた。クムスンを見た。
「どうしたらいいの?」
「お義母さん・・・」
ジョンシムは泣き出した。
script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?2db9cb=googleTranslateElementInit"></script> google-site-verification: google3493cdb















