
それだけ日本が世界に向かって遺贈度が高くなった証拠でしょうけど・・・尖閣諸島問題で日本に動揺が走るほど対応策が各家庭には浸透していません。これも立派な政府の仕事です!安心できる対応策を学ぶ事は今後には避けて通れない・・・・・

【論風】日本危機管理学会理事長 東京理科大学客員教授 原田泉
2010.10.29 05:00
http://www.sankeibiz.jp/business/news/101029/bsj1010290503002-n1.htm
■新しい番号制度 プライバシーリスク回避を
現在、民主党の調査会で社会保障と税にかかわる番号制度が、また政府IT戦略本部では電子行政の共通基盤としての国民ID制度が実施に向けて検討されている。少子高齢社会を迎え行政の効率化は不可欠であり、急増する社会保障費に対し税・保険料負担と社会保障給付の公平性を担保し、制度の透明性と信頼性向上を図り、給付付き税額控除などの新たな政策展開と電子行政推進のため情報社会の基盤として新しい番号制度の導入は不可避と思われる。今後いかなる制度や社会システムが構築されるか注目されるところだ。
◆独仏では厳格に運用
しかし、少なからぬ国民が分野横断的な共通番号制の導入によって国家の監視や管理が強化され、個人の自由が脅かされ、また行政職員による個人情報ののぞき見や不正利用などが行われるのではないかとの懸念を持っている。現在バラバラに管理されている分野別の個人情報が、新制度によって名寄せ可能となりプライバシー侵害が増大するかもしれないとの不安もある。
このような国民の意識や感情は、その国の歴史的社会的環境によって形成されるが、民主主義国においては個人の権利と公共の福祉のバランスが肝要である。個人情報の提供・利用において、イヤなら他の選択肢がある民間領域と異なり、法的根拠に基づき基本的には選択の余地がない行政領域では、個人情報の信託を受ける立場として国民のプライバシーを十二分に尊重し、信頼を醸成せねばならない。
実際、欧州ではプライバシーリスクに極めて厳格に取り組んでいる。ドイツでは1970年代に分野横断的な個人識別番号の導入が提起されたが、連邦憲法裁判所が違憲と判断し、行政機関が国民の生活を管理監視可能なデータの保持はできないことになっている。また、中央集権的で国家権力が強いフランスでも官民で利用できる電子国民IDカードの導入を進めているものの、その監視機関として強力な権限を持つ国家機関「CNIL」が国民のプライバシーと人権を守っている。
英国では、電子国民IDが9・11同時多発テロを受け、当時のブレア首相の労働党政府によって強力に推進され、既に一部地域で配布が行われていた。
しかし、政府機関のデータ流出などプライバシーに対する懸念に加え、目的の不明確さ、膨大なコストに対する費用対効果などが問題視され、昨年の政権交代でキャメロン首相率いる新政府によって廃止となってしまった。
◆「影響評価」手法も有効
一方、プライバシー問題と行政の効率化を両立させているケースもある。オーストリアでは、基礎番号から行政サービスごとに異なる番号を派生させるセクトラルモデルが運用されており、行政機関同士で住民データを安全に融通することが可能となった。漏洩(ろうえい)被害も行政サービス単位にとどまり、国が国民を監視することも困難な仕組みが実現しているのである。
既にカナダやオーストラリア、米国などで実施されているプライバシー影響評価(PIA)も注目される。
これは個人情報の収集を伴う情報システムの導入や改修にあたり、事前にプライバシーへの影響を評価し、潜在リスクを回避するための運用技術的な変更を促す一連のプロセスであり、ITシステム稼働後のプライバシーリスクを最小に抑えることができる。重大な法令違反や、プライバシー上の懸念事項が顕在化した場合、それがシステム構築後だと対策は対症療法的で非効率となり、時間やコスト負担も大きくなる。このようなことがないようにプライバシーリスクが予想されるシステム導入にあたって事前に実施するのである。
以上のようなセクトラルモデルやプライバシー影響評価などを日本の状況に合わせた形で取り入れて新しい番号制度を構築してもらいたい。
◇
【プロフィル】原田 泉
はらだ・いずみ 慶大大学院修士修了。日本国際貿易促進協会などを経てNEC総研から国際社会経済研究所へ。現在同研究主幹。情報セキュリティ大学院大学客員教授、早稲田大学非常勤講師なども務める。54歳。東京都出身。

【論風】日本危機管理学会理事長 東京理科大学客員教授 原田泉
2010.10.29 05:00
http://www.sankeibiz.jp/business/news/101029/bsj1010290503002-n1.htm
■新しい番号制度 プライバシーリスク回避を
現在、民主党の調査会で社会保障と税にかかわる番号制度が、また政府IT戦略本部では電子行政の共通基盤としての国民ID制度が実施に向けて検討されている。少子高齢社会を迎え行政の効率化は不可欠であり、急増する社会保障費に対し税・保険料負担と社会保障給付の公平性を担保し、制度の透明性と信頼性向上を図り、給付付き税額控除などの新たな政策展開と電子行政推進のため情報社会の基盤として新しい番号制度の導入は不可避と思われる。今後いかなる制度や社会システムが構築されるか注目されるところだ。
◆独仏では厳格に運用
しかし、少なからぬ国民が分野横断的な共通番号制の導入によって国家の監視や管理が強化され、個人の自由が脅かされ、また行政職員による個人情報ののぞき見や不正利用などが行われるのではないかとの懸念を持っている。現在バラバラに管理されている分野別の個人情報が、新制度によって名寄せ可能となりプライバシー侵害が増大するかもしれないとの不安もある。
このような国民の意識や感情は、その国の歴史的社会的環境によって形成されるが、民主主義国においては個人の権利と公共の福祉のバランスが肝要である。個人情報の提供・利用において、イヤなら他の選択肢がある民間領域と異なり、法的根拠に基づき基本的には選択の余地がない行政領域では、個人情報の信託を受ける立場として国民のプライバシーを十二分に尊重し、信頼を醸成せねばならない。
実際、欧州ではプライバシーリスクに極めて厳格に取り組んでいる。ドイツでは1970年代に分野横断的な個人識別番号の導入が提起されたが、連邦憲法裁判所が違憲と判断し、行政機関が国民の生活を管理監視可能なデータの保持はできないことになっている。また、中央集権的で国家権力が強いフランスでも官民で利用できる電子国民IDカードの導入を進めているものの、その監視機関として強力な権限を持つ国家機関「CNIL」が国民のプライバシーと人権を守っている。
英国では、電子国民IDが9・11同時多発テロを受け、当時のブレア首相の労働党政府によって強力に推進され、既に一部地域で配布が行われていた。
しかし、政府機関のデータ流出などプライバシーに対する懸念に加え、目的の不明確さ、膨大なコストに対する費用対効果などが問題視され、昨年の政権交代でキャメロン首相率いる新政府によって廃止となってしまった。
◆「影響評価」手法も有効
一方、プライバシー問題と行政の効率化を両立させているケースもある。オーストリアでは、基礎番号から行政サービスごとに異なる番号を派生させるセクトラルモデルが運用されており、行政機関同士で住民データを安全に融通することが可能となった。漏洩(ろうえい)被害も行政サービス単位にとどまり、国が国民を監視することも困難な仕組みが実現しているのである。
既にカナダやオーストラリア、米国などで実施されているプライバシー影響評価(PIA)も注目される。
これは個人情報の収集を伴う情報システムの導入や改修にあたり、事前にプライバシーへの影響を評価し、潜在リスクを回避するための運用技術的な変更を促す一連のプロセスであり、ITシステム稼働後のプライバシーリスクを最小に抑えることができる。重大な法令違反や、プライバシー上の懸念事項が顕在化した場合、それがシステム構築後だと対策は対症療法的で非効率となり、時間やコスト負担も大きくなる。このようなことがないようにプライバシーリスクが予想されるシステム導入にあたって事前に実施するのである。
以上のようなセクトラルモデルやプライバシー影響評価などを日本の状況に合わせた形で取り入れて新しい番号制度を構築してもらいたい。
◇
【プロフィル】原田 泉
はらだ・いずみ 慶大大学院修士修了。日本国際貿易促進協会などを経てNEC総研から国際社会経済研究所へ。現在同研究主幹。情報セキュリティ大学院大学客員教授、早稲田大学非常勤講師なども務める。54歳。東京都出身。













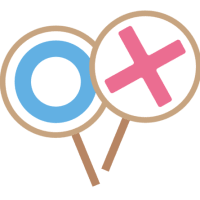






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます