
ホンダマチック!マン島勝利!F1世界チャンピオン!ジェット機の製造販売!言い出したら限がないくらい多くの目標に向かって実績を作り上げた数少ないメーカーだと思っています。もう1つ身近な事でいえば他社の中古車は一切販売しないホンダオンリーの中古車販売
アシモ10歳 ホンダ苦心 ヒト型ロボ、実用へ開発分岐点!
2010.10.30 05:00
http://www.sankeibiz.jp/business/news/101030/bsc1010300500001-n1.htm
ホンダのヒト型ロボット「ASIMO(アシモ)」が二足歩行に成功してから、31日で10周年を迎える。この間、アシモは人の動きを理解する知能化技術などを備える一方、歩行アシスト装置などロボット開発からの副産物も生まれた。ただ、2015年を目指していた“実用化”にはまだ課題が多いようだ。ヒト型ロボットはトヨタ自動車なども開発を進めるが、韓国や中国も“ロボット大国・日本”を追い上げており、開発の加速が期待されている。
◆二足歩行で“進化”
「二本足で十分歩けるようにはなった。ただ、アシモが人間の10歳児と同じようになったかといわれたら、できていない」
本田技術研究所(埼玉県和光市)の広瀬真人主席研究員はこう話す。
ホンダがヒト型ロボットの開発に着手したのは1986年。四輪車・二輪車市場の成熟が予想される中、新たな基礎研究の対象としてロボットが挙がった。吉野浩行同研究所社長(当時)のもと、「家の中で人間をサポートするロボット」という、技術重視のホンダならではのコンセプトで開発が始まった。
二足歩行がほぼできるようになったのは90年代初頭。そこから小型化や無線化などを進め、2000年にアシモが誕生した。
その後は処理能力の進歩に合わせてアシモも“進化”。人が指差した場所に移動したり、登録された人の顔を認識して用件を言ったりできるようになった。現在は人を避けてすれ違ったり、トレーにコーヒーを乗せて指定の場所に配膳したりする実証実験に取り組んでいる。
ホンダは、小型で耐久性の高いエンジン制御部品をアシモに採用するなど、自動車メーカーの強みを生かしてきた。08年には二足歩行の研究をもとに、高齢者など脚力が低下した人をサポートする歩行アシスト装置を発表するなど成果も出てきた。
ただ、広瀬主席研究員は15年にはロボットが一家に1台になると話したこともあったが、「まだ時間がかかる。実用化の手応えはない」と打ち明ける。
一方のトヨタは01年、自動車の溶接などで蓄積した産業用ロボット技術をもとにロボットプロジェクトを立ち上げた。05年に名古屋市で開かれた愛知万博(愛・地球博)では楽器を演奏するヒト型ロボットを公開。07年には家事や介護・医療現場などで人間を支援する「パートナーロボット」の開発概要を発表し、10年代の早い段階の実用化を掲げた。車いす型ロボットでは病院で実証実験を始めるなど、サービス分野のロボット実用化はそこまできている。
◆「用途みえない」
ロボットの用途がサービス分野まで拡大すれば経済効果は大きい。経済産業省が今年4月に発表したロボットの将来市場予測(国内メーカー出荷額合計)によると、ホンダやトヨタなどが開発しているサービス分野のロボットの普及で15年には1兆5990億円、35年には9兆7080億円に拡大すると見込む。
産業用では日本メーカーは世界シェアの約7割を占めるとされる「ロボット大国」。経済発展が続く新興国ではロボットの稼働台数さえ少ない。みずほインベスターズ証券の石田雄一シニアアナリストは「中国などは省人化や自動化投資が遅れている。人件費が高騰する中で産業用ロボットの市場は拡大する」と予想、産業用については将来性を約束する。
しかし、介護などサービス分野向けはまだ機能開発段階。石田シニアアナリストも「ロボットが人間を抱えるだけでも現在の何倍もの重量が必要になる。技術や価格、安全性も課題で、ヒト型ロボットの用途はみえてこない」と話す。
これについて、ホンダは「人間にない機械ならではの能力を使わないと価値は出ない」(広瀬主席研究員)と、二足歩行の次の展開を模索。ネットワーク機能を備えた多機能携帯端末などと合わせた利用法も視野に入れている。
ヒト型ロボットについては韓国や中国なども政府のバックアップを受けて開発を強化。「日本が追い抜かれる可能性も出てきている」(大手メーカー)。
実用化に向けては、周辺技術と用途を組み合わせるなど開発の方向性を定めることが必要といえそうだ。(田村龍彦)
アシモ10歳 ホンダ苦心 ヒト型ロボ、実用へ開発分岐点!
2010.10.30 05:00
http://www.sankeibiz.jp/business/news/101030/bsc1010300500001-n1.htm
ホンダのヒト型ロボット「ASIMO(アシモ)」が二足歩行に成功してから、31日で10周年を迎える。この間、アシモは人の動きを理解する知能化技術などを備える一方、歩行アシスト装置などロボット開発からの副産物も生まれた。ただ、2015年を目指していた“実用化”にはまだ課題が多いようだ。ヒト型ロボットはトヨタ自動車なども開発を進めるが、韓国や中国も“ロボット大国・日本”を追い上げており、開発の加速が期待されている。
◆二足歩行で“進化”
「二本足で十分歩けるようにはなった。ただ、アシモが人間の10歳児と同じようになったかといわれたら、できていない」
本田技術研究所(埼玉県和光市)の広瀬真人主席研究員はこう話す。
ホンダがヒト型ロボットの開発に着手したのは1986年。四輪車・二輪車市場の成熟が予想される中、新たな基礎研究の対象としてロボットが挙がった。吉野浩行同研究所社長(当時)のもと、「家の中で人間をサポートするロボット」という、技術重視のホンダならではのコンセプトで開発が始まった。
二足歩行がほぼできるようになったのは90年代初頭。そこから小型化や無線化などを進め、2000年にアシモが誕生した。
その後は処理能力の進歩に合わせてアシモも“進化”。人が指差した場所に移動したり、登録された人の顔を認識して用件を言ったりできるようになった。現在は人を避けてすれ違ったり、トレーにコーヒーを乗せて指定の場所に配膳したりする実証実験に取り組んでいる。
ホンダは、小型で耐久性の高いエンジン制御部品をアシモに採用するなど、自動車メーカーの強みを生かしてきた。08年には二足歩行の研究をもとに、高齢者など脚力が低下した人をサポートする歩行アシスト装置を発表するなど成果も出てきた。
ただ、広瀬主席研究員は15年にはロボットが一家に1台になると話したこともあったが、「まだ時間がかかる。実用化の手応えはない」と打ち明ける。
一方のトヨタは01年、自動車の溶接などで蓄積した産業用ロボット技術をもとにロボットプロジェクトを立ち上げた。05年に名古屋市で開かれた愛知万博(愛・地球博)では楽器を演奏するヒト型ロボットを公開。07年には家事や介護・医療現場などで人間を支援する「パートナーロボット」の開発概要を発表し、10年代の早い段階の実用化を掲げた。車いす型ロボットでは病院で実証実験を始めるなど、サービス分野のロボット実用化はそこまできている。
◆「用途みえない」
ロボットの用途がサービス分野まで拡大すれば経済効果は大きい。経済産業省が今年4月に発表したロボットの将来市場予測(国内メーカー出荷額合計)によると、ホンダやトヨタなどが開発しているサービス分野のロボットの普及で15年には1兆5990億円、35年には9兆7080億円に拡大すると見込む。
産業用では日本メーカーは世界シェアの約7割を占めるとされる「ロボット大国」。経済発展が続く新興国ではロボットの稼働台数さえ少ない。みずほインベスターズ証券の石田雄一シニアアナリストは「中国などは省人化や自動化投資が遅れている。人件費が高騰する中で産業用ロボットの市場は拡大する」と予想、産業用については将来性を約束する。
しかし、介護などサービス分野向けはまだ機能開発段階。石田シニアアナリストも「ロボットが人間を抱えるだけでも現在の何倍もの重量が必要になる。技術や価格、安全性も課題で、ヒト型ロボットの用途はみえてこない」と話す。
これについて、ホンダは「人間にない機械ならではの能力を使わないと価値は出ない」(広瀬主席研究員)と、二足歩行の次の展開を模索。ネットワーク機能を備えた多機能携帯端末などと合わせた利用法も視野に入れている。
ヒト型ロボットについては韓国や中国なども政府のバックアップを受けて開発を強化。「日本が追い抜かれる可能性も出てきている」(大手メーカー)。
実用化に向けては、周辺技術と用途を組み合わせるなど開発の方向性を定めることが必要といえそうだ。(田村龍彦)













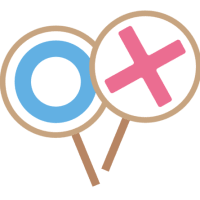






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます