
謎の建物とは・・・・・(Yahoo地図)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.62086667&lon=139.73971667&ac=13103&az=17.4.25.33&v=2&sc=3
三菱の建物と言えばビックリする事が多いのも事実です(田舎者ですから~)
品川駅から御殿山ガーデンに向かっていたら右手にとてつもない長い壁があり確か三菱のマークが門に付いていた記憶が・・・・・
あとは日本橋の横にある三菱倉庫の建物です。レンガ造りでカッコ良さが記憶に残っています・・・・・
丸の内は私からすると宇宙みたいな世界ですから~丸ビルに向かう時地下道は国道ではないですよね・・・・・
と言いたくなるほどの広さですから田舎者には心臓に悪い(笑)
企業グループ研究「三菱編」 坂本龍馬の海援隊が日本最初の株式会社?!
2011/05/09 16:00

日本で最初に設立された会社はどこでしょうか?
NHKの大河ドラマ「龍馬伝」を見た人は坂本龍馬が設立した亀山社中(1865年結成)で、その2年後、土佐藩の外郭機関として改称された「海援隊」だと答えるのではないでしょうか?確かに「海援隊」はその後、ドラマでは香川照之演じる岩崎彌太郎が引き継ぎ、九十九商会、三菱商会、郵便汽船三菱会社(後の日本郵船)、三菱商事へと発展させました。岩崎彌太郎は幕末から明治にかけての最大の実業家であり、海運業を軸として明治新政府の仕事を受注し、大きく発展しました。ちなみに今も三菱グループが使用している「スリーダイヤ」の三菱マークは土佐藩主山内家の三ツ柏紋と岩崎家の三階菱紋を合わせたものということです。
若者がつくった「株式会社」
しかし、「日本で最初の株式会社が海援隊だ」というには異論もあるようです。この論は経済学者の坂本藤良氏が最初に言い出したとのことですが、後に、小栗上野介の「兵庫商会」の方が早いと言っています。小栗上野介は徳川幕府の旗本で、1860年(万延元年)日米修好通商条約批准の遣米使節の一員として渡米、地球を一周して帰国。その後の八年間幕政を支えました。坂本氏は後に「取り消そうとしても坂本龍馬が有名で、海援隊に貼ったレッテルが私の手を離れて一人歩きしてしまった」と苦笑していたということです。
いずれにしろ、坂本龍馬、岩崎彌太郎、小栗上野介などなど、幕末、押し寄せる欧米列強の開国の圧力に対抗し、新しい日本をつくろうという気概をもった当時の若者によって「株式会社」が日本に誕生しました。
占領軍に寄って行われた財閥解体
ここで歴史は一気に、太平洋戦争の終戦(1945年)に飛びます。日本を占領した連合国総司令部(GHQ)は日本を戦争に導いた一因に財閥の存在があったということから「財閥解体」の方針を打ち出しました。1946年、三菱財閥の統括会社であった三菱本社は解散されられただけでなく、GHQの指令は三菱各社の社長や役員の追放にまで及びました。
ではそれほどまでに戦前の日本の産業界に影響を持っていた財閥とはどのようなものなのでしょうか?
三菱財閥と岩崎彌太郎
ウエキペディアによると財閥とは「家族または同族によって出資された親会社(持ち株会社)が中核となり、支配している子会社にさまざまな産業を経営させている企業集団であり、大規模な子会社はそれぞれの分野で寡占的な地位を占める」となっています。
日本では三菱(岩崎家)以外に三井(三井家)、住友(住友家)、安田(安田家)などがあり、三井、三菱、住友は三大財閥と呼ばれています。
ここで歴史を戻します。三菱財閥創業者の岩崎彌太郎は明治維新後、次々と事業の多角化を図ります。鉱山の買収による鉱業への進出(三菱鉱山、現・三菱マテリアル)や官営長崎造船所を借り受けて進めた造船業(三菱造船、現・三菱重工業)のほか、損害保険(東京海上日動火災保険)、生命保険(明治安田生命保険)、銀行業(三菱為替店、現・三菱東京UFJ銀行)などが彌太郎の時代に設立されました。
「技術の三菱」をつくった四代目・岩崎小彌太
岩崎彌太郎は明治18年(1985年)50歳で病死し、その跡は弟の岩崎彌之助が2代目総帥として引き継ぎます。彌之助は事業の多角化を進め、1980年、陸軍省の用地であった丸の内のほか、神田三崎町練兵場の土地の払い下げを受けて、丸の内ビジネスセンターのもととなるいわゆる“三菱村”を建設しました。三菱地所は1906年に三菱合資会社に置かれた地所用度課が発展したものです。
三代目の岩崎久彌は彌太郎の長男で、明治26年(1893年)から大正5年までの20年間に総務、鉱山、炭坑、造船、銀行、営業、地所の各部を置き、現在の事業部制を置き、経営の合理化を図りました。神戸製紙所(現・三菱製紙)、麒麟麦酒、旭硝子などが創業されたのもこの時期です。
三菱財閥四代目の岩崎小彌太は彌之助の長男で、彌太郎から小彌太まで、長男、弟、息子、甥と初代から四代までトラブルなく家業を継承したことが、三菱財閥最大の成功の要因と言えます。
小彌太は大正5年(1916年)から昭和20年(1945年)のGHQによる財閥解体まで三菱の全事業を統括し、事業をさらに拡張させました。三菱重工業は太平洋戦争における日本軍の名機“零戦”の開発元として知られます。また、三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)、日本光学工業(現・ニコン)、三菱ガス化学、三菱電機、三菱石油(現・JXホールディングス)、新興人絹(現・三菱レイヨン)、日本タール工業(現・三菱化学)、三菱化工機、三菱製鋼などが小彌太の時代に設立されました。こうした大正から昭和にかけて日本産業の重化学工業化を中心となって推進した三菱財閥は「技術の三菱」と呼ばれました。
(ライター 丸山隆平)












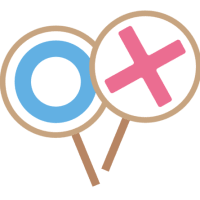






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます