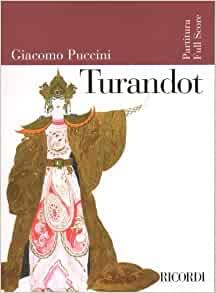歌手、合唱、演出、オーケストラすべてが最初から最後まで完璧で、奇跡的な上演だった。不安定な天候のせいで体調が今一つだったこの日、パルジファル全幕を最後まで観られるかどうか不安もあったが、歌と音楽と演劇に全細胞を癒され、涙し、浄化されてホールを後にした。この酷い現実に平気なふりをして生きていかなければならない現代人は、すべて今回の『パルジファル』を観るべきだと思う。
亞門さんの最近のオペラ演出では定番の、登場人物の分身としての黙役が登場し、パルジファルの(さらに若い)少年時代を演じる子役がたくさんのことを演じる。7/13のパルジファルは福井敬さんで、福井さんも10代の少年のように若く見えた。ワーグナーを歌うとは、威嚇的に張り上げて歌うことではなく、演劇的な内容をともなった歌唱を聴かせることだと福井さんからまたしても学ぶ。美術館を思わせる装置、たくさんのキリストやマグダラのマリアの絵画、類人猿の大きな標本など、最初は「これらは何を示しているの?」と違和感があったものの、すぐに心が納得した。パルジファルは、どこかの秘密結社のやばいオペラなんかではない。頭で理解しようとすればするほど、本筋から外れる。心で感じるべき楽劇なのだと思った。
アムフォルタス黒田博さんは、10年前の二期会の上演でも同役で、10年前にもこんな痛々しい「存在」がオペラの世界にはあるのかと驚愕したが、亞門演出ではいよいよ殉教者かいまわの際の重病人のようで、元々美しい面立ちの方なので、本物のキリストのように見えた。先日の「フィルスタッフ」はヴェルディの最後の作だが、「パルジファル」はワーグナーの最後の作。想像界の最終的な姿を演じることが出来るすごい歌手であり役者であると再認識した。そこにいるだけで、深い。歌手としての器が果てしなく大きいのだ。
クンドリ田崎尚美さんは、こんなに美しいクンドリがいるのだろうかと世界中の歌劇場に自慢したくなるような輝かしさで、重く沈痛な役を観たことのない妖艶な姿で歌った。以前演じられたゼンタやエリーザベトの面影をクンドリに投影してしまうという、不思議な見方をしてしまったが、田崎さんがクンドリを演じることは、運命にセットされていたことだと思う。ものすごく「選ばれて」舞台の上にいた。クンドリという存在は謎であり、自然霊の一部のようでもあり、クリングゾルの傀儡として登場するが、アムフォルタスの分身のようでもある。
クンドリがパルジファルに母を思い出せつつ、誘惑に失敗する場面は、観ていてかつてないほど滂沱の涙に溢れた。「お前に逃げ道はない。すべての道を封じてやる」というクンドリの歌詞が、呪詛というより自己崩壊すれすれの嘆きに聴こえたのは衝撃的だった。
現代の子供のようなパルジファルの姿と、タロットカードの図案のような古代の人々との装束が不思議と自然に共存していた。
3幕はもう、目を開けていることが出来なかった。荒地のような姿で現れたパルジファルの足をクンドリが洗う。アロマの精油を垂らすような仕草。歌手のマドンナが「本名のミドルネームのヴェロニクは、キリストの足を洗った女性の名前」と語っていたことを思い出した。救世主として選ばれたパルジファルの背後には、ゴリラがいる。黙ってゴリラがそこにいるだけで、涙腺が決壊した。何が嘘で何が茶番なのか、ゴリラがすべてを語っていて、このゴリラは天に指をさして洗礼者ヨハネのポーズまでとる。着ぐるみの中の人にお礼を言いたくなった。
クンドリは宙に浮かんで消えていくのだが、この場面は演出の離れ業で、ワーグナーのスコアをただ崇拝しているだけでは出てこない。
亞門さんは、ワーグナーを友達のように感じ、生きてオペラに関係している人たちの痛みや苦しみと、ワーグナーの生きた苦しみをつなげてループにする。オペラは人間の痛みで、愛の痛みで、その傷口を押し広げることで価値が生まれる。演出の正解とは、自分の愛を信じることにのみよって出せるものではないのだろうか。知識や知恵の力比べを超えて、巨大な愛は立ち現れる。
福井さん、田崎さん、黒田さん、全員が「これは果たして演じているということなのだろうか」と思えるほど、破壊的で衝撃的な歌声を聴かせる箇所があり、それぞれが抱えている人生の痛みのようなものを感じた。自分は奇跡を見ているのだ。大きく映し出される地球の映像に飲み込まれるように、彼らと同じ星にいる一体感に包まれた。
ワーグナーの音楽が、これほどまでに魅力的であることも驚きで、一秒一秒の響きに溺れそうなほど陶酔的だった。
ヴァイグレと読響は、夏至の前に二回の素晴らしいコンサートを聴かせ、ドヴォルザークの『交響曲第8番』の最終楽章では、愛のような恋のような祝福の響きに「夏の夜の夢のようだ」と思わずにはいられなかった。歌劇場のマスターであるヴァイグレは、自分の評価や建前なんかどうでもいい、オペラとシンフォニーの愛を伝えることこそが指揮者の使命だと知っている。
パルジファルが宇宙的な愛のオペラであり、未来に向かって開かれている物語だと知った貴重な初日だった。
グルネマンツ役の加藤宏隆さんの実力を改めて知る上演でもあった。バス・バリトンでいくつもの上演を拝見してきたが、貴重な屋台骨であり、根強い存在感がある。『パルジファル』の濃い登場人物の中で、渋い優しさを発揮されていて、初日組のアンサンブルを完璧なものにしていたと思う。16日にも同キャストで公演が行われる。