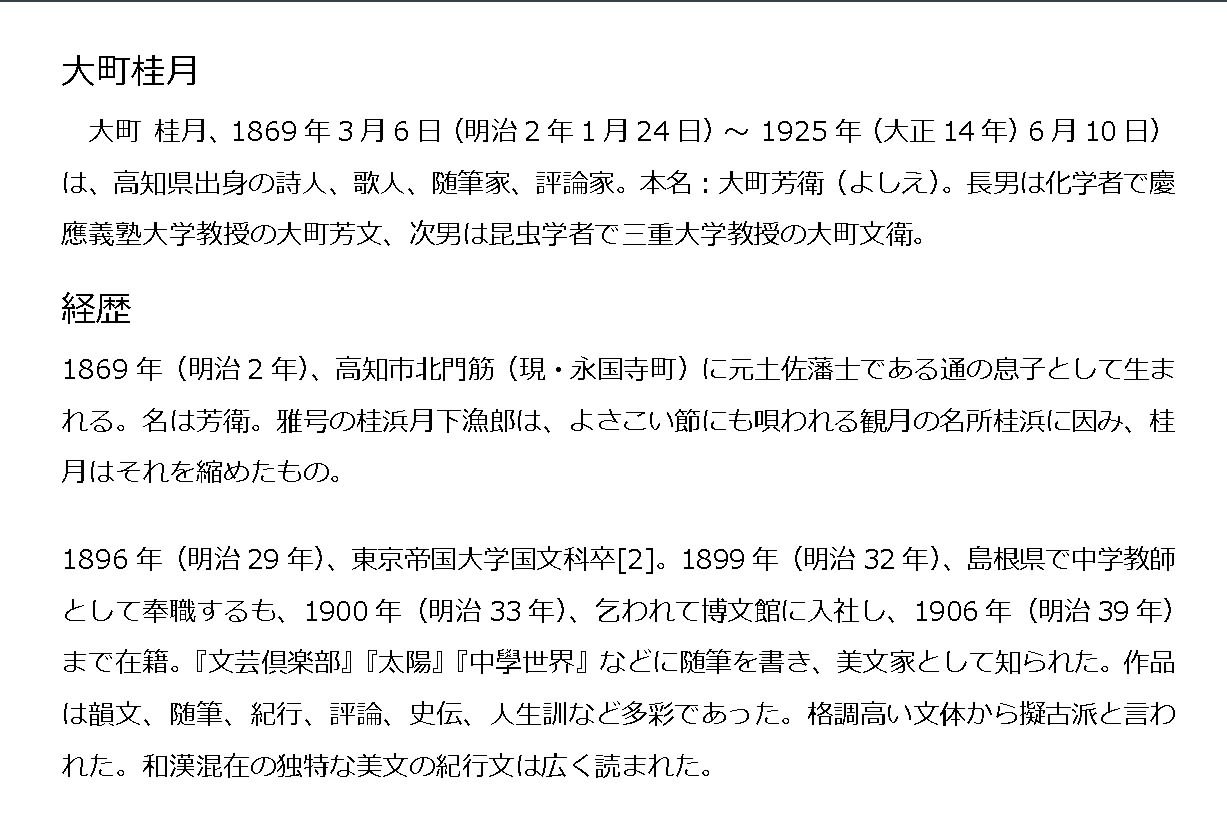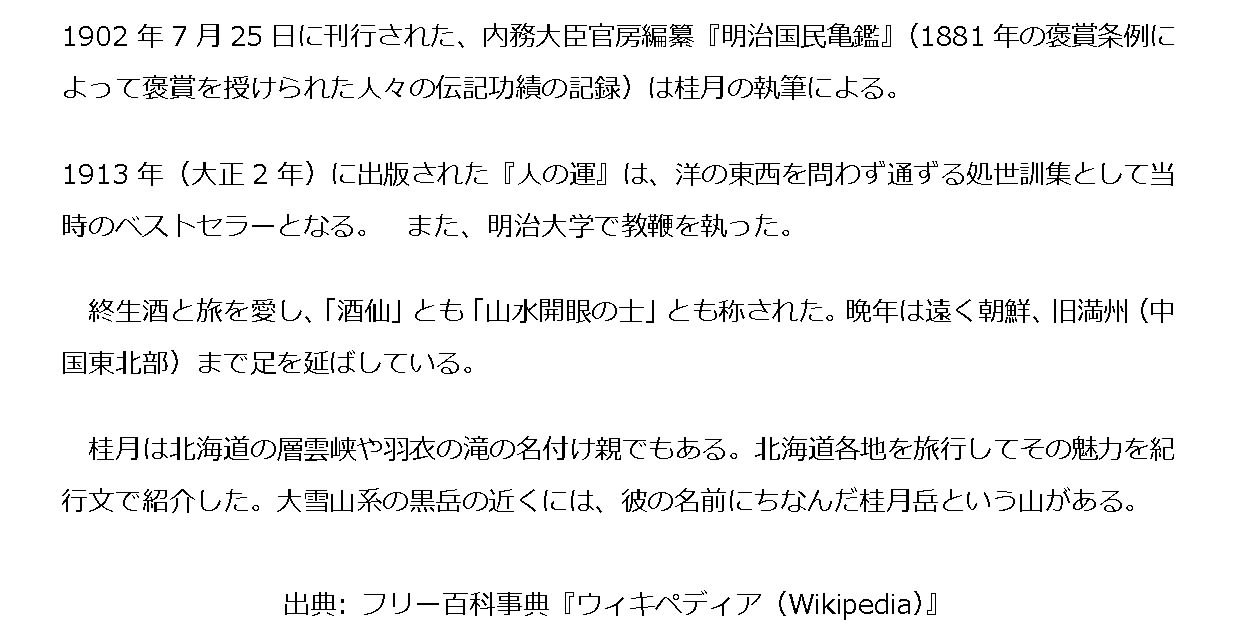秋の筑波山
大町桂月
一 関城の趾
東京の人士、若し土曜日より泊りがけにて山に上らむとならば、余は先づ筑波登山を提出せむとする也。
上野より水戸線に由りて、土浦まで汽車にて二時間半、土浦より北条まで四里、馬車にて二時間、北条より筑波町まで一里、徒歩して一時間、都合六時間以内の行程、これ東京よりの順路なるが、上野発が午後二時二十分なれば、途中にて日が暮るべし。山に上らうといふ者は、それくらゐの事は辛捧せざるべからず。

筑波山麓より筑波町まで、ほんの五六町の坂路也。筑波町に着きさへすれば、旅館四つ五つあり。その夜一泊して、翌朝山に上るべし。往復五時間あれば十分也。筑波町にて午食して、昨日の路を帰るとすれば、土浦まで歩きても、その日の中には、東京に帰らるゝ也。
ことしの九月二十四日と二十五日と、休日が二日つゞきければ、三児を伴ひ、桃葉をあはせて同行五人、上野より日光線に由り、小山にて乗りかへて下館に下る。下館より筑波町まで五里、大島までは馬車通ず。
されど、我等は下妻さして行くこと二里、梶内より右折して関城の趾を探り、若柳、中上野、東石田、沼田を経て、一時間ばかりは闇中を歩きて、筑波町に宿りぬ。全二日の行程なれば、筑波登山の外、関城趾の覧古を兼ねたる也。

日本歴史に趣味を有する者は、何人も北畠親房の関城書といふ者を知れるなるべし。其書、群書類従の中に収めらる。これ当年親房が結城親朝に与へたる手紙をひとまとめにしたるもの也。
親房は言ふまでもなく、南朝の柱石也。親朝も、もとは南朝の忠臣なりき。其父宗広は建武中興に与つて大いに功ありて、勤王に始終したりき。親朝父と共に王事につくしたり。宗広死するに臨みて、必ず賊を滅せよとさへ遺言したり。
親房の子顕家、鎮守府将軍となりて陸奥に至りし時、親朝は評定衆、兼引付頭人となりて国政に参与したり。後に下野守護となり、大蔵権大輔となり、従四位を授けられ、修理権太夫にまでも進めり。
思ふに関東の一大豪族、武略と共に材能もありて、当時有数の人材也。然るに、南風競はず、北朝の勢、益々隆んなるに及び、父の遺言を反古にし、半生の忠節に泥を塗りて、終に賊に附したり。
関城書は、親房が関城に孤立せし際、親朝がまだ形勢を観望せるに当り、大義を説きて、その心を飜へさむとせしもの也。辞意痛切、所謂懦夫を起たしむるの概あり。然れども、親朝の腐れたる心には、馬耳に東風、城陥りて、親房の雄志終に伸びず。名文空しく万古に存す。
当年の関城主は誰ぞや。関宗祐、宗政父子也。延元三年(1338年)、親房は宗良親王を奉じて東下せしに、颶風に遭ひて、一行の船四散し、親房は常陸に漂着し、ひと先づ小田城に入る。然るに城主小田治久賊に心を寄せければ、関城に移れり。宗祐は無二の忠臣也。親房を奉じて忠節を尽せり。
当時、関東は幾んどすべて賊に附して、結城親朝さへ心を飜しぬ。唯々宗祐の関城を根拠として、伊佐城主の伊達行親、真壁城主の真壁幹重、大宝城主の下妻政泰、駒城主の中御門実寛だけが南朝に属せしが、興国四年(1343年)十一月、高師冬大挙して来り攻むるに及び、大宝城陥りて政泰討死し、関城も陥りて宗祐父子討死し、親房は吉野に走れり。これより関東全く北朝に帰するに至りぬ。
大宝沼の北端、三方水に囲まれたる丘上は、これ関城の趾也。沼に臨みて宗祐父子の墓あり。関城の碑も立てり。大宝沼は城趾の両側を挟さんで、遠く南に延び、その尽くる処を知らず、東の方二三里を隔てて、筑波の積翠を天半に仰ぐ。風光の美、既に人をして去る能はざらしむるに、忠魂長く留まれる処、山河更に威霊を添ふるを覚ゆ。茫々五百年、恩讐両つながら存せず。苦節ひとり万古にかをる。明治の世になりて、宗祐は正四位を贈られ、宗政は従四位を贈らる。地下の枯骨、茲に聖恩に沽へる也。
二 筑波登山
路傍の草中に、蛙の悲鳴するを聞く。蛇が蛙を呑み居るならん。助けてやれとて、石をなぐれば、蛙をくはへたる蛇あらはれて逃げゆく。木の枝を折り取りて蛇を打てば、蛇弱りて、蛙飛び去る。今一打を蛇の頭上に加ふれば、頭つぶれて死す。子供ども、快哉と呼ぶ。
日暮れたる後、また蛙の悲鳴を聞く。小石を二つ三つなぐれど、なほ悲鳴を聞く。大なる石をなげつくれば、悲鳴は聞えずなりぬ。蛇死して蛙のがれたるか、蛇蛙共に死したるか、それとも蛇命を全うして蛙を呑み了りたるか、闇中の事なれば、知るに由なし。これ筑波の途上、親子が興じあひたるいたづら也。
沼田村より山路にさしかゝる。林間の一路、闇さは闇し、家は無し。十六をかしらに、末の子が十一、何も見えざるに、足の疲れを覚えけむ、筑波町はまだですか、まだですか。もうぢきだ、ぢきだ、男だ。辛捧せよと呼びかはして行く程に、灯光路に当る。
これが筑波町かと思ひの外、山中の一軒家也。まだ何町あるかと聞けば、もう二三町也。この闇きに、提灯なきは危し。提灯つけて送らせんといふ。田舎にうれしきは、人の深切也。それには及ばずと断りて、なほ闇をさぐり、筑波町に達して宿りぬ。
〔参考〕筑波山の奇岩を巡るコース 女体山から白雲橋へ
〔参考〕男体山を登る
筑波に遊ぶこと、これで三度目也。在来の書物には、筑波町より頂上まで一里卅二町とあれどこの頃新しく処々に立てられたる木標の示す所によれば、男体山まで廿一町廿三間、男体山より女体山まで八町、女体山より廿五町半、往復都合凡そ五十五町也。それを朝七時に宿を出て、十二時に戻り来りぬ。
茶店の路を要するもの、男体の途に三つ、女体の途に二つ、頂上に三つ。下からわざわざ上つて来て居ります。やすんでいらつしやれと強ひられて、素通りも出来ず。一軒に五分づゝ休むとしても、都合四十分かゝる。蘭を採つたり、つくばねの実を採つたり、山毛欅茸を採つたり、路草くふことも多かりしかば、斯く五時間も長くかゝりたる也。

男体山へ上る途の名所は、小町桜と、水無川の、水源と也。小町桜のある処は、むかし日本武尊の休憩あらせられし処と称す。水無川は、百人一首にある陽成院の『筑波根の峯より落つる水無川恋ぞつもりて淵となりぬる』にて、有名なるもの也。
女体の途の名所には、弁慶七戻あり、一種の石門也。上に横はれる大石、落ちんとして落ちず、さすがの弁慶も、過ぐるをはゞかりたりとは、とんだ引合に出されたるもの也。


頂上には、男体女体の二尖峯相並びて突起し、南に離れて連歌岳あり、東につらなりて宝珠岳あり。なほ女体よりの下り路に、北斗石、紫雲石、高天原、側面大黒石、背面大黒石、出船入船などの奇巌、峯上に突起す。就中女体峯頭が最も高く、且つ眺望最もすぐれたれど、この日は濃霧濛々として眺望少しも開けざりき。

男体山には伊弉諾尊を祀り、女体山には伊弉冊尊を祀る。其外、頂上に摂社頗る多し。男体の一角に測候所あり。これ明治三十五年に故山階宮菊磨王殿下の設立し給へる所、筑波山新たに光彩を添へぬ。然るに、殿下今や亡し。測候所は文部省が引継げりと聞く。金枝玉葉の御身を以て、斯かる山上に測候所を設立し給ひし御志の程、世にも尊く仰がるゝ哉。殿下御在世の時、同妃殿下、登山せさせ給ひて、
三 小田城と太田三楽
筑波山は山しげ山しげけれど
思ひ入るにはさはらざりけり
思ひ入るにはさはらざりけり
げに、古より樹木しげかりけむ。筑波山の高さは僅に三千尺ぐらゐなれど、関東平野の中に孤立せるを以て、関東にては、何処からも見ゆ。随つて、筑波山上よりは、関東を残らず見渡すを得べし。
関城趾方面よりは、男体のみが見えて、女体は見えず。右に豊凶山をひかへ、左に葦穂、加波、雨引の三山をひかへて、勢、秀抜也。

これ側面観なるが、正面より、即ち山麓の臼井村より見れば、男体女体の双峯天を刺して満山鬱蒼たり。春日山や、嵐山や、東山や、近畿には鬱蒼たる山多けれども、関東の山には樹木少なし。唯々筑波山のみは樹木鬱蒼として、関東の単調を破る。

午後一時、筑波町を発足して帰路に就く。北条まで歩きて馬車に乗る。小田村の路傍、「これより南三町小田城趾」としるせる木標の立てるを見る。これ当年北畠親房が一時たてこもりたる処也。然るに城主小田治久は勢を見て北朝に附しぬ。瓜のつるに茄子はならず。祖先が祖先なれば、子孫も子孫、この小田氏は戦国時代になりても、勢を見て北条氏に附しぬ。されど、本城は太田三楽に取られたり。
太田三楽は、太田道灌の曾孫也。智仁勇を兼ねたる名将として鳴りとゞろきたる英雄なるが、其一生は失敗の歴史也。豊臣秀吉小田原征伐の際、徳川家康に謂つて曰く、関東に二つの不思議あり。卿之を知れりや。曰く、其一は太田三楽ならむ。曰く、然り。曰く、今一つは思ひうかばず。曰く、矢張り太田三楽也。我等の如き者でも、天下を取れるに、三楽の如き人が一国も取り得ざるが不思議なる也と。

三楽は非凡の英雄也。故に秀吉も家康も期せずして、これを関東の一不思議としたり。宇佐美定行も言へり、当代、主君と仰ぐに足るべき人は、わが謙信公の外に唯々三楽あるのみと。斯かる英雄が一国も取り得ざるは、不思議と云へば不思議なれども、実は不思議に非ず。三楽が若しも小田氏の如く勢に附したらば、失敗はせざりしならむ。
三楽は
 骨を有す。成敗以外に、巍然として男子の意気地を貫きたり。成敗を以て英雄を論ずべからずとは、三楽の事也。滅亡に瀕せる上杉氏を助けて、旭日の勢ある北条氏に抗したり。安房の里見義弘と結びたるも、鴻の台の一戦に大敗したり。越後の上杉謙信を頼みたるも、謙信は関東に全力を注ぐ能はざりき。
骨を有す。成敗以外に、巍然として男子の意気地を貫きたり。成敗を以て英雄を論ずべからずとは、三楽の事也。滅亡に瀕せる上杉氏を助けて、旭日の勢ある北条氏に抗したり。安房の里見義弘と結びたるも、鴻の台の一戦に大敗したり。越後の上杉謙信を頼みたるも、謙信は関東に全力を注ぐ能はざりき。失敗又失敗、本城の岩槻さへ取られ、はる/″\常陸まで落ちゆきて佐竹義宣をたより、片野に老後の身を寄せたり。然れども、雄志毫も衰へず。老武者の英姿は、いつも筑波山下に躍動したりき。

父の小田天庵、藤沢に居り、子の守治、小田に居る。三楽は程近き片野に在りて日夜工夫をこらせど、如何せむ。敵の城はかたく、我兵は少なし。唯々小田天庵は毎年大晦日に、年忘とて連歌の会を催し、酒宴暁に至るを定例とせり。三楽之を聞き知りて、乗ずべきは此時なりと勇みぬ。されど、手兵のみにては不足也。茲に真壁掃部助と言ひあはせて、一の窮策を案じ出だせり。
小田の重臣に内応するものあり、乗ずべしとて、佐竹方や多賀方の豪傑どもを招き、その内応の手紙さへ示したるに、豪傑ども、三楽に加勢することを諾す。然るに愈々小田城に押しよせて見れば、一向内応の模様なし。諸将こは如何にと怪しめば、実は内応ありたるに非ず。手紙も、にせ手紙也。唯々連歌の酒宴ある夜なれば、内応にもまして都合よし。願はくは一臂の力をかされよといふ。これも一理あり。
今更ぐず/\言ひても仕方なしとて、一呼して城を抜きたり。その後、天庵は一度小田城をとりかへしたるが、再び三楽に取られたり。かゝる程に、大敵外よりあらはれ、北条氏は秀吉の為に亡ぼされたり。
かくて、三楽の宿志は、思ひがけずも、秀吉によりて達せられたるが、三楽其人は、あくまでも不運の英雄なりき。
北条氏滅亡の後、間もなく病死して、英魂むなしく筑波山下に眠る。
〔参考記事〕
鉄砲の伝来と普及 小田氏治、大田勢の鉄砲に驚き小田城の奪還ならず没落
つくば市の「小田城」、落城と奪還を繰り返した防御上の弱点は何か