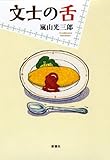○大澤真幸『「正義」を考える:生きづらさと向き合う社会学』(NHK出版新書) NHK出版 2011.1
 本書は単独で読んでも十分面白いし、マイケル・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』の註解として読んでもいい。特にサンデルの著書が、なんとなく腑に落ちなかったという読者にはおすすめだと思う。
本書は単独で読んでも十分面白いし、マイケル・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』の註解として読んでもいい。特にサンデルの著書が、なんとなく腑に落ちなかったという読者にはおすすめだと思う。
冒頭には角田光代の小説『八日目の蝉』が紹介されている。八日目の蝉とは「なくてもいいはずの人生」の比喩だ。この小説が共感を読んだのは、現代人の多くが、自分の人生を、何のためにあるのか分からない時間(物語化されない人生)と考えているからではないか。このような問題認識を確認して、あるべき社会構想の検討に進む。
以下、しばらくはサンデルの著書と同様に、古典的な政治哲学の検討が続く。最初は功利主義。しかし、功利主義は、常に一定の犠牲を必要とする。「最大多数の最大幸福」は絶対に成り立たず、「一定数の最大幸福」か「最大多数の一定幸福」に譲歩せざるを得ない。これに対して、幸福を道徳の規準とせず、自由を正義の普遍的条件とするのがリベラリズム。代表者はカント。しかし、普遍性を徹底すると、友人も殺人鬼も同等に扱わなければならなくなる(そうそう、この点についてサンデルの弁護は詭弁だよなあ)。
次に登場するのがコミュニタリアン(共同体主義者)。著者によれば、サンデルはコミュニタリアンの立場に立つ政治哲学者なのだそうだ。ああ、なるほど。コミュニタリアンは、与件としての共同体こそが正義の条件であると考える。たまたま日本に生まれたからには、日本人として果たすべき義務と責任があると考えるのだ。しかし、これには、(1)他の共同体を批判する根拠が一切なく相対主義に陥る、(2)「われわれ」と「他者」の境界線が論理的でない、(3)共同体における物語の困難を克服できない、等の欠陥がある。
ここで著者は、コミュニタリアンの助っ人、アリストテレスを参照する。しかし、うまくいかない。なぜなら、アリストテレスは、「資本」という現象が登場する以前の社会システムを前提にしているからだ。ここから、サンデルの著書をぐいと踏み出して、著者の独創的な思索が展開する。西欧における資本主義の成立過程を政治哲学的に解釈するもので、むちゃむちゃ面白い。ホッブズが「リヴァイアサン」で描いた社会のモデルは、清教徒革命以降の共和制的な社会なのではないか、とか、中国では反資本主義運動であった文化大革命が、伝統を打破することによって、資本主義的なイノヴェーションを可能にした(スラヴォイ・ジジェクの説)とか、やたらと刺激的な指摘が続く。
さて、前章の興奮を鎮めるように、著者は意外な人物について短く語る。――イエスである。イエスはコミュニタリアンではないが、リベラリストでもない。では、イエスの原理とはいったい何か。
再び、現代社会を特徴づける「資本主義」についての考察。高度化した資本主義社会において労働者は二極化し、研究開発や情報操作などの知的労働に携わる少数の人々は、多文化主義に接近する。対して、多数の周辺労働者は、宗教的原理主義やエスノナショナリズム(ネット右翼)に近づく。しかし、両者は、同じ空虚(普遍性)を取り戻したいという身振りなのではないだろうか。
では、失われた普遍性はどうすれば取り戻せるか。著者の答えはこうだ。共同体において「何者でもない」と否定されることを介して、われわれは連帯することができるのではないか。回答の注釈として、もう一度参照されるのがイエスであり(放蕩息子の帰還、ブドウ園の主人)、エイミー・ベンダーの寓話的な小説『癒す人』である。この小説はいいな。傷を負うことで癒される、傷を通じて、狭い共同体の外への回路が開かれる寓話、とだけ述べておこう。
私はふと、むかし読んだプラトンの『国家』を思い出した。作中人物のソクラテスは、さまざまな立場の最高善を掲げるソフィストたちを、次々に論破しまくる(サンデル教授みたいに)。ところが、「何が最高善なのか」という最後の問いに対しては「ひとつの物語をしよう」と言って、突如、子どものような寓話を語り始めるのだ。でも、私はこの美しい寓話(エルの物語)が好きだった。曖昧な回答と言うなかれ。明晰な論理、議論は大切である。でも「生きる」ことの最後の真実(それは「正義」よりも重いものだ)は、寓話によってしか語れないのではないかと思う。
 本書は単独で読んでも十分面白いし、マイケル・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』の註解として読んでもいい。特にサンデルの著書が、なんとなく腑に落ちなかったという読者にはおすすめだと思う。
本書は単独で読んでも十分面白いし、マイケル・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』の註解として読んでもいい。特にサンデルの著書が、なんとなく腑に落ちなかったという読者にはおすすめだと思う。冒頭には角田光代の小説『八日目の蝉』が紹介されている。八日目の蝉とは「なくてもいいはずの人生」の比喩だ。この小説が共感を読んだのは、現代人の多くが、自分の人生を、何のためにあるのか分からない時間(物語化されない人生)と考えているからではないか。このような問題認識を確認して、あるべき社会構想の検討に進む。
以下、しばらくはサンデルの著書と同様に、古典的な政治哲学の検討が続く。最初は功利主義。しかし、功利主義は、常に一定の犠牲を必要とする。「最大多数の最大幸福」は絶対に成り立たず、「一定数の最大幸福」か「最大多数の一定幸福」に譲歩せざるを得ない。これに対して、幸福を道徳の規準とせず、自由を正義の普遍的条件とするのがリベラリズム。代表者はカント。しかし、普遍性を徹底すると、友人も殺人鬼も同等に扱わなければならなくなる(そうそう、この点についてサンデルの弁護は詭弁だよなあ)。
次に登場するのがコミュニタリアン(共同体主義者)。著者によれば、サンデルはコミュニタリアンの立場に立つ政治哲学者なのだそうだ。ああ、なるほど。コミュニタリアンは、与件としての共同体こそが正義の条件であると考える。たまたま日本に生まれたからには、日本人として果たすべき義務と責任があると考えるのだ。しかし、これには、(1)他の共同体を批判する根拠が一切なく相対主義に陥る、(2)「われわれ」と「他者」の境界線が論理的でない、(3)共同体における物語の困難を克服できない、等の欠陥がある。
ここで著者は、コミュニタリアンの助っ人、アリストテレスを参照する。しかし、うまくいかない。なぜなら、アリストテレスは、「資本」という現象が登場する以前の社会システムを前提にしているからだ。ここから、サンデルの著書をぐいと踏み出して、著者の独創的な思索が展開する。西欧における資本主義の成立過程を政治哲学的に解釈するもので、むちゃむちゃ面白い。ホッブズが「リヴァイアサン」で描いた社会のモデルは、清教徒革命以降の共和制的な社会なのではないか、とか、中国では反資本主義運動であった文化大革命が、伝統を打破することによって、資本主義的なイノヴェーションを可能にした(スラヴォイ・ジジェクの説)とか、やたらと刺激的な指摘が続く。
さて、前章の興奮を鎮めるように、著者は意外な人物について短く語る。――イエスである。イエスはコミュニタリアンではないが、リベラリストでもない。では、イエスの原理とはいったい何か。
再び、現代社会を特徴づける「資本主義」についての考察。高度化した資本主義社会において労働者は二極化し、研究開発や情報操作などの知的労働に携わる少数の人々は、多文化主義に接近する。対して、多数の周辺労働者は、宗教的原理主義やエスノナショナリズム(ネット右翼)に近づく。しかし、両者は、同じ空虚(普遍性)を取り戻したいという身振りなのではないだろうか。
では、失われた普遍性はどうすれば取り戻せるか。著者の答えはこうだ。共同体において「何者でもない」と否定されることを介して、われわれは連帯することができるのではないか。回答の注釈として、もう一度参照されるのがイエスであり(放蕩息子の帰還、ブドウ園の主人)、エイミー・ベンダーの寓話的な小説『癒す人』である。この小説はいいな。傷を負うことで癒される、傷を通じて、狭い共同体の外への回路が開かれる寓話、とだけ述べておこう。
私はふと、むかし読んだプラトンの『国家』を思い出した。作中人物のソクラテスは、さまざまな立場の最高善を掲げるソフィストたちを、次々に論破しまくる(サンデル教授みたいに)。ところが、「何が最高善なのか」という最後の問いに対しては「ひとつの物語をしよう」と言って、突如、子どものような寓話を語り始めるのだ。でも、私はこの美しい寓話(エルの物語)が好きだった。曖昧な回答と言うなかれ。明晰な論理、議論は大切である。でも「生きる」ことの最後の真実(それは「正義」よりも重いものだ)は、寓話によってしか語れないのではないかと思う。