
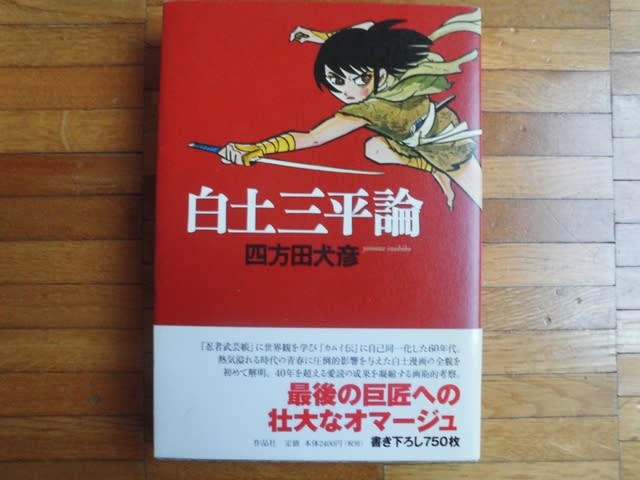

-------------------------------
昔勤めていた会社に、バンドをやっているパートの女の子が居た。その子が、或るライブハウスが、火事になったと言う。「なんで?漏電?」と訊いたら、キッス(知らない人はゴメンなさい。口から火を吐いたりするパフォーマンスをするハードロックバンドです)みたいに火を吐いたら燃え移って火事に成ったと言う。
処でライブハウスは60年代に出来た。はじまりはジャズ喫茶だった。「ライブハウスという言葉は和製英語だ。その意味は1977年に紹介されているが、ライブハウスという言葉の誕生は70年代前半まで遡る。当然のことながら、ライブハウスという言葉が誕生する以前からも、現在のライブハウスと同様に機能する空間は存在していた。50年代のロカビリー・ブーム、そして60年代半ばのグループ・サウンズのブームではジャズ喫茶がライブシーンの拠点となり、芸能システムに組み込まれたメイン・ストリームに位置していた。
1950年代から60年代にかけて、メイン・ストリームのライブシーンを牽引したのはジャズ喫茶だった。その一方で、60年代後半にはオルタナティブのライブシーンが芽生え始めていた。文字どおりのライブハウスが誕生したのは70年代半ばだが、その起源は、60年代後半のカウンターカルチャーという時代の空気のなかで誕生したロック喫茶にみることができる。
1969年にライブハウスの「BYG」ができる。渋谷では初めての本格的なライブハウスで、それまでジャズ喫茶やディスコで演奏していたアーティストが集って来た。1階がレストラン、2階がジャズとロックのレコード喫茶、地下がライブスペースという構成になっていた。
70年代は中野-高円寺ー吉祥寺の中央線沿線の若者文化だった。
1970年代はライブハウスという新たな実演の「場」が数多く設置された時期でもあった。それはあくまで、先行していたジャズ、ロック、フォーク、ブルース喫茶という音楽ファン対象のコミュニティ装置の延長線と考えられる・・・・
東京では中央線を中心に何軒かのライブハウスができた。74年11月に「荻窪ロフト」、同年、吉祥寺に「曼荼羅」、そして高円寺に「JIROKICHI」、その1年後に渋谷「屋根裏」が出現することになる。75年発行の『コンサート・ガイド』(のち『シティーロード』)には、何とこの1年で東京に二十数店ものロックやブルース。フォークのライブを見ることができる空間(ホールを含め)が出現したとある。この時期を始めとして、規模は小さいが流行にめざとい芸能音楽事務所や楽器メーカー、電気事業会社、レコード会社がテスト・ケースとしてライブハウス経営(ライブハウスと言う定義もない時代であったが)に参入し始めた。新宿には「クレイジー・ホース」「開拓地」ができ、小沢音楽事務所が「新宿ルイード」を発信させる。高田馬場には「PEOPLE」、三ノ輪には「モンド」がそれぞれあった。渡辺プロダクションが興した「銀座メイツ」も日劇ウエスタンカーニバル風にキャンディーズや天地真理、中尾ミエなどを登場させた。
70年代東京のライブハウス事情にも大きな変化が出てきた。まず75年12月に出来たパチンコ屋の上階にある「渋谷屋根裏」のライブ・スケジュールが強力になっていく(シティ・ポップス全盛の時代ですら「屋根裏」はパンクのライブをやっていた)。「新宿ルイード」(小沢音楽事務所)も芸能界絡みのブッキングとは言え田中俊博と言うメジャー・ロックのスペシャリストが入り、歌謡曲路線からロック系にシフトしつつあり、シャネルズ、佐野元春、白井貴子、山下久美子などパワフルな布陣を揃えてきた。「曼荼羅」は浦和から吉祥寺に移転してきたギンギンのロックをやり始めた。高円寺「JIROKICHI」もロフトのスケジュールを意識し、素晴らしいブルースのスケジュールを組むようになった。また、「渋谷エピキュラス」を始め、新宿厚生年金会館、郵便貯金ホール、日比谷野外音楽堂はロック野外イベントの聖地となり、大型ロック・コンサートが開催できる様にも成ったのだ。
さらに、ロック・シーンに大きな影響を残した「ツバキハウス」もディスコのさきがけとして新宿に店を構える。ジャズの大御所「ピットイン」はフュージョンを基盤として六本木に新しいライブハウスを造ろうとしていた。
受験生しか聴かなかった深夜放送(「オールナイトニッポン」が中心)もどんどんロックを流していた。東京の主要都市(渋谷・新宿・六本木など)から発信される新鮮な情報に我々は圧倒されていたのだ。まあ、私は小学生の頃から深夜放送を隠れて聞いて居たのだけども。。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
若松孝二映画考........。
「千年の愉楽」
『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』と『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』はいかにも若松孝二監督らしい、いや今時は同監督以外、誰にも取り組むことのできない作品だった。その若松監督が最新作として取り組んだのが、中上健次の1982年の短編『千年の愉楽』の映画化だ。「中上文学」はかなり特殊だ。現に「被差別」特有の「血族」や「路地」などの言葉・概念を見るだけでもそんな特殊性がわかるため、私は本格的に中上文学にハマることはなかった。しかし、映画の世界では『軽蔑』が2011年に高良健吾の主演で映画化された為「中上文学最後の可成り特殊な純愛映画」を見る事が出来た。
若松監督は本作の公開準備中である2011年10月17日に不慮の事故で亡くなった。
そんな思いを持って本作を観ると、寺島しのぶをオリュウノオバ役に起用したのは『キャタピラー』の演技を見れば当然だが、彼女は原作で描かれたオリュウノオバとは全然年齢が違うため、映画化にあたっては「路地の男たちを見守りながら年を重ねていく若きオリュウノオバ」という風に台本を大幅修正した。しかしそれでも、中上健次の原作『千年の愉楽』が描くのは、壮大なスケールでの性と生。もっと具体的に言えば、紀州南端の町の「路地」に生きる美しき「中本の男」たちの生と死だ。
「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」
ベトナム戦争、パリの5月革命、文化大革命、日米安保反対闘争、世界がうねりを上げていた1960年代。学費値上げ反対運動に端を発した日本の学生運動も、安田講堂封鎖、神田解放区闘争、三里塚闘争、沖縄返還闘争など、農民や労働者と共に、社会変革を目指し、勢いを増していった。活動家の逮捕が相次ぐ中、先鋭化した若者たちによって、連合赤軍は結成され、1972年2月のあさま山荘へと至る。その後、彼らの同志殺しが次々と明らかになり、日本の学生運動は完全に失速して行った。テレビ視聴率89.7%、日本中の目を釘付けにした「あさま山荘」の内部では、一体何が起きていたのか。彼らはなぜ、山へ入り、同志に手をかけ、豪雪の雪山を越え、あさま山荘の銃撃戦へと至ったのか。そして、「あさま山荘」の中で、最年少の赤軍兵士の少年が叫んだ言葉とはー。
「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」予告編

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
『日本のブルースハープ奏者列伝』
「妹尾隆一郎」
1949年6月17日生まれ、大阪府大阪市出身のブルースハーモニカ奏者。大学入学時に上京し、ポール・バターフィールドのハーモニカに衝撃を受けて以来、ハーモニカの道へ邁進。72年、B.B.キングの来日公演の前座に出演。74年にブルース・バンド、ウィーピング・ハープ・セノオ&ヒズ・ローラーコースターを結成。76年に初アルバム『メッシン・アラウンド』を発表。以降、ソロやバンド活動のほか、他アーティストとの共演やツアー参加、番組音楽制作、後進への指導など幅広く精力的な活動を展開し、日本におけるブルース・ハーモニカの第一人者として活躍。2017年12月に治療専念のためライヴ活動休止を発表後、12月17日に死去。68歳没。
Roller Coaster feat. 妹尾隆一郎 - A Tribute To Little Walter Jacobs (Harmonica Cover)
「西村ヒロ」
山口県出身。少年時代にギターを弾き始め、大学在学中にブルース・ハープを手にする。1984年12月から半年、シカゴでセッション活動をして腕を磨いた。タング・ブロックの名手として知られ、数々のレコーディングやライブ・サポートをこなす。また、自らのバンド、HooDoo Boozeでも精力的に活動を行っている

「NATUKO」

東京のモッズシーン、ブルーズシーンの中に、華奢な身体に似合わずブルーズハープを吹きまくり、ディープにヴィンテージな味わいの曲を歌う女性NATSUKOがいる。彼女のブルーズハープの実力は、世界的なハーモニカメイカーであるドイツのHOHNER社公認アーチストとして認定されるほど折り紙つきであり、日本人女性のブルーズハーピストとしては、最高峰の領域にいる。
ボーカリストとしても、Blues, Jazz, Jive, New Orleans R&Bなどのヴィンテージサウンドを、思いのほかラウドに歌い上げるパフォーマンスは、一度見たら忘れられないインパクトを持っている。
彼女の存在や、その秘めたポティンシャルについては、あまり数の多くないライブで直接触れた人達を中心に、限られたゾーンの中でしか知られていない。
そのNATSUKOが、アーチストとして一歩前に進み出す為に、初めてレコーディングを行い、『Blue Stocking』と題したデビューアルバムを発売。
Blues Harp Natsuko Band-Rocket 88
 「コテツ」Bluesharp奏者。
「コテツ」Bluesharp奏者。
1971年東京生まれ。17才から10ホール・ハーモニカを吹き始め、2001年、シンガーソングライター/ピアニスト、YANCYとのデュオ「コテツ&ヤンシー」でアルバム・デビュー。
現在は、ドクター・ジョン、バディ・ガイ、オーティス・ラッシュとの競演でも知られる、KOTEZ&YANCY。ムッシュかまやつ、LEYONA、鮎川誠、近藤房之助、山岸潤史などゲストを迎えたコラボレーション活動もあるブルーズ・バンド、blues.the-butcher-590213(永井ホトケ隆+沼澤尚+中條 卓+KOTEZ)。八木のぶお、KOTEZのツイン・ハーモニカによる2つのユニット、HARP MADDNESS、電気HARP MADDNESS。ベーシスト、江口弘史の提案により、KOTEZのVOCALを全面に打ち出したユニット、100%KOTEZsings。TAPスタイルの異なる、ふたりの女性ダンサーとのユニット「なまはむめろん」等をレギュラーに、ライヴ、レコーディング、CFナレーション、音楽ライターなどを幅広く活動中。
荻窪RNS七周年記念ライブ シカゴビート「コテツ」
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
片付けて居たら。高校生の頃に描いた漫画がまた出てきた。探して居たら小説も出て来たが、丁度シナリオの勉強をやり出した時で、暇つぶしに書いて居たモノだろう。昔は何にでもチャレンジして居たっけ・・・・

私は4月で64歳を迎えた。しかし、自分では精神年齢は40歳ぐらいだと思って居る。此の間、中学校の同級生数人と偶然にばったり会うことがあったのだが。皆んな老けていて驚いた。大体が服装がいけない。年寄り然とした、じじいの格好をしているのがいけない。私は歳だが、髪は長髪にしているしパーマを掛けて居る。服装も成るだけ洒落た格好を心がけて居る。私の頭の隅にはトラッド・ファッションと1970年代のフラワームーブメントのファッションセンスが常にある。だから、成るだけ、それに沿う様な格好を考えて居る。良いではないか。もう生きても10数年の短い命だ。それから、ジーパンは今はすべて日本産のものを購入して居る。今、海外では日本産のジーンズがもてはやされて居る。日本産のジーンズは海外で評価が高い。しかし私がお洒落な格好をしても、最近は誰からも何か笑われたりとか文句を言われたことは一度も無い。強いて言えば、私が調子が最悪に悪かった時を見ている訪問看護師から、「〇〇さんは、前は今みたいにちゃんとして居なかったんだから・・・」と言われるぐらいです。(笑)
ジーパンと言えば亡くなった父親が「俺だってジーパンを履いてみたいんだ」と言うので「履けばいいじゃないか」と言っても「なぁに〜が」と言っていた。親父は会社を5時に退社すると夜の12時までパチンコ屋に居た。毎日だ。自分の玉が無くなると隣の男がやっている様子を食い入る様に見ていて、「じじい!そんなに玉が欲しいのならくれてやらぁ〜」と投げつけられた玉を拾ってまた始めて出たと喜んで居たと言う。そして玉がもらえない時には床に這いつくばって、落ちている玉を拾い、また、始めていたらしい。毎日夜の12時半に帰って来て、母に食事を作らせて、私はリビングにあった、テレビで放送大学の「芸術論」の講義を楽しみに見ていると、人の眼の前でわざと新聞を広げて邪魔をする。そして「お前はバカか、勉強は学生時代でおしまいだ!」と怒鳴る。私は「何をバカなことを言っているんだ、学びは一生だろ。」とよく喧嘩になった。親父は結局タバコの煙が充満しているパチンコ屋に毎日7時間近く居て、その為に肺がんになり、最後は骨ガンに転移して、そして死んでいった。大バカ野郎だと思う、しかし自分が設立した会社を兄貴とその息子らに乗っ取られて焼けに成って居たのも確かな事だけど。
私は親父の会社に入る前にバイトを幾つかした。東京出版のアルバイトは半年した。本の仕分けと取次店までの区分けだが、バイト代は10日ごとに支払われた。大体3万5千円位だった。そこから昼食代として三百円が引かれた。食堂では秋刀魚定食か、惣菜パンに牛乳だった。今はオートメーション化されて居て、機械がやって居て、かつて働いていた人たちはどうなったのだろうかと思っていたら、何とAmazonが全員を引き取って雇用したと聞いた。他に古本屋などでバイトをした。私は極力本は処分しないたちだ。どうしてもの時は町の古本屋に売りに行く。ブック・オフとかには持っていかない。あくまで町の古本屋だ。もう数年前になるが、津野海太郎氏が編集して出して居た「季刊・本とコンピューター」という月刊誌を10冊纏めて売りに行ったら6千円に成った事があった。しかし。いざ、古本屋に勤めてみると、その厳しさ、大変さが良く解ったものだ。そしてバイトと言えば、高校の頃、知り合いの同級生が自宅にやって来て。パーティーのバンドをしてくれと切実に頼まれた。聞けば仕出し弁当屋が主催するパーティーで頼んでいたバンドが、断ってきたというので困っていると言う。あまり乗る気ではなかったが、そいつが気の毒に思い引き受けた。会場に行ってみると仕出屋の社長が居て、一人1万円をくれると言う。機材は揃って居た。私はとりあえず自分を含めたギター3人とベース、キーボード、ドラムを引き連れて演奏を始めた。レーナード・スキナードの曲から、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープルの曲を演奏した。しかし反応がイマイチだった。その内、カラオケ・タイムになり、女の子が松田聖子やらピンク・レディーの曲を歌うと言い出した。ギター3人でなんとかバックをこなして居たが、途中、嫌気が差したギターが1人とベースがもう帰ると言って居なくなった。何気なく、ふと会場に居る男たちを見てみると、リーゼント・スタイルが殆んどだと言う事に気が付いた。だからロックン・ロールをやれば良いかも知れないと思い。ギターをベースに持ち替えて、クリフ・リチャード。ファッツ・ドミノ。リトル・リチャード。チャック・ベリーの曲を立て続けに演奏した。ギターもキーボードも合わせて乗ってやった。そうしたら皆んな雄叫びを上げて、踊り狂い始めた。中にはビールを私の頭から掛ける者も出て来た。散々な目にあったが、主催者の仕出し弁当屋は大喜びだった。おかげで友人の面目も立ったし、金も貰えた。そんな事があった。即席編成のバンドではあったが、良くやったと思う。。。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
さて、映画です。今回は「パリは霧に濡れて」です。ルネ・クレマンが放った、サスペンス映画です。現代の高度に発達した産業社会の緊張によって生み出される不安と恐怖に苛まれ疲弊する現代人の心理状態を描出するサスペンス・ドラマ。1971年フランス映画です。
「ストーリー」
最近になって、時として記憶を失ったり、自失するジル(F・ダナウェイ)は今日も、ふと気がついたときには、セーヌを行き来する貨物船に乗っていた。はっとしたジルは、カフェに向い、夫に電話をかけた。いきなり夫のいら立った声がはね返ってきた。家に戻ると、夫のフィリップ(F・ランジェラ)とのいつもの耐え難い会話が待っていた。とげとげしい言葉のやりとりのあとの夫の異常ないたわりにジルは、ますます混乱を深めざるを得なかった。フィリップとジルはパリに住むアメリカ人夫婦で、二人の間には八才になるキャシーと四才のパトリックがいた。フィリップはいまは著述家として生計を立てているが、アメリカでは電子工学の会社でその明晰な能力を発揮し、現代科学の最先端に立っていた。ところが、何年かのち突然会社をやめ、逃れるようにフランスにやってきたのだ。ジルの精神異常はますます激しく、最近はすっかり親しくなった階下のアメリカ人シンシア(B・パーキンス)に何かと頼ってしまうことが多くなった。しかしシンシアはよくジルの小さな思いちがいをこまかく指摘し、そのたびジルは新たなショックを受けた。そんな状態のジルが、小型車を運転していて、事故を起してしまった。ところが自宅に帰ったジルに花束が届き、一通の手紙が添えてあった。急いで戻ってきたフィリップはそれを見て戦慄した。彼はまさに手紙の主から脅迫を受けていたのだ。数年前、電子工学に携さわっていたフィリップはいつしか産業スパイの役割まで担っていたのだ。フィリップはそんな息づまるような生活から逃れて、パリにやってきたのだ。ところが、組織は彼をまだ解き放していてはくれなかったのだ。クリスマスも近いある黄昏、恐れていた事件が起った。サーカスの帰り、セーヌにかかる橋の上で二人の子供が忽然と姿を消したのだ。捜査はまずノイローゼのジルに向けられた。必死に証言するフィリップだが、フィリップにはわかっているのだ。相手は“彼ら”なのだ。しかし必死の捜査を続ける警察は、遂にジルから事件の鍵となるべき証言を得たのだ。子供たちが姿を消す直前デパートでかつてベビー・シッターとして家へ出入りしていたハンセンなる女性(K・ブランゲルノン)の姿を見たというのだ。子供たちは隠れ家で発見された。ハンセンを手先に使ったのは何とシンシアであった。そしてシンシアこそ組織が送りこんだ人物であったのだ。
Gilbert Bécaud - La Maison Sous Les Arbres (The Deadly Trap / Sisli Günler | 1971)
脚本にダニエル・ブーランジョが参加している。フェイダナ・ウエイの母性が光る一遍だ。霧中のパリ、セーヌからサン・マルタン運河へと進む運搬船の上では、どこか幼さを残すフェイ・ダナウェイがまどろんでいる。かくも美しきシーンで始まるこの映画は、だが、彼女の運転する2CVが炎上するに及び、急激に「乗り物映画」としての輝きを失ってしまう。サスペンス作家クレマンは今回も「組織」なるマクガフィンを登場させる。ダナウェイの夫は元産業スパイで米国からパリへと逃げてきたらしい。彼の才能を愛でる「組織」は是が非でも彼を復帰させようと二人の子供を誘拐する。見所はフェイダナウェイの悲しみとやりきれない屈折した思いだ。子役もまだ小さいのにしっかり演技をしている。名匠ルネ・クレマンの面目躍如が炸裂している。とにかく、クレマンの忘れ去られた圭作として知られる本作は非常に物語が良く。脚本、脚色は実に良いと思う。米国からパリに越した家族に起きる事件…明かせぬ過去を持つ旦那。記憶障害の妻…誘拐された子供達。この静寂な心理劇と大女優ダナウェイの芝居は必見でお勧めです。
_____________________
「押井守の論考」・・・(同人誌を発行して居るヘーゲル奥田氏の論考です。哲学の歴史にも 成って居るのでこの文だけで、哲学の事が解りますので。難しそうで嫌だとは思わずに、読んで観て下さいね、勉強になりますから)・・・
さて、われわれはまず押井守の世界をどこから、どのように読み始めるべきなのだろうか? 正直なところ、領域をいちはやく特定することは大変困難である。押井守の作品世界に内在するテーマは、ひどく広範囲にわたり、また尚且つその深さにおいても非常にさまざまな水準に及んでいる。たとえばある者は『ビューティフル・ドリーマー』に古代中国思想の問題意識を見いだしたろう。またある者は『天使のたまご』の中に、フロイトやメルロ=ポンティのいわゆる“肉の存在論”のほのかな香りを嗅ぎ取ったかも知れない。『紅い眼鏡』にファウス卜的逃走や60年代イデオロギー闘争の世代の思想的背景を感じた者、『御先祖様方々歳!』の背後にレヴィ=ストロースの親族構造論の片鱗を見た者、パトレイバー『劇場版』に象徴言語の隠喩によってなる超越諭的な言語ゲームを垣間見た者、『迷宮物件/FILE-538』にホフスタッターの不思議な論理の存在を感じた者……いったいわれわれはどの先達に教えを請えばよいのだろうか。
押井守が現在の形で注目を集め始めたのは、TVシリーズ「うる星やつら」におけるオリジナルのエピソード『みじめ!? 愛とさすらいの母!』から、というのが現在もっとも支配的な説である。この作品において押井氏はずいぶんと苦言を受けられたそうだが、マニアックなものの見方をするファンの間ではその評価は可成り上がったらしい。たしかに、その内容は、すくなくともゴールデンタイムに放映されたTVシリーズアニメとしては、大変ハードな問題を扱っている。現実と夢の不可分性を論じたこの作品は、それ以降の押井守作品の作品性を方向づける原基的なものであった。じっさい、それ以降の押井守作品の評論を読むと、その殆ど全てがこの作品の固有の問題地平を、それ以降の作品のものと無差別に近い扱いで論じている。
だが実際のところ、この段階の議論には限界がある。現代に生さているわれわれは、整備されたマニュアルがないと新しい行動を起こすことをためらいがちだが、この傾向は残念なことに“思考”の面に最も顕著にその例を見ることができる。考えなくてもよい場合、われわれは思考を休む。どう考えてよいかわからない時はなおさらである。大抵の人は押井作品の中に、何か漠然と「高度な思考」を嗅ぎとるが、数の観念の未熟な未開人が両手指の数以上をすべて「タクサン」として総括してしまうように、多くの観賞者はそれを「むずかしいテーマ」として総括する。彼はそれ以上考えることをしない。そしてそんなとき彼の自我を守るのは、「作品は“感性”で観るものさ」という常套旬である。
シュペングラーの詩的な記述で有名な、崖から落ちる瞬間の人間の脳裏を横切る瞬時の回想は、実は蓄積されたあらゆる記録から打開策を検索しようとする脳の最後の情報処理機能だという説がある。新しい方法がない、あるいは必要ないとき、われわれはいままでの経験の範疇と方法とで考えようとする。だがこのとき、われわれが超個人的な技術的思考に到達する確率は、がっかりするほど低い。
押井守の作品と対決するためには、あなた個人の限られた思索の歴史を超えた“方法”が不可欠である。そのマニュアルはあるにはあるが、図書館へ行く労力と、はげしい退屈に対する覚悟が必要である。そこで此処ではまず、ひとつの技術的思考方法と、“知”のフィールドがそこに至った軌跡をおおざっぱに記すことにする。大学等で専門的な研究をされた諸氏には退屈な記述となるだろう。その場合は読みとばしていただいて結構である。
〜存在と意識〜
われわれは一般に、周囲をとりまく日常的な《世界》を、客観的・公開的な環境世界として無条件に信じ、疑わない。こういった素朴な認識態度は“自然的態度”や“素朴実在論”などとよばれる。
しかし一方、一見自明とも思えるこうした客観的世界を無条件に信じず、主観的認識を中心に素朴な実在論に疑問を唱える立場がある。世界の成立根拠を客観的な実在に置かず、あくまで意識と意識に映ずる表象に求めるという思想群である。こうした立場は内省論、懐疑論、観念論等とよばれ、時代・地域に関係なく常に人類の思想史上に現れる傾向にある。なかでも近代以降に限定すれば、特にヨーロッパにこの思想的傾向が強い。
そもそも近代人のこうした思考習癖は、デカルトのコギト以降“意識”に対する興味が特別な重要性を帯びてきたことに大きく由来するだろう。意識自身にとって“意識”は比較的透明性をもっているのに対し、意識の“外”の世界は常に不透明性を帯びている。バークリーやフィヒテのように主体の意識の内部に認識の王国を築く没世界的な内省論にしろ、デカルト自身やデイヴィッド・ヒュームのように主体の認識の不完全性からただ眼前に広がる世界の実在を信じ得ず、意識それ自体の内部と外部とにそれぞれの世界を創造し、その双方の間に絶望的な断絶を設けてしまった二元論的な懐疑主義にしろ、その深層構造を同じくする知の場からきわめて自然に産み出される思考と言うことができよう。またこういった視点から考えた限り、空間の認識にとどまらず時間の認識にも同様の知的態度を見ることができる。すなわち、客観的な時間の存在を完全に、あるいは条件つきに否定し、時間の成立根拠をそれを認識する主体に由来するとする思想である。西洋哲学において、アウレリウス・アウグスティヌスに一つの源流をもとめられるこの思想もやはり近代思想史にその姿を現し続けている。カントールによる時空間の実在性の証明もこれらの思想群を沈黙させるには至ってはいない。
こうした知的態度の対立の根底には、存在と意識の対立の思考習慣がある。
伝統的な哲学では、意識や精神は神からの付与をその由来とし、広く“存在”の中に含まれるものであった。この“存在”は総括的に第一哲学としての形而上学において語られ、精神と存在とは対立するものとしては捉えられてはいなかった。はるかな時間を経、中世から近代に移ろうとする時代、デカルトの「懐疑」という方法において初めて《意識》は《存在》の従属物以上の地位を与えられることとなる。のちに実存哲学の先駆と称された“我”の発見は、人類の思想史中最もドラマティックな瞬間であった。だがそれは同時に、人間がまさに死にゆく神の呪いを受けた瞬間でもあった。オリュンピカに記された悪夢において雷鳴とともにデカルトを襲ったのは、“悪意の霊”に象徴される涜神の意識と、自身の所業に対する激しい不安と怖れであったという。そしてその時より始まった、存在と意識のトートロギーに満ちた関係を明らかにしようとする近代西洋哲学の必死の試みは、独断と懐疑との峡をあてもなく彷徨することとなる。
この問題は、カントが「コペルニクス的転換」ののちに慎重に提示した紳士的な説明で、ひとたびは結論づけられたかに見えた。だがその結論すら、多くの不徹底さを残していた。結局、存在と意識とのリアルな関係論の総合的な理論化は、カントの後に現れ“近代”を終焉せしめたヘーゲルの巨大な体系の出現を待ってすら完全には成し遂げられなかった。そしてその近代最後の激突は皮肉にも、へーゲルに挑むマルクスとキェルケゴールという三つの弁証法の中に発現するのである。
ヘーゲルの体系は、意識の論理によって成っている。デカルトはコギトという“意識”によって“存在”に懐疑をとなえ否定したが、ヘーゲルにおいて“存在”は“存在の意識”であって、意識による存在の否定はすなわち“意識”による“存在の意識”の否定、つまり意識による意識の自己否定という矛盾の構造を展開する。“存在の意識”は意識であるとともに在在であるから、自己自身を自己の対象として外化する。しかし同時にやはりそれは意識でありつづけることによって自己を自己へと統合する。このダイナミックな発展の構造がへーゲル弁証法の基本原理である。
これは“意識”の体系でありながら、存在論としての形而上学の形式をとる独特の体系である。だが、近代最大の体系であるヘーゲル論理学も、やはり真に総合的な“存在”の論理を解明しつくすには至らなかった。その一つの現れとして、ヘーゲル形而上学の方法に対するマルクスの攻撃的な評価はあまりにも有名であろう。また、現実的な“生”のカテゴリーとして“実存”の問題を提出し、質的弁証法によって観念論としてのへーゲル体系を此判したキェルケゴールの立場も忘れるわけにはいかない。
しかし、自らの方法に“科学”を標榜し、唯物論の弁証法を展開するマルクスの立場は、つまるところすべてをプロトコル命題に還元しようとする論理実証主義と同様、存在の深層を知らずただ此岸的事実の総体を読む“ただの”唯物論であった。また逆に、世界公開性と、主体が物理的次元で依存せねばならないはずの客観的存在を見失い、なおかつ彼岸者である神にのみ救済を求めねばならなかったキェルケゴールも、やはり不完全であった。真理の真相は、存在と意識、主体と客体を、高次の次元よりともにつらぬく“何か”にあった。究極の真理を夢見つつ、果たすことなく消えていった哲学者の幾人かは、ぼんやりと、しかし確実にそれを“見て”いた。押井守も、いまそれを見ている。
〜意志の哲学〜
科学の歴史は進歩の一途をたどってきた訳ではない。現代の科学的世界は人類にとって二度目の経験であり、その間には明らかな退歩の歴史があった。
科学的思考法の最初の発達は、紀元前約600年のイオニアで始まった。世界を秩序あるものとし、論理と実験を武器に世界の真相に迫るその態度は、現代の方法と大変よく似ていた。それは数100年のうちに衰退し、アレキサンドリアの崩壊とともに失われた。そののち、長い中世の暗黒が歴史を覆っていく。人類がこの成果を再び手にするのにはルネッサンスの時代を侍たねばならなかった。哲学の歴史にも、きわめて似た事情を見ることができる。
イオニアの科学が栄えていたころ、哲学の追及は世界の真相に対してなされていた。存在の実相こそ哲学的思索の変わらぬテーマであった。ある人物の出現を境に、哲学は“存在の実相”から離れることになる。それは必ずしも退歩ではなかったかもしれない。だがそれはある意味で“堕落”であった。その人物は、ソクラテスだった。
二ーチェは、哲学を堕落せしめた張本人としてソクラテスを糾弾する。この“自ら名乗る愚者”によって、人類の知は存在そのものの意味を語る“大地の思惟”を忘れ、矮小な“道徳”を云々するようになった。以来、人類が再び存在の思惟を取り戻すには近代の到来を待つことになる。
存在の真相の思惟が人類の思想史に再びその姿を見せたのは、19世紀を持った近代の終盤の時代であった。実在と現象の二元論が激しく交錯している時、それは“意志の哲学”という奇妙な思想の形をとって現れた。
アルトゥール・ショーペンハウエルの“盲目的な生への意思”は、激しい批判を経てニーチェの“権力への意志”の思想を生む。だがそれらの思索の背後には、イマニエル・カントの“物自体”があった。
マルクスがカントの哲学を批判した「不可知論」という嘲笑的な評価は、あまりにも広く知られている。だが、このときマルクスのおかした過ちについてはそれほど広く知られてはいない。“存在の思惟”はマルクスの時代の射程を超えたものだった。そして何よリマルクスは「嘲笑わねばならなかった」。嘲笑うことこそが、みずから起こした宗教に対する彼の開祖としての最も誠実な儀礼行為だったのである。
カントの“物自体”の思想は、つまるところカテゴリー論である。カントは思惟の形式を「分量」「性質」「関係」「様相」の四つの群から成る十二の範疇(カテゴリー)に分け、理性の可能的経験の領域と、その限界を示唆することに取り組んだ。この仕事は、理性の理論を確立し、宇宙の涯や時間の限界の問題に一つの解答をもたらした。だがその成果の本質は、後のハイデッガーの展開した存在論的差別の方法論に通ずるものであった。すなわちそれは哲学史にとって、単なる実在と現象の二元論を超越した、高次の存在論の可能性を開示する“事件”だったのである。“物自体”に対するニーチェの心酔、『カント・ブーフ』にみられるハイデッガーの評価は、この点にその由来をもっている。〔補遺 こういったカントの思惟は、ただ思弁的、形而上学的な段階の議論に留まるものではない。この思索は、あらゆる学術や文化の局面にその現実的な発露の例を見ることができる。たとえば言語学的哲学における世界とシンボルの乖離、行動主義的な心理学における性向と行動の関係論、経済学における産業的部分と企業的部分の弁証法、格闘技における勝負と勝敗の不一致、キリスト教における救済と原罪の思想──人間の認識領域は現象界に限られており、物自体を直接認識することはできない。人間が宇宙空間における光線を直接見ることができず、ただその反射によってしかその存在を知ることができないのと同様に時間や空間などを直接認識しえず、ただその内的存在物(即ち現象)によってそれを認識するしかないという“認識力の限界”こそ、人類の悲劇の大きな原因なのである。また、このことはひとつの思考実験を生んだ。もしも、人間の認識力にこのカテゴリーを超越する能力があったら? 感覚的知覚に依存し、現象の世界のみに束縛された悟性に、存在の実相を直接感じとることのできる認識力があたえられたら?……おそらくその者は現在の人間とは認識論的に次元のまったく異なる存在者となるだろう。
自らをカントの正当な後継者とするショーペンハウエルは、残念ながらあまりに“詩的”だった。“存在の真相”をいちはやく見抜いたその『意思と表象』の哲学は、しかし彼自身の望むようには評価されなかった。だがその悪魔的な魅力に満ちた形而上学は、超時代的な天才を出現させた。ひそやかに死への誘惑を囁くショーペンハウエルの哲学に対する激しい憤りとともに、ニーチェは現れた。その“権カへの意志”の思想は、存在の本質を求める古代の思索を復活させた。二十世紀最大の思想家マルティン・ハイデッガーも、知の考古学者ミッシェル・フーコーも、大地の思索者ツァラトゥストラの弟子だった。
そして時代は、“近代”の終焉を迎えようとしていた。
〜現代〜〜
19世紀末、物理学は混迷の時代を迎えていた。ニュートン力学に対するマッハの無謀とも思える挑戦は、近代物理学の根底を問いなおすものだった。彼の比較物理学の提唱は、皮肉の意味をこめて『物理学的現象学』と呼ばれた。また数学界においても、新しい知的潮流が起こっていた。デーデキントの無限小解析やカントールの集合論などをその例とする数学的思考の算術化の傾向である。
これら思想的流派の知的運動は、近代までの世界を何らかの意味において裏打ってきたプラトン主義の思考習慣を打ち破る胎動であった。「証明の背後の何ものかではなく、証明が証明するのだ」というヴィトゲンシュタインの言葉に顕されるように、知は自らを“構成”する。それは、“現代”の到来を意味していた。
時を同じくして、哲学の世界にもひとつのエポックが訪れようとしていた。カントールの同僚のひとりが、数学の思考法を哲学に持ち込んだ。彼の名は、エドムント・フッサールといった。彼は、物理学のマッハからその学派の名称を借用した。それまで何らかの形で“芸術的”な様相をすら持っていた“哲学”を、彼は「厳密に学問的な方法」によってあらたにシステム構築しようとした。彼はその知的運動を、誇り高い自負とともに『現象学』と名づけた。
現象学は、記述の哲学である。それはどこまでも冷静に、的確に、あらゆる諸科学が暗黙のうちに認め問わないその根底にまで立ち戻って記述する一種の科学哲学である。したがってそれは、あらゆる認識の大前提となる“意識”の、その“指向性”という根源的な性質が向かうもの、すなわち“直感に原的に与えられた事象”としての《現象》をその固有の対象とする。そのとき、われわれが自然的態度のもとにひたっている歴史、文化、伝統的な思考習慣、諸科学からの理論や知識、個人的および主観的なものの見方などといった各種のイドラ、さらには世界そのものを在りとする存在定立一般をすら問題対象の外部へ置く。それは“括弧入れ”と呼ばれる思考技術の一方法であり、“判断中止”(エポケー)とも呼ばれる。それはあたかも、複雑な外科手術が、各器官の有機的関連の維持に対する十分に注意深い配慮のもとに、麻酔され、切開され、処理されるのによく似ている。この思考実験的な方法を、方法論的に“還元”と呼ぶ。
この“還元”は、世界の実在を疑うデカルト的懐疑とは異なり、世界への関与や関心から一時的に身を引くことにより自然的態度においては到達し得なかった認識と世界の真の関係に迫ろうという思考技術である。だが同時にこれは、世界と主体の関係を超越的に理解するための技術でありながら、世界と主体の関係そのものを一時的にしろ問題の外に置くという矛盾を内包している。したがってこの思考作業は、段階的に、精密に、注意深く進められる。まず「形相的還元」においては、眼前に提示された対象の本質的把握がめざされ、次いで“主観”の領域を主題とする「現象学的還元」では没個人的な“私の”世界構成としての自我論的構成が問題とされ、さらに「間主観的還元」において多数主観の共同主観的構成による普遍的な対象の客観性が確保される。〔補遺 単純な見方をすれば、作品『天使のたまご』はこの“現象学的還元”の段階から“間主観的還元”にいたる知的フィールドにおいて語られる「現象学的作品」であるという理解も極端な誤りではなかろう。しかしそもそも、アニメーション等映像メディア上で語られる芸術は、それ自体現象学的要素を強く持っている。虚構であることを前提としつつもその作品世界を感覚対象とする態度は、(不徹底ではあるが)ある意味で明らかに現象学的な思考技術としてのエポケーであり、ひとつの還元である。また特にアニメーションは、非実在的(irreal)な“絵”でありながら、それが動き、声を発することによって「意味を付与され」、「生気を吹き込まれ」、“指向的対象”として構成される。これは、やはり非実在的で客観的な色や音、すなわち「色のごとき或るもの」といった“感覚の色”や“感覚の音”などの材料的成分から成る、いわゆる“ヒユレー的契機”が、“ノエシス的契機”によって「意味を付与され」、「生気を吹き込まれ」て“指向的対象”としての“ノエマ”として構成されるという“現象学的還元”の説明とほぼ一致する。
またこの場合、声優の存在はきわめて大さな意味を持つ。知覚感性論における“外”の原初的指標は「眼」と「声」によって啓発されるが、特にデリダの指摘によれば、自己現前性を出発点とする明証性は音声記号中心主義に起因するのである。
現代においてこうした例は、映画のスクリーン、テレビの液晶スクリーン、コンピュータのCRT等の中に非常にしばしば見ることができる。これは、フッサールの時代にはまだあまり見ることのできなかった情況である。すなわち現代は、過去のいかなる時代にもまして現象学的な時代だと言える。そういった意味で、現象学的視点は見直されるべきなのかもしれない。以下述べることとなるが、フッサールのこの思考技術は、(必ずしもフッサールの意図どおりの形でなしに)さまざまな知的潮流に受け継がれていく。アメリカの実在論および自然主義哲学、ヨーロッパの実存哲学、また心理学をはじめとするその他の精神諸科学、そして各種の視覚的芸術。タルコフスキーや押井守も、この影響下にある。このことはこの文の重要な主張のひとつである。
フッサールの試みは、極端な見方をすれば要素論的な“観照の記述”の学であり、一種の思考技術である。それは眼前の世界に無秩序に広がるままにされていたさまざまな存在物を、いったん全体化し、排去することによって得られる「もの」、すなわち現象学的残渣としての純粋な意識と、それに指向的統一を与える“ノエマ(意味)”および“ノエシス(意味付与作用)”などに関する厳密な記述を目的としていた。だがそれは結局の処、その名の示すとおりあくまで“現象の学”であった。このあとヨーロッパの知的潮流は、フッサールの思いもかけぬ方向へ フッサールのこの思考技術は、思いがけない効果を生もうとしていた。眼前的な存在物の排去という操作は“世界”に被われていた自己意識から、それを被う対象的存在を剥ぎ取リ、その内部の深淵を剥きだす結果を生んだ。それによってもたらされたのは、自己意識と対象的存在との背後に共通に横たわり、その深殻に見え隠れる“深淵的存在”の示唆と、それの周囲に漂う“不安”の概念であった。ここにおいて思想史は、M・ハイデッガーの出現という決定的な事実を刻む事となる。
〔補遺 かつて“存在の思惟”への到達をはたした哲学を検討したとき、ひとつの方法上の共通点を見いだすことができる。それは意識に映ずる現象からの“存在”への接近が、人間の能力として保証されること、言葉を変えれば、人間という存在者そのものが、深淵的存在へといたる認識の現実的通路として重要な意味を擁しているということである。たとえばカントは、因果律に規定された現象界においては保証され得ない人間の本質的自由を、唯一確保できる方法として、現象界から物自体への意識の超越を説いた。そして此処で注目すべきなのは、その超越が人間の遂行行為(カントにおいては定言命法による道徳的格率の遂行)によってなされうるという考えである。同様にニーチェにおいても、精神の革変によって向かうべき“超人”がやはり深淵的存在への鍵を握っている。フッサールの弟子たちが、現象学的方法とキェルケゴールの遺産である“実存”の融合へと向かったのはこうした必然性があったのかも知れない。また逆に言えば、人類の思想史が“存在”へのアプローチのためにこの“実存”の概念に到達するまで、数千年の歳月を要した訳である。
われわれ目の前に与えられているテキストは、あくまでも単なる「存在するもの」である。それは“存在者”もしくは“存在物”であって、けっして“存在”そのものではない。ハイデッガーの指摘によれば、従来の哲学における観念論や実在論の論争は、どちらもこの“存在するもの”と“存在”の差異を不明確なままに展開された、下位の議論であるという。すなわち、世界所属的なレベルにある“存在するもの”を、いかように──たとえば内省論的な観念論の立場からであろうと、唯物論的な実在論の立場からであろうと──解釈しようとも、それは存在論的無差別をおかしたオブジェクト・レベルの議論にすぎない。存在そのものについての論及は、存在するものについての議論とは峻別されねばならない。これが“存在論的差別”である。
こういった存在論への手がかりとしてハイデッガーは、人間の存在への研究、すなわち現存在の実存論的分析論を具体的方法とする解釈学的現象学を提唱した。そして押井守は、ハイデッガーのこの方法から出発した。押井守作品群との関係については、いちいち述べることはしない。読者諸君自身の記憶と思考力をもって、その方法論的相似性を読み取っていただきたい。
 |
存在と時間〈上〉 (ちくま学芸文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 筑摩書房 |
 |
押井守論―MEMENTO MORI |
| クリエーター情報なし | |
| 日本テレビ放送網 |
-------------------------------------------------------------------------------


















