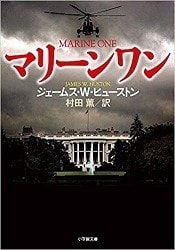「マリーンワン」は、アメリカ合衆国大統領の専用ヘリコプターのコールサインである。主に国内の移動用として使われる。所属はアメリカ海兵隊。
風雨の強い大荒れの夜、アダムズ大統領は別荘キャンプ・デービッドに向かった。操縦士として乗務したのは海兵隊大佐チャック・コリンズ。副操縦士をラッド中佐が務めた。
チャック・コリンズは海兵隊のトップガンで信頼がおけるが、反大統領というのが立場を危うくする。ベテランの機長をもってしても、荒れ狂う暴風には勝てなくて、ヘリコプターは真っ逆さまに墜落炎上する。全員死亡。
当然、訴訟問題に発展する。残されたファーストレディとコリンズの妻を含めて遺族を原告として、名の売れたトム・ハケット弁護士が担当する。
被告になるのは、ヘリコプターを製作したフランスのワールドコプター社になる。それを弁護するのは、コリンズと同じ海兵隊ヘリ出身の弁護士マイク・ノーラン。
法廷を舞台にしたリーガルサスペンスで、数少ない良書の一つと言える。まさに硬派の作りで、チャラチャラしたラヴロマンスなどはない。文体も、余計な比喩や持って回ったユーモアもない。ストレート一本勝負のピッチャーのようなのだ。
文庫本約660頁の457頁でようやく冒頭陳述に至る。急転直下の展開には目が離せなくなる。勿論、サスペンスやカーチェイスもあるが、別の興味が沸く記述もある。
例えば「ワシントンDCの北西地区にあるカフェ「メルセデス・グリル」(実在するか不明)だ。この店はワシントンの政治家、警察関係者、それに彼らが好む言い方を借りれば、二番街(セカンド・ソサエティ)の住人たちの行きつけの場所だ。
一番街(ファースト・ソサエティ)というのは、省庁に勤める裕福な階層の白人たちのことだ。勤め先は連邦議事堂、最高裁判所、連邦政府の省庁などでほとんど白人だ。彼らが連邦政府の政策を作り、隣接するバージニア州やメリーランド州に住居を構える。
本当のワシントン、すなわち二番街の住人たちは、ワシントン特別区内に住み、行政を動かしている。市長、市議会、警察、消防局、地元で活躍する聖職者、市民運動家たちだ。一目瞭然、二番街はみんな黒人だ。
ワシントンは二つの市で構成されているともいえる。横並びでなく上下の構造をなし、黒人たちを下に敷いて、白人たちが乗っている。白人たちの世界はそれに気づかないが、黒人たちはよく知っている。
このカフェは、オーナーもその家族も黒人で、客も黒人なのだ。黒人一色の店に入ったマイク・ノーランは戸惑う。視線が一斉にマイクに向けられ、一番街の人間でないと判れば視線が穏やかになる。しかし、マイクは、よそ者でありそこに侵入している様な感じが消えない。
ティニー(黒人の私立探偵、マイクと同じ海兵隊出身)は、私といわず誰とでもこの店で会いたがる。彼に対して、横柄に振舞って無理難題を吹っ掛けるのはたいてい白人だからだ」アメリカの分断が、おいそれと解消するはずがないのがよく分かる。
この本から学ぶとすれば、もう一つアメリカ合衆国大統領についてがある。それは大統領退任後である。現役大統領時の給料を生涯受領でき、生涯警護官がつき事務的な仕事をする職員もつくとある。だから回顧録で800万ドルを稼いだクリントン元大統領がいる。

著者のジェームス・W・ヒューストンは、1953年10月26日インディアナ州ウェストラファイエットで生まれた。高度な技術を持つトップガンの卒業生で退役後弁護士になる。2004年、世界に17の事務所と1000人の社員を抱える国際法律事務所モリソン&フォアスターにパートナーとして入社。数多くの有名事件に関与するなど事務所に貢献したが、2016年4月14日
多発性骨髄腫で62歳という現代ではまだ若いと言われる年代でこの世を去った。5人の子供と9編の作品を遺した。