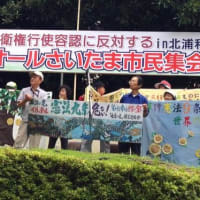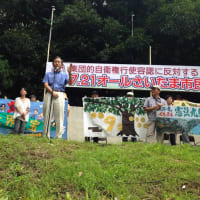「おまぎ9」(おまぎ9条の会の略)では、ミニ学習会を始めました。8月29日、夜7時より、場所はよく使わせていただいている喫茶店「芸術村」をお借りしました。
午後7時より、事務局のほか、大学生1人の6人が参加。この日の話題提供者は、大学で中国史を教えている北田さんです。テーマは題して「憲法と戦争の精神史」。なかなか壮大な中身ですが、概略、お話は次のようなあらすじでした。
(1)テーマの意味。
人類の長い歴史を振り返って、戦争と憲法を考えてみよう。近年の歴史研究では、戦争の発生と進化、そしてその行動を支える人間の精神史のしくみが、理解されてきた。
(2)人類の経済生活の型と戦争
人間は、農耕民が生まれ、生産物が蓄えられるようになって、戦争を本格的に起こしました。日本では弥生時代に、鏃の大きさが大きくなったのは、人間を殺傷するためだと言われています。
戦争は、「環濠(かんごう)集落」という、周りを堀で囲った集落づくりに現れています。これは敵の攻撃から守るための施設であり、最初は弥生時代に、次には、中世につくられました。
封建制は、戦争が恒常化し、武力の均衡が生み出した政治体制です。人類は、古代統一国家の平和が訪れたのち、中世の戦争と動乱の時代に突入していきました。
(3)近世以降における戦争と憲法
近世以降になると、ヨーロッパの勢力が武力の発展を力に、世界を侵略しました。これは、20世紀の2つの世界大戦の大惨禍にまで引き続いていきます。こうした世界をまきこんだ戦争の経験の中から、人類の平和への様々な試みが生まれていきます。(カント「恒久平和のために」、オリンピック、国際連盟、国際連合)
その平和の思想の核となったのは、「主権」つまり一人の人間が自分のことは自分で決めるという権利の芽生えです。日本の憲法9条もその法的な結晶の一つです。
(4)資本主義と「平和の精神史」
資本主義は、社会から暴力装置を国家に回収し、平和のうちに競争を行うことに成功した最初の社会体制だといえます。一方で、アメリカを先頭に、暴力・実力による支配の復帰がもたらされているかに見えます。このとき、暴力の時代から、平和の時代へ、人々の精神的な力によって、時代をすすめることが求められます。
約45分の説明の後、参加者が感想、質問を出し合い、問題意識を交流しました。話題提起が人類史という、広々としたものだっただけに、各人も自由にそれぞれの視点から、感想が述べられ、充実した学習でした。
次回は、9月25日(月曜日)、午後7時から、同じ「芸術村」で行う予定です。ぜひお気軽に、コーヒーをいただきながら、ひと時、平和と憲法について、おしゃべりしませんか。
午後7時より、事務局のほか、大学生1人の6人が参加。この日の話題提供者は、大学で中国史を教えている北田さんです。テーマは題して「憲法と戦争の精神史」。なかなか壮大な中身ですが、概略、お話は次のようなあらすじでした。
(1)テーマの意味。
人類の長い歴史を振り返って、戦争と憲法を考えてみよう。近年の歴史研究では、戦争の発生と進化、そしてその行動を支える人間の精神史のしくみが、理解されてきた。
(2)人類の経済生活の型と戦争
人間は、農耕民が生まれ、生産物が蓄えられるようになって、戦争を本格的に起こしました。日本では弥生時代に、鏃の大きさが大きくなったのは、人間を殺傷するためだと言われています。
戦争は、「環濠(かんごう)集落」という、周りを堀で囲った集落づくりに現れています。これは敵の攻撃から守るための施設であり、最初は弥生時代に、次には、中世につくられました。
封建制は、戦争が恒常化し、武力の均衡が生み出した政治体制です。人類は、古代統一国家の平和が訪れたのち、中世の戦争と動乱の時代に突入していきました。
(3)近世以降における戦争と憲法
近世以降になると、ヨーロッパの勢力が武力の発展を力に、世界を侵略しました。これは、20世紀の2つの世界大戦の大惨禍にまで引き続いていきます。こうした世界をまきこんだ戦争の経験の中から、人類の平和への様々な試みが生まれていきます。(カント「恒久平和のために」、オリンピック、国際連盟、国際連合)
その平和の思想の核となったのは、「主権」つまり一人の人間が自分のことは自分で決めるという権利の芽生えです。日本の憲法9条もその法的な結晶の一つです。
(4)資本主義と「平和の精神史」
資本主義は、社会から暴力装置を国家に回収し、平和のうちに競争を行うことに成功した最初の社会体制だといえます。一方で、アメリカを先頭に、暴力・実力による支配の復帰がもたらされているかに見えます。このとき、暴力の時代から、平和の時代へ、人々の精神的な力によって、時代をすすめることが求められます。
約45分の説明の後、参加者が感想、質問を出し合い、問題意識を交流しました。話題提起が人類史という、広々としたものだっただけに、各人も自由にそれぞれの視点から、感想が述べられ、充実した学習でした。
次回は、9月25日(月曜日)、午後7時から、同じ「芸術村」で行う予定です。ぜひお気軽に、コーヒーをいただきながら、ひと時、平和と憲法について、おしゃべりしませんか。