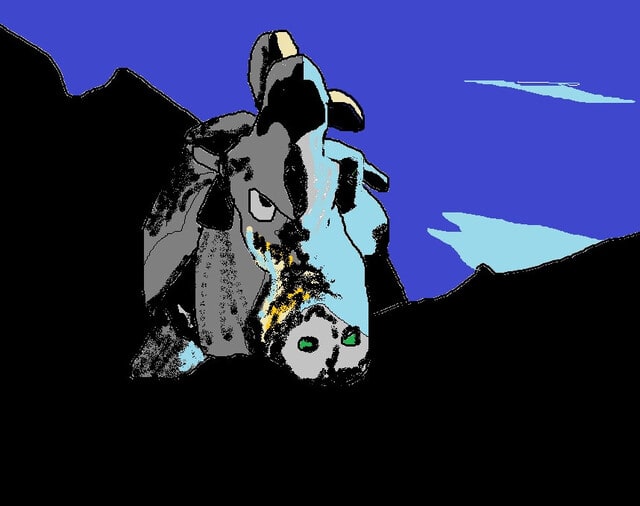
なほ長生きを恨み、諸神・諸仏をたたきまし、「七日がうちに」と、調伏すれば、願ひに任せ、親仁眩瞑心にて、各々走けつけしに、笹六、うれしき片手に、年頃拵へ置きし、 毒薬取り出し、「これ、気付あり」と、素湯取りよせ、噛み砕き、覚えず毒の試みして、忽ち、空しくなりぬ。 さまざま、口をあかすに、甲斐なく、酬、立所をさらず、 見出す眼に、血筋引き、髪、縮みあがり、骸体、常見し五つがさほどになりて、人々、奇異の思ひをなしける。そののち、親仁は、諸息かよいで、子は先だちけるをしらで、これを歎きたまへり。
親が死ぬことが条件の金を借りて親を毒殺しようとしたところ、つい毒味のつもりでその毒薬を飲んで自分が死んでしまった「本朝二十不幸」の冒頭の話。で、貸した方は生き延びている親から金を取り立てることは出来ないので、そんな欲のある仕事は駄目だよと話がしめられるわけだが、――考えてみると、金貸しもそうだが、この話にはしっかりした人間が誰もいないのだ。親も息子も周りの人間も程度の差こそあれどこかいい加減である。戦時下の太宰治の注目は、西鶴の話にこういう〈全員微妙〉という話が散見されることにあったのかもしれないが、しかし、これが、いくら戦争中であっても、太宰の話のように皮肉としての笑い話で済んでいる場合はまだ日本人にとってよかったともいえるかもしれない。まだ、大衆の時流(戦争)に乗らないいいかげんさという持続力があるように思えるからである。
考えてみると、大衆社会みたいな漠然とした視角を保っているから、西鶴も太宰もみんな駄目だねえ、というため息をついていればよかったのではないだろうか。戦争の前には一見平和ぼけとは思えない、戦争についての長い論戦がそこかしこで行われていた。日中戦争、太平洋戦争より以前の言論の血なまぐさというのは本当に流血沙汰だったし、しかも永い間続いた。で、そういう長い論議というのはやたらこまけえ神経質な戦いになっていて、――そんな状態で一発物理的にぶっ放したり飛んで来たりすると、それはその神経質な神経に衝突した爆音みたいなもので、我々の判断力はヒステリックに壊れるのである。真剣に論議すりゃいいというものでもないのだ。
むずかしいものである。あまりに元気がよい阿呆な意見というのは「バカかこいつは」としか評しようがなかったりするけれども、それを言ってしまうと焚き火にガソリンをぶっかけるようなものだ。だからといって褒めるわけにもいかず、理知的な褒め殺しとかはすっとこどっこいには通用しない。ついこちらの怒りだけを悟られてしまうであろう。がっ、無視したら怒られそうである。一緒に飯食うのがよいという説もあるが、そりゃそこらの食べると頭が働く類いのひと同士のはなしで、それが難しい場合も多い。過去を振り返ってみるに、案外、食事というのは禍根を残すものだとわたくしは思う。
しかも食事での雑談や井戸端会議は、虚実のあいまいなところが面白いので、議論は意図的にただのファクトを避けるようになるのであった。しかもわれわれは、こういう雑談さえ今や苦手であり、雑談が出来ないのにコミュニケーションとかいうても無理、というのが自明の理であるという、この世の常識が分からなくなっている。だから、コミュニケーションをいつまでたっても、言ったとおり、書かれているとおりにとるという夢の周りを旋回する人たちがふえている。かくして、そこから、きまじめなコミュニケーションによって合意形成をはかるみたいなことを言い始める人間が分岐して現れる。これは言語の行為としては行動的に見えるが、その実逆であって、合意形成とか課題解決とかに苦労するみたいな自意識に苦しむようになってから、我々は全体的に体が動かなくなってしまったのである。それは、考えるのに時間がかかるというのではなく、問題提起の自由がないのに解決能力があるはずがないという自明の理に過ぎない。問題提起と解決はつねにセットになっているから我々は行動可能なのだ。問題がどこから沸いてくるか分からない現実をふまえろということまでは分かるが、そのあとの問題の析出が解決する人間に絶対的に任されていないのだからこまったものである。そして、その析出係たる人間たちは、井戸端会議をできるレベルで有能であり、必然的にファクトから遠ざかろうとしている。
これはすべてわれわれが大衆社会を肯定して、つまり他人を当てにして、問題提起や解決を他人に任せて生きるのが楽だと思っているから起こっている悪循環ではなかろうかと思う。
この前映画で見た『破戒』がかかれた頃、つまり明治三十九年頃であるが、「野菊の墓」、「肉弾」、「号外」、「坊っちゃん」、「草枕」、「神秘的半獣主義」「国体論及び純正社会主義」が発表されている。それにしても、息もつかせん勢いである。そこには、大衆はだめだねえ、という嘆きはなく、迫り来る個人に対する戦いがある。権力であっても個人の顔をしている。
先日、藤村の作品はどこか全体的にどこでもない場所みたいな雰囲気だと述べた。このどこでもない場所への追求は、「新しさ」みたいな観念を伴っていたし、なんとしても個人として生きたいという願いにつきうごかされていたに違いない。しかし、そう事態は簡単でもないようだ。柳田國男の「重い足踏みの音」という藤村についての回想文がある。これがすごい文章で、我々が人間をみるというか友人をみる見方そのものが、なんとなく陰影をなくしているのがわかろうというものだ。柳田は藤村の創作を禅みたいな態度だとみていた。藤村のいわゆる「こんな私でもなんとか生きたい」という苦悩に罪と罰の問題を見る人は多いだろうが、柳田はそれを禅的だという。それは確かに鋭いな思うと同時に人間の平凡さに着目した見方であるとも思うのだ。柳田によれば、東京人としての藤村はなにか独特な苛々した不自然さ?(うまく要約できんが)があったみたいであり、これは本当じゃないかと思う。都会での社交が暴力的なかんじになってしまう一方で、山村の名家の中でなら美徳を発揮出来ただろうと柳田は言う。いや、暴力的とは柳田は言ってないか。。。そこらは柳田の言い方はそれこそ藤村とは違った、お国柄や土地との関係を捨象できないただの人間としての「描写」なのであり、――柳田にとっては、木曽人みたいな前近代?を引き摺った藤村が、「禅」の行為者としてみえたのである。また、柳田の『破戒』評をみると、作品が風景描写的なのに、だからこそなのか微妙な嘘が混じっていて、実際と違うというと批判している。柳田が見聞きしたいわば「本当」の現実はこれまた柳田らしく、いわば観察可能な平凡さがある。藤村が自分の輪郭を空想しているのに、柳田は大衆社会をみていたのだ。我々の持っている視角は、民俗学的な興味を失って薄まった柳田的な視点である。
我々はそこで、大衆を無視した出家的なありかたを目指してしまいがちだが、別の山岳を目指すという手もある。久谷雉氏の『影法師』は確かに山岳の縦走みたいなとことがある。
鳴らさずに、
峠をいくつも越えられる、棒をかゝへて浮いたまゝ。
あのヘルメットをかぶった人たちだつて
棒を呑んだら魚になれるよ、
――「雲雀」









