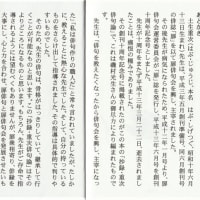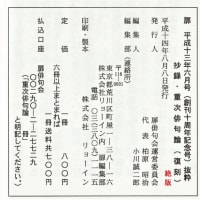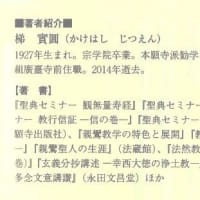『山上宗二記』茶湯者の覚悟 「濃茶呑ヤウ」 その一考察
詳しくは こちらから
前田秀一 プロフィール
3.茶の湯大成の背景
「西行の和歌に於ける、宗祇の連歌に於ける、雪舟の絵に於ける、利休が茶に於ける其の貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。・・・」16)(311頁)
これは、松尾芭蕉が貞享4年(1687)10月から翌年4月にかけて,伊良湖崎,伊勢,伊賀上野,大和,吉野,須磨,明石の旅をつづった芭蕉第3番目の紀行『笈の小文』の冒頭に書かれた有名な風雅論の一節である。和歌の道で西行のしたこと、連歌の道で宗祇のしたこと、絵画の道で雪舟のしたこと、茶道で利休のしたこと、それぞれの携わった道は別々だが、その人々の芸道の根底を貫いているものは同一である。
中世から近世に至るそれぞれの時代に一世を風靡した芸道を列挙して それを貫くものはひとつ、すなわち「風雅の道」、これは不易(いつまでも変わらない文化)であると主張したもので、それぞれの時代の文化の背景を言い得て妙である。
歴史的に見て芸道の基盤ができたのは中世であった。中国伝来の文化は、平安時代までは専ら学問の範囲に終始することが多く、芸能と言われる範疇のものでもその方面の知識や技術の習得から修業過程論に至り、さらには人生論へと展開する、いわゆる「道」の位置づけに置かれた。その一つとして平安時代には「和歌の道」があった17)(4~7頁)。
「道」は、王朝文化に基盤を置くもので王朝文化の継承意識の上に成り立っていたが、これが中世(平安末期から安土桃山時代)に入って王朝の衰退とともに家を中心とした伝統文化の専門的継承が本格的になってくるにつれて、末世意識とともに広義の諸道(諸芸能)の世界における道の論が発生し、展開をうながした。
鎌倉時代に入ると学問のほかに、管弦・舞楽をはじめ、漢詩・和歌の文学、観想、医術、武芸などまで取り込んでより広義に展開していった。
室町期・八代将軍・足利義政の時代(1449~1473年)、家督継承問題から大名間の派閥抗争が激化し、諸大名の結束が乱れ、応仁の乱発生の原因となった。世相は、荘園領主への請願をはじめ、各種の一揆〔荘家、土(百姓)、国人(武士)、宗教(一向、法華、根来等)〕が多発し、社会的にも一揆が容認されていた。一揆は、飲食を共にして一体感を呼び起こす「一味同心」で堅く結束していた18)(41頁)。
応仁・文明の乱(1467~1477年)後、古代的な美意識が決定的に崩壊し、新たに中世的な美・幽玄への美意識が深まり、「歌」主道論は能楽論や連歌論へと変わった。連歌では高山宗砌、蜷川智蘊、飯尾宗祇などが脚光を浴び、禅竹、心敬など陽の当らないところにいた実力派たちから「侘び」や「冷え」の美が高く評価されるようになった15)(42頁)。
一方、応永11年(1404)、明の永楽帝と日本を代表する三代将軍・足利義満との間で結ばれた通商条約に従って、割符を持った政府公認の管理貿易によって長期的な繁栄に乗り出した日明貿易の実態は、将軍、有力大名、天龍寺、醍醐の三宝院などが出資者となり、博多や堺の商人が商売の実務にあたっていた。生糸や絹織物など大量に買い付け、日本で売れたため出資者は潤い、次第に貿易利潤の獲得競争に発展していった。
寛正6年(1465)、日本を出港した三隻の遣明船が文明元年(1469)に帰国の途に就いた時、当初予定していた兵庫の港が応仁・文明の乱で全壊した上に大内氏の支配下にあったため、急遽、土佐沖を迂回して堺港へ入港した。その後、細川氏が支配する遣明船は堺港を出発・到着港とした10)(60頁)。
文明元年(1469)、堺の港に遣明船が入港して以来、防衛とともに、商業資産を守るために天文期以降に周濠(環濠)が整備され、堺は世界的な商業都市として発展していった。

住吉大社の「開口庄官」などを起源として南北庄の荘園領主が変わる中で、津田氏や今井氏など後に茶人として活躍する有力商人たちが台頭し会合を重ねて利害の異なる諸集団を一つの都市としてまとめる調停機能を発揮し、外交、自衛組織として室町幕府や守護と関わりを持った19)(18頁)。
十六世紀には幕府や細川氏の衰退により世界的な商業都市として栄えた堺は安定した後ろ盾を失うが、管領・細川氏を傀儡とした政権樹立を目指していた阿波の豪族・三好氏が海外貿易の拠点として堺の流通機能に注目し堺の豪商との関係構築をはじめ堺南北庄の代官とは別に堺奉行を設置した。豪商自らも三好政権の中で役割を果たしていくことが求められ、堺奉行にも豪商と交流するために文化的教養が求められた20)(124頁)。
財政が破たんした室町幕府は、将軍家の所有していた美術品を売却したり、代物弁済するようになっていった。経済力をつけていた堺の豪商はじめ有力者たちは、「東山御物」の唐物絵巻や美術工芸品、茶道具を競って入手した15)(209頁)。


杭全神社(大阪市平野区) 連歌所および連歌の会(杭全神社御由緒より)
室町時代の文化の特徴は、集団芸能の発達にあり、連歌はその代表例である。複数の人が一ヶ所に集まって、和歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を分けて交互に詠みつづけて一つの作品を仕上げて行く連作形式の詩である。鎌倉時代から百句を一作品とする百韻の形式が整えられ、南北朝時代を経て室町時代に最盛期を迎えた。和歌の良し悪しは個人、ひいては家の名誉に関わるので、後世に残るような素晴らしい歌を詠もうという執着心や雑念が生じるが、連歌は「当座の逸興」、その場が盛り上がればいいという芸道である。連歌の参加者は相互に対等であり、他の参加者と強調しつつ主体性を発揮し、最終的には、没我し、集団的に熱狂していた18)(101頁)。
宗匠を迎えて一味和合の精神で数日かけて行う連歌の会では、国人(武士)一揆や宗教(法華、根来、一向)一揆の結成につながることもあり、一座百韻ごとの連句を十日間続けて行う千句連歌は一揆の親睦を深め、結束を固める平時の姿とも言われていた。
「此中惣テ茶湯風體ハ禅也、口傳、密傳等ハ云渡スナリ、書物ハ無シ」3)(53頁)。
茶の湯を大成した千利休には口伝、秘伝を主体とし自らしたためた書はないが、利休を師と仰いだ山上宗二の著作『山上宗二記』が補っている。その中に連歌に関わる記述がある。
「紹鴎三十マテ連歌師也、三条逍遥院殿詠歌大概之序ヲ聞、茶湯ヲ分別シ、名人ニナラレタリ、」3)(98頁)
「古人ノ云、茶湯名人ニ成テ後ハ、道具一種サヘアレハ、侘数寄スルカ専一也、心敬法師連歌ノ語曰、連歌ハ枯カシケテ寒カレト云、茶湯ノ果モ其如ク成タキト紹鴎常ニ云ト、辻玄哉云レシト也、」3)(97頁)
「客人フリ事、在一座ノ建立ニ、條々密傳多也、一義初心ノ為ニ紹鴎ノ語傳ヘラレタリ、但、當時宗易嫌ルル也、端々夜話ノ時云出サレタリ、第一、朝夕寄合間ナリトモ、道具ヒラキ、亦ハ口切ハ不及云ニ、常ノ茶湯ナリトモ、路地ヘ入ヨリ出ルマテ、一期ニ一度ノ會ノヤウニ、亭主ヲ可敬畏、世間雜談無用也、夢菴狂言謌
我佛隣ノ寶聟鼠天下ノ善悪
此歌ニテ可心得、茶湯事、數奇ニ入リタル事可語」3)(93頁)
神津朝夫氏は、『山上宗二記』を精査、解読され通説に対して異論を提唱されている。その論の一端を引用して以下に要訳した15)(46頁)。
武野紹鴎は三条西実隆に連歌の指導を受け、日本の歌論『詠歌大概』から美意識を学び、それを茶の湯に応用して侘び茶を方向付けた。それは、伝統的に評価の確立している茶道具をつかい、そこに新たな趣向を生み出す道具組を編み出すというものであった。
昔から茶の湯の名人とされる人は、道具一つさえあれば侘び茶を点てることができるといわれている。若いころは格調が高くあっても、ゆく先々には連歌師・心敬が詠んでいるように「枯れて寒々とした」という境地を得るようになりたいものだ、と武野紹鴎は日頃から弟子の辻玄哉に云っていた。
連歌の一座と同じように、紹鴎は茶の湯の座は、そこに集まる人々が、利害共同者として商売の話や諸大名の動向に関する情報交換など世間雑談を行う場であると口伝したが、宗易(利休)はそれを嫌って、「常」の茶会でも一生にただ一度の会のように亭主を敬い、連歌師・牡丹花肖柏が狂歌に歌っているように世間雑談のないものであることを求めた15)(223頁)。
我が仏 隣の宝 婿舅(しゅうと) 天下の戦 人の良し悪し


唐物 天目台茶碗 創作焼き茶碗(畳に直接置く)
武野紹鴎は、連歌の世界から学んだ伝統的な美意識を活かして唐物道具を集め、立派な座敷で道具を見せる茶の湯を目指した。
宗易は、武野紹鴎の教えを辻玄哉を通して伝え聞いたが、武野紹鴎と違って連歌にも深入りすることなく、伝統的な茶道具を揃えることはしなかった。むしろ運び手前や作法を見せる侘び数寄を大事とし、茶席の振る舞いも一生にただ一度の会(「一期一会」)のように亭主と客人が相互に敬い合い、緊張感を持った静かな一座(「和敬清寂」)とすることを目指した。
SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから