
『魔の山』読了計画の5回目。
今回は382頁から706頁までの第五章を(5日をかけて)読んだ。
第一章が、ハンス・カストルプのベルクホーフ到着当日、
第二章は、ハンス・カストルプの少年時代、
第三章は、ハンス・カストルプのベルクホーフ到着2日目が、
第四章は、到着3日目から3週目の直前までが描かれている。
第五章には、
「永遠のスープと突然の光明」
「『あ、見える』」
「自由」
「水銀の気まぐれ」
「百科辞典」
「フマニオーラ(古典学芸研究)」
「まぼろしの肢体」
「死人の踊り」
「ワルプルギスの夜」
という9の節があり、

ハンス・カストルプのベルクホーフ到着後7ヶ月目までが描かれている。
第一章から第四章に比べ、物語の進む速度がさらに速くなって、
それまでの四つ章に比べ、頁数も増える。
第一章(33頁)、第二章(36頁)が短編小説、
第三章(115頁)、第四章(184頁)が中編小説だとすれば、
第五章(324頁)は、この章だけで長編小説に相当する分量があり、
改行が少なく、難解な箇所も多く、読了するのに難儀し、日数を要した。
第五章では、
時間はもはや流れるものではなく、単調で変化しないものになり、その結果、
第五章・第一節のタイトル「永遠のスープと突然の光明」が示すように、
正午の食事に出てくるスープは「永遠のスープ」に思えてくる。

そんな中、ある日の夕暮れに、
ハンス・カストルプの教育係を自任するセテムブリーニが現れ、
死に対して健康で高尚で、その上、宗教的である唯一の見方とは、
「死を生の一部分、その付属品、その神聖な条件と考えたり感じたりすること」
だとした上で、こう述べるのだった。

死を精神的になんらかの形で生から切り離したり、生に対立させ、忌まわしくも死と生を対立させるというようなことがあってはならないのです。(419頁)
病気を礼賛するハンス・カストルプに対し、
それは人間のイデーを汚す陰気な気紛れだとし、
こんごともそういうあなたの練習や実験にお手伝いしたり、またあなたが危険な見方に片寄る危険のあるときは、あなたに干渉してその矯正に努めることをお許し願えましょうか。(421頁)
とまで言った。
【蛇足】
三島由紀夫,北杜夫,辻邦生,吉行淳之介,大江健三郎,大西巨人,平野啓一郎など、
トーマス・マンから影響を受けた作家は多いが、
『魔の山』を読んでいて、
「サナトリウムが舞台」ということもあって、
私は太宰治の『パンドラの匣』を思い出したのだが、
太宰治は『魔の山』に影響を受けたのではないかと思って調べてみると、
『パンドラの匣』は太宰治の知人の日記を素材にして執筆した作品だそうで、
『魔の山』とはあまり関係がなさそうだった。
もうひとつ。
死に対して健康で高尚で、その上、宗教的である唯一の見方とは、
「死を生の一部分、その付属品、その神聖な条件と考えたり感じたりすること」
という箇所を読んで、
村上春樹の『ノルウェイの森』にも同じような主旨の一文があったことを思い出した。
調べてみると、『ノルウェイの森』は、
『魔の山』を下敷きにして書かれた小説である(らしい)ことが判った。
私は『ノルウェイの森』を二度読んでいて、
一度目は『ノルウェイの森』が刊行された1987年、
二度目は、映画『ノルウェイの森』が公開された2010年。(映画レビューはコチラから)

『魔の山』も『ノルウェイの森』も、サナトリウム、療養所が重要な舞台になっていること、
どちらの作品にも、肉体だけではなく精神をも病んだ人物が登場することなど、
共通点が多いことを思い出したし、
『ノルウェイの森』の主人公の「僕」が『魔の山』を読んでいる描写が何度もあったことも思い出した。

『ノルウェイの森』をまた読む機会があったら、熟読し、
『魔の山』と『ノルウェイの森』の関係性も論じてみたいと思う。
『ノルウェイの森』を最初に読んだ当時は、
帯にあった「100パーセントの恋愛小説!!」というキャッチコピーに惑わされ、
恋愛小説として読んだのだが、
『ノルウェイの森』は村上春樹にとっての『魔の山』だったのだ。(ビックリ)
そう思って『ノルウェイの森』を再々読したら、
今度は前2回とは違った読み方ができるに違いない。

ハンス・カストルプは、ショーシャ夫人への恋慕を募らせ、発熱を繰り返すようになる。
そんなハンス・カストルプに、セテムブリーニは、
理性の世界、ヨーロッパ側の世界につなぎとめようとする。
「進歩促進国際連盟」で活動しているというセテムブリーニは、
魔女キルケーの虜になったオデュッセウスをふまえて、
この泥沼、この魔女に島からお逃げください。(513頁)
と警告する。
11月初旬、ハンス・カストルプの関心は解剖学や生理学へ向かい、
高価な学術書を注文して取り寄せ、
「生命とは何か」と問い始める。
そして次のような考えに行き着く。
生命とはいったい何であったか。それは熱だった。形態を維持しながらたえずその形態を変える不安定なものが作り出す熱、きわめて複雑にしてしかも精巧な構成を有する蛋白分子が、同一の状態を保持できないほど不断に分解し更新する過程に伴う物質熱である。生命とは、本来存在しえないものの存在、すなわち、崩壊と新生が交錯する熱課程の中にあってのみ、しかも甘美に痛ましく、辛うじて存在の点上に均衡を保っている存在なのだ。生命は物質でも精神でもない。物質と精神の中間にあって、瀑布にかかる虹のような、また炎のような、物質から生れた一現象である。生命は物質ではないが、しかし快感や嫌悪を感じさせるほど官能的なもので、だから、自分自身を感じうるほどまでに敏感になった物質の淫蕩な姿、存在の淫らな形式である。(572~573頁)
こうした「生命の像」こそがショーシャ夫人であり、
「存在の淫らな形式」が病気のことなのだと理解するようになる。
主人公の滞在から7ヶ月が過ぎた1908年3月3日、
謝肉祭の火曜日にベルクホーフで盛大な宴が催される。
第五章・第九節の「ワルプルギスの夜」は、

無論、ゲーテの『ファウスト』の「ワルプルギスの夜」に依拠しており、
お祭り騒ぎの中で、クラウディア・ショーシャは、艶めかしい大胆な服と、紙の三角帽子で、
ハンス・カストルプを魅了する。
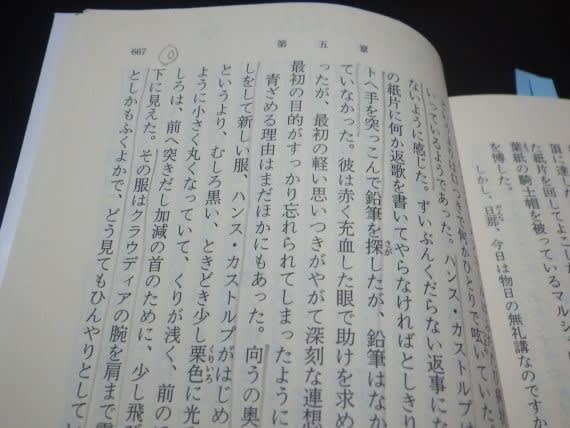
その服はクラウディアの腕を肩まで露出させていたが、その腕はすんなりとしかもふくよかで、どう見てもひんやりとしているらしく、黒い絹地の服から抜けでるように白く際立っていた。(667~668頁)
ハンス・カストルプは、ショーシャ夫人のこの白い腕(肩)に魅了されるのだが、
同じようにある夫人の白い肩に魅了された青年を知っている。
それは、バルザックの小説『谷間のゆり』の主人公・フェリックスだ。
青年貴族フェリックスが、モールソーフ伯爵夫人(アンリエート)と出逢うシーンで、
彼がアンリエートに一目惚れするのが「肩」であったのだ。
一人の婦人が、わたしの貧弱な体格を感ちがいして、母親の気のむくのを待ちくたびれて眠りかけている子供とでも思い、巣に舞いおりる親鳥のような仕ぐさで、わたしのそばに腰をおろした。たちまち、わたしは自分の魂のなかに輝いた女のにおいを感じた。ちょうど、その後、東方の詩美が輝いたように。わたしは隣に坐った女を見つめ、祝典に眩惑された以上にこの女に眩惑された。この女がわたしの全祝典になった。わたしの以前の生活をよく理解されたら、あなたはわたしの心のなかにわきおこった感情を察してくれるでしょう。わたしの目は、たちまち、丸やかな白い肩にひきつけられ、その上をころげまわりたい気がした。かすかにばら色をおびたその肩は、まるで初めてむきだしになったかのように、赤らむかのかと思われた。そのしとやかな肩は、魂を持っており、しゅすのような皮膚は、光を受けて絹織物のように輝いていた。その肩は一本の線によって分けられ、私の視線は、手よりも大胆に、その線にそって流れた。
(中略)
だれにも見られていないことを確かめたあとで、わたしはまるで母の乳房にとびつく小児のように、その背によりかかり、頭をくねらせながら肩一面に接吻した。(旺文社文庫/石川湧訳)


かように女性の肩は魅力的なのだ。(コラコラ)
セテムブリーニは、『ファウスト』を引用しながら、アダムの最初の妻で、中世に魔女とみなされた「リートリ」に気をつけるようハンス・カストルプに注意を促すが、
ハンス・カストルプはセテムブリーニの制止を振り切るようにショーシャ夫人のもとに行ってしまう。
ベーレンス顧問官は余興で、目をつぶったまま名刺の裏に仔豚の絵を描くという芸を披露し、喝采を浴びる。
ハンス・カストルプは自分もやってみようと、鉛筆を貸してくれる人を探す。
ここで、少年時代にヒッペに鉛筆を借りたエピソードが繰り返されるのだ。
セテムブリーニの制止を振り切ってショーシャ夫人のもとに行ったハンス・カストルプは、
彼女と一緒に、ドイツ語とフランス語を織り交ぜながら、様々なことを語り合う。
そして、ついに、ハンス・カストルプは、自分の愛情を告白し、
肉体と愛と死はひとつだと言う。
ショーシャ夫人は、部屋に戻る際、
「私ノ鉛筆、忘レナイデ返シニキテネ」(706頁)
と、かつてヒッペが言った同じ言葉を言って去っていく。
ハンス・カストルプとショーシャ夫人の、ドイツ語とフランス語でのやりとりは、
読者の方がドキドキするような展開で、ラストの一言も見事。
こうして第五章は終わるのだが、
これほど面白い展開になるとは思っていなかった。

『魔の山』は、
第一章~第五章までを前半部(上巻)、
第六章・第七章を後半部(下巻)となっており、
今回の第五章で、上巻を読了したことになる。
でも『魔の山』全体としては、まだ半分しか読んでいないことになる。
山で言えば、やっと五合目といったところ。
「海抜0メートルから登る富士山」で言ったら、
やっと五合目登山口に着いたところである。
気を引き締めて、これから登頂を目指したいと思う。
















