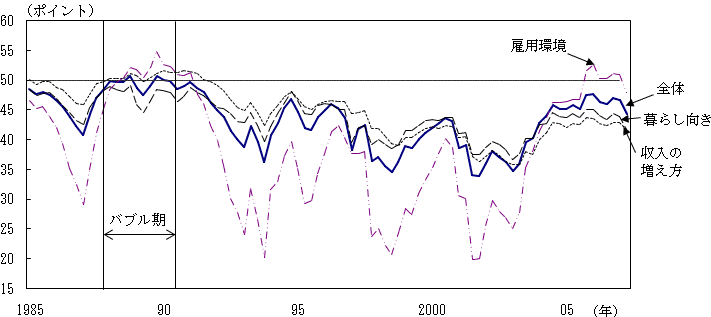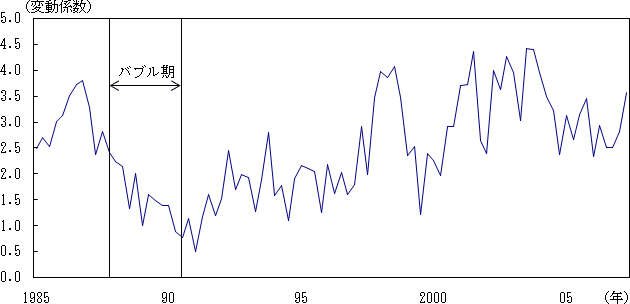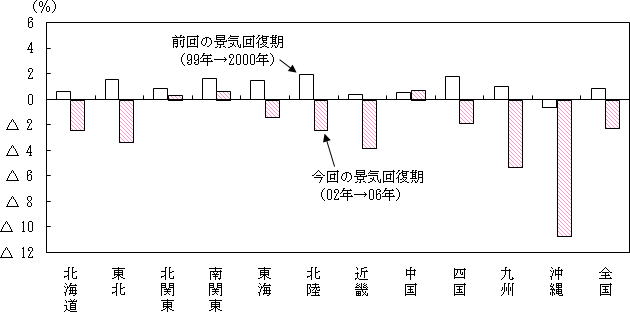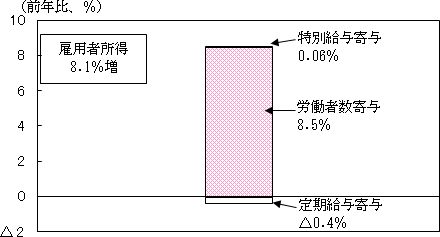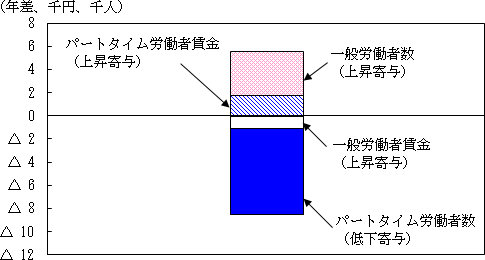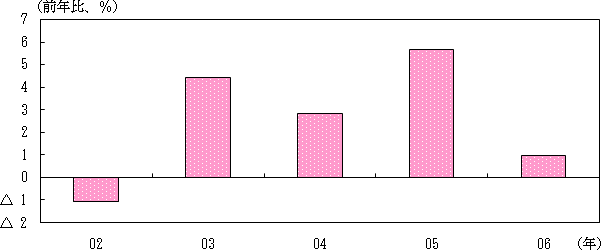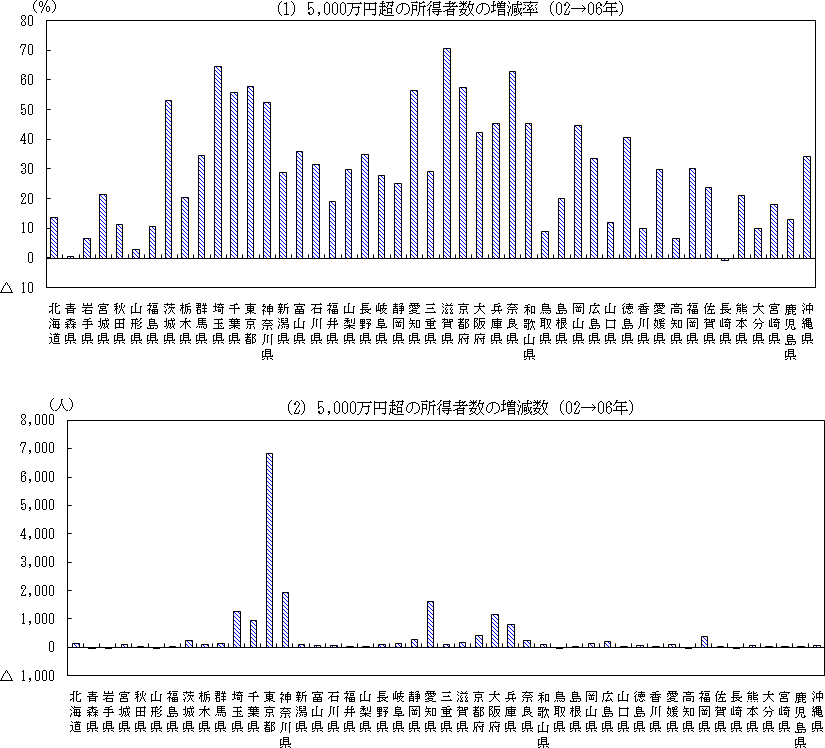中央大学教授 宮本太郎さん
2018/10/17
日本は「2040年」を越えることができるであろうか。これまで団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年が越えるべき峠とされてきた。
だが、気が付くと2025年は目前であり、その先に2040年という、より高い峰が控えていることが見えてきたのである。
2040年とはどのような年なのか。それは、日本がこれまで対処を怠ってきた二つの不均衡が極限に達する年である。
第一に、世代間の不均衡が著しい水準に達する。2040年に、日本の人口は約1億1000万人になり、1.5人の現役世代(生産年齢人口)が1人の高齢世代を支えるかたちになる(国立社会保障・人口問題研究所、2017年推計、出生率・死亡率中位仮定、以下同じ)。
現役世代と高齢世代の数が接近することはしばしば肩車にたとえられるが、私にはそれは楽観的にすぎる比喩に思える。高齢世代のあり方が大きく変化するからだ。
2040年には85歳以上人口が高齢人口の3割近くになり、高齢世代がさらに高齢化する。また、就職氷河期に安定した雇用を得ることができなかった世代がそのまま高齢となり、高齢世代の困窮化もすすむ。そして高齢世帯のなかで単独世帯が4割を超え、高齢世代の孤立化が進行する。
これをどう支えるかだが、2015年から2040年までに現役世代の人口は約1750万人減少する。これまで現役世代の減少は、女性の就業率上昇などでカバーされてきたが、今後は楽観できない。現役世代の中でも不安定雇用層が増大し、生活に困窮するばかりか、企業内の教育・訓練の対象からも外れ、労働生産性という点でも力を発揮できない。
高齢化・困窮化・孤立化で高齢世代が「重み」を増すなか、高齢者を支える側と目される現役世代が数の上でも生産性でも弱体化する。これは肩車というより重量挙げの社会である。
第二に、東京圏と地方の人口不均衡が限界に達する。地方では2040年には高齢人口も減り始め、2025年よりも高齢者が減少する県が21に及ぶ(国立社会保障・人口問題研究所、日本の地域別将来推計人口、2018年推計、以下同じ)。だが、地方における現役世代の減少と流出はそれ以上に進む。
以前、日本創成会議が、出産年齢の女性が2010年から2040年の間に5割以上減少する自治体を消滅可能性自治体と呼び、その数が896に達すると発表して衝撃を呼んだことは記憶に新しい。
これに対して、東京都の人口は、2040年にいたっても1376万人と2015年の1351万人を上回る。現役世代の流入によるところが大きいが、東京は子どもを産み育てることが最も困難な都市で、出生率は最も低い。そこに人口移動による、人口の社会増が集中することになる。なかでも膨らむのが高齢人口で2015年から90万人以上増える。私はこれを「漏斗(ろうと)化」と呼んでいる。
漏斗の斜面を下って地方から東京に現役世代が集まる。一見すると漏斗の底つまり東京では人口規模は維持されているように見える。しかし実は漏斗の底に穴が空いている。つまり、出生率は最低であり後期高齢者も多いことから、地方から東京への人口移動を差し引けば、人口減少は確実に進行していくのである。
世代間の不均衡と東京圏と地方間の不均衡が極大化し、「重量挙げ化」と「漏斗化」が絡み合って進む2040年に、私たちはどう対処するべきなのか。
2018年5月、経済財政諮問会議に厚生労働省などから提出された資料では、2040年の社会保障給付の総額は、190兆円で、121兆円であった2018年の1.6倍になる。内訳は、介護が2.4倍、医療が1.7倍になっている。年金についてはマクロ経済スライドで抑制されるために1.3倍にとどまる。想定されるGDP(国内総生産)に対する社会保障支出の比率(ベースラインケース)は24%になる。
実は、この社会保障支出それ自体は驚愕するような規模ではない。北欧諸国を見れば分かるが、GDP比で25%を超える社会保障支出をおこないながら、日本よりも高い経済成長率を実現してきた国はいくつかある。
問題は、80兆円ほど必要になる国と地方の税負担分を確保できるかということと、仮に確保できたとしても、これまでの社会保障支出の枠組を維持したままで、「重量挙げ化」と「漏斗化」の進展に対処しきれるかということである。
この二つの問題は深く関連している。現役世代(主な納税世代)が支える力を発揮できるような支援が必要であるのに、税の還元感がおよそ乏しく、富裕層から困窮層への再分配も機能しないために、さらなる負担増への合意が困難になるのである。
したがって、社会保障支出のプライオリティを見直し、納税者の納得感と担税力を高めつつ、2040年に備えなければならない。では、どこから手をつけるべきか。
第一に、東京圏でも地方でも、現役世代の支える力を高める支援にもっと力を割くべきである。とくに良質な就学前教育(保育と幼児教育)は、子どもたちが、たとえ困窮した世帯に産まれても生涯にわたって力を発揮する条件を提供する。また保育の質は、母親が働くことを選択する上での分岐点ともなる。
政府は待機児童解消を掲げるが、多くの自治体は、子どもはもうすぐ減り始めるからという判断で、保育の質を犠牲にしがちである。だが、「重量挙げ化」に対処するためには、子どもの力を高め、より多くの母親の就労につながる保育の質が重要なのだ。
第二に、高齢世代が地域で力を発揮する条件を広げることである。「生涯現役社会」もまたお馴染みのスローガンだが、在職老齢年金を受け取りながら地域で多様な仕事に就くことができれば、70歳以上も地域でのつながりを保てる。いわば「年金兼業型労働」(堺屋太一)である。
高齢者が介護に関わる「積極的老老介護」もあろうし、高齢者が子どもと触れあいを広げる「幼老」型の施設も生まれている。年金受給者の就労意欲を高めるために、在職老齢年金が減額される所得基準の見直しを進めつつ、地域で高齢者の活躍の場を広げていくことが大事だ。
第三に、居住を支援していく施策の重要性である。高齢世代であれ現役世代であれ、住むところさえ確保できれば生活は安定する。ところが、全国で空き家率が13%を超えているのに、高齢者や母子世帯に家を貸すリスクを懸念する家主は多い。国土交通省は、こうした人々にも積極的に家を貸し出す家主を登録し、改修の補助金などを出す仕組みをスタートさせたが、登録数は必ずしも増えていない。
地方では、駅前などの利便性の高い地域に、こうした登録住宅を集中させ、介護や見守りのサービスとつなげること、さらには保育の場なども併設してサービスの担い手が働きやすい環境をつくっていくことが有効であろう。いわば居住・福祉・就労が連携するコンパクトシティづくりである。
また、ヨーロッパでは、低所得層への家賃補助である住宅手当が社会保障給付として給付されているところが多い。とくに、現役世代であれ、高齢世代であれ、家賃支出が生活を圧迫する東京圏では、住宅手当は有効な施策となる。
2040年を越えることができれば、この国と地域の持続可能性は大きく高まる。だがそのためこそ、2040年に私たちが直面する課題を直視し、社会保障、雇用、住宅、まちづくりを横断する政策論議をすすめることが必要だ。
みやもと・たろう 1958年、東京都生まれ。中央大法卒、同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。立命館大学法学部助教授、北海道大学法学部教授を経て、中央大学法学部教授。社会保障審議会委員。近著に『共生保障 「支え合い」の戦略』(岩波新書)。
(写真:AFP/アフロ)