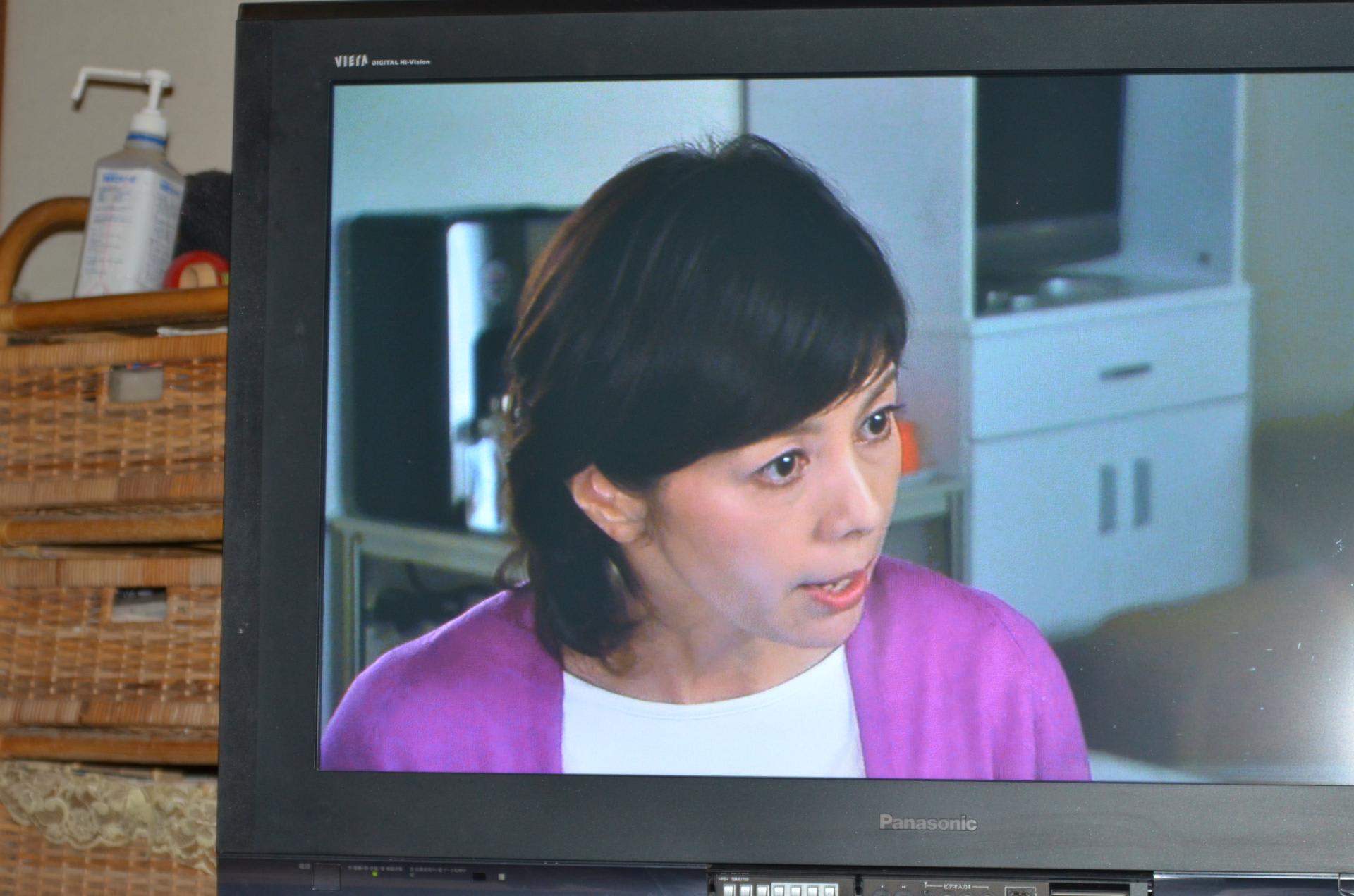
ある日、3通の郵便物。一つは、雛屋の請求書。もう一つは、娘宛のセールスのはがき。もう一つは、吉岡桂子という女性からの私宛のはがき。はて?誰だったかとと思ったら、後ろに「朝日新聞東京本社編集委員」とある。思い出した。先年の終わり、「ザ・コラム」という欄に自分の父親と農業について書いた記者である。
読まなかった人のためにかいつまんで中身を紹介する。彼女の父親は兼業農家であった。定年退職した後も山間の村で細々とコメつくりをしている。年末が近づいたある日、恒例になっている餅つきの日程を電話で聞く。そこで「やめたんよ、イネ」と母親から「衝撃的な」返事を聞くのである。そこから、彼女なりの農業の未来を考えようとする。「考えようとする」のであって、考えて結論に至っているわけではない。その素直な態度は好感が持てる。
これまで農業について発言してきた原 真人という朝日の編集委員は小農を敵としてきた。「小さな農家に補助金をやるから大きな農家が育たない。こいつらは蛆虫だ。大きな農家を育てれば、もっとコメは安くなり、国際競争にも勝てる。…日本は貿易国家だ。コメなんかに足を取られてTTp参加を迷うな」であった。アベノミクスそのものである。読売、サンケイと寸分も違わない。
吉岡委員も朝日のこれまでの主張の影響は受けている。『農業を守ることが「お荷物」になり、強みの工業分野で攻めきれなかった通商交渉の観点からすれば「ようやく」だろう。中途半端な兼業は、専業に臨む農家の足を引っ張ってきた面もある』と中段で述べている。たぶん、これまでの編集委員の聞きかじりだと思う?
ところが、父親のやっている山間の農地(日本の大半を占めている)は借りる人もなく、借りても引き合う農業がない。父親は補助金があるからコメつくりを続けてきたわけではない。引き合っても引き合わなくてもやめるわけにはいかないと頑張ってきた。しかも農家には「餅つき」のような、都会人が忘れ果てた人間らしい暮らしがあることをうっすらと知っている。都会生活の中で経済合理主義に思想の軸足は移っているが、「ふるさとが山に消えていく」のは、心のどこかで許せないないのだ。そこで、小さな農家の行く末を「考え続けるしかない」と決意する・・・。
「農家の二世までは農から完全には離れられない」というのが私の恩師、福岡大学の永尾誠之助教授の卓見である。81歳になる吉岡さんの父の存在が、朝日新聞の他の「へぼ」編集委員との差になっている。
これまで私の意見に返事を返してきた朝日新聞の人間はいない。素直な、その気持ちを忘れずに「小さな農家の行く末」考え続けてほしいと願っている。
「素直といえばこの人~科捜研の沢口靖子さん」




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます