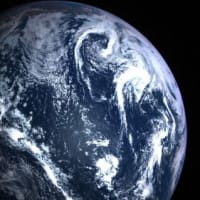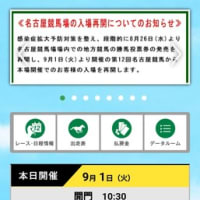昔といえるほど昔ではないが、あの頃の街には臭いがした。
それは決して心地好いものではなかったが、ある種の好奇心を掻き立てるような独特の陰影と胡散臭さを潜ませていた。
それは時間と共にだんだんと色褪せていく記憶がそう思わせるのだろうか。
都心は、いまや清潔感とまばゆいばかりの光に溢れ、まるで快適なエンターテイメントの中。
無味無臭、あるいは意図的に作り出された香りに満ちた豪華な癒しの空間。
どこかの誰かの計算されつくした明確な意志。
完成された夢。
逃げも隠れもできない。
行き場を失った人の心は、危うげな動機へと惹かれていくだろう。