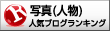ラバウル隊はラエ基地からポートモレスビーへ侵攻し、華々しい成果を挙げていた1942年6月の頃、ソロモン諸島のガダルカナル島では日本の海軍の設営隊が未開のジャングルを切り開いて飛行場を作ろうとしていた。南太平洋に睨みを利かしアメリカとオーストラリアの連絡網を切断するのが目的である。ガダルカナルに飛行場ができればラバウルの飛行機は移行される予定である。やっとのことで滑走路が完成したとき、米軍による総攻撃を受けて奪われたのである。後にこの名もなき小さな島が太平洋戦争で最大の激戦地となる。昭和17年8月7日がガダルカナル戦の運命の日なのであるが、期せずしてラバウル航空隊の精鋭メンバーはラエからラバウルに呼び戻されていた。そしてガダルカナルが奪われるとともにラバウル航空隊はガダルカナルの敵輸送船団を攻撃することとなった。ガダルカナルの飛行場が完成した直後、アメリカ軍は設営隊を全滅させた。設営隊約2000人は兵士でも何でもなく、単なる土木作業員であったため武器などほとんど使えなかったことが全滅につながった。大本営は敵の調査もせずに900人の陸軍兵を送り込んだ。このときの指揮官は一木大佐で、突撃前夜は勝ち戦の気分であったという。ところが、米軍海兵隊は11000を超える兵士がいた。結果は、最初の夜襲で一木支隊は全滅、海兵隊の火砲にあっけなく惨敗する。この時の生存者は数十名しかおらず、もちろん一木清直支隊長は軍旗を焼いて自決するのである。1942年8月21日のことであるから、ガダルカナル開戦の僅か二週間後のことである。ここで重要なことは、1942年8月7日に始まったガダルカナル戦が終結したのは1943年2月7日であるから、何と6ヶ月に渡って一木隊のような敗北を繰り返した末、22000以上の戦死者を出したことである。その戦略の無さのために太平洋戦争最悪の戦いとなったのである。
一方、開戦の翌日に制空隊として選ばれたのは、笹井惇一・坂井三郎・西澤廣義・太田敏夫をはじめとするラバウルの猛者たちである。17機の零戦と9機の九九式艦上爆撃機はガダルカナルに向けて飛び立った。ところで、ラバウルからガダルカナルまでの距離は約1000km、に対して零戦21型の巡航距離は3300kmである。しかも30分間の戦闘を行った場合は2500kmとなる。つまり往復がギリギリなのである。一方九九式艦上爆撃機はというと、巡航距離は1400kmであるから片道切符での出撃である。従って輸送船団攻撃の後は予定海域に不時着して飛行艇の救助を待つこととなるのである。当時ソロモン諸島海域に投入された飛行艇は川西航空機の二式大型飛行艇で、運用開始は1942年2月であるからデビューしたばかりといってよい。レシプロエンジン4発装備の飛行艇としては当時世界最高の性能を誇っていた。搭載可能な爆弾は2トン、巡航距離は7000kmを超えた。これが第一次ソロモン海戦である。
空中ではラバウル航空隊が善戦する中(追って詳述予定)、当夜海上では三川軍一司令官率いる第8艦隊が夜襲によるアメリカ巡洋艦撃破をしたのであるが、輸送船団を追わずに撤収している。これは真珠湾攻撃における第3次戦闘を実施しなかったのと同じ(皮肉なことに真珠湾攻撃でタンクや各種施設の破壊を提案したのは三川軍一である)で、ガダルカナル陸上戦でのアメリカ軍に豊富な武器と食料を供給し優位に戦わせたことに繋がったことはゆうまでもない。三川艦隊撤収の理由は、「夜が明ければ、サラトガ・エンタープライズなどの空母から発艦したグラマン戦闘機に狙い撃ちにされる」というものである。しかしこの弱気の作戦は裏目となる。前日のラバウル航空隊の善戦によりアメリカ空母のグラマン戦闘機はかなりダメージを受けており、当日再びやってくるラバウル航空隊と第8艦隊の砲撃に協調性があったなら、ソロモン対戦の戦局は大きく変わっているし、ガダルカナル島内での戦いもアメリカ海兵隊の物資不足で相当違っていたはずなのである。こうしたことを考えると三川軍一司令官の撤退判断ミスには大きな責任がある。歴史的には第一次ソロモン海戦は日本が勝利したことになっているが、大きな間違いである。こういう場合私はついつい敗戦後の三川軍一司令官を調べてしまうのであるが、三川は93歳まで生きた。
二式飛行艇を紹介したいところですが残念ながら未作成につき、零式水上観測機を紹介します。日本海軍最後の水上複葉機式偵察機でもあり太平洋戦争初期には艦隊とともに水上基地に配属されて対潜攻撃を行ったほか、後方旋回式7.7mm機銃を備えていることから、戦闘機として空中戦を繰り広げたこともあり抜群の性能を発揮した。三菱重工が水上機を手がけてこれだけの名機を作り上げたのはめずらしい。因みに複葉機は案外空中戦が得意なのである。