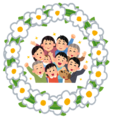住宅ローンを完済した際に、抵当権抹消登記が必要なことをご存知ですか?
そもそも、住宅ローンを借りた際に、自宅には抵当権設定登記がされています。
例えば、マイホームを購入したときに、売買代金を支払うと所有権の登記と一緒に
金融機関の抵当権設定登記が行われています。
少し専門的な説明をすれば
1.所有権移転登記(年月日売買を原因として所有者を買主名義とする登記)
2.抵当権設定登記(金融機関を抵当権者とする登記)
のような登記が行われています。
そして、数十年後に住宅ローンが完済したとき、この抵当権設定登記がどうなるのか
というのが今日の話題です。
結論からすると、住宅ローンが完済したとしても、所有者が何もしなければ抵当権の登記は
そのままです。
完済したら自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありませんし、銀行が抹消登記
手続をしてくれるわけでもありません。
所有者自ら抵当権抹消登記手続きをしない限り、抵当権の登記はそのままです。
金融機関から完済時にいろいろな書類が渡されたと思います。
・借入時の契約書(金銭消費貸借契約書)
・抵当権設定契約書
・保証契約書
・オプションの契約書
・各種個人情報の同意書の控え などなど
その中に、抵当権抹消登記に使用する書類も入っています。
・解除証書(名称はいろいろです。抵当権設定契約書と一体化している場合もあります)
・銀行からの委任状
・登記識別情報もしくは登記済証(抵当権設定契約書に登記所のハンコが押されているもの)
などです。
そして、抵当権を抹消するにはこれらの抵当権抹消登記に必要な書類とともに、
抵当権抹消登記の登記申請書を作成して登記所に提出する必要があります。
登記申請書は、そのひな型が登記所のホームページに掲載されています。
それを利用すると作成しやすいです。
とはいえ、銀行や登記所が代わりに作成してくれることはないので、必ず所有者が作成することになります。
また、登記申請の際は、登録免許税といって印紙を貼る必要があります。
登録免許税は不動産1個につき1000円です。
不動産の数え方は登記簿毎となります。
例えば、戸建ての場合、少なくとも土地1個・建物1個なので不動産の数は2個=2,000円です。
マンションの場合も基本的な考え方は同じですが、土地が複数の場合も多いです。
抵当権設定契約書の「不動産の表示」「物件の表示」と記載されている中で
「敷地権の表示」と書かれている部分の不動産の数を数えてください。
登記申請に期間の制限はありません。
とはいえ、銀行からの委任状に記載されている代表取締役が代わってしまったりすると
手続としてはやや面倒です。
また、銀行の名称が変わったり、合併などをしていた場合も面倒になります。
なので、早めの登記手続きをお勧めします。
また、ご自身の現在の住所やお名前が登記上の記載と異なっている場合、
例えば、登記上の住所が引越前の住所になっているような場合は、抵当権登記申請前(同時でも可)に
住所の変更登記が必要です。
最後は少し細かいお話にもなってしまいましたが、いずれにしても、住宅ローン完済後には
抵当権抹消登記が必要であるということを覚えておいていただくとよろしいかと思います。
そもそも、住宅ローンを借りた際に、自宅には抵当権設定登記がされています。
例えば、マイホームを購入したときに、売買代金を支払うと所有権の登記と一緒に
金融機関の抵当権設定登記が行われています。
少し専門的な説明をすれば
1.所有権移転登記(年月日売買を原因として所有者を買主名義とする登記)
2.抵当権設定登記(金融機関を抵当権者とする登記)
のような登記が行われています。
そして、数十年後に住宅ローンが完済したとき、この抵当権設定登記がどうなるのか
というのが今日の話題です。
結論からすると、住宅ローンが完済したとしても、所有者が何もしなければ抵当権の登記は
そのままです。
完済したら自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありませんし、銀行が抹消登記
手続をしてくれるわけでもありません。
所有者自ら抵当権抹消登記手続きをしない限り、抵当権の登記はそのままです。
金融機関から完済時にいろいろな書類が渡されたと思います。
・借入時の契約書(金銭消費貸借契約書)
・抵当権設定契約書
・保証契約書
・オプションの契約書
・各種個人情報の同意書の控え などなど
その中に、抵当権抹消登記に使用する書類も入っています。
・解除証書(名称はいろいろです。抵当権設定契約書と一体化している場合もあります)
・銀行からの委任状
・登記識別情報もしくは登記済証(抵当権設定契約書に登記所のハンコが押されているもの)
などです。
そして、抵当権を抹消するにはこれらの抵当権抹消登記に必要な書類とともに、
抵当権抹消登記の登記申請書を作成して登記所に提出する必要があります。
登記申請書は、そのひな型が登記所のホームページに掲載されています。
それを利用すると作成しやすいです。
とはいえ、銀行や登記所が代わりに作成してくれることはないので、必ず所有者が作成することになります。
また、登記申請の際は、登録免許税といって印紙を貼る必要があります。
登録免許税は不動産1個につき1000円です。
不動産の数え方は登記簿毎となります。
例えば、戸建ての場合、少なくとも土地1個・建物1個なので不動産の数は2個=2,000円です。
マンションの場合も基本的な考え方は同じですが、土地が複数の場合も多いです。
抵当権設定契約書の「不動産の表示」「物件の表示」と記載されている中で
「敷地権の表示」と書かれている部分の不動産の数を数えてください。
登記申請に期間の制限はありません。
とはいえ、銀行からの委任状に記載されている代表取締役が代わってしまったりすると
手続としてはやや面倒です。
また、銀行の名称が変わったり、合併などをしていた場合も面倒になります。
なので、早めの登記手続きをお勧めします。
また、ご自身の現在の住所やお名前が登記上の記載と異なっている場合、
例えば、登記上の住所が引越前の住所になっているような場合は、抵当権登記申請前(同時でも可)に
住所の変更登記が必要です。
最後は少し細かいお話にもなってしまいましたが、いずれにしても、住宅ローン完済後には
抵当権抹消登記が必要であるということを覚えておいていただくとよろしいかと思います。