
(その1からの続き)
【古代ローマ(所有と自由)】
負債が導入したモラル上の混乱が、どれだけ根深くわたしたちの思考の伝統を形成しているのか、プラトンの著作がそれを証言してくれているとしたら、そのモラル上の混乱が、どれほど根強くわたしたちになじみの制度さえも形成しているのか、ローマ法が明らかにしてくれている。
ドイツの法学者ルドルフ・フォン・イェーリングが、ローマ帝国は(1度はその軍隊によって、2度目はその宗教によって、3度目はその法律によって)3度世界を征服した、と述べたことは有名である。ローマ法が法的・憲法的秩序の言語と概念的土台を提供しているのは、あらゆる場所においてである。法学部の学生は、南アフリカからペルーに至るまで、ラテン語で専門用語を暗記することに長時間費やすことになっている。ローマ法が、契約、義務、不法行為、財産、司法権について、そしてより広い意味では、政治的生活もまた基礎を置いている、シチズンシップ、諸権利、自由について、わたしたちの基本的な考え方のほとんどを提供しているのだ。
ローマ法において、所有すなわちドミニウムとは、人が物に対して持つ絶対的権力によって特徴付けられる「人と物の関係」である。
生命を持たない物体と人間が「関係」を持つことがどういうことか、はっきりしない。人間どうしは関係を持つことができる。だが、その関係は常に相互的なものだ。では、物と「関係」を持つとは、いったいどういうことか?仮に関係を持つとして、その関係に法的な地位を与えることはなにを意味するのか?
所有とは人と物の関係などではないことは明らかである。それは、物に関する人びとの間の了解あるいは取り決めなのである。ときに、わたしたちがこのことに気付かないことがあるとしたら、その理由はただひとつ。多くの事例において――特に自分の靴、車、電動工具に対する権利を想定するさいには――わたしたちは、イングランドの法律の表現でいえば「全世界に対抗して」保持された権利を念頭においているからである。わたしとこの地球上のそれ以外のすべての人間の間で共有された了解であり、それによれば、わたしの所有物に対してわたし以外の万人は干渉しないであろうし、それゆえわたしは自分の所有物を多かれ少なかれ意のままに扱うことが認められるのである。
しかし、ひとりの人間と地球上のそれ以外の全員の間の関係を、それそのものとして把握することはむずかしい。物との関係として考える方がずっと簡単なのである。
だとしても、実際にはこの意のままにふるまう自由なるものが、きわめて限定されたものであることは明らかである。わたしのチェーンソーに関する権利において唯一「絶対的」なのは、ほかのだれかがそれを使用することを妨げるわたしの権利のみである。
それにもかかわらずローマ法は、所有の基本的な形式は私的所有であり、私的所有とは所有者がその所有物でもって欲することはなんでもできる絶対的権能である、と主張しているのである。こんなことを財産法の基盤にした伝統はローマ法以外にはないのである。なぜなら、それをしてしまうと、ほとんどすべての実際の法規は例外の連鎖になってしまうからである。権利上は好きに扱っていいとしても事実上はそうはいかない、という実態により、例外規定が無数に発生せざるを得なくなる。
どうしてこんなことになったのか?最も説得力のある説明は、オルランド・パターソンのものだ。それによれば、絶対的私的所有という観念は奴隷制に由来している。つまり、所有を人間どうしの間の関係ではなく人間と物の間の関係として想像するには、どちらか一方が物であるような2人の人間どうしの関係を出発点とすればよい。こうしてみれば絶対的権能の強調の意味も理解できる。
“主人はその奴隷に対して絶対的権能を持つ。人とその所有物との関係を、主人とその奴隷という人間どうしの関係として見れば理解できるということか。”
(絶対的私的所有を意味する)dominium[ドミニウム]について、この語は「主人」や「奴隷所有者」を意味するdominusから派生しているが、そのさらなる源泉は「家」や「世帯」を意味するdomusである。
この語はもちろん英語のdomesticに関係しており、それは現在でも「私生活に付随すること」を意味すると同時に、家を掃除する使用人をも指している。
domusの意味はfamilia、つまりfamilyと重なり合うとはいえ、familia自体の究極的な語源は「奴隷」を意味するfamulusなのである。家族とはもともとは1人のpaterfamilias[家父]の家族的権威のもとにあるすべての人間のことであり、その権利は、少なくともローマ法初期においては、絶対的なものと考えられていた。
というわけで、ドミニウムという観念を形成し、それによって絶対的私有財産の近代的原理を創造することによって、ローマの法学者たちが何よりもまず行なったのは、家庭内の権威の原理、すなわち人間に対する絶対的権能の原理を取り込み、そういった人間の一部(奴隷)を物として定義し、もともとは奴隷に対して適用されていた論理を、ガチョウや馬車や納屋や宝石箱などなどに、つまり法律が関与するすべてにまで、拡張することであった。
時間がたつにつれ、これはますます法的擬制となっていった。
ローマの奴隷制を、歴史的な観点からみてかくも奇妙なものにしているのは、2つの要因の合体である。
第1のものはそのまったくの恣意性である。たとえば、ある種の人びとは先天的に劣っているので奴隷であることを運命づけられているというような考え方は、そこには存在しなかった。その代わり、奴隷の境遇は、だれにもふりかかりうる不運とみなされていた。その結果、奴隷が自分の主人より、あらゆる面において優っているという事態も何ら不思議なものではなかった。主人が喜んでそのことを認めることすらあったかもしれない。なぜなら、純粋な権力の関係でしかないような関係性なのだから、そこにそうした奴隷の優越性は何らの影響も与えないからだ。
第2の要因は、この権力の絶対的な性質である。たいていの場合、これは抽象的原理のようなものにすぎなかった。ほとんどどこであっても、このような権利は統治権力によって迅速に制限されるのである。少なくとも皇帝や王たちは、自分のみが他者を死に至らしめる命令を下す権限をもつ唯一の存在であると主張するものである。しかし、共和政ローマには、皇帝は存在しなかった。主権的身体があるとしたら、それは奴隷主たちの集合[的身]体だったのである。
かくしてdominus[ドミヌス]と奴隷の関係は、征服の関係、絶対的政治権力の関係を世帯内に導入することとなった(実際には、それを世帯の本質にした)。どちらの側にとっても、これがモラル上の関係でなかったことを強調することは重要である。
*****
ローマの奴隷制による浸透力ある悪影響の最たるものは、ローマ法を通じて、人間の自由についてのわたしたちの観念に大混乱がもたらされたことである。
古代世界のどこにおいても、「自由」であることはなによりもまず奴隷ではないということを意味していた。奴隷であるということは、なによりも社会的紐帯およびそれを形成する能力の消滅を意味していたので、自由とは他者に対するモラル上の関与を創出し、それを維持する能力を意味していたのである。
英語の“free”は“friend”を意味するゲルマン系の語源に由来している。自由であることは、友をつくること、約束を守ること、平等な共同体のなかで生きることを意味したからである。定義上、自由であることは、それに付随するあらゆる権利や責任とともに、市民共同体に根をおろすことを意味したのだ。
しかしながら、後2世紀までには、これが変化し始める。法律家たちはlibertas[リベルタス]を、ほとんど主人の力能/権力と見分けがつかなくなるまで徐々に再定義していった。
自由とは、実力あるいは法によって妨げられないことなら、望むがままにことを行なうことのできる自然の能力のことである。奴隷とは、万民法の制度であって、自然に反して、ある人間が別の人間の所有物になることである。
中世の注釈者たちはここにひそむ問題に即座に気がついた。これは、万人が自由であるということを意味しているのではないか?つまるところ、奴隷でさえも、許可を与えられさえすれば何でもできるわけである。
“自由人は法によって、奴隷は主人によって妨げられないことなら、望むがままにことを行なうことができるのだから、自由人の自由と奴隷の自由との違いは、その程度が違うだけとなる。”
自由と奴隷であることが程度の問題にすぎないなら、論理的に、自由についてのあらゆる制限が、程度の差はあれ不自然ということにならないか?社会や社会的統制や、さらには所有権さえ、同じように不自然である、ということを含意してはいまいか?ローマの法律家の多数が結論付けたのは、まさにこれである。
ひるがえってこのことは、私有財産と政治的権力の間に本質的な差異はない、ということを意味している。少なくとも政治的権力が暴力に基づいている限り。
時間が経つにつれ、ローマの皇帝たちもまた、自らの支配権のおよぶ領域において絶対的自由を有していると主張した。同時に、ローマ社会は、共和国から、後の封建制ヨーロッパにますます接近していく形成体へと変容を見せていく。それを推進したのは、従属農民や債務使用人、そのほか、ありとあらゆる種類の奴隷に囲まれた、広大な地所を所有する実力者たちだった。
そのさい彼らは、動産奴隷制をほぼ根絶しつつも、一方では、貴族階級は正真正銘のゲルマン人征服者の子孫であり、平民は本性からして従属者であるという観念を導入したのである。
この新たな中世世界においてさえも、古いローマ時代の自由の概念は生きのびた。自由とは端的に権能のことである。自らの領地内において欲することなら何でも行なう権利であった。この権利もまた、たいてい、征服の結果にすぎないとみなされていた。
ローマ法が12世紀に復活し近代化され始めたころには、dominium[ドミニウム](絶対的私的所有を意味する)という語が特別な問題を提起するようになった。当時の一般的な教会のラテン語において、それは「領主権」と「私的所有」をともに意味するようになっていたからである。所有権が本当に絶対的権力の一形態であるならば、王あるいは一部の法律家にとっては神よりほかにそれを有し得る者が存在できるとは考えがたかったからである。
“グレーバーはここでこの議論を終える。「終えることが重要である」と言う。そして、「自由とは原理的にみずからの所有物についてなんでも好きなことをする権利であると考える伝統」についての話になる。終えることが、その話の理解を助けると言う。”
その伝統によれば、所有は権利とされるだけにとどまらず、権利それ自体が所有の一形式とみなされる。つまり権利とは個人が所有できるものであるという考え方にあまりになじんでいるため、それがいったい本当のところはどういうことなのか、考えることさえまれである。
実際には、ある人間の権利とは、端的に別の人間の義務である。わたしの言論の自由とは、他者がわたしの発言に関してわたしを罰しない義務のことである。
これは所有権をめぐるものとまったく同じ問題である。すなわち、世界中すべての人びとが負っている義務について考えるとしても、それをそのまま考えることはなかなか面倒である。権利と自由を「保持すること」にして考えるほうがはるかに簡単なのだ。
自由を「所有する」とはいったいなにを意味するのか。
歴史的にみれば、単純な答えがある。われらは権利と自由の自然の所有者なりと主張してきた者たちが、それでもって主要に言わんとしたのは、権利や自由も好きなように譲渡したり売却したりできねばならないということだった、というものだ。
すなわち、(自由は)売却され、交換され、貸付され、さもなければ譲渡される。そうなると、負債懲役制度あるいは奴隷制についてさえも、本質的に何ら間違ったところはないという帰結になるのである。
まもなく、似たような議論が、国家の絶対的権力を正当化するために利用されるようになった。政府とは本質的に、契約すなわちある種のビジネス協定であり、それによって市民は自発的に自らの自然権のいくぶんかを君主に譲渡するというわけである。
最終的には、類似の理念が、わたしたちの現在の経済生活をつくる基本的で支配的な制度の基盤となる。すなわち賃労働である。賃労働、それは実質的には、奴隷制が自由の売却とみなしうるように、自由の貸与なのである。
わたしたちが所有しているのは、わたしたちの自由だけではない。おなじ論理がわたしたちの身体にさえ適用されるようになると、わたしたちの身体は、そのような定式上では、家屋、車あるいは家具と実質的にはなんら変わらないものとして扱われることになる。
この観念が基礎を置く財産をめぐるローマ的伝統を考慮するならば、わたしたちがわたしたち自身を所有しているということは、奇妙なことに、わたしたち自身に主人と奴隷の役割を同時に割り当てることなのだ。「われわれ」は(財産に対して絶対的権能を行使する)所有者であると同時に(絶対的権能の対象である)所有される事物でもある。
古代ローマの世帯は、歴史のもやのうちに忘却されたどころか、わたしたち自身についての最も基本的な概念のうちに保存されている。
法学者たちが千年も費やしてローマの所有概念につじつまを合わせようとしたように、哲学者たちは何世紀もかけて、いかにしてわたしたちが自分自身に対する支配関係を持つことが可能になったのか、理解しようと努めてきた。
(しかし、)最も浸透した解決策――だれもが「精神」と呼ばれるものを有しており、それは「身体」と呼びうるものから完全に分離しており、精神は身体に対して自然な支配権をもっていると主張すること――は、現代の認知科学から得られる知見とまっこうから対立している。したがって、これが虚偽であることは明らかである。
それでもわたしたちはそれにしがみ続けているのである。それなくしては、所有、法律、自由についての日常的観念がどれひとつとしてつじつまが合わなくなってしまう、という単純な理由のためである。
【いくつかの結論】
本書の最初の4章は、ひとつのジレンマを描写している。アダム・スミス流に社会を個人の集合体として想像することと、負債こそがすべてであってあらゆる人間諸関係の実体そのものであると考えるような視点の間で身動きできなくなっているように思われるのである。
(アダム・スミス流の考え方において、)諸個人にとって唯一の意義ある関係は、自分自身の所有物との関係である。その世界において諸個人は、相互の便宜のためにある物と別の物とをうまい按配で物々交換するのであって、視界から負債はほぼ完全に姿を消している。
(負債こそすべてという考え方においては、)人間関係はいずれにしても本質的にはあくどいビジネスであり、わたしたちの相互的な責任自体がすでに必然的に罪業と犯罪にもとづいている、という(ことになる)。
続く3章で、わたしは、もうひとつの異なる視点があることを示し、どのようにしてそこにたどりついたのか説明しようと試みた。「人間経済」の概念を展開したのはそのためである。
人間経済において人間について真に重要であると考えられているのは、人間は各人が他者との関係の固有の結節体であるということである。それゆえ、だれかが何か別の事物や別の人間と等価であると考えられることは決してない。人間経済にあって貨幣は、人間を買ったり取引したりする手段ではなく、むしろ、そのような売買や取引がいかに不可能であるかを表現する方法なのである。
次にわたしは、こうした事態がどのように解体していったかについて論じた。人間が交換の対象となり得るとしたらいかにしてか。
最初はおそらく嫁として贈られた女性であり、いきつくところは戦争で捕虜とされた奴隷である。そして、こういったすべての関係に共通しているのは暴力である。人々を唯一無二の存在にしている他者(姉妹、友人、ライバル……)との関係性からなる、果てしなく複合的である網の目から彼らを剥奪し、取引可能である何かへと還元することができるのは、棍棒、綱、槍、銃による脅迫のみなのである。
こういった事態が、日常的市場も衣服、道具、食品といった平凡な日用品も存在すらしない場所で発生可能であることを強調することが肝要である。人間経済において、人間の最も重要な所有物は絶対に売買できないのであって、それは人間を売買できないのとまったく同じ理由にもとづいている。
“売買ではなく、暴力によって関係性が断たれたのだということを強調している”
人間経済では、人をその文脈から剥奪する力能が現れるとき、しばしばその力能が目的それ自体とみなされる。ある男の個別性を叩き潰すことは、別の者の評判や社会的存在感を高めるものとみなされていたのである。わたしが英雄社会と呼んできたものにおいては、この種の名誉と汚名の足し引きが周縁的な日常実践から引き上げられ、政治の本質そのものとなっている。英雄たちは他者を矮小化することによって英雄となる。
アイルランドとウェールズでは、他人を貶め、唯一無二である人間を家庭から剥奪し、匿名の計算単位――つまりアイルランドの少女奴隷通貨、ウェールズの洗濯女――へと還元する力能そのものが、それ自体、名誉の最高表現であったことをみてとることができる。
英雄社会では暴力の役割は隠されていない。それどころかむしろ賛美されている。しばしば暴力が、個人の最も親密な関係の基盤を形成することもある。
歴史の拡がりを見渡すならば、最大限に賛美される人々と最大限に貶められる人々の間の奇妙な一体感にだれもが気付くはずだ。とりわけ皇帝や王と奴隷との間のそれだ。多くの王が奴隷をはべらせ、奴隷を大臣に任命した。エジプトのマムルーク朝のように、実際に奴隷たちからなる王朝まで存在している。奴隷と犯罪者には、家族や友人などほかに忠誠を誓う対象がいないからである。しかし、ある意味で、王たちにしても実際はそうであったに違いない。
王と奴隷はたがいに映し合う鏡像なのである。普通の人間が他者への義務によって規定されているのとは異なって、彼らはともに力関係によってのみ規定されている。人間のありようとして想像しうる限り、ほとんど完璧なまでに孤立し疎外された状態にあるのが、まさに彼らなのだ。
ここでようやく、自分自身を主人であると同時に奴隷として定義するわたしたちの奇妙な習慣について、自らの自由の主人としての自己とか、自分自身の所有者として自己とか、そのような概念でもって古代の世帯の最も野蛮な側面を複製しているわたしたちの奇妙な習慣について、つまるところいったい何が問われているのかがみえてくる。これこそが、わたしたち自身を完全に孤立した存在として想像しうる唯一の方法なのである。
ローマ人の新しい自由概念から、ホッブズやロック、スミスといった自由主義哲学者による人間社会の起源についての奇妙な幻想まで、一直線につながっている。
多数の奴隷の所有者であったトマス・ジェファソンは、奴隷制のモラル上の基盤に直接に矛盾する文言によって『独立宣言』を始めることを選択した。「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与されていることを信ずる」。かくして、アフリカ人は人種的に劣っていたという議論にせよ、アフリカ人ないしその祖先は正当かつ合法的に自由を剥奪されたという議論にせよ、ともに土台から揺さぶられるのである。しかしながら、だからといってジェファソンが、権利と自由について根本的に新しい概念を提起することはなかった。後続する政治哲学者も同様である。
わたしたちにとって、最も大切な権利と自由のほとんどは、モラルおよび法の枠組み総体にとっての一連の例外である。そして、本来そのような権利や自由など存在するはずもないのだ、と、その枠組みはささやいているのである。
公式の奴隷制は撤廃されたが、(9時から5時まで労働に就いている者ならだれもが証言できるように)少なくとも一時的にあなたの自由を譲渡[疎外]することは可能である、という観念は持続している。
暴力についてならば、その大部分は視界の外に追いやられた。だがその原因は、なによりもまず、テーザー銃[スタンガンの一種]や監視カメラが恒常的に脅威を与えていなくても済む世界が存在すること、そのような仕組み/取り決めに基盤を置く世界がどのようなものなのか、わたしたちが想像すらできなくなっているところにある。
“つまり、暴力による秩序というものにどっぷりと浸り続けているうちに、もはや当たり前すぎる暴力が見えなくなってしまっていて、暴力に基盤を置くのではない社会というものを想像すらできなくなっているということか”













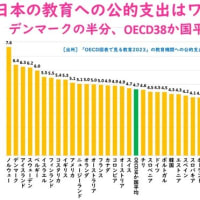



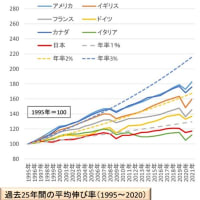


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます