内田樹さんの教育論はおもしろい。最近のブログで、連続して教育のお話をしている。でも、ときどき同意できないこともある。たとえば、3月15日にエントリーされた『教育の奇跡』というブログで、ジャック・ラカンの言葉を引用している部分である。
このジャック・ラカンの言葉について内田さんは、「これは『教える』ということについて語られたうちで、もっとも挑発的で、もっとも生産的な命題の一つだと私は思う。教えることを職業にしているすべての人間はこの命題にまっすぐに取り組んで、自分なりの解釈を下す義務があると私は思う」と評価している。
本当にそうだろうかと思う。内田さんの言葉を借りて言い直すと、「教壇のこちら側に立たされている間は(知っている者の立場に立たされている間は)(教えるべきことを知らなくても)つねに十分に知っている」ということになるのだが、難しい。
待てよ!人は赤ん坊からでも、ほかの動物からでも、そこいらに転がっている石ころからでも、彼らが教える意図がないにもかかわらず、学ぶものは学ぶ。教えられる側に知識や経験が豊富にあり、賢い人ほど、学ぶことが多いと思う。これは日常的に起きていることであり、めずらしいことでもない。そうすると、教壇に立っているのは「先生」なのだから、先生は「つねに十分に知っている」はずだという思い込みさえあればよく、先生が適当にわけのわからないことを言っていても、それがわからないとすれば、教えられる側の自分が悪いのだと思って、懸命に何とか意味付けをし、それぞれにとって有意義なものをそこから引き出すはずだということになる。なるほど、内田さんは、十分に知識や経験があり、聡明だから、ラカンが言った私にはわけのわからない言葉の内に、深いものを見付け、学んだわけだ。ということは、ラカンが偉いわけではなく、内田さんが偉いのである。ここでは、ラカンでもヤカンでもどちらでもよかったわけだ。禅問答の公案のようなものかもしれない。ラカンさんという師が、修行中の弟子に公案を与える。弟子は懸命に考える。そして見付けた答えを師に提出する。師が満足すればOKとなる。このとき、師は事前に答えを知っている必要はない。弟子に考えさせて、結果を評すればいいだけだから。
たしかに、こういうかたちで学ぶことは、教えられる側が教える側を越える可能性を与えることになる。また、これは、教える側の意図や目的から、あるいは束縛から、教えられる側が自由になり、自動的に各個性がそれぞれに学ぶ内容を決めることにもなる。そうなるとなかなか深い意味が込められていることになるかもしれない。そういう学び方ができる人はよく学び、教える側を乗り越える能力ある人は乗り越えてゆくだろう。でも、そういう学び方ができない人はどうすればよいのかという問題がある。特に初等教育においてそれでいいのかという疑問もある。したがって、内田さんが「教師であるためには一つだけ条件がある。一つだけで十分だと私は思う。それは教育制度のこの豊穣性を信じているということである」というのは言い過ぎではないかとも思う。
ところで、ラカンという人はあまり信用ができない。理由は、アラン・ソーカル/ジャン・ブリクモン共著の『「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用』という本を読んでいるからだ。その中で、ラカンの文章が引用され、批判されている。本当にまったく意味がわからない文章を書く人である。引用されている文には、数学の概念、用語が多用され、ラカンの専門である精神分析と関連付けられている。しかし、ソーカルたちは、本当にこの人は自分が使っている数学の概念、用語の意味がわかっているのか疑問を持っている。たぶんわかっていないと思っている。少しだけ引用の引用をしてみる。
この他にも、曲面の一種であるcross cap(叉帽)を cross cutと間違えたり、「私が『無理数=不合理』と言うとき、何も私はある種の測り知れない情動の状態を指しているのではなく、正確に虚数と言われているものを指しているのです」と言って、虚数と無理数を混同していたり、「ゼロが『無理数=不合理であるような微積分学』としての人生」などと、ほとんど意味不明のことを述べている。
ソーカルたちは結論のところで、「ラカンの『数学』はあまりにも荒唐無稽なので、どのような心理学的な分析にも、それがまともである限りは、役に立たない」と述べている。また、「精神分析と数学の間の彼のアナロジーは、おおよそ考えられる限り気ままなものだが、彼はそれらのアナロジーの経験的あるいは概念的正当化を金輪際与えない。(ここで挙げた例だけでなく、他のいかなるところにおいても)」とも述べている。
「ラカンを擁護する人たちが批判に対抗するときに使いたがる戦略を『でもなく・でもない』方式と呼ぶことができる。これらの著作は科学として評価されるべきでもなく、哲学として評価されるべきでもなく、詩として評価されるべきでもなく、……でもない。こうなると現世的神秘主義というほかないものにつきあわされていることになる。時が経つにつれ、ラカンの著作は、言葉遊びと断片化された統辞法をないまぜにすることで、ますます判じ物めいてきた。これは多くの聖典に共通する特性である。そしてこれらのテクストが、弟子たちによる敬虔なる教義解釈の基礎となってゆくのだ。こう見てくると、つまるところ、われわれは新たな宗教を相手にしているのではないかと疑っていいようだ」と結んでいる。
知る人ぞ知るルイ・アルチュセールは「ラカンがフロイトの思想に、その思想が要請する科学的な諸概念をついに賦与したということを認めさえすればよい」と、ラカンを擁護している。何だか意味はよくわからないが、科学的な用語を自身の論文の中に散りばめたということを評価すべきで、その意味などわからなくてもよいということか。
少しだけ引用と言いながらずいぶん引用してしまったが、この本では、この他にクリスティバ、イリガライ、ボードリヤール、ドゥルーズ、ガダリなど、ポストモダン派として、難解な文章を書くことで評判になっている人たちの著作を検証し、彼、彼女たちは、自分自身が未消化であるにもかかわらず、現代科学の概念、用語の皮相な博識ぶりを誇示し、科学に疎い読者を感服させ、さらには威圧し、そのことで、自らの言説を神秘化し、権威付けているのだということを明らかにしている。大変面白いので、興味のある人は読んでみることをお薦めする。
たしかに、一定の背景的知識がないと理解できない言説もある。しかし、そういう種類のまともな言説では、「ゼロが『無理数=不合理であるような微積分学』としての人生」のように、「微積分学」と「人生」など、普通に考えて結び付くはずのない言葉を敢えて結びつけた場合には、その理由を説明するものである。そうしないのは、単なるこけおどしをしているだけだと思った方がよい。わけのわからないことを有り難がる必要はないということだ。人との会話でも、必要だと思ったら、わかるように説明してもらうことが大切だ。その説明を億劫がったりする人は、相手にわかってもらうつもりもないのに話しているということになるのだから、それ以上聞く必要はないし、わからなくてもかまわない。実際に、わざと相手がわからない言葉を使うことで、自分を相手に対して上位に置きたがる人がよくいるので、そんな人を相手にして時間を無駄にする必要はないと思う。
「人間は知っている者の立場に立たされている間はつねに十分に知っているのです。誰かが教える者としての立場に立つ限り、その人が役に立たないということは決してありません」
このジャック・ラカンの言葉について内田さんは、「これは『教える』ということについて語られたうちで、もっとも挑発的で、もっとも生産的な命題の一つだと私は思う。教えることを職業にしているすべての人間はこの命題にまっすぐに取り組んで、自分なりの解釈を下す義務があると私は思う」と評価している。
本当にそうだろうかと思う。内田さんの言葉を借りて言い直すと、「教壇のこちら側に立たされている間は(知っている者の立場に立たされている間は)(教えるべきことを知らなくても)つねに十分に知っている」ということになるのだが、難しい。
待てよ!人は赤ん坊からでも、ほかの動物からでも、そこいらに転がっている石ころからでも、彼らが教える意図がないにもかかわらず、学ぶものは学ぶ。教えられる側に知識や経験が豊富にあり、賢い人ほど、学ぶことが多いと思う。これは日常的に起きていることであり、めずらしいことでもない。そうすると、教壇に立っているのは「先生」なのだから、先生は「つねに十分に知っている」はずだという思い込みさえあればよく、先生が適当にわけのわからないことを言っていても、それがわからないとすれば、教えられる側の自分が悪いのだと思って、懸命に何とか意味付けをし、それぞれにとって有意義なものをそこから引き出すはずだということになる。なるほど、内田さんは、十分に知識や経験があり、聡明だから、ラカンが言った私にはわけのわからない言葉の内に、深いものを見付け、学んだわけだ。ということは、ラカンが偉いわけではなく、内田さんが偉いのである。ここでは、ラカンでもヤカンでもどちらでもよかったわけだ。禅問答の公案のようなものかもしれない。ラカンさんという師が、修行中の弟子に公案を与える。弟子は懸命に考える。そして見付けた答えを師に提出する。師が満足すればOKとなる。このとき、師は事前に答えを知っている必要はない。弟子に考えさせて、結果を評すればいいだけだから。
たしかに、こういうかたちで学ぶことは、教えられる側が教える側を越える可能性を与えることになる。また、これは、教える側の意図や目的から、あるいは束縛から、教えられる側が自由になり、自動的に各個性がそれぞれに学ぶ内容を決めることにもなる。そうなるとなかなか深い意味が込められていることになるかもしれない。そういう学び方ができる人はよく学び、教える側を乗り越える能力ある人は乗り越えてゆくだろう。でも、そういう学び方ができない人はどうすればよいのかという問題がある。特に初等教育においてそれでいいのかという疑問もある。したがって、内田さんが「教師であるためには一つだけ条件がある。一つだけで十分だと私は思う。それは教育制度のこの豊穣性を信じているということである」というのは言い過ぎではないかとも思う。
ところで、ラカンという人はあまり信用ができない。理由は、アラン・ソーカル/ジャン・ブリクモン共著の『「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用』という本を読んでいるからだ。その中で、ラカンの文章が引用され、批判されている。本当にまったく意味がわからない文章を書く人である。引用されている文には、数学の概念、用語が多用され、ラカンの専門である精神分析と関連付けられている。しかし、ソーカルたちは、本当にこの人は自分が使っている数学の概念、用語の意味がわかっているのか疑問を持っている。たぶんわかっていないと思っている。少しだけ引用の引用をしてみる。
トポロジーの概念を精神分析に結びつける講義で、
「このトーラスは現実に存在し、それは正確に神経症の構造なのです。それは類比(アナロジー)ではありません――抽象化したものでもないのです」
* トーラスとは、浮き輪のような曲面のことを言う。「トーラスが正確に神経症の構造」であることの根拠についての説明は、この部分以外のところでも一切ないとのこと。
「この享楽の空間では、何らかの有界なもの、閉じたものを取り上げること、それはひとつの場所=軌跡であり、その場所=軌跡について語ること、それはひとつのトポロジーなのだ」
* ここでは、空間、有界、閉じた、トポロジーという4つの数学の専門用語を、それらの意味に配慮することなく使っているが、数学的に見れば、この文章はまったく意味をなさず、さらに、これらの数学の概念がどのように精神分析にかかわってくるか、まったく説明していないとのこと。
「このトーラスは現実に存在し、それは正確に神経症の構造なのです。それは類比(アナロジー)ではありません――抽象化したものでもないのです」
* トーラスとは、浮き輪のような曲面のことを言う。「トーラスが正確に神経症の構造」であることの根拠についての説明は、この部分以外のところでも一切ないとのこと。
「この享楽の空間では、何らかの有界なもの、閉じたものを取り上げること、それはひとつの場所=軌跡であり、その場所=軌跡について語ること、それはひとつのトポロジーなのだ」
* ここでは、空間、有界、閉じた、トポロジーという4つの数学の専門用語を、それらの意味に配慮することなく使っているが、数学的に見れば、この文章はまったく意味をなさず、さらに、これらの数学の概念がどのように精神分析にかかわってくるか、まったく説明していないとのこと。
この他にも、曲面の一種であるcross cap(叉帽)を cross cutと間違えたり、「私が『無理数=不合理』と言うとき、何も私はある種の測り知れない情動の状態を指しているのではなく、正確に虚数と言われているものを指しているのです」と言って、虚数と無理数を混同していたり、「ゼロが『無理数=不合理であるような微積分学』としての人生」などと、ほとんど意味不明のことを述べている。
ソーカルたちは結論のところで、「ラカンの『数学』はあまりにも荒唐無稽なので、どのような心理学的な分析にも、それがまともである限りは、役に立たない」と述べている。また、「精神分析と数学の間の彼のアナロジーは、おおよそ考えられる限り気ままなものだが、彼はそれらのアナロジーの経験的あるいは概念的正当化を金輪際与えない。(ここで挙げた例だけでなく、他のいかなるところにおいても)」とも述べている。
「ラカンを擁護する人たちが批判に対抗するときに使いたがる戦略を『でもなく・でもない』方式と呼ぶことができる。これらの著作は科学として評価されるべきでもなく、哲学として評価されるべきでもなく、詩として評価されるべきでもなく、……でもない。こうなると現世的神秘主義というほかないものにつきあわされていることになる。時が経つにつれ、ラカンの著作は、言葉遊びと断片化された統辞法をないまぜにすることで、ますます判じ物めいてきた。これは多くの聖典に共通する特性である。そしてこれらのテクストが、弟子たちによる敬虔なる教義解釈の基礎となってゆくのだ。こう見てくると、つまるところ、われわれは新たな宗教を相手にしているのではないかと疑っていいようだ」と結んでいる。
知る人ぞ知るルイ・アルチュセールは「ラカンがフロイトの思想に、その思想が要請する科学的な諸概念をついに賦与したということを認めさえすればよい」と、ラカンを擁護している。何だか意味はよくわからないが、科学的な用語を自身の論文の中に散りばめたということを評価すべきで、その意味などわからなくてもよいということか。
少しだけ引用と言いながらずいぶん引用してしまったが、この本では、この他にクリスティバ、イリガライ、ボードリヤール、ドゥルーズ、ガダリなど、ポストモダン派として、難解な文章を書くことで評判になっている人たちの著作を検証し、彼、彼女たちは、自分自身が未消化であるにもかかわらず、現代科学の概念、用語の皮相な博識ぶりを誇示し、科学に疎い読者を感服させ、さらには威圧し、そのことで、自らの言説を神秘化し、権威付けているのだということを明らかにしている。大変面白いので、興味のある人は読んでみることをお薦めする。
たしかに、一定の背景的知識がないと理解できない言説もある。しかし、そういう種類のまともな言説では、「ゼロが『無理数=不合理であるような微積分学』としての人生」のように、「微積分学」と「人生」など、普通に考えて結び付くはずのない言葉を敢えて結びつけた場合には、その理由を説明するものである。そうしないのは、単なるこけおどしをしているだけだと思った方がよい。わけのわからないことを有り難がる必要はないということだ。人との会話でも、必要だと思ったら、わかるように説明してもらうことが大切だ。その説明を億劫がったりする人は、相手にわかってもらうつもりもないのに話しているということになるのだから、それ以上聞く必要はないし、わからなくてもかまわない。実際に、わざと相手がわからない言葉を使うことで、自分を相手に対して上位に置きたがる人がよくいるので、そんな人を相手にして時間を無駄にする必要はないと思う。













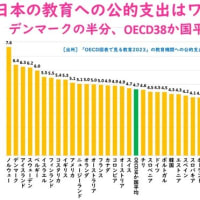



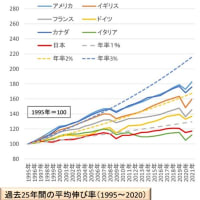


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます