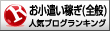第一場(約3年半後の1970年7月下旬。 北京・中南海にある陳伯達の家。陳伯達のモノローグ)
陳伯達 「なにもかも面白くない。 文化大革命で俺はあれほど活躍し、劉少奇や登小平ら実権派の連中を根こそぎ葬り去ってやった。おかげで俺は、去年の九全大会で、毛沢東、林彪、周恩来に次いで、党内でナンバー4(フォー)の地位に就くことができた。
ところがどうだ。その後、党内で大きな顔をしてのさばり出したのは、江青を中心とする張春橋らの上海グループだ。 あいつらは毛主席の信頼と厚い庇護のもとで、すっかり主流中の主流におさまってしまった。
その結果、毛主席の側近として、長い間実権を振ってきた俺の立場は、しだいに影の薄いものとなってしまったのだ。 張春橋や姚文元など大して実績のない青臭い連中が、文化大革命の果実を独り占めにして、毛主席に可愛がられている。
俺は文化大革命で中央文革小組を率いて、最も功績を上げたというのに、どうして江青達の風下に置かれなければならんのだ。実に不愉快だ。 毛主席だって、先行きそう長くは生きられないだろう。こうなったら、俺は自分の将来のことを考えて、林彪副主席に付くことにしよう。
林彪将軍こそは、九全大会で憲法の前文の中に、毛主席の後継者と正式にうたわれた人だ。いずれ近い内に、林彪時代が必ずやって来る。 そうなったら、いま毛主席に最も可愛がられている江青グループも、それに周恩来グループだって実権を失っていくだろう。
一ついい考えがある。林彪将軍を国家主席に就かせるのだ。 林彪だって、九全大会でナンバー2(ツー)の副主席になりながら、実際の役職では、周恩来総理の下で国防部長にとどまっている。あれでは、林彪だって面白くないだろう。
それに、文化大革命が一段落した結果、毛主席の後継者に決まった林彪に対して、周恩来や江青達の風当たりが、最近特に強まってきている。 だから、林彪だって内心はイライラしているに違いない。
そこで、憲法改正草案では、国家主席を置かないことになっているが、俺はこれに真正面から反対してやる。 そして、毛沢東を“天才”と持ち上げて、天才・毛沢東が国家主席に就くべきだと主張してやろう。
ところが毛沢東は、かつて劉少奇が国家主席になって痛い目にあっているので、自分が国家主席になることも、国家主席を置くことも嫌がるだろう。 しかし、中国に国家元首がいないというのは、おかしなことだ。国家主席を存続させろという、俺の主張は正しいはずだ。
毛沢東が国家主席にならなければ、あとは林彪がなるしかない。俺はこれに賭ける。 林彪を国家主席に押し上げて、俺は彼を支援するのだ。そうすれば、いずれ毛沢東が亡くなった時に、林彪と俺が中国の実権を握ることができるのだ。
そうなれば、老いぼれの周恩来だって、女狐の江青だって落ちぶれていくしかない。 よし、来月の九期二中全会で、俺は国家主席存続論をぶち上げてやろう。林彪だって、必ず俺の意見に賛同してくれるに違いない」
第二場(8月下旬。 廬山での第九期第二回中央委員会全体会議場の一室。毛沢東、林彪、周恩来、江青)
毛沢東(激しい怒り声で)「一体、陳伯達の今日の演説はなんだ! 憲法改正草案に国家主席を設けないようにしようと、われわれは長い間、意思統一を図ってきたではないか。 わしは何度も、国家主席を置くべきでないと言ってきたが、陳伯達はこれまでなんの反対もしてこなかった。
ところが、今日になって突然、あいつは国家主席を存続させろとぶち上げた。わしは自分の耳を疑ったほどだ。けしからんにも程がある。 あいつの発言で、会議は滅茶苦茶になってしまった。あの裏切者めが!」
江青 「そうカッカとすると、血圧が上がりますよ。 でも、このところ陳同志はおかしいと思っていましたわ。私と顔を合わせても、ちょっと会釈するだけで、そそくさと逃げるように立ち去っていましたものね」
周恩来 「困ったものだ。 国家に元首がいないのはおかしいという、彼の主張にも一理はある。中央委員の中には、国家主席存続論に同調する者がわりにいるかもしれない」
毛沢東 「卑怯な裏切者だ! あいつは自分の言いたいことを言ってしまうと、さっさと立ち去ってしまったが、どうせこれから裏工作をしようというのだろう。 わしを天才、天才と持ち上げておいて、国家主席に就任しろと言う。
わしは、天才などはこの世におらんと繰り返し言ってきたのに、あいつがあんなにわしを持ち上げるものだから、中央委員の中には、わしの国家主席再任を当然と見る者が出てくるだろう。 馬鹿な話しだ! わしが死んで、党主席と国家主席の二人のトップが出来たらどうなるのだ。
又、わしと劉少奇の争いのような混乱が生じるだろう。劉少奇を国家主席にしたことを、最大の痛恨事だと思っているわしに対して、あいつは平然として挑戦してきた。許せん! 副主席、君はどう思う?」
林彪 「あまり突然のことなので、私も戸惑っています。 毛主席が国家主席にならないのなら、誰がなるというのでしょう」
毛沢東 「わしがならないのなら、党副主席の君がなるしかないだろう」
林彪 「とんでもない! 私はそんなことは考えたこともありません」
毛沢東 「それなら君も、陳伯達の主張には反対だというのだな」
林彪 「私は主席の考えに賛成です。 ただ、彼の天才論は間違っていないと思います。私は、毛主席を天才だと思っていますから」
毛沢東 「そういう考え方がおかしいのだ。 マルクス主義の唯物論からいけば、天才などというものは存在しないはずだ。それは、主観的唯心論から出てくる概念だ」
江青 「そうですわ。陳伯達は、毛主席を天才に仕立て上げて、国家主席に無理やり就けようと考えているのです。 そして、毛主席がそれを断ることが分かっているので、その場合、自分か他の第三者が国家主席に就くべきだと思っているのです。 そういう政治的な野心こそ、危険な考え方ではないでしょうか」
周恩来 「毛主席以外に、国家主席になる人がいるとすれば、林総、党副主席である貴方しかいないはずだ」
林彪 「とんでもない! 私は党副主席、国防部長で十分過ぎるくらいだ。陳伯達の主張がそういう風に憶測されるなら、私も陳の言うことには賛成できない」
毛沢東 「副主席、それでは君も陳伯達の意見に反対してくれるのだね」
林彪 「天才論はともかく、国家主席存続論には反対します」
毛沢東 「よし、それではこれから、陳伯達批判を党内で徹底的に広げていこう! あいつは三十年以上もわしの秘書をやりながら、“虎の威を借りる狐”のようにのし上がってきた男だ。わしがあいつの批判を始めれば、あんな奴は立ち所に失脚するまでだ。 許してはおかん。わしの信頼と庇護を無にする奴など、絶対に許すもんか!」
第三場(10月初旬。 北京・中南海にある林彪の家。林彪、妻の葉群、息子の林立果のいるところへ、陳伯達が入ってくる)
陳伯達 「どうもご無理を言って、お邪魔します」(陳が来客用の椅子に座る)
林彪 「君が来ることは、誰にも秘密にしてある。知っているのは、この三人だけだ」
陳伯達 「有難うございます。 副主席、もうご存知のように、毛沢東は私に対する批判キャンペーンを党内で始めています。私はいずれ失脚するでしょう。 それは、それでいいのです。私は長年仕えてきた主席に歯向かったのですから。
それより、気をつけて頂きたいのは、周恩来や江青の動きです。彼らは、文化大革命によって、人民解放軍がこれまでになく大きな勢力を持ってきたことに反発しています。 彼らは陰に陽に、毛主席に対し解放軍の力を弱めるよう進言しています。
すでに、文革で一度失脚した国務院の高級官僚どもが、周恩来の差し金で徐々に復活してきているほか、江青グループの張春橋達が頭角を現わしてきたのはご存知でしょう。 この二つの勢力は互いに牽制し合いながら、狙いを副主席のグループに絞ってきているのです。彼らにとって、共通の敵はあなたのグループです。副主席は、その点を十分にご承知ですか」
林彪 「周総理や江青が、われわれを心良く思っていないことは知っている。 しかし、毛主席は文革を発動する前から、われわれを本当の味方だと思い、厚い信頼を寄せてきたではないか。 毛主席が健在である限り、われわれが不利な立場に追い込まれることはないはずだ。君の心配は杞憂だよ」
陳伯達 「いや、毛沢東は、副主席が私に対する批判を十分に行なっていないことに、疑問を抱いているようです。 年を取ると、人は一層疑い深くなるもの。まして毛沢東は、江青や周恩来の言うことばかりを聞いて、他の連中の言うことには、だんだん耳を傾けなくなっているようです」
林彪 「そうかなあ。私は唯一の副主席であり、毛主席の後継者だと天下に明らかにされているじゃないか」
陳伯達 「それが油断です。 副主席は人が良いから、毛沢東の怖さや底の深さがお分かりにならないかもしれない。あの男は自分の絶対的な権力を守るために、これまでナンバー2(ツー)と見られてきた人物を、次々に粛清してきたではありませんか。
王明も彭徳懐も、劉少奇も皆しかりです。 まして副主席は、文革によってこれまでになく強大な勢力を党内外に持つようになった。だから、毛沢東は警戒しているのです。 それに、先ほど申し上げたように、毛沢東の警戒心を江青や周恩来が煽っているのです」
林彪 「うむ、江青や周総理には気を付けている。彼らは何を考えているか分からないからな」
陳伯達 「それに率直に言いますと、毛沢東は、文革によって人民解放軍の影響力が強くなり過ぎたと思っているのです。 チャンスがあれば解放軍の勢力を叩こうと、最近では考えるようになっています」
林彪 「そんなことがありえるだろうか。 われわれの協力がなかったら、毛主席は劉少奇らを倒すことができなかったはずだ」
陳伯達 「それこそ油断です。 毛沢東は、勝つためにはどんな勢力とも手を結ぶが、一旦勝利した後は、今度は刃(やいば)を味方の中に向けてくるのです。あの男は四十年来、そういうことを繰り返してきたのです。 それで毛沢東は、絶えず党の第一人者として君臨してきたではありませんか」
葉群 「陳同志の言われることは、胸にズシリとこたえます。(林彪に向って)あなた、気を付けなければなりませんわ。 私があなたの手引きで政治局員になったことに、江青などは非常に反感を持っています。
女の嫉妬というものは、女同士の間だと電気のように伝わってくるもの。江青の忌まわしい視線を受けると、私には痛いほど敵意を感じるのです」
林彪 「そういうものかね。私ほど毛主席に忠勤を励んできた者は、他にいないと思っているのだが・・・」
葉群 「あなたは文化大革命の勝利に、少し気が緩んでおられるのですわ。 こうして、陳同志がわざわざ忠告に来られたのは、大変ありがたいことです。 一時、陳同志が不幸な目に遭うことがあっても、毛主席亡き後、私達が最高権力を握った暁には、陳同志の復権を“いの一番”にしようではありませんか」
林彪 「おいおい、陳同志はまだ失脚したのでもなんでもないぞ」
陳伯達 「いや、私はもうすぐ失脚するでしょう。毛沢東の憎しみに満ちたギラギラ光る眼が、私の背後に迫ってくるのを感じるのです。 二中全会で、国家主席を存続させるように主張したのは、私の大きなミスだったのでしょう。
しかし、それもこれも皆、失礼ですが副主席の身の上を思えばのこと。その点、十分に分かって頂ければ幸いです。 それでは、私はこれで失礼します。また、内密に伺うつもりです。ご機嫌よう」(陳伯達、退場)
林彪 「かわいそうに、あの男も毛主席に捨てられ、頼る所もなくここへやって来たんだな。 陳伯達はあんなことを言っているが、あわよくば、自分が国家主席になりたかったのではないか・・・人の心なんて分からん。
陳伯達には気の毒だが、私はあの男を批判することで、すでに毛主席と約束している。だから、毛主席が私を疑うようなことはないはずだ。 私が国家主席になろうと思っていないことは、毛主席も知っているはずだ」
葉群 「それならいいんですけど。 でも、陳同志が言うように、毛主席は自分を脅かすような力を持ってきた人間には、非常に猜疑心を抱く人です。しかも、江青や周総理があなたへの敵意から、毛主席に何を吹き込むか分かったものではありません。 その点、十分に気を付けないと・・・」
林彪 「分かった分かった。 しかし、あまり取越し苦労をするのは身体に良くない。今日はぐっすり眠るぞ。 それでは」(林彪、部屋の奥へと退場)
第四場(11月上旬。 北京・中南海にある毛沢東の家。毛沢東、康生、江青)
康生 「主席、あなたはご存知ないでしょうが、このところ二度三度と、陳伯達が密かに林彪副主席の家を訪れているのですぞ。これは、私の密偵が調べ上げたものです。 あの裏切者の禿頭めが副主席に泣きついているのです」
毛沢東 「本当にそうか」
康生 「間違いありません」
江青 「あなた、なんということでしょう。いくら陳伯達が卑怯な裏切者でも、こともあろうに林彪副主席の所へ行くなんて・・・副主席も副主席です。 陳伯達批判をすると私達に約束したというのに、なにもその当人と会わなくてもいいでしょう。なにか企んでいると疑われても仕方のないことですわ」
毛沢東 「林彪は陳伯達を批判することに同意したが、全面的に賛成したわけではない。なにか、いやいや同意したという感じだったな」
江青 「そうです。副主席は国家主席の存続論には反対しましたが、天才論は弁護するような言い方をしていました。 あの人は、自分が毛主席に次いで、第二の天才だと思っているのじゃないかしら。たしかに、軍事的才能はあるのでしょうけど」
毛沢東 「それにしても、陳伯達に会うというのはおかしい。 林彪はわしに絶対的な忠誠を誓っているのだぞ。誰かがそそのかして、陳伯達と会わせたのだろうか」
康生 「その点は分かりません。しかし、副主席はともかく、副主席を取り巻く解放軍の連中が文革のあと、党中央に対して不満を持つようになっているのは確かです。 総参謀長の黄永勝や、空軍司令の呉法憲達は、身分不相応なまでに取り立てられたというのに、増長して党中央に不満を持つようになったのです」
毛沢東 「けしからん奴らだ。 たかが軍人の分際で、なにが不満だというのだ。黄永勝などは政治局員にまでしてやったというのに・・・」
江青 「彼らは林彪副主席のまわりに集まって、独立王国を創ろうとしているのでしょう。 このまま放っておけば将来、党内に取り返しのつかない禍根を残すことになります。“毒草”は早いうちに刈り取らなければなりませんわ」
康生 「しかも、陳伯達は副主席の家で、黄永勝や呉法憲達とも会っているようですし、彼らがどんな企みをしているか、まったく見当も付きません」
毛沢東 「分かった。わしも決心がついたぞ。 近いうちにまず、林彪系の北京軍区第二政治委員の李雪峰や、北京衛戍区司令の鄭維山を更迭してやろう。そして、陳伯達批判に名をかりて、黄永勝達の不審な態度を究明してやる。 そうすれば、あいつらが腹の底で何を考えているか、おぼろげに分かってくるはずだ。
わしはどうやら、解放軍を甘やかしてきたようだな。文化大革命に功績があったというので、あの連中を優遇し過ぎていたようだ。 あいつらは軍人だ。軍人を国家の行政面でのさばらせておくのは良くない。そんなことを許しておいたら、連中はますます増長して、何をしでかすか分かったものではない。
このところ、周恩来総理からも随分苦情を聞かされてきた。今の康生の報告で、わしも決心がついたぞ。 林彪自身はわしに対して忠実なはずだが、取り巻きが良くない。林彪は単純な男だから、わしに従うだろうが、いつ取り巻きどもに担ぎ上げられんとも限らない。 解放軍は文革で十分に役目を果たしたのだ。これからは、お前達と周総理が手を取り合って活躍する番だ」
江青 「あなたは、副主席に“下心”がないように言われますが、本当にそうでしょうか。 四年前、文革の真っ最中に、あなたが私にくれた手紙では、林彪らに同意しないとやっていけないと書いてあったではありませんか。そして、林彪将軍のある種の考え方に、深く不安を感じると書いてありましたね。
あの時は、文革で劉少奇らに勝てるかどうかの瀬戸際でしたから、林彪将軍の力を喉から手が出るほど欲しかったので、あの人の考え方などには目をつぶってやってきました。 でも今こそ、副主席がどんな人物なのかを再検討する必要がありますわ。劉少奇なきあと、最大の問題はあの人にあるのではないですか。
あなたの後継者に決まってから、あの人のやったことといえば、腹心や取り巻き連中を次から次に、党の要職に就けたことぐらいですわ。 だから私には、先ほど言ったように、あの人が自分の“独立王国”を党内に創ろうとしているとしか思えないのです」
康生 「江青同志の言われるとおりだ。 主席、もうこの辺で、林彪包囲作戦を進めていかないと、将来とんでもないことになりますぞ」
毛沢東 「うむ、わしには考えがある。 北京にいる林彪系の軍人をまず片づけてから、その後の対応策を練るとしよう。それでいいじゃないか」