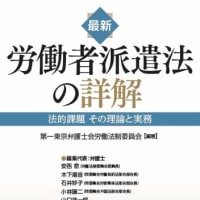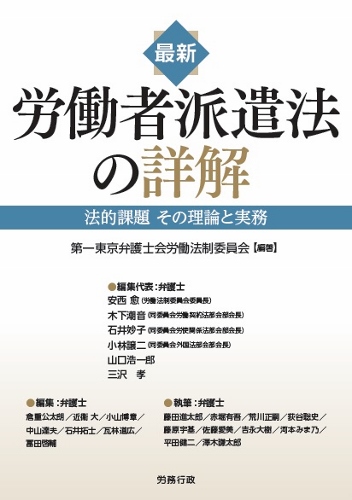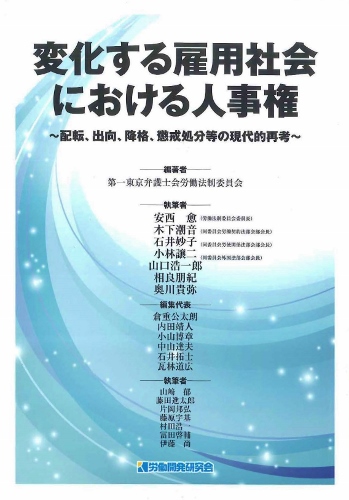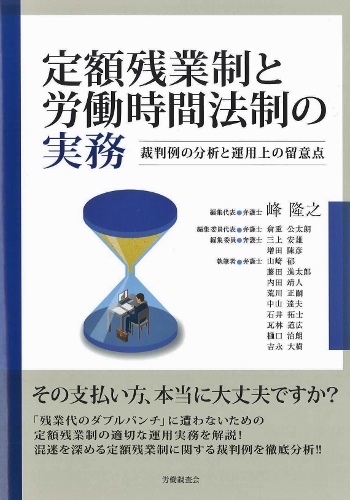Q20アスベスト(石綿)の危険性に対する予見可能性,使用者の安全配慮義務の程度は,どのようなものですか?
大阪地方裁判所平成22年4月21日判決が,アスベスト(石綿)の危険性に対する予見可能性,安全配慮義務の程度に関し,以下のように判示しているのが,参考になると思います。
ア 被告は,原告Aとの雇用契約の付随義務として信義則上,その生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務又はそのような社会的関係に基づく信義則上の注意義務(以下,これらを合わせて「安全配慮義務等」という。)を負うものである。そして,被告が,同義務の前提として認識すべき予見義務の内容は,生命,健康という被害法益の重大性にかんがみ,安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧があれば足り,必ずしも生命,健康に対する障害の性質,程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はないというべきである。
イ ところで,前記認定事実に基づけば,粉じんによるじん肺の生命,身体に対する危険性は,我が国においては,古くは江戸時代から知られており,石綿肺についても昭和初期及び被告が営業を開始した後の昭和27年ころから,大阪府泉南部を中心とする石綿加工工場等を対象とした調査が繰り返し実施されるなど,種々の調査,検診が行われ,昭和33,34年ころには,新聞報道でも石綿肺の健康被害が取り上げられていたことが認められる。また,昭和22年には,石綿肺が労災補償の対象と規定され,昭和35年には,石綿をも規制の対象とするじん肺法が制定されていたものである。
そして,前記認定事実に基づけば,被告は,昭和26年の設立時の社名からも明らかなように,石綿紡織,石綿製品であるクラッチ,ブレーキの組立等,石綿製品の製造・加工等を業とした株式会社であり,原告Aが稼働していた当時,本件工場に従業員数十名を擁し,その一角で技術研究も行っていたことが認められる。
そうすると,石綿の粉じんが人の生命,健康を害する危険性を有するものである以上,被告は,石綿製品の製造,加工業等を営む事業者として,昭和35年に上記じん肺法が施行されたこと等の経過を踏まえ,遅くとも原告Aが就労した昭和37年ころまでには,少なくとも石綿に関連する法規制を把握し,これに従うことはもちろん,十分に情報収集をするなどして,石綿粉じんの健康被害等の危険性や対策について把握することは可能であったし,これを行うべきであったということが相当である。
ウ これに対し,被告は,早くとも平成に入るまでの間は,石綿製品は,製造・加工段階で適切な規制さえすれば十分であり,製品として流通する石綿含有製品には危険性がないという認識であったことや,石綿関係労働者に肺がんや中皮腫が発生している事実を指摘したのは昭和51年通達が初めてであり,同年当時でも石綿粉じんには危険性がないというのが一般的な認識であったところ,こうした状況下で,被告のような小企業が,独自の調査研究で石綿の危険性を予見することは不可能である旨主張する。
しかしながら,そもそも被告は,石綿製品そのものの製造・加工に携わる事業者であるから,中小企業であるからといって,取扱製品の危険性等についての予見可能性や安全配慮義務等が軽減されるとは,にわかに認めることができない。そして,前記認定のとおり,石綿粉じんの危険性は,昭和51年以前にも,数々の調査報告その他の知見によって指摘されており,石綿肺の危険性も認識されていたところである。昭和51年通達が,石綿関係労働者の健康被害を初めて指摘したもので,当時は,石綿粉じんに危険性がないというのが一般的認識であったと認めるに足りる証拠はなく,むしろ,一般紙の新聞報道等でも,石綿による石綿肺や肺がんの健康被害が取り上げられていたものである。被告が中小企業であるからといって,このような状況を認識することまでも困難であったとはいえない。
なお,被告は,業界が指導内容として発行した本件冊子は,石綿が安全,無害であることを大前提として記載されたものである旨主張する。しかしながら,本件冊子を子細に検討しても,そのように解されるかどうかは,にわかに即断できないうえ,仮にそうであったとしても,本件冊子があくまでも業界側で作成した冊子であること及び前述した知見ないしは国の法令による規制等に照らせば,上述した結論を左右するものでないことは明らかである。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
エ また,被告は,上記ウの実情に照らせば,被告について,国の規制及び業界の指導以上に厳しい予見可能性があるということはできないとも主張する。
しかしながら,当裁判所の上記認定,判断は,あくまでも,当時における国の規制を前提にしたもので,これ以上に特に厳しい予見可能性を被告に要求するものではない。被告のとった措置は,国の規制等に照らしても不十分なものであり,安全配慮義務等に違反したものといえることは,後述のとおりである。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
弁護士 藤田 進太郎
大阪地方裁判所平成22年4月21日判決が,アスベスト(石綿)の危険性に対する予見可能性,安全配慮義務の程度に関し,以下のように判示しているのが,参考になると思います。
ア 被告は,原告Aとの雇用契約の付随義務として信義則上,その生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務又はそのような社会的関係に基づく信義則上の注意義務(以下,これらを合わせて「安全配慮義務等」という。)を負うものである。そして,被告が,同義務の前提として認識すべき予見義務の内容は,生命,健康という被害法益の重大性にかんがみ,安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧があれば足り,必ずしも生命,健康に対する障害の性質,程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はないというべきである。
イ ところで,前記認定事実に基づけば,粉じんによるじん肺の生命,身体に対する危険性は,我が国においては,古くは江戸時代から知られており,石綿肺についても昭和初期及び被告が営業を開始した後の昭和27年ころから,大阪府泉南部を中心とする石綿加工工場等を対象とした調査が繰り返し実施されるなど,種々の調査,検診が行われ,昭和33,34年ころには,新聞報道でも石綿肺の健康被害が取り上げられていたことが認められる。また,昭和22年には,石綿肺が労災補償の対象と規定され,昭和35年には,石綿をも規制の対象とするじん肺法が制定されていたものである。
そして,前記認定事実に基づけば,被告は,昭和26年の設立時の社名からも明らかなように,石綿紡織,石綿製品であるクラッチ,ブレーキの組立等,石綿製品の製造・加工等を業とした株式会社であり,原告Aが稼働していた当時,本件工場に従業員数十名を擁し,その一角で技術研究も行っていたことが認められる。
そうすると,石綿の粉じんが人の生命,健康を害する危険性を有するものである以上,被告は,石綿製品の製造,加工業等を営む事業者として,昭和35年に上記じん肺法が施行されたこと等の経過を踏まえ,遅くとも原告Aが就労した昭和37年ころまでには,少なくとも石綿に関連する法規制を把握し,これに従うことはもちろん,十分に情報収集をするなどして,石綿粉じんの健康被害等の危険性や対策について把握することは可能であったし,これを行うべきであったということが相当である。
ウ これに対し,被告は,早くとも平成に入るまでの間は,石綿製品は,製造・加工段階で適切な規制さえすれば十分であり,製品として流通する石綿含有製品には危険性がないという認識であったことや,石綿関係労働者に肺がんや中皮腫が発生している事実を指摘したのは昭和51年通達が初めてであり,同年当時でも石綿粉じんには危険性がないというのが一般的な認識であったところ,こうした状況下で,被告のような小企業が,独自の調査研究で石綿の危険性を予見することは不可能である旨主張する。
しかしながら,そもそも被告は,石綿製品そのものの製造・加工に携わる事業者であるから,中小企業であるからといって,取扱製品の危険性等についての予見可能性や安全配慮義務等が軽減されるとは,にわかに認めることができない。そして,前記認定のとおり,石綿粉じんの危険性は,昭和51年以前にも,数々の調査報告その他の知見によって指摘されており,石綿肺の危険性も認識されていたところである。昭和51年通達が,石綿関係労働者の健康被害を初めて指摘したもので,当時は,石綿粉じんに危険性がないというのが一般的認識であったと認めるに足りる証拠はなく,むしろ,一般紙の新聞報道等でも,石綿による石綿肺や肺がんの健康被害が取り上げられていたものである。被告が中小企業であるからといって,このような状況を認識することまでも困難であったとはいえない。
なお,被告は,業界が指導内容として発行した本件冊子は,石綿が安全,無害であることを大前提として記載されたものである旨主張する。しかしながら,本件冊子を子細に検討しても,そのように解されるかどうかは,にわかに即断できないうえ,仮にそうであったとしても,本件冊子があくまでも業界側で作成した冊子であること及び前述した知見ないしは国の法令による規制等に照らせば,上述した結論を左右するものでないことは明らかである。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
エ また,被告は,上記ウの実情に照らせば,被告について,国の規制及び業界の指導以上に厳しい予見可能性があるということはできないとも主張する。
しかしながら,当裁判所の上記認定,判断は,あくまでも,当時における国の規制を前提にしたもので,これ以上に特に厳しい予見可能性を被告に要求するものではない。被告のとった措置は,国の規制等に照らしても不十分なものであり,安全配慮義務等に違反したものといえることは,後述のとおりである。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
弁護士 藤田 進太郎