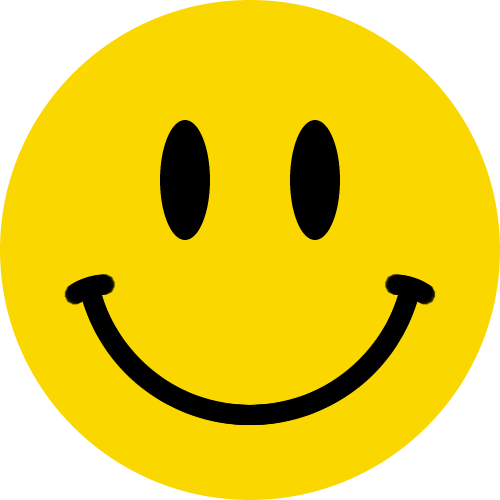田無駅 (たなしえき)
青梅街道、所沢街道が交差しかつ青梅街道の宿場町として江戸時代より
交通の要所として栄える。宿場町として陸運により発展していたため、
鉄道の誘致に積極的ではなく甲武鉄道(現在のJR中央線)の開業により
その地位を一時失う。その後は西武鉄道新宿線の開通などで東京の
市街地となり、企業誘致や都心部のベッドタウンとして栄えている。
西部新宿線内の乗換駅ではない途中駅としては最多の利用客数を誇り、
この点では西武線全体でも大泉学園駅に次いで2番目であり、
また92駅ある西武鉄道全駅でも8番目の数字である。
「田無」の地名の由来としては説がいくつかあり、
1 田んぼが無いため田無となった説
2 棚瀬が変化し たなし となり田無の字があてらてた説
3 田成が田無に変化した説
4 種なし が田無となった説、田無では税の取立てが厳しく種まで
とられてまうため周囲の村から「種なし」の村と呼ばれた。
1の説では、畑作が中心だった、現在の多摩地区ではどこでも田は無い。
2と3の説では、途中で意味は正反対に変わってしまっていること。
4の説も田無の集落が近隣より比較して早くに成立していることなどから
決め手となる説がないのが現状である。

青梅街道、所沢街道が交差しかつ青梅街道の宿場町として江戸時代より
交通の要所として栄える。宿場町として陸運により発展していたため、
鉄道の誘致に積極的ではなく甲武鉄道(現在のJR中央線)の開業により
その地位を一時失う。その後は西武鉄道新宿線の開通などで東京の
市街地となり、企業誘致や都心部のベッドタウンとして栄えている。
西部新宿線内の乗換駅ではない途中駅としては最多の利用客数を誇り、
この点では西武線全体でも大泉学園駅に次いで2番目であり、
また92駅ある西武鉄道全駅でも8番目の数字である。
「田無」の地名の由来としては説がいくつかあり、
1 田んぼが無いため田無となった説
2 棚瀬が変化し たなし となり田無の字があてらてた説
3 田成が田無に変化した説
4 種なし が田無となった説、田無では税の取立てが厳しく種まで
とられてまうため周囲の村から「種なし」の村と呼ばれた。
1の説では、畑作が中心だった、現在の多摩地区ではどこでも田は無い。
2と3の説では、途中で意味は正反対に変わってしまっていること。
4の説も田無の集落が近隣より比較して早くに成立していることなどから
決め手となる説がないのが現状である。